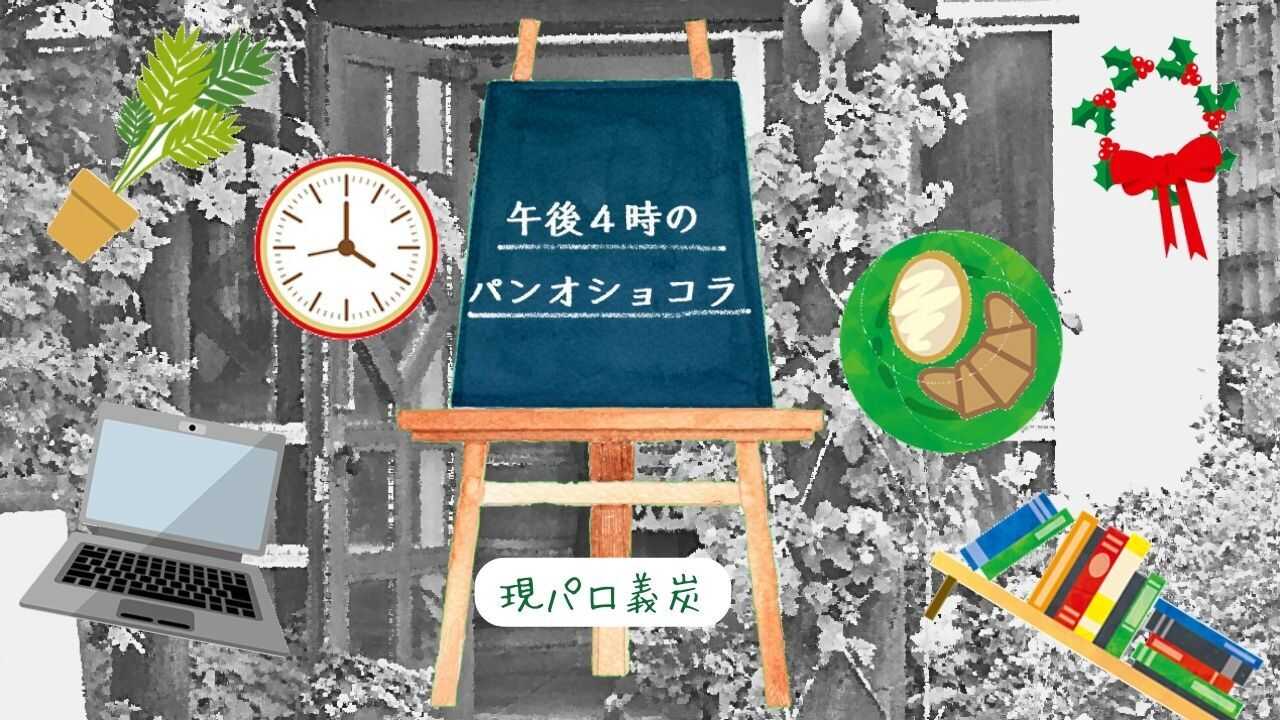錆兎から結婚の報告を受けたその日。それはきっと、義勇の人生にとって一つの分岐点だった。
互いの近況や結婚式に関してなど、錆兎と小一時間ほど雑談していたあいだも、義勇の穏やかで幸せな心地は揺るがなかった。
好きだという想いはなにも変わらないのに、錆兎の幸せを祈る心だけが自分のなかにあることに、深く安堵し、義勇は幸せを噛みしめた。これから真菰とともに鱗滝に報告しに行くという錆兎と別れた後も、静かな高揚は続いていて、竈門ベーカリーに行ってみようかとふと思う。
義勇のお気に入りのパンオショコラの焼き上がり時間は午後四時。今からでは多少早いが、幸い今日もパソコンは持ち歩いている。
幸せな気持ちのまま仕事をして、パンオショコラが焼き上がったら声をかけてくれと、炭治郎に頼んで……。
そんなこれからの予定を脳裏に描きつつ愛車に乗り込んだところで、ポケットから響いたのはメッセージアプリの通知音。見ればメッセージは担当編集者からだった。
今年の春に編集部の配置換えで担当になったのは、義勇とそう変わらぬ年ごろの女性だ。デビュー以来担当してくれた編集者は定年を迎え、不愛想で言葉足らずな義勇を最後まで心配しながら退職し、今は田舎に戻っているらしい。
短大卒の新人である彼女が、義勇は正直少し苦手だ。
義勇をまるで見世物のように盗み見ては嬌声を上げたり、あからさまに媚を売ってきたりする女性たちに対するような苦手さではない。そういう点では、義勇にいっさいのぼせ上がることのない彼女の態度は、むしろ好ましくはある。
ただ、やたらと義勇に対して当たりがキツイ。常に笑顔を絶やさず言葉遣いも丁寧なのだが、話す内容には毒がある。引継ぎの顔合わせの際から全開だった彼女の毒舌に、義勇は呆然としたものだ。
そんな義勇を見て、前担当者が冨岡さん気に入られたようですねと笑ったのは、いまだに解せない。
彼女は学生時代からうちでバイトしてくれてたんですけどね、見込みがないと思った作家には、むしろ愛想が良いんですよ。彼女が歯に衣着せずに接するのは、伸びると確信した作家だけです。冨岡さん、かなり気に入られてますよ。
そんなことを言われても、友達がいないだのだから嫌われるだのと、笑顔のままばっさりと斬られるほうの身にもなってもらいたい。穏やかで幸せな心地に水を差されるのはまっぴらだ。
それでも、このまま無視するわけにもいくまい。ご機嫌伺いや進捗状況の確認だけなら、連絡などしてこないことは承知している。そんな担当からの連絡ならば、なにか用があるのだろう。
しかたなく確認すると、新刊のゲラが上がった報告と、編集部に届いたファンレターやアンケート葉書の受け渡しに、打ち合わせがてらこれから逢えないかという連絡だった。
今日これからというのはいきなりすぎるが、断っても断らなくても、毒舌が返ってくることは学習済みだ。
脳裏に描いていた予定がもろくも崩れ去った無念さも相まって、思わず溜息をつきたくなる。
了承を伝えて間もなく届いた返信は、待ち合わせ場所の指定。思わず二度見してしまったのは、しかたのないことだろう。
「なんでだ……?」
竈門ベーカリー。見直してもやっぱりそう書いてある。ご丁寧に届いた地図も、たしかに炭治郎の店を示していた。
打ち合わせにはいつも、駅からほど近いショッピングモール内の喫茶店を利用していたというのに、なぜいきなりあの店の名が出てくるのか。
今までの会話で一度でも義勇が竈門ベーカリーの名を口にしていたなら、聡明な彼女のことだ、馴染みの店でと気を利かせたのだろうと推測することはできる。だが、義勇はあの店にかぎらず、自分の行きつけの場所について話したことはない。
錆兎や真菰ならいざ知らず、自分のテリトリーに他人を入れることを義勇は好かない。それは担当編集者であっても同様だ。
ともあれ、悩んだところで回答が得られるわけもない。義勇は少し考えて、いつも打ち合わせに使う喫茶店に変更してほしいと返信した。実際、義勇のいる場所からならそちらのほうが早い。
すぐに返ってきた言葉は、そんなだから嫌われるんですよ、だった。
なんで!? と思わずスマホを凝視してしまったが、ポンポンと現れる新たなメッセージには義勇の提案に了承する旨が書かれていたので、それだけで良しとするしかない。
義勇専用と化している個室のような席を、あの見透かすような目で見られないだけでも上々だ。
溜息とともにスマホをポケットにねじ込み、義勇は打ち合わせへと向かうべく愛車のエンジンをかけた。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
「冨岡さん、ご足労いただきありがとうございます。言い出した私のほうが遅くなり、申し訳ありません」
最寄り駅から徒歩二十分ほどの場所にあるショッピングモール内の喫茶店で、義勇の向かいに腰かけた義勇の担当編集者、胡蝶しのぶは、にっこりと笑って労いと謝罪を口にした。
だが、愛想の良い言葉はここまでなことを、もう義勇は知っている。そもそも今の発言には、最初の指定に従ってくれれば待たせることもなかったのに、という言葉が隠されているのだろう。
気が合わないだとか、癇に障るなんてことはいっさいないのだが、どうにも苦手意識が拭えぬ相手だ。
そうは言っても、しのぶが優秀であることに変わりはない。しのぶが担当になってから、義勇の小説は表現の幅が広がったと言われ、以前より評価されることが多くなったのも事実だ。
──冨岡さんの小説の登場人物は、どれも似通ってるんですよねぇ。お友達がいないからですか?──
──告白のシチュエーションが変わり映えしないと思うんです。話し相手が少ないと語彙がかぎられてくるんでしょうか──
──ヒロインの描写はきめ細やかなのに、なんでほかの女性キャラはおざなりになるんです? お友達をモデルに……ああ、すいません。冨岡さんにはガールフレンドなんて縁のない話でしたね──
……指摘は的確だと思う。なぜ必ず義勇をこき下ろす言葉がついてくるのかはわからないが。
そのたび無表情のままへこむ義勇に気づいているのかいないのか、しのぶは必ず、いい作品になるようがんばりましょうで締めるので、一応は応援されているのだと思いたいところだ。
「では、デザイナーさんにはこのまま進めていただきます。というところで、お待ちかねのファンレターです。今回もお馴染みさんから届いてましたよ」
ゲラを受け取り、装丁のチェックや次作の構成など一通り打ち合わせを済ませたところで、しのぶが紙袋を差し出してきた。
しのぶの言うお馴染みさんとは、デビュー一年目ぐらいから新作を出すたびファンレターをくれる子供のことだろう。語彙や使う漢字などの幼さからすると、最初に手紙をくれたのはおそらくは小学生かせいぜい中学に上がったころだろうと、義勇は見当をつけている。
当時はファンレターなどろくに貰ったことはなかった。そのうえ、義勇が主に書いているのは恋愛小説で、子供からのファンレターというのはたいそうめずらしい。だがそんな物めずらしさだけでなく、読者からの手紙を受け取るたびつい探してしまうぐらいには、義勇もその子の手紙を楽しみにしている。
だんだんと達者になっていく手紙の文字や言葉遣いに、子供の成長の速さを実感するのもなかなかに楽しいものだが、自身の恋心と重ねて読んでいるというその子の想いは微笑ましく、義勇にも共感できるところが多かった。
思わず赤面しそうになるほど、熱烈な称賛で溢れかえっているのは気恥ずかしいが、素直な気持ちだけを綴ってくれているのだと思うと、義勇もまた、素直に感謝の気持ちが湧く。
返事を書いたことはないので一方通行の遣り取りだが、義勇が小説を自分の生涯の仕事だと思い定めた一因が、その子からの手紙であることは間違いない。
書評でこき下ろされても、貰った手紙を読み返しては、この子の期待を裏切るわけにはいかないと奮起する。錆兎に勧められたからという当初の理由だけでは、きっと今日まで書き続けることはできなかっただろう。
今回の手紙は、夏休み前ごろに出た本の感想だろうか。きっと今回もあそこが好きだ、ここに感動したと、興奮が義勇にも伝わってくるような文字で、一所懸命に書かれていることだろう。
今年は義勇にはめずらしいことに発行ペースが早く、クリスマスにはまた新刊が出る。夏の本に告知が挟まっていたはずだから、次の本を楽しみにする言葉も書き連ねられているかもしれない。
想像して笑みが浮かんだが、しのぶの次の言葉にその笑みは消えた。
「それでですね、経費削減の折、今回から冨岡さんの我儘は却下されることになりました。なので、手紙は今回からすべて封筒に入ったままです」
有無を言わせぬ圧をしのぶの笑みに感じるのは、きっと気のせいではないだろう。
なんで、と言葉にする前に、しのぶは笑顔のまま器用に眉間に皺を刻む。
「封筒から出して手紙だけの状態で渡してほしいなんて、そんなわけのわからない我儘、今までまかりとおっていたほうが不思議なくらいです。冨岡さんはたかがそれくらいと思われるかもしれないですけど、たかがそれくらいのことに、私たちの勤務時間は削られるんですよ? バイトの子にやってもらうにしても、たった一人の我儘作家のために封筒から手紙を取り出して輪ゴムで止めるだけなんていう仕事に、給料を払うような余裕は今の出版業界にはありません。もちろん、危険物が入っていないかチェックしますから、今までどおり編集部で封は開けます。でも、いちいち手紙だけ取り出すなんて手間のかかること、これからはできませんのでご了承くださいね」
「……わかった」
滔々と語られる正論に、反論する言葉が浮かばず義勇がしぶしぶうなづけば、よろしいとでも言うようにしのぶは笑みを深めた。だがすぐにその笑みは消え、いかにも不思議そうに小首をかしげている。
「お聞きしたことなかったですけど、なんで封筒はいらないなんて我儘を言ってたんですか? ゴミを増やしたくないとか?」
「差出人の名前や住所は知りたくない」
憮然として言うと、しのぶの瞳がきょとんとしばたいた。
変人だとは思っていたけれど、本当に変な人ですね。
無言のままだが、しのぶの目と表情がそう言っている。
だから言いたくなかったんだと、義勇は居心地悪さを押し隠すように、意味なく紙袋を覗き込んだ。輪ゴムで止められた封筒や葉書は、いつもと変わらぬ量に見える。すべてが好意的とはかぎらないが、あまりにも的外れすぎる批判以外は、義勇は真摯に受け止めることにしている。しのぶの指摘と読者の批評はほぼ同一で、だからこそ義勇は、担当作家への言葉にしては失礼すぎる毒舌に反論ができない。
夏前に出た新刊は、義勇が一番弱点としている人物造形に力を入れたつもりだが、それでもしのぶからは、もっとお友達が増えるといいですねと、生温い視線で微笑まれたからそういうことなのだろう。
恋心を書くのには苦労したことがない。声に出せない自分の想いや、もしも錆兎と結ばれたらとの妄想をそのまま綴っているようなものだから、錆兎への想いを主人公に代弁してもらえばそれで済む。そのせいか、その点についての義勇の文章は好評で、しのぶから改善を求められることも少ない。
ただ、とにかく登場人物が類型的だ。さもありなん。なにせ義勇が書く人物たちは、一に錆兎、二に錆兎、とにかく主人公の相手のモデルは錆兎ばかりだ。すぐにそれと悟られる書き方はしていないつもりだが、それでも真菰には義勇が書く男の人は錆兎に似ていると、笑われることは多かった。
錆兎への秘めた思いから生まれる小説だから、それは当然なのかもしれないが、プロとしては恥じ入るほかない。
かてて加えてその他の登場人物たちがマズイ。真菰や姉の蔦子に鱗滝、片手で足りる程度のかろうじて友人と言っていい人たち。それぐらいしか義勇の引き出しにはモデルがいない。二作目で前担当から早くも指摘された、最大の弱点である。
それでもどうにか物書きの端くれを名乗れているのも、あの子からのファンレターのお陰だった。称賛と期待に奮起させられただけではない。手紙に綴られた子供の言葉から性格やら外見やらを想像し、この子だったらこう言うだろう、こんなふうに感じるだろうと思い描きながら書いた小説が、義勇にとって今も重版を続けている初めての本となったからだ。
「冨岡さんのことですから、どうせ名前を知ったら迂闊にその名前は使えなくなるとか、あとは、そうですねぇ……逢いたくなったら困るとか? そういうことでしょう?」
呆れた声は、それでもどこか優しい響きをしていた。義勇より一つ年下のはずだが、こういうときのしのぶは出来の悪い弟を見るような目で義勇を見る。べつに不快ではないが、少しばかり不甲斐なさを覚えるのは事実だ。
図星を刺されたことも相まって居心地悪さは増し、義勇は誤魔化すようにコーヒーカップを手に取った。
しのぶの言葉は確かだが、それでも少しだけ足りない。
一番最初に貰ったファンレターは匿名だったけれど、すぐに義勇は誰からなのか気づいた。錆兎の文字も、言葉選びも、義勇は熟知していたのだから当然だろう。
気恥ずかしくて、嬉しくて、ちょっぴり不甲斐なさも感じたその手紙は、今も一等大事な義勇の宝物だ。錆兎からだと気づいたことは、今も錆兎には言っていない。
名前と住所を知るということは、逢おうと思えば逢えるということで、それはもしかしたら、その人が義勇だけに打ち明けた秘密や想いを、暴く行為にも繋がるのかもしれないと思った。だから義勇は、読者の名を知りたくはない。
この世界のどこかに、義勇の書く登場人物と同じ想い──義勇の想いと同じような心を抱えた人たちがいて、義勇と同じように日々切なさに泣いたり、少しの接触に舞い上がったりして過ごしている。
冨岡義勇が真滝勇兎だと、手紙をくれる誰もが知らないように、義勇も、同士のようなその人たちの素顔など知らないままでいい。あの子も含めて。それでなくては不公平だ。
「それはそれとして、冨岡さん? 私に聞きたいことがあるんじゃないですか?」
「ない」
唐突な問いかけに、ろくに考えずほぼ即答した義勇は、次の瞬間、飲みかけたコーヒーを噴き出しそうになった。
「竈門ベーカリー」
むせて盛大に咳き込む義勇に、しのぶはあらあらと楽しげに笑っている。
「その反応を見ると、やっぱりご存じなんですね」
「……なぜ」
「だって冨岡さん、どうしてパン屋で打ち合わせなのか聞き返さなかったでしょう? カフェスペースがあることを知っていたからじゃないんですか?」
なんてことだ。ようやく咳き込み止んだ義勇は、疲れ切った溜息をついた。
「胡蝶は」
「本当に言葉が足りませんね。まぁ、わかりますからいいですけど。私はそのお店のことは、名前と場所しかまだ知りません。だから今日、打ち合わせついでに行ってみようと思いまして」
疑問に答えているようで答えていない。不満と訝しさが視線に現れたのだろう、しのぶは小さく笑うとコーヒーに口をつけている。
答える気はないということかと思ったが、そういうわけでもなかったらしい。しのぶはカップを置くとさらりと言った。
「妹の片想い相手のお宅なんです」
瞬間、脳裏に浮かんだ炭治郎の笑顔に、ドクリと鼓動が跳ねた。