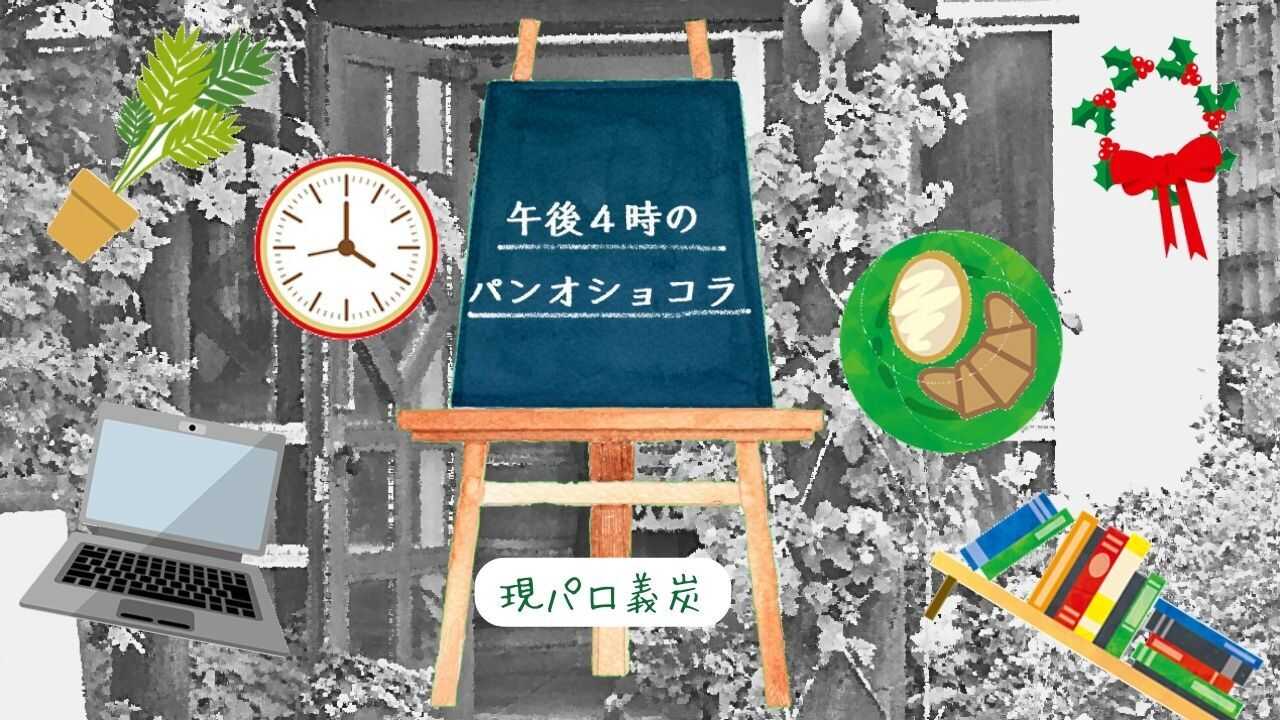ホワイトクリスマスにはなりそうにもない晴天の本日、小さな個人レストランで結婚式は行われる。金のかかる式場などではなく、まだ学生である自分達に相応な式をあげるのだと、錆兎と真菰は笑っていた。
いかにも錆兎と真菰らしいなと、義勇は微笑ましく思う。友人の知り合いだというレストランを、貸し切らせてもらえたのは幸いだ。なにせクリスマスイブである。レストランにとっては稼ぎどきだ。だというのに昼の時間だけとはいえ融通を利かせてもらえるのだ。ひとえに錆兎と真菰の人徳ゆえだろうと、義勇は身内贔屓はなはだしい感慨に浸っていた。
人前式というのがまた、二人には似合っている。堅苦しくないようにすると言っていたとおり、いかにもな正装の人は少ない。義勇はスーツだが、辛うじてジャケットを着ている程度の友人もいるぐらいだから、アットホームな式になりそうだ。
真菰はウェディングドレスだそうだが、きっと世界一きれいな花嫁になるだろう。見るのが楽しみだ。
本当なら親友としてスピーチなどしなければならないところだろうが、義勇にそんなことされたら俺らのほうがヤバイと錆兎と真菰が笑うので、出席だけで許されたのがありがたい。
従業員の更衣室は花嫁の控室として使われたので、花婿である錆兎の控室は急遽ブルーシートで囲われた店の裏口だ。真冬に屋外で着替えさせられる花婿とは、なんとも締まらない。結婚式の主役は花嫁だということを、まざまざと思い知らされる差ではある。
「外出許可がおりて良かったな」
控室と呼ぶのもおこがましい店の裏口で、義勇はタキシード姿の錆兎に笑いかけた。
真冬とはいえ今日は比較的暖かくて良かった。めでたい晴れ舞台だというのに、こんな場所で震えながら待つのはさすがに憐れ過ぎる。
「ああ、お陰で爺さんに真菰の花嫁姿を見せてやれる」
笑顔でうなずく錆兎は幸せそうだ。車椅子に乗ってではあるが、鱗滝も参列できたのは本当に良かったと、義勇も思う。
来年の春は越せないとの言は事実なのだろう。鱗滝はすっかりやせ細っていた。義勇が子供のころには誰よりも逞しく見えた鱗滝の姿が、やつれていくのは、やはり物悲しい。けれども、嬉しそうに笑う鱗滝の顔に、憂いはなかった。もしかしたら、今日一番幸せなのは新郎新婦ではなく、鱗滝かもしれない。
「緊張してるか?」
義勇が少しからかいを交えて問えば、錆兎は軽く肩をすくめた。
「主役は真菰だからな。俺は添えもんだ。緊張するほどのもんじゃないだろ」
そうは言うが、人生の晴れ舞台には違いない。常の錆兎にはない、どこかソワソワとした空気を感じて、義勇は小さく笑う。
「……俺は、ちょっと緊張してる」
不意打ちのように囁き声で言えば、きょとんとした錆兎は、訝しげに首をかしげた。
レストランからは賑やかなざわめきが聞こえてくる。じきに始まる式の準備でみんな大わらわなのだろう。料理以外は友人たちの手で全て賄われる手作りの式だ。素人ゆえに段取りもイマイチなのが、会場からの喧騒でよくわかる。
それでも祝う気持ちは誰もが同じで、今日逢ったすべての顔は満面の笑みばかりだった。
「義勇?」
「ずっと……錆兎に秘密にしてたことがある」
言ってもいいかと視線で訴えた義勇に、錆兎の表情が改まった。小さくうなずかれ、義勇は一度深く息を吸い、吐き出した。
「好きだった……ずっと、俺は、錆兎に恋してた」
まっすぐに錆兎の目を見て告げた言葉は、我ながら穏やかだった。
錆兎はなにも言わない。少しだけ目を見開いたが、嫌悪の色はどこにも見られなかった。
「すまない。言わないままじゃ、先に進めないと思った」
「いや……嬉しいよ。でも、ごめん」
「うん」
錆兎は微笑んでいる。やっぱり錆兎は義勇を否定しない。知っていたけれど、少し不安だったから、義勇の顔にも安堵の笑みが浮かぶ。
「すっきりした」
錆兎への恋にきちんと終止符を打たなければ、なにも始めることはできない。そう思ったから、今日を選んだ。結婚式直前にいきなり親友から告白されるなんて、錆兎にしてみれば迷惑かもしれないが、長らくの片恋に免じて許してほしい。
「……義勇にだけ言わせるのはフェアじゃないな」
うーん、と少し芝居がかった唸り声をあげて言った錆兎は、不意に真面目な顔をして、じっと義勇を見つめてきた。今度は義勇がきょとんとする番だ。
なにか錆兎にも義勇に言えない秘密があったということだろうが、義勇の告白以上の秘密などそうそうないだろう。義勇は先ほどの錆兎と同様に、どうぞ、と言うようにうなずいた。
「俺は、一度だけおまえにキスしようとしたことがある」
ぽかんと口を開いて凝視する義勇に、錆兎が小さく噴き出した。
「……嘘?」
「まさか。おまえにそんな嘘なんかつくもんか」
「あぁ……知ってる」
ならば、それは事実なのだ。義勇の知らぬ間に、錆兎とのファーストキスのチャンスは訪れ、果たされず消えたということか。
「中二のときだったかな。夏休みで、おまえの家で二人で宿題してた。真菰は家族旅行でいなくて、蔦子姉さんは買い物に出かけて、二人きりだった」
思い出そうとしたが、あまりにもそれは日常の光景すぎて、思い当たる日が多すぎた。
「おまえは前の晩に観たかった深夜映画を観たとかで、ずっと眠そうだった。数学の課題を終わらせた途端に、限界って言って寝転がってた」
具体的なことは思い出せない。けれどその日の光景を、義勇はまざまざと思い描ける。
きっと窓は開け放たれていた。エアコンはつけていない。すだれ越しに差し込む夏の日差し。風鈴の音が、セミたちの喧騒の合間を縫うようにひびいていただろう。
卓袱台に広げられたノート。向かいに座って、言葉はなくそれぞれシャーペンを走らせる。
青い江戸切子のグラスは真菰のお気に入りで、真菰がいるときには麦茶はいつもそのグラス。けれど真菰はいなかったのなら、卓袱台に置かれていたのは、多分マグカップだ。グラスだと飲むたび手が濡れて、いちいち拭くのが面倒だからと、二人だけなら麦茶だろうとアイスコーヒーだろうとマグカップに注いでしまう。
終わったと伸びをして、義勇はごろりと横になったのだろう。座布団を枕代わりに、額に汗を滲ませて。錆兎の気配を感じながら、カップのなかでカランと氷が音を立てるのを聞きつつ、きっとすぐに眠りに落ちた。
おそらく義勇の想像と錆兎の記憶に、大きな齟齬はないはずだ。
出逢ってからずっと繰り返してきた、ありふれた夏の日の光景。
「すぐにおまえは居眠りしだして、俺が課題を終えたころには熟睡してた。終わったぞって起こそうとして、おまえの顔を覗き込んだときだ。義勇にキスしたいって、思った」
錆兎は静かに微笑んでいる。真冬だというのに、その日の蝉しぐれが聞こえた気がした。
「もう少しで触れられるってとこで、郵便配達が来てな。慌てて離れたとこでおまえも起きたから、残念ながらおまえのファーストキスは貰い損ねた」
「……好きだった?」
「うん。けど、正直言うと、恋してたかはよくわからない。恋になりかけてたってとこだな」
「そうか……」
錆兎のなかにも、自分への想いはあったのか。
義勇との恋が生まれかけた瞬間は、錆兎にもあったのだ。
郵便配達が来て良かった。少し顔を伏せて、義勇は素直にそう思った。
錆兎とキスしていたなら、今もこんなふうに穏やかに笑い合える関係でいられたかわからない。
今となって思えば、錆兎への恋は信仰心に似ていた。だからこそ、きれいで純粋な想いしか向けてはいけないとかたくなに思い込んでいたのだろう。
義勇にとっては、神様のような錆兎。そこに生々しさを求めたら、いつかは破綻していたかもしれない。もしもそのまま対等に、恋人同士になれたとしても、しょせんはもしもの話だ。果たされなかったからこそ思い浮かぶ淡い幻想。決して訪れることのない未来の話。
けれど、それでも確実に、錆兎と真菰ではなく、錆兎と義勇が結ばれる可能性はあったのだ。
ならばもう、それだけでいい。
義勇、と不意に呼びかけられて、義勇は顔を上げた。悪戯っ子のような笑みが至近距離にあった。
「せっかくだから、一度くらいキスしとくか……?」
義勇は逃げない。囁くような錆兎の声に、義勇も囁きで返す。
「……なんの記念に?」
「そうだな……秘密が秘密じゃなくなった記念、とか」
クスリと笑いあった互いの吐息が、互いの唇を擽る。
「やめとく」
二人の距離は人差し指の厚み分。二人の間に差し込んだ義勇の指先に、錆兎の唇が触れた。
近すぎて少しぼやける視界で、錆兎は密やかに笑っている。きっと自分も同じ顔で笑っているのだろう。
「そう言うと思った」
「なぜ?」
顔を離して、錆兎は、今度はカラリと快活に笑った。
「だっておまえ、好きな奴がいるんだろう?」
義勇は一途だからな、好きな奴としかキスなんてしないだろ? 錆兎は少しのからかいを込めて言う。
「どんな奴だ?」
言われて少し考える。炭治郎のひととなりを伝える言葉なら、いくらでもある。けれど錆兎に告げるなら、一番ふさわしい言葉を選びたい。ちょっとだけ、プロの小説家としての意地も込めて。
「……二人で池に落ちた日に、先生が焚いてくれた焚火を覚えてるか?」
「ん? あぁ、あれか。もちろん。生き返ったっていうか、死なずに済んだぐらいの勢いでホッとしたよな」
それは、義勇が錆兎への恋を自覚した日の想い出だ。
錆兎と二人揃って池に落ち、ずぶ濡れになった義勇は足を挫いて動けなかった。顔を怪我して出血していた錆兎も動いていいものかわからずに、真菰が鱗滝を呼んでくるまで、二人でしがみつき合って震えていた。
夏とはいえ山のなか、しかも全身ずぶ濡れだ。心底寒くて、痛みも重なり、不安で不安で泣き出さないのが不思議なほどに怖かった。
真菰とともにようやく鱗滝が来たものの、ほかの大人は出払っていた。鱗滝一人で子供二人を担いでいくわけにもいかず、もう一人大人を連れてくるまで待てと焚火を焚いてくれた。
結局、あの池に咲いていた花は採ることができず、大人たちには盛大に叱られ、怪我のために残りの日数はろくに遊べなかった。
今はもうその花の名も知っている。池に咲いた睡蓮を摘もうなど、子供というのはまったくもって無謀なことをするものだと、我ながら苦笑するしかない。
恋を自覚した衝撃はともかく、総合的には残念な想い出だ。それでも、あの焚火の温かさを思い起こすと、それもまた楽しかったと思える。
「あのときの焚火みたいな子供だ」
笑って言った義勇に、錆兎はパチリと少し子供っぽくまばたきして、すぐにその日一番の明るい笑みを見せた。あの日咲いていた睡蓮の花を思わせる白いタキシードを着て、夏の日差しの下に咲く大輪の花のように、錆兎は笑う。
「そりゃ、たまらなくあったかいな」
「うん……生き返らせてくれるぐらいには」
笑いあっていると、戸口から顔を出した友人が声をかけてきた。
「錆兎、そろそろ移動してくれ」
「おう……って、ちょっと待て義勇! 今なんか、スルーしちゃいけない言葉がなかったか!? 子供ってなんだ、子供って!」
一言余計だったか。
しまったと眉を寄せた義勇に、慌てて詰め寄ろうとする錆兎を止めたのは、式進行役の友人の声だ。
「錆兎、急げよ! おまえはこっち! 花嫁さん待たせんな!」
「おい、村田、あんまり引っ張るなよっ。義勇! 今度ちゃんと聞かせてもらうからなっ!」
引きずられるように戸口をくぐる錆兎に向かい、義勇は笑いながら人差し指を唇に当てた。錆兎の唇に触れた指先で、投げキスを一つ。交わし損ねたファーストキスの代わりに錆兎に投げる。
ぽかんとした顔のまま引っ張られていく錆兎を見送って、義勇は清々しい気持ちで空を仰いだ。
今度こそ、これでおしまい。初恋は愛に変わって、ささやかな間接キスで終止符が打たれた。
きっと、いい式になるだろう。微笑みながら見上げた空は、底抜けに澄んでいた。