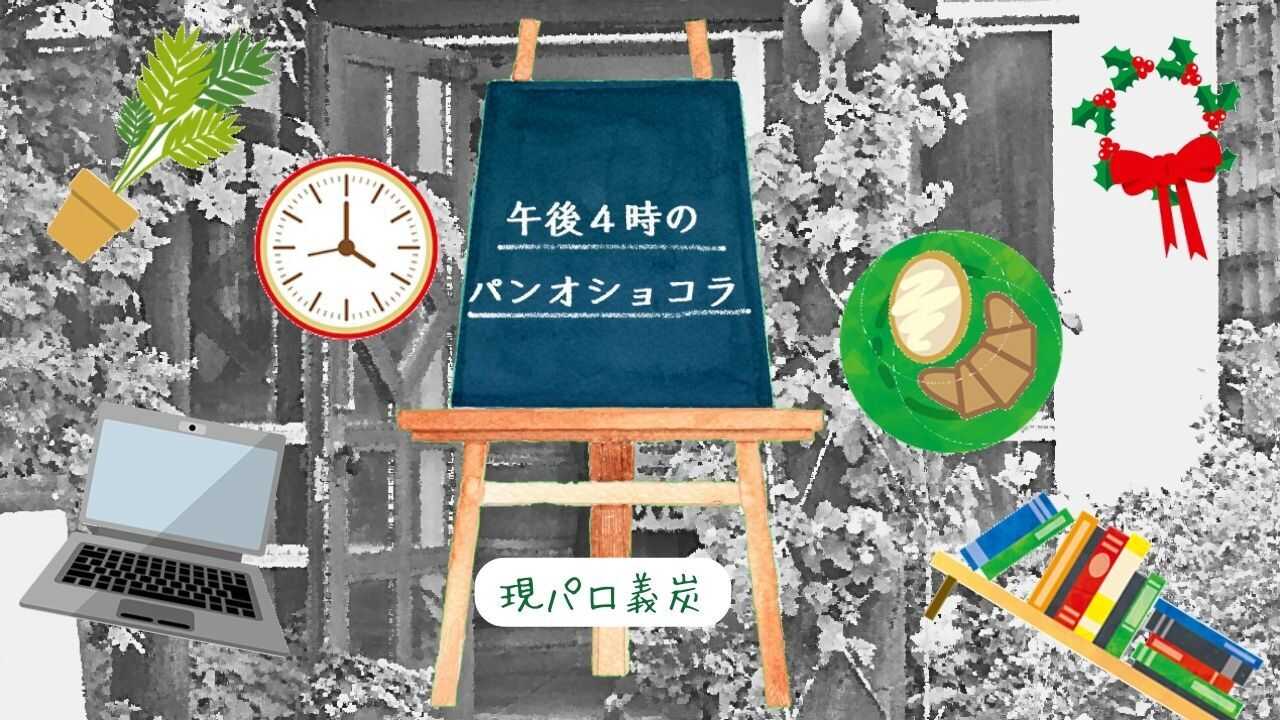眩しさに覚醒をうながされ、小さく唸りながら目を覚ました義勇が一番最初に浮かべた言葉は、変な夢を見たな、だった。
炭治郎が教えたこともない義勇の家に来て、教えたこともない義勇の名を呼んで、子供にするように頭を撫でる。ありえないだろう、そんなこと。
夢に見るほど炭治郎が気になるのかと溜息をつきかけたところで、腹近くに感じる重みに気づき、視線をそちらに向けた義勇は、驚きに目を見開いた。
まだぼんやりとしていた意識が一気に覚醒する。ベッドに乗せられた頭は赤みがかった髪色。耳に下がる花札に似た大振りのピアス。
「……炭治郎?」
夢じゃなかったのか。思った刹那、カッと頭が沸騰した。
「おいっ!」
「うわっ!! え? え? なに?」
飛び起きた炭治郎がきょろきょろと周囲を見回すのに、イラッとする。自分も起き上がり、義勇は不機嫌な声で唸るように言った。
「なんでそこにいる」
「え、あっ、冨岡さん! おはようございます、気分はどうですか?」
「最悪だ」
言った途端に盛大に慌てだし、救急車呼びますと立ち上がろうとした炭治郎に、深く溜息をつく。
「そうじゃない。昨日より体は楽になった」
「本当ですか? 無理してませんか?」
「ない。それより、おまえはなんでそんなとこで寝てるんだ」
エアコンは利いているようだが、それでもなにもかけずに座ったまま眠っているなど、シャワーで体を温めた意味がないではないか。夢じゃなかったのなら、昨夜の炭治郎の濡れた髪だって現実だ。義勇の言いつけを守って、きちんと髪を乾かしていたのならいいのだけれど。やけにそればかりが気にかかる。
「……すいません、あの、禰豆子から冨岡さんがかなり具合が悪そうだったって聞いて、つい……ポイントカードに住所が書かれてたので来ちゃいました! ごめんなさいっ!!」
勢いよく土下座した炭治郎の謝罪は、質問の意図からすれば的外れだが、そう言えばそもそもの疑問点はそこだったなと気づき、次いで義勇はその言葉の意味にぽかんと口を開けた。
「ポイントカード……」
「あの、スタンプが溜まって引換券として回収したやつです……冨岡さんがずっと持ってたんだって思ったら、その、捨てるのもったいなくて……本当にごめんなさい!」
「おまえ……個人情報保護法を知ってるか?」
「知ってます! あ、あの、でもですね、お客様の住所は年賀状を送るのに使うだけで、ほかの人のポイントカードは責任もって廃棄してますし、冨岡さんのポイントカードも無くしたり落としたりしないように宝箱にしまってありましてっ…………本当にすいませんでした」
しゅんと肩を落としてうつむく炭治郎に、義勇はもう一度嘆息すると、もういいと言いながらベッドを下りた。
「と、冨岡さん? あの、まだ寝てたほうが……」
「昨日からシャワーも浴びてなくて気持ち悪い」
「駄目ですよ! まだ熱も下がってないかもしれないのに、シャワーなんて!」
キッと眉尻を上げて叱る炭治郎に、義勇も盛大に眉をしかめた。
「このまま眠るなんて冗談じゃない」
もうあの男の感触は消え去っているが、やはり体は洗い清めたい。ふと歯に挟まっていた毛の感触まで思い出し、ゾッと背が震えた。歯も磨きまくろうと、心密かに義勇は決意する。いずれにせよ、寝汗がひどかったようで、このままでは気になって眠れそうにないほど肌がべたついてもいた。
立ち止まることなく部屋を出ようとした義勇の足を止めたのは、物理的な抑制だった。
「駄目ですってば! 気になるなら俺が拭きますから!」
ガシリと義勇の足にしがみついて言う炭治郎に、義勇は冗談じゃないと慌てて炭治郎の腕を振りほどこうとしたのだが、炭治郎も引く気はないようだ。
ホテルを出る際に身支度したときには、とくには見受けられなかったが、目の届かない場所には噛み跡や内出血が残されているかもしれない。その手の知識に疎い炭治郎でも、さすがにキスマークぐらいは聞いたことがあるだろう。わからなくても、これどうしたんですかなどと聞かれでもしてみろ、なんと答えればいいというのか。
しばらく攻防戦は続いたが、根負けした義勇が自分で拭くということで、炭治郎も一応の納得を見せた。歯磨きは諦めるしかない。
湯とタオルを用意しに炭治郎が部屋を出た途端、深い溜息が零れたのはしかたないだろう。あの押しの強さはいったいなんなんだ。第一、炭治郎は自分を避けていたのではないのか。店で義勇に示した態度はなんだったというのか。
思い返して、またどろりと心の底で澱みが揺れ蠢いた。溝浚いは完全に失敗だ。澱みはまったく消え去っていない。酷使した体は痛むし風邪は引くしと、まさに踏んだり蹴ったりだ。
顔を見るのも二度とごめんだが、あのテク無し遅漏のサディスト野郎には、もう一発ぐらいお見舞いしてやっても罰は当たらないだろう。
苛立ちを持て余していると、炭治郎が湯気の立つ洗面器を手に戻ってきた。
「背中拭けますか?」
「大丈夫だ。いいから出てろ」
素っ気なく言い捨てれば、炭治郎は少し寂しげに眉を下げたが、素直に部屋を出て行った。
パタンと音を立ててドアが閉まったのを確認して、義勇は服を脱ぎ洗面器に沈むタオルを絞ると体を拭いた。熱くないよう気を遣ったのか、湯の温度はちょうど良く、肌を拭き清めると先ほどまでとは異なる溜息が知らず口をついた。
炭治郎が家のなかにいるのに下着まで脱ぐのはためらったが、一番清めたい場所をそのままにもできない。なんだか思春期のガキみたいだ。思いつつも、ドアを気にしながら手早く済ませる。新しく取り出した下着と部屋着に着替えたところで、ドアがノックされた。
「もう入っても大丈夫ですか?」
「……あぁ」
応えを返したとほぼ同時にドアは開き、炭治郎が入ってくる。手に持ったお盆にはマグカップと小鉢が乗っていた。
「すいません、勝手に台所借りちゃいました。あ、ちゃんと布団に入ってくださいね」
歩み寄りながら炭治郎が世話焼きらしくうながしてくる。ここで反論したところでまたもめるだけだろう。少しばかり億劫に思いつつも、義勇は素直にベッドへと戻った。
「風邪薬用意したので、その前に少しでいいですからこれ食べてください」
「……すりおろしりんご?」
「はい。本当はお粥作りたかったんですけど、寝てる最中に冨岡さんお腹鳴らしてたから、すぐに食べられるほうがいいかと思って」
からかうふうでもなく言われた言葉に、義勇は思わず言葉に詰まった。寝ながら腹の虫を鳴らすなんて、赤っ恥もいいところじゃないか。
義勇の狼狽には気づかなかったのか、炭治郎はベッドの傍らに正座して、すりおろしりんごを掬ったスプーンを「はいアーン」と差し出してくる。
「……自分で食える」
「あ……そ、そうですよね! いつも禰豆子たちが風邪ひくとやってたもので、つい……ごめんなさい」
謝る炭治郎の顔に見える自己嫌悪の色から、義勇は思わず視線を逸らせた。
炭治郎が自分の言葉で一喜一憂するたびに、義勇の感情も合わせて揺れる。それが義勇を苛立たせる。平常心を保とうと、黙々とスプーンを口に運んでいると、それをじっと見ていた炭治郎が意を決したように口を開いた。
「あの、冨岡さん……冨岡さんが店に来なくなってたのって、恋人ができたからですか……?」
「は?」
思いがけない言葉に、思わずぽかんとしてしまう。
恋人? 誰に? そんなもの生まれてこのかたいたことはないが。
怪訝に思っていると、炭治郎は覚悟を決めたという顔で、言い募ってくる。
九月ごろにショッピングモールへ行ったら、義勇がとてもきれいな人と一緒にいるのを見た。喫茶店の窓から見える二人の姿に、道行く人の多くが凄い美男美女カップルと騒めいていた。自分もとてもお似合いだと思う。彼女からプレゼントらしい紙袋を受け取って、義勇は嬉しそうだった。恋人ができたのに炭治郎に好意を寄せられるのは迷惑で、だから店に来づらかったのではないのか。
言いながら炭治郎は何度も言葉を詰まらせ、泣き出すのを堪えていた。借り物のスウェットの膝を握り締めた手が震えている。義勇を見る瞳には、明らかな嫉妬の色があった。
炭治郎にしてみれば、義勇に逢えなくなる不安や義勇とともにいた女性への嫉妬で、平常心など保てないのだろうが、義勇にしてみれば阿保らしいの一言だ。
炭治郎が見たのは、考えずともしのぶとの打ち合わせだとわかる。受け取った紙袋はファンレターだ。
そんなもので誤解して、炭治郎はあんなにも不自然に自分を避けようとしたのか。
呆れ返るのと同時に、ふざけるなと身勝手な怒りも湧く。おまえの態度に俺がどれだけ……と考えたところで、義勇の怒りはスッと冷めた。
怒ってどうするというのだ。そんなことを口にすれば、炭治郎にまた期待させてしまう。自分としのぶについてはありえない勘違いでしかないが、炭治郎に恋するしのぶの妹は現実だ。今はまだ自分の勝手な想像でしかなかったようだが、いずれは義勇の想像も現実になるのだろう。
「……もう、俺を好きだとか言うのはやめろ」
カチャリとスプーンを置いて、義勇は固い声で呟いた。
サッと青ざめた炭治郎は、きっと自分の言葉が事実なのだと誤解をさらに深めたに違いない。傷つく瞳を見ていられなくて、義勇は空になった器だけ見つめ、言葉を重ねた。
「俺が店に行ったときにいた女の子は、おまえのことが好きなんだろう? あの子と付き合うほうがいい。お似合いだ」
「なんで……なんでそんなこと言うんですかっ!? 冨岡さんが迷惑なら、もう好きだなんて言いません。でも、ほかの人と付き合えなんて言わないでください! 俺が好きなのはたった一人です! 今までも、これからも、俺のことを好きになってもらえなくても……好きなんです。想うことぐらい許してくれたっていいじゃないですか……っ」
「勘違いだと言っただろ! おまえが好きだと言う男は、おまえの記憶のなかにしかいない! 勝手に人を美化して、憧れを恋だと勘違いしてるだけだ!」
「勘違いなんかじゃない! 美化なんてしてない! 俺が好きなのは、優しくて人が好きで、でも人に近づくことに臆病で、ちょっとドジだったりする人です。子供みたいにパンを選んでるあいだじゅうトングをカチカチ鳴らしたり、食べるのが下手でしょっちゅう口に食べかすつけてたりする……そんな、あなたです。想い出のなかの冨岡さんより、ずっと、ずっと、大好きでたまらないのは、そういうあなたです……」
思わず。
そう、思わず、顔を上げ炭治郎を見ずにいられなかった。
嘘だ。最初に浮かんだのはそんな言葉。たった一度だ。幼いころにたった一度、助けただけ。ただそれだけで、好きだと言う炭治郎の言葉は、信じられなかった。
初恋だと言うのは嘘ではないのだろう。それでも、勘違いだとしか思えなかった。弱っているときに優しくされたから、恋だと思い込んだだけだろうと思っていた。
再会した後ならなおさらだ。好かれるようなことはなに一つしていない。優しいなんて言われる覚えがない。
竈門炭治郎という少年のことはもう信用している。店で逢う短い時間ですら、炭治郎のひととなりは容易に知れた。誠実で生真面目、頑固なのが玉に瑕な、思い遣りに溢れた優しい子だ。こんな子を信用せずにいるほうが難しい。
けれど、炭治郎の恋心については、義勇は信じたことがなかった。信じてどうなる。好かれた要因が義勇が気紛れに見せた優しさなら、もうとうにそんなものは幻想だったと思い知ったはずだ。
「……優しいなんて、おまえが勝手に思い込んでるだけだ」
「思い込みなんかじゃないです! 冨岡さん、初めて店に来たとき、俺のこと嫌がって早く帰りたいって思ってましたよね。それなのに会計が済んだ後、すぐに帰らないでまた棚を眺めてたでしょう? ベビーカーを押したお母さんが店に来るのが見えて、待ってたんですよね? 手が塞がったお母さんの代わりに、ドアを開けてあげるために」
そんなこと、覚えてない。困るのは、心当たりがありすぎることだ。だって、そんなの当たり前のことで、特別なことをしたわけじゃない。
「冨岡さんは、いつもそうです。杖をついたお爺さんが来たときには、わざわざ席を立って通路に落ちてた紙ナプキン拾ってましたよね。足を滑らせたらいけないって思ったんでしょう? お爺さんがレジを済ませてる間に拾って、お爺さんが気付かないうちに席に戻ったの見てました。お仕事に集中してても、気が付いたら冨岡さんは人のために動いてる。誰も見ていなくても。本屋で逢ったときもそうでした。子供が上にある本を取れないで背伸びしてたら、なにも言わないでその本取って下に置いてあげてました。いつだって冨岡さんは、少し離れた場所で人を見てる。人が好きで、誰かが楽しそうにしてるのを見てるだけで、自分も幸せに思えるからじゃないんですか? 冨岡さんはそんなふうに、見返りなしで人に優しくできる人です。あの日、店に来た冨岡さんに逢ってから、ずっと冨岡さんを見てたから、俺、知ってます。そんな冨岡さんだから、好きなんです」
結局のところおまえは人が好きなんだよな。
昔、そう言ったのは錆兎だ。真菰が小説を書いてみたらどうかと、義勇に言ったときのことだ。
『義勇はよく人を見てるからな。小説って言うのは、自分じゃない誰かの人生を言葉にするってことだろう? おまえに向いてると思う。自分から人に近づいてくのは尻込みする癖に、人に自分がなんて言われようとケロッとしてるのは、人が楽しそうにしてるのを見てるだけでおまえも楽しめるからだろ? 結局のところおまえは人が好きなんだよな。そういう奴は小説を書くのに向いてる気がする。義勇みたいに人が好きじゃなきゃ、他人の人生書いて、人を感動させたり笑わせたりなんかできやしないんじゃないかな』
だから書いてみろよと笑った錆兎に、顔が熱くなるのを止められなかった。
錆兎は、自分のことをちゃんと理解してくれている。それが嬉しかった。全部が全部その通りとは言えないが、義勇の本質は義勇自身よりも錆兎のほうが知っているとさえ言えるぐらいに、錆兎は義勇を見ていてくれた。
だから、錆兎の期待に応えられるなら、やってみようと思った。
そして今、小説を書くことは、義勇にとって生き甲斐になっている。
そうして今、炭治郎が言ったのは……。
「すまない、今日は帰ってくれ……」
「冨岡さん……」
「怒ってるわけじゃない。迷惑だとも思っていない。だが、今日は帰ってくれ……ちゃんと、いずれ店には行くから……多分、クリスマスごろには」
声は自分でも意外なほど静かだった。少し黙り込んだ炭治郎が、小さくうなずいて涙を拭うと立ち上がる。
「薬、飲んでくださいね……またのご来店、お待ちしてます……」
炭治郎の声も静かだった。諦めだったのか、期待だったのか、それは義勇にはわからない。わからなくていいと思う。だから義勇は小説を書いている。
炭治郎が部屋を出て行く。しばらくすると、玄関の引き戸が開閉する音が聞こえた。
薬を飲まなければ。頭の片隅でちらりと思う。炭治郎が用意してくれたマグカップの白湯は、もうすっかり冷えているだろう。それでも炭治郎が義勇のために用意したものだ。入れ直すなんて考えられない。
絆されているとでも言えばいいのだろうか。元々人として好ましい少年だった。そんな子が一途に想ってくれるのだから、気にかかるのは当然だろう。
それでも応えることができないのは、錆兎への恋心があったからだ。
恋する相手は一人でいい。もしも万が一、錆兎への恋を捨てて新しい恋をするのなら、きっと錆兎の面影を持つ人になるのだろうと思っていた。諦めようと捨て去ろうと、錆兎以外に恋なんてできない。だからきっと、錆兎の代わりに錆兎に似た人を選んで好きなふりをするのが、自分にとっての新しい恋になるのだと思い込んでいた。
けれどきっとそんな日は来ない。錆兎は錆兎だ。どんなに似た人だろうと、錆兎の代わりにはなれない。
だから代わりに小説のなかで、恋をした。小説のなかで、義勇は何度も錆兎と恋をした。片想いも、両想いになれるのも、小説でなら自由だ。
違う人生を、幾度も義勇は綴る。錆兎には向けられない嫉妬も劣情も、小説には素直に綴った。自分の代わりに生きる人を書きたかった。一つひとつの言葉は、義勇が命を与えてやらなければ、ただの言葉の羅列にしかならない。小説という形にして初めて、義勇が口に出せない想いも、苦しみも、認めたくない穢れですら、人の目に触れることを許された。
義勇の心だけじゃない。モデルにした義勇の周りの人々や手紙をくれる読者たちもまた、義勇の想像のなかで、義勇が綴る言葉の一つひとつで、違う命を吹き込まれイキイキと動き出す。それがたまらなく好きなのだと、気づいたのは多分、幼いあの子の手紙を読んでから。
錆兎が、炭治郎が、言った通りだ。結局は、自分は人が好きなのだ。
自分がその輪に入れなくても、笑顔を見たり会話が聞こえたりするだけで、ふわりと心が浮き上がって、その人たちの人生を思い浮かべてしまう。知っている人が少ないから、どうしても類型的になりがちなのは困りものではある。だが、笑っているその人がなにを思い、なにに哀しみ、なにを求めるのかを想像しているだけで、その人の人生をともに歩んでいるような気にさせてくれるから、人を見ているのが好きだった。
セックスの相手と抱き締めあうのが嫌なのは、恋してないからだけじゃない。互いに欲を晴らす道具でしかないと思いたかったからだ。人だと思ってしまえば、そんな身勝手な行為につき合わせることは、義勇にとって苦痛でしかなくなる。抱き締めて温もりや鼓動を感じたら、今自分がただの穴や棒でしかないと思っている相手は、人になってしまうから、抱き締めあいたくなどなかった。
なんて身勝手で、汚らわしいんだろう。
そんな自分が、炭治郎の想いに答えていいのか、まだ分からない。けれど、きちんと考えなければならないと思った。
たとえ絆されているだけだとしても、義勇の心は炭治郎に向かっている。錆兎の代わりじゃない。炭治郎は誰の代わりにもなれないし、ならない。炭治郎だから、好きだと思う。誰の代わりでもなく炭治郎だから、愛おしいと感じるのだ。
それでもまだ認めきれずにいるのは、自分の臆病さゆえだ。人に近づくのは少し怖い。自分が人に好かれる質ではないことぐらい、二十年以上生きていれば察しもする。それでも人が好きだから、小説を書いている。
他人が考えていることはわからない。だから想像する。想像した人たちの心を言葉にして、自分の想いも言葉にして、生み出した愛しい人たちの人生を紙面の上でともに歩む。
そんな自分の背を、間違ってないよと押してくれる人たちがいるから、今も小説を書いている。
ふと、受け取って以来、そのまま置きっぱなしにしていた手紙の束を思い出した。あの子からの手紙もあったのに、すっかり忘れていたなんて薄情な話だ。
申し訳なさに突き動かされて、義勇は紙袋を取りに茶の間に向かった。
紙袋を手にベッドに戻り、封筒に入ったままの手紙を一通一通取り出しては、読み進める。初めて手紙をくれる人もいれば、何度か書いてくれている人もいた。
それぞれ自分の言葉で義勇に心を届けてくれる。ときおり、義勇の不甲斐ない悪癖を叱咤したり、自分の恋の秘密を打ち明けてくれたりする言葉もあって、義勇はそのたび心のなかで送り主へと言葉をかけた。
わかるよ。つらいよな。がんばって。ありがとう。ごめんなさい。がんばるから。
手紙をくれる人たちが、真滝勇兎ではない冨岡義勇を好きになってくれるかはわからない。それでも義勇の本を読み、わざわざペンを取り手紙を書いてくれるだけで、冨岡義勇という男を肯定してもらっている気になる。
少しずつ凪いでいく心に安堵しながら、次に手にした封筒の宛名を見た義勇は、すぐにあの子からだと気づいた。手紙に綴られる文字と同じ筆跡で書かれた、真滝勇兎様の文字。
封筒から取り出した便せんは、いつもよりもかなり枚数があった。
この子は筆まめらしく、いつもそれなりの枚数を書いてくれるのだけれど、今回は格別多い。
なにか変わったことでもあったのだろうか。見ず知らずの名前も知らない子ではあるが、義勇にとっては特別な子だ。
気になりつつ手紙を読めば、いつもと同じく、本の感想が興奮も露わな文字で書き連ねられていた。