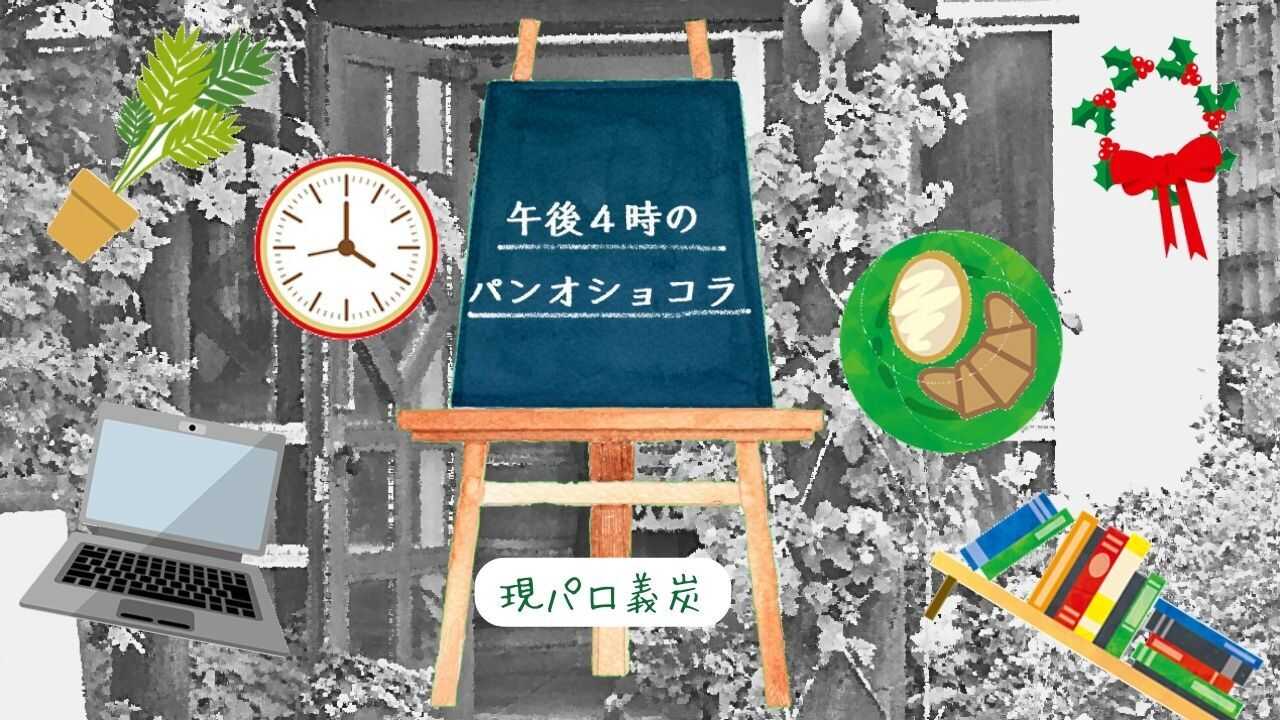鱗滝の体調を考えて午前から始まった式はつつがなく終わり、二次会まで出席しても、時刻は午後四時。めでたい席ではあったが、車を理由に酒は固く断った。錆兎と真菰の結婚と同じくらい、義勇にとっては一世一代の大事な用が控えていたので。
三次会だと騒ぐ友人たちには断りを入れ、義勇が向かったのは竈門ベーカリーだ。駐車場に愛車を停めて、積んでおいた紙袋片手に、クリスマスリースの飾られた店のドアを開ける。
「いらっしゃ…い、ませ……」
初めて店を訪れた日と同様に、パンの補充をしていた炭治郎が振り返った。義勇の姿を認めた瞬間、赤い大きな目はいっそう丸く見開かれ、早くも少し潤んで見える。
「冨岡さん……」
「パンオショコラ、焼き立てはあるか?」
言いながらトレイとトングを手に取った義勇に、炭治郎が慌ててうなずく。
「今並べたばかりです。あのっ」
「ホットコーヒーも」
カチカチとトングを鳴らしながら、炭治郎を見ずに義勇は棚に近づいた。焼き立てのパンオショコラをトレイに乗せてレジに向かえば、炭治郎はもうコーヒーを用意して待ち構えている。
札と一緒に出したポイントカードは今回でスタンプ満了。次回、三百円分のパンと引き換えに渡したら、今度もこのカードは炭治郎の宝箱とやらに入れられるんだろうか。
想像して少し笑った義勇を、炭治郎はソワソワと物言いたげに見上げている。
不安でしょうがないのだろう。けれど、どう切り出せばいいかわからない。わずかに寄せられた眉からはそんな葛藤が透けて見え、泣き出しそうに瞳が潤んでいる。
苛める気はないのだが、そんな顔も嫌いじゃないなと義勇は思う。現金なもので、認めてしまえばもう、炭治郎を可愛いと思う心には歯止めがかからないらしい。
「渡すものがある。手が空いたら席に」
「えっ、あ、はい!」
現金なのは炭治郎も同様だ。義勇の言葉に途端に顔を輝かせている。へにゃりと笑った顔が可愛い。泣き出しそうな顔も可愛いが、やっぱり笑顔が一番愛おしい。
久々に訪れた竈門ベーカリーは、クリスマス一色だ。表にもツリーが置かれていたが、店内にも至る所に小さなサンタやトナカイのぬいぐるみが飾られている。衝立代わりの観葉植物にも、モールやオーナメントが飾られていて、いつものように葉の隙間から店内を眺めるのはちょっと難しい。
こんな可愛らしい場所では、自分はかなり浮いてるんじゃないだろうか。思いながらコーヒーに口をつけたら、客が途切れたのか炭治郎がやって来た。
「あの……冨岡さん、今日はどうしたんですか?」
「クリスマスごろには行くと言っただろ」
「や、そうじゃなくてっ、その格好……」
赤く染まった顔はそっぽを向いているが、視線がチラチラと義勇を窺い見ている。義勇がスーツなど着てくるのは初めてだから物めずらしかろうが、直視しないのはどういうわけか。
「結婚式」
「えっ!? あ、あの人と、ですか……?」
バッと音がするぐらいの勢いで義勇に顔を向けたのはいいが、その顔は悲壮に青ざめている。
「親友のだ」
「え? あ、そっか。そりゃそうですよね。冨岡さんの結婚式だったら、うちに来る時間なんてないですよね」
ホッとしたように笑う炭治郎は、しかし、いまだに誤解したままのようだ。とんでもない勘違いをしてくるものである。
「いくらなんでも結婚するのにこのスーツはないと思うが」
「すっごく格好いいです! 冨岡さんのスーツ姿、滅茶苦茶格好いいです!」
食い気味に力説してくる炭治郎に、思わず腰が引けた。そんなにか。いや、褒められているのだから嬉しいことは嬉しいが、いつもの適当な服装じゃ駄目なのかと、少し複雑な気分だ。
しかしまぁ、それはどうでもいい。炭治郎が好む服などは次回以降リサーチするとして、義勇はとりあえず気になっていたことをまずは口にしてみる。
「義勇さんじゃないのか?」
「へ? え、えっと」
「義勇さんって呼んでただろ、俺の家で」
夢じゃなかったのなら、たしかにあの夜、炭治郎は義勇さんと囁き呼びながら、義勇の頭を撫でてくれていたはずだ。次の朝には冨岡さんに戻ってしまっていたが、呼ばれるのなら名前のほうがいい。
「お、覚えてたんですか!?」
カァッと顔を赤く染め、あわあわとうろたえだす炭治郎に、義勇は少し呆れた。
「そこまで照れることか?」
「だ、だってっ、名前で呼ぶなんて、なんか、その……凄く、仲がいいみたいじゃないですか……」
そりゃ仲が良くなくちゃ困るだろう。今後の関係を思えば。
「炭治郎」
ヒュッと息を飲み義勇を凝視する炭治郎の顔が、ますます真っ赤に染まった。もう耳や首筋まで赤い。
「名前……」
「凄く仲がいいなら、名前で呼ぶんだろう?」
はくはくと唇をおののかせて、炭治郎はひたすらに義勇を見つめてくる。ゆらゆらと瞳が揺れているのは、涙がこぼれかけているからだろう。
あぁ、愛おしいな。
思いながら義勇は、傍らに置いていた紙袋を炭治郎に差し出した。
「あのときの服、洗濯してあるから」
「あ、ありがとうございます。そうだ! 俺も借りたスウェット返さなきゃって思ってたんです。今持ってきますから」
「今度でいい。それより、中身確認しなくていいのか」
と言うよりも、ぜひともこの場で確認してもらわねば。視線でうながせば、炭治郎はいちいち確認しなくても信用してますよ? と言いたげな顔で小首をかしげたが、素直に紙袋を覗き込んだ。
「……冨岡さん、これっ!」
「義勇さん」
端的に言い直しを要求すれば、炭治郎は、うっと少し怯んだようだが、恐る恐る口を開いた。
「あの、義勇、さん……」
「なんだ?」
「真滝勇兎さんの本が入ってるんですけど……このタイトルって、たしか明日発売の本ですよね? なんで冨…ぎ、義勇さんが持ってるんですか?」
「貰ったから」
嘘じゃない。新刊が出るたびに、献本用にと何冊か、義勇の元にも本は送られてくる。冨岡さんが渡す相手なんてかぎられてるのに、場所をとってお邪魔かもしれませんけど。しのぶのそんな言葉つきで。まぁ、反論はするまい。
「いらないか?」
「いりますいります! ありがとうございます! あ、お金払いますからっ」
取って返そうとする炭治郎の腕を掴み、引き留める。プレゼントとしては貰いものの流用のようで申し訳ないぐらいなのに、さらに代金まで払われてたまるものか。
「クリスマスプレゼントだ、金はいらない。本に挟んであるのと一緒に受け取ってくれたらいい」
表紙裏に書いたメッセージは、まだ気づかなくてもいいけれど、しおり代わりに挟んだもう一つのプレゼントは、ぜひとも今受け取ってほしい。
きょとんとしつつ本を取り出し、はみ出している細いチェーンに炭治郎は首をかしげている。そのページを開いた炭治郎の顔は、果たして義勇の想像通りで、たいへん満足だ。
「と…義勇さん、この鍵って……」
まだ馴染めないのか冨岡と言いかけるのは少々不満だが、真ん丸に見開かれた目が可愛いので、義勇の機嫌はすこぶる良い。
「貸したスウェットは今度うちに来るときに返してくれればいい。もし俺がいなかったら、その鍵で勝手に入って待ってろ」
「……義勇さんの家の鍵……って、そんなもの貰えませんっ!」
狼狽を露わに鍵を突き返してくる炭治郎に、義勇はムッと眉を寄せた。その反応は想定外だ。いや、遠慮するだろうとは思ったが、なぜ泣きそうな顔をするのかがわからない。
「なんで?」
「だって、ぎ、義勇さんの家に勝手に入るなんて……もし、彼女さんと逢っちゃったら、俺、どうしたらいいのかわかりません……」
「彼女なんていない。おまえが見たのは仕事相手だ。俺がゲイだって知ってるだろ? 女が恋人のわけないだろうが」
呆れ声で言ってやれば、泣き出しそうだった顔がきょとりとあどけない思案顔になり、次いでふわりと嬉しそうな笑みに変わった。
「じゃあ、義勇さんに恋人はいないんだ……」
「現時点では、まだいないな」
悪戯心から澄ました顔で言うと、炭治郎はまた不安げな顔をする。たいへん悪趣味だと自分でも思うけれど、義勇の言葉にくるくると表情を変える炭治郎を見るのは、たいそう気分が良かった。
「恋人ができる予定があったりするんですか……? で、でも、義勇さんはずっと好きな人がいるんですよね? その人以外は好きにならないって……」
「今日はそいつの結婚式だ」
ストンと炭治郎の肩が落ちた。義勇を見る目には、労りと嫉妬と不安の色が絡み合っている。
「好きな人が結婚したから、だから、ほかの人を恋人にするんですか……?」
「そうじゃない。親友への恋が終わったのは事実だが、恋人になりたいのはそいつのことが好きだからだ」
ちゃんと恋がしたい。小説のなかでだけでなく。炭治郎と二人で。
想像だけじゃなく、生身の自分で。きれいなだけじゃない、嫉妬や劣情も含めたすべての想いを、炭治郎にやりたい。炭治郎からも渡してほしい。
「そいつも俺のことが好きなままらしいから、断られることはないと思う」
「そう、なんだ……」
炭治郎はまだ気づかない。自慢の鼻はどうした。
「まだ高校生だから、しばらくは健全なお付き合いになるだろうけどな」
「高校生……そう、ですか……」
おまえのことが好きだという気持ちに匂いがあるなら、きっとこの場に溢れかえって、息もできないぐらいに匂い立っているだろうに。
義勇はうつむく炭治郎の腕をとり、そっと引き寄せた。
「だから、卒業まではこれぐらいで我慢しろよ……?」
触れただけのキスは、きっと誰にも見られていないはずだ。この席は義勇専用で、店内からの視線は炭治郎が作った観葉植物の壁で遮られ、二人の姿は見えないのだから。
火がついたように真っ赤に染まった炭治郎の顔に、義勇は満足し小さく笑うと、手を放した。
「レジ」
「え? あ、えっと、あのっ」
「早く行け」
客が待ってるぞと言外に伝えれば、炭治郎は、今日は絶対に閉店までいてくださいね! と言い置いて、慌ててレジへと足を進めた。その背を見ながら肩を竦め、義勇は内心で少しだけ安堵した。
無事に伝わってなによりだ。このまま気づかれず、恋人になれないまま帰っていたら、本に書いたメッセージがとんでもなく間の抜けたものになってしまう。
ファーストキスだったのにと、もしも文句を言われたら、俺にとってもファーストキスだと教えてやろうか。それを聞いたときと、本を開いて義勇が真滝勇兎だと知ったときと、さて、どちらが見物だろう。
きっとどちらも可愛かろうと、赤く染まる炭治郎の顔を思い浮かべて、義勇は幸せな心地でパンオショコラに噛り付いた。
──大切な読者から、大切な恋人になった君へ。本のなかより素敵な恋を、いつまでも二人で続けられることを願って──