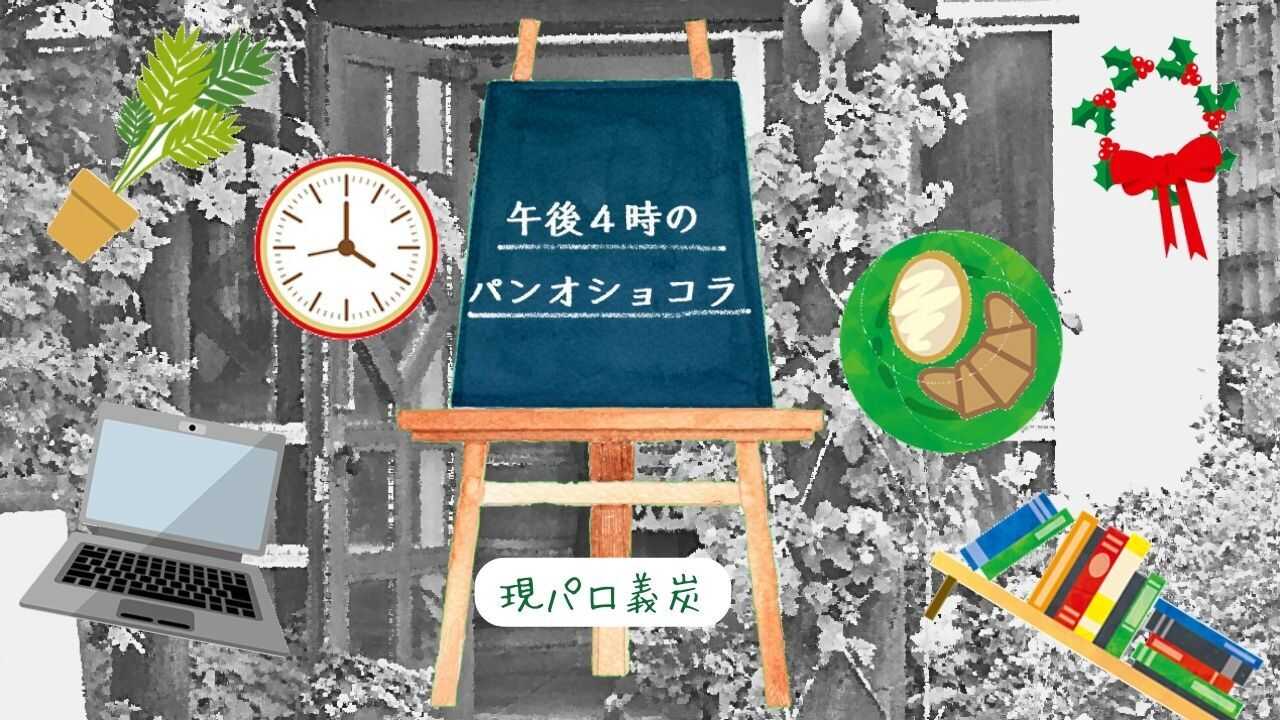「おい、そんな溜息つきながら書くぐらいなら、一休みしたらどうだ?」
キーボードを叩きながら何度目かの溜息をこぼした義勇は、錆兎の呆れたような声に、弱々しく顔を上げた。
「そんなに話に詰まってるのか? めずらしいな」
「いや……そういうわけじゃないんだが……」
「そうか? 俺がいるのが気になるなら素直に言えよ? 気を遣わせるのは俺もごめんだ」
まさか。そんなことあるものかという言葉は、声になるまでもなく錆兎にはしっかり伝わったようだ。端正な顔に悪戯っ子のような笑みを浮かべ、義勇と俺の仲で今さらそれはないってわかってるけどなと言って、義勇の頭へと腕を伸ばしてくる。
ぐしゃぐしゃと髪を撫でられ、やめろと口では言っても、心の内ではもっと撫でてほしいと願ってしまう。
不愛想でなにを考えているのかわからない。誰もがそう言う義勇を、こんなふうに子供のように扱うのは、幼馴染である錆兎と真菰ぐらいなものだ。真菰は女ということもあり、子供扱いは言葉ばかりで、義勇の頭を撫でたりはしないが。
一人きりの家族である姉が嫁に行き、今、義勇の頭を撫でるのは錆兎だけだ。
スキンシップが激しいタイプというわけではないのだが、義勇の髪を撫でるのは気に入っているようで、幼いころから錆兎はたびたびこんなふうに、義勇を撫でてくる。その都度、義勇が胸ときめかせつつ、感情が出にくい己の表情筋に感謝していることなど、錆兎は知る由もあるまい。義勇とて、万が一錆兎に知られたら、腹を切って詫びる覚悟である。
「あの店が閉店した」
「あぁ、なるほど。これからどこで書けばいいのか悩んでいるのか」
義勇の一言で錆兎は言いたいことを悟ってくれたらしい。真の悩みまではさすがにわからなかったようだが、それを説明する気は義勇にもない。
まさか新たな執筆場所として紹介されたベーカリーで、店員の少年に惚れられたかもしれないなど、どの口が言える。まだ炭治郎から告白されたわけでもなし、なぜ惚れられたなどと思うのかと、問い返されても困る。
ほかのことならなに一つ錆兎に隠しごとなどないが、ゲイとしての自分の諸々については、決して錆兎には知られたくはない。
無論、錆兎は義勇がゲイであろうと、絶対に偏見の目など向けないと信じている。だが、自分が義勇の恋愛対象になる可能性に思い至ったとき、錆兎がどんな反応をするのか、想像するだけで怖いのも事実なのだ。
告白なんてするつもりはない。それでも万が一、心に秘めた錆兎への恋心を悟られてしまったら。錆兎は決して義勇を傷つけるような言葉で拒否はしないだろうが、今とはどうしたって付き合い方は変わってしまうだろう。幼馴染で親友という今の関係を壊すことが、義勇にとってはなによりも怖かった。
ただ想っているだけでいいのだ。報われ、結ばれたいなど、思ってはいない。あさましい肉欲も、みっともない嫉妬も、錆兎に対して抱きたくはない。きれいな想いだけを錆兎には向けていたかった。
「あ、しまった。そろそろ時間か」
「真菰か?」
壁に掛けられた時計を見て慌てだす錆兎に、義勇は声に少しだけからかいを滲ませた。付き合いの浅い者なら気づきようもない細やかな違いだが、錆兎はちゃんと汲みとってくれる。からかうなと義勇の額を軽く突いてくる指先に、どれだけ義勇が幸せを感じているかは知らないだろうが。
少し照れくさげに今日は飯を作ってくれることになってると言いながら、錆兎は、読んでいた文庫本をトートバッグにしまうと立ち上がった。
「じゃ、そろそろ帰るな。今日はいきなり来て悪かった」
「いや、助かった」
「そうか? 今日はあんまり役には立たなかったみたいだがな。もしいい店が見つからなかったら遠慮せず呼び出せよ?」
それじゃあまた学校でと言って帰っていく錆兎を、玄関先で見送り、義勇は小さく溜息をついた。
大学で顔を合わせた瞬間に、おまえの家に寄ってくからと言った錆兎は、きっとその寸前までそんな気はなかっただろう。言葉や表情には出さずとも義勇が悩んでいることを感じ取り、心配してそう言ってくれた。長い付き合いで義勇はそれを知っている。
それでも、義勇が聞いてほしいと願う気配を滲ませないかぎり、錆兎は深く詮索することはない。ただ傍にいて、義勇が相談するか自身で答えを見つけ出すまで、じっと待ってくれるのだ。
錆兎はいつでも、義勇の表に出ない感情の機微を的確に読み取り、気遣ってくれる。口下手でコミュニケーション能力の低い義勇が、周りから誤解され敬遠されることを、心底心配してくれる。
錆兎のそんな優しさに触れるたびに、錆兎への恋心は募って積もって、今ではもう、義勇の心の大半は錆兎への想いで占められている。
自覚したのは小学生のころ。そろそろ十年になろうとする片恋は、高校を卒業するまで肉欲を伴っていた。いつか錆兎の恋人になれたらいいのにと、ひっそり夢見ていたのは高三の終わりまで。決定的な失恋に、自分の察しの悪さを嘆いた。
錆兎と義勇と真菰。小学校入学と時期を同じくして、同じ剣道場で出逢ってともに育った幼馴染。道場の孫息子である錆兎は、義勇と真菰の兄貴分で、体が弱く健康のためと入門してきた真菰は、錆兎と義勇の妹分。義勇はと言えば、二人からなぜか末っ子扱いされている。妹のように思っている真菰にまで、しょうがないなぁ義勇はとせっせと面倒をみられる関係は、今も変わらず続いていた。
いつまでも変わらず、三人の関係は、きれいな正三角形を描いたまま続くのだと思っていた。心の奥で錆兎と結ばれることを夢見ても、それが実現することはないだろうと諦めていた義勇にとって、それだけが救いだったとも言える。
『あのな、俺たち付き合うことになった』
同じ高校を選んで、共に過ごした高校生活の終わりに、錆兎と真菰が照れくさそうに義勇に言った言葉は、理解するまで数秒を要した。
なぜ気づかなかった? いつから想い合っていたんだろう? 自分だけが蚊帳の外だったんだろうか。
せめて二人の間の空気の変化に気づいていたなら、この日に対して心の準備もできただろうに。
あぁ、俺は本当に察しが悪い。三人変わらずと思っていたのは、俺だけだったんだ。
愕然として言葉を失った義勇の様子に、常の二人ならすぐに気づいたことだろう。けれど幼いころから二人を知る義勇に告白する面映ゆさと緊張や、互いへの想いが通じ合っている喜びで胸を占められている二人が、義勇の受けた衝撃に気づくことはなかった。
笑え。笑え。喜んでやれ。おめでとうって言ってやれ。祝福しろ。
──笑えっ!!
自分に懸命に言い聞かせ、おめでとう、まったく気づかなかった、水臭いなと、笑ってみせた義勇一世一代の演技は、二人に気づかれることなく受け入れられた。
気づかれなくて幸いだ。だからこそ、今も義勇は二人の傍にいられる。幼馴染として。親友として。二人の傍に、錆兎の傍に、いることを許されている。
卒業を祝ってこれから一緒に食事にでも行こうと言う二人に、すまないが用があるし邪魔をするほど野暮じゃないと、笑ってみせたあの日。高校を卒業したその日が、義勇の恋が破れた日であり、義勇が初めて男と寝た日になった。
二人と別れてふらふらと繁華街をさまよい歩き、偶然見かけた子供に絡んでいた輩を憂さ晴らしに叩きのめしても、まったく心は晴れず。家に帰っても、姉が話しかけるのにさえ上の空だった。
深夜になっても眠ることすらできなくて。真菰に対する嫉妬や、言ってくれなかった二人への哀しさや憤りが胸に溢れて。自分がどうしようもなく汚く思えた。
ずっと錆兎に触れたかった。いつか錆兎に抱かれてみたかった。男に性的な興味などなく、誰よりも男らしい錆兎が、男に抱かれるなんてきっと受け入れがたいだろう。そのときには自分が受身の立場になってもいいなんて。そんなことを考えていた自分は、どれほど馬鹿で、汚らしいんだか。
初めてした自慰は、錆兎への想いを自覚してしばらく経ったころだった。切っ掛けは覚えていない。それでも、錆兎の笑顔や、頭を撫でてくれる手を思い描きながらしたそれは、終わってみれば罪悪感で死にたくなったけれど、頭がおかしくなりそうなほど気持ちが好かった。
言わないから。告白なんてしないから。絶対に自分の想いを押し付けたりしない。そんな言葉を免罪符にして、何度も、何度も、錆兎に触れられることを想像しながら自分を慰めた。
男が好きだから錆兎に恋したのか。錆兎に恋したから男が性的な対象になったのか。義勇にももうわからない。いずれにせよそのときまで、義勇の恋心も性的な欲求も、錆兎一人にしか向かうことはなかったのだから、どちらが先でもどうだっていい。
でももう終わりにしよう。こんなあさましくて身勝手な欲を、錆兎に向けちゃいけない。錆兎には、きれいな想いだけ捧げたい。失恋したって好きだという気持ちが消えないのなら、澄んだきれいな心だけを錆兎には向けたい。報われなくていい。幸せを願えるだけでいい。汚らしい欲を捨てたきれいな心だけで、錆兎を想いたい。
ふらりと家を出て、ぼんやりと歩いた繁華街。声をかけてきた、今ではもう顔も思い出せない男が、義勇の初めての男になった。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
茶の間に戻ってパソコンに向かっても、どうしても集中できず。時計の音ばかりが耳について、とうとう義勇はパソコンの電源を落とした。
やっぱり筆が進まない。このままでは死活問題だ。
これからいったい自分はどこで執筆すればいいのやら。大学の図書館やカフェテラスは論外。誰に見られるかわかりゃしない。義勇が小説を書いていることを知っているのは、錆兎と真菰、そして他県に嫁いだ姉だけだ。ほかの誰にも言う気はないし、知られるのもごめんだと思う。
高校時代に、義勇は口下手だけれどとてもきれいな文章を書くから、いっそ小説でも書いてみたらどうかと、真菰が言ったのは単なる思い付きでしかなかっただろう。義勇だって最初は冗談としてしか受け止めていなかった。錆兎が、いいかもしれない、一度書いてみろよなんて言い出さなければ、きっと義勇は小説など書くことはなかったはずだ。
まったくもって自分と言う男は、一事が万事、錆兎錆兎錆兎なのだなと、自分に呆れ果てるしかない。
つたないながら書きあげた小説は、絶賛してくれた錆兎と真菰の手によって、義勇が知らぬ間に出版社に送られ、編集者から連絡を受けた。
錆兎たちの絶賛は素人目に加え贔屓目もあったようで、電話で聞かされた内容は、義勇が思わずへこむほどの酷評だ。やっぱり小説など書いたこともなかった自分の文章など、プロから見れば箸にも棒にも掛からぬレベルなのだと思ったのに。今言ったところを直せばじゅうぶん出版できます。頑張りましょう! などと言われ、今に至る。
自分の文が褒められて嬉しいというよりも、錆兎の評価が正しく人に認められるものだったことのほうが嬉しくて。錆兎に恥を掻かせてなるものかと、編集者の指摘に従って生真面目に手直しした小説が、義勇のデビュー作だ。
賞を取ってのデビューというわけでもないので、はっきり言って売り上げ部数はお粗末の一言。それでも、今でも文筆業を名乗れる程度には出版を重ねられているのだから、きっと自分は恵まれているのだろう。
そこそこ資産家だった両親の遺産のお陰で、おそらくはこの先も、働かずとも食っていくには困らない。小説など趣味として書くだけでもよかった。けれど、今では義勇自身、これが自分の仕事だという自負がある。口下手な自分が、唯一、人並みに自分の言葉を伝えられる表現方法。もう、小説を書くのをやめるという選択肢は、義勇にはない。
はぁ、と深く溜息をついて、義勇はちらりと時計を確認した。時計の針は五時半を示している。
どこかで夕飯を軽くとって……と考えたとき、不意に思い浮かんだのはあのパン屋だった。思わず義勇は顔をしかめる。
初めて竈門ベーカリーを訪れた日から、一週間が経とうとしている。もう炭治郎だって、義勇に店を訪れる気などないことを察している頃合いかもしれない。正直なところ、移動された鉢植えで隔離された席は、烏間の喫茶店の気に入りの席と同じくらい、居心地は良さそうだった。近くに感じられる人の気配、けれど、不躾な視線などからは隔離された空間。義勇にとっては理想的な執筆場所だ。
いまだ行けずにいるのは、炭治郎が義勇に向ける視線の熱さ、その一言に尽きる。
とはいえ、背に腹は代えられぬとも思うし、あの店のパンは義勇の好みをピンポイントでついていて、もう食べられないのはやはり残念だ。喫茶店のモーニングで食べていたクロワッサンやトースト、ロールパンなどだけでも美味いと思っていたのに、あの日炭治郎に強引に勧められて食べたパンオショコラ。あれがいけない。
歯触りの良いクロワッサン生地に溶け込むチョコは、甘さとほろ苦さのバランスが絶妙で、思わず目が見開いた。ぐっと噛んだ瞬間に口いっぱいに広がったそんなチョコの味に感嘆すると同時に、次に歯が捉えた溶け残ったチョコのチャンクの食感は、柔らかすぎず硬すぎず。これまた絶妙の触感のバランスが楽しい。クロワッサン本体も、さっくりとしたチョコのない部分と、チョコの染み込んだ部分で食感が異なるのが堪らなくて、お得なパンだなと感心した。
今この瞬間のおいしさは、焼き立てだからこその美味しさだけれど、うちのは冷めてもほかの店のものより美味しいって評判なんです。自信満々そうに言った炭治郎の言葉は、まったくもって嘘偽りなどなかった。
あの一つですっかりパンオショコラにハマってしまって、ほかの店をいくつか買ってみたのだが、竈門ベーカリーで食べたものには遠くおよばない。
「……食いたいな」
ぽつりと呟いてしまったら、もう駄目だった。きっと口に出したら我慢が効かなくなると思ったから、あれが食べたいと思うたびに心のなかで打ち消してきたというのに。
もしかしたら炭治郎はいないかもしれない。高校生のようだから、毎日店の手伝いをするとはかぎらない。いや、もし炭治郎がいたとしても、あそこまで気遣ってやったというのにあれきり音沙汰のない義勇など、なんて薄情な奴だと見切りをつけている可能性だってある。その場合、あの居心地の良さそうな席も元通りになってしまっているかもしれないが、少なくとも絶品なパンオショコラは買いに行ける。
浮かぶのはあの店へと行く理由ばかりだ。
一度だけ。一度だけ行ってみようか。パンオショコラと、しばらく食べる分のロールパンなどを買ってくるだけ。もしも炭治郎の態度が素っ気なくなっていたなら、それで良し。執筆場所を探すという悩みは解決しないが、気に入りのパンはこれからも食べられる。
「……行くか」
自分で自分の背を押すように呟いて、義勇は溜息とともに立ち上がった。
もしもあの鉢植えがあのときのままなことを考えて、一応とノートパソコンを持って家を出る。我ながらいじましいなと思いながら、義勇は愛車へと足を進めた。