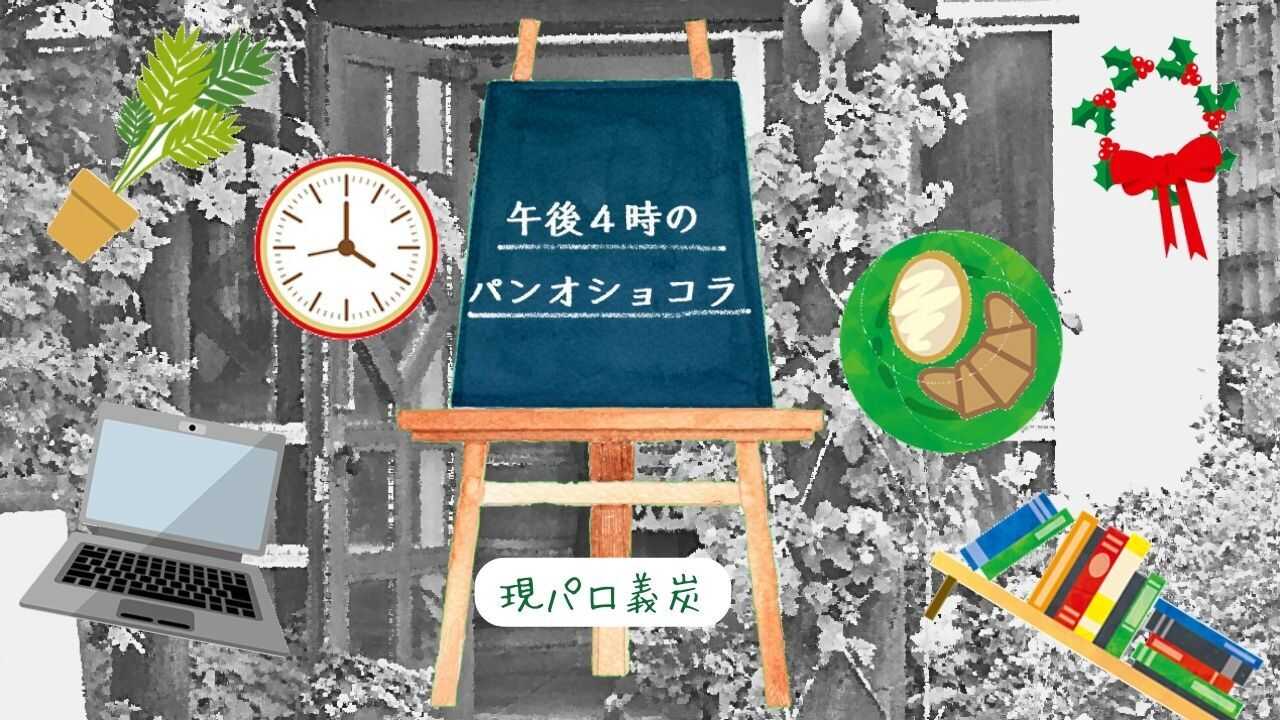──真滝先生に、謝らなくちゃいけないことがあります。俺は、真滝先生に嘘をついてました──
読み進めるうちに現れたその一文に、義勇は小さく眉を寄せた。嘘などつける子には思えないのだが、なにがあったのだろうか。
──真滝先生には、俺の好きな人のことを何度か手紙で教えたことがありますよね。ごめんなさい。本当は、その人のことなんて、俺は全然知らなかったんです。
今まで書いていたのは、俺の想像です。初めて真滝先生に手紙を出してから今まで、俺はその人に逢えませんでした。手紙に書いたのは、もしもその人に逢えたらっていう想像ばかりでした──
そうだったのか。
義勇は今まで貰った手紙の内容を思い返す。
優しくその人に笑いかけてもらえるだけで幸せだ。俺のことを心配して、厳しいことも言ってくれるのが嬉しい。誰にでも優しいけれど、ちょっと口下手でぶっきらぼうだから、誤解されやすい人。そんなところも大好きだから、俺が傍にいてあげたい。
嬉しげに綴られたそれらは、全部、この子の想像から生まれたものでしかなかったのかと思うと、やけに切なかった。義勇が、錆兎との恋を想像して書き連ねた言葉を読みながら、この子もまた、逢えないそいつとの恋を想像して過ごしたのだ。
──でも、もう二度と逢えないのかもしれないと思ってたその人に、今年の春に逢えたんです! 俺はビックリしちゃって、変な態度をとったと思います。だからその人に嫌がられちゃって、すごく悲しかった。
その人は、俺の想像以上に優しい人で、俺の想像通り口下手で誤解されやすそうな人でした。真滝先生が書く小説のなかの人に似ています。もしかしたら、真滝先生にも似てるんでしょうか──
恋しい相手との再会の様子に、義勇も読みながら一喜一憂する。
登場人物と義勇が似ているのだろうかという問いかけには、そうかもしれないと声にせず答えて微笑んだ。
義勇が書くヒロインや主人公は、義勇の想いの代弁者であることが多いから。たしかに義勇に似ているかもしれない。
この子の恋のお相手が自分に似ているというのは、なんだか申し訳ない気もするが、それ以上に面映ゆかった。
──俺はあんまりその人には好かれてません。むしろ嫌がられてると思います。それでもその人のことがやっぱり好きです。その人のことを知るたびに、どんどん好きになっていきます。俺の想像なんかより、もっとずっと素敵な人です。
だから少しでも好きになってもらいたくて、その人の役に立ちたくて、がんばってるつもりなんですけど、うまくいかないみたいです。
だけど、この前、とうとうその人に告白しました──
それはまたがんばったんだなと、感嘆する。今までの手紙では、見ていられるだけでいい、それだけで幸せだと、恋を実らせるつもりはなさそうだったのに。
──勘違いだって言われました。憧れるのはやめろとも。自分のことを悪く言って、俺に諦めさせようとするその人から、悲しい匂いがしてました。俺は鼻が利くんです。だからその人がひどい言葉を言いながら、悲しんでることがわかりました。だから、好きになってもらえるようにがんばるって言ったんですけど、その人には好きな人がもういて、ほかの人を好きにはならないって言われました──
ドクリと、鼓動が跳ねた。
まさか。そんなことが、あるわけがない。
便せんを持つ手が小さく震えた。
思い浮かぶのは、澄んだ赤い瞳から、キラキラときれいな涙をこぼしていた、幼くも凛とした子供。
その涙が、眩しかった。
いつも素直な言葉で義勇の背を押してくれる、小さな読者。義勇の小説の、多分、一番の理解者だろう、この子。もしかして。鼓動が知らず早まる。
──それでもやっぱり俺は、その人が好きで、できれば恋人にしてもらいたいと思ってます。でも、その人が好きな人と恋人になるのを応援したい気持ちもあります。変でしょうか。だけど真滝先生の小説の恋人同士みたいに、その人が幸せになってくれたら、俺もそれだけで幸せなんです。
俺のことを好きになってほしいけど、諦めたくないけど、その人が幸せになってくれるほうが嬉しいって思います。多分、その人が恋人といるところなんて見たら、俺はすごく嫉妬するだろうし、自分が恋人になれたらどんなふうに俺に触ってくれるかとか、想像しちゃったりもするだろうから、きれいな想いで幸せだけ願うのは無理かもしれないんですけど。
真滝先生、それでも俺はその人をずっと好きでいていいですか? その人が好きな人と恋人同士になっても、俺がその人のことを好きな気持ちはきっと消えないと思います。ずっと、ずっと、恋し続けると思います。真滝先生の小説の人たちみたいに。だから、真滝先生に認めてほしいんです。ずっとその人を、冨岡さんを好きでいていいよって。真滝先生だけは認めてくれるって、思ってもいいですか?──
不意に文字がぼやけた。ぽたりと水滴が落ちて、インクを滲ませるのに慌てる。袖口で必死に拭った便せんを傍らに置くと、義勇は封筒を手に取り裏返した。
見慣れた文字で綴られた差出人の名を、震える指で辿る。
竈門炭治郎
おまえだったのか。全部。俺の背を押すのは、いつだっておまえなのか。全部、おまえだったのか。
「炭治郎……」
そっとその名を口にしただけで、胸の奥から込み上げるものがある。その感情はよく知っている。
嫉妬も、劣情も、隠さず書いてきた。それを受け入れて、自分と同じと炭治郎は言う。きれいなだけじゃない恋情を、一途に向けて。きれいな愛情も、生々しい恋情も、すべてたった一人、義勇に向けて。
あぁ、もう認めてしまえ。こんなにも震える胸を、ごまかせるはずもない。
「……俺も、おまえが……恋しい……」