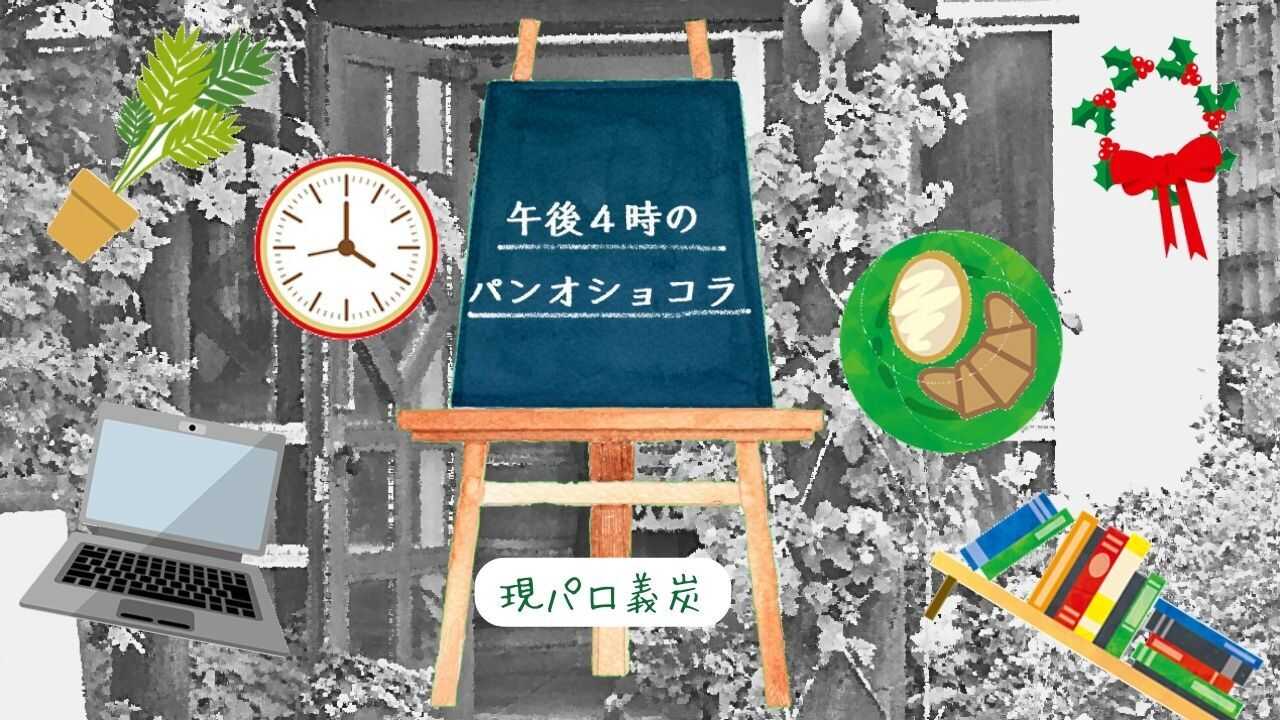錆兎からめずらしく外で逢えないかと言われたのは、まだ残暑厳しい九月半ばだった。
夏休みもそろそろ終わる。一足先に新学期が始まった炭治郎は、大学は夏休みが長くて羨ましいと苦笑していたが、学業と文筆業の二足の草鞋を履く義勇にしてみれば、休暇という意識はあまりない。
来年の今ごろは、卒論の準備に取り掛からねばならないこともあり、きっと慌ただしくなることだろう。遅筆とまでは言わないが、それなりに執筆には時間がかかる義勇にしてみれば、今年の内に依頼された仕事は終わらせてしまいたいところだ。だから長期休暇とはいえ、義勇にとってはそれなりに忙しい日々だった。
それでも、例年に比べればずいぶんと健康的に過ごしているような気がするのは、多分気のせいではないだろう。なにより、寝不足に苦しむことが少なかった。
夏休み前に炭治郎と街中で偶然逢って以来、深夜にハッテン場で相手を探す回数は格段に減った。それは取りも直さず錆兎と逢う回数が減ったことを示している。理由は明確で、道場の師範であり錆兎の祖父でもある鱗滝の体調が、この夏からぐんと悪化したからだ。
老齢とはいえ頑健な鱗滝ではあるが、今年の猛暑はさすがに堪えたのだろう。元々、春先から体調を崩しがちになっていたが、夏前には入院する羽目になり、今も病床にいる。
義勇もたびたび見舞いに行っているが、病室を訪れるたび、鱗滝の鍛え抜かれた体が薄く頼りなくなっていくのを感じずにはいられなかった。
義勇の家族が姉の蔦子一人きりなのと同様に、錆兎にも肉親は鱗滝しかいない。蔦子は他県に嫁いだだけで、逢おうと思えばいつでも逢うことができる。だが、鱗滝に万が一のことがあれば、錆兎は天涯孤独となる。
もちろん、錆兎とてすでに成人したれっきとした大人だ。まだ大学生とはいえ、錆兎ならば自分一人の食い扶持ぐらいどうにでも稼ぐことができるだろう。入院費などについても心配はいらないという錆兎の言に、強がりは見受けられず、その点について義勇はあまり心配はしていない。
それに、錆兎には真菰もついている。学業と見舞いで常より遥かに忙しくなった様子の錆兎だが、細々とした家事などは真菰がマメに手伝いに行っているようで、ずいぶん助かっていると笑っていた。真菰も懐いていた鱗滝や恋人である錆兎の役に立てることを喜んでいるし、二人の交際は順調そのものだ。
錆兎と逢えれば、どうしようもなく嬉しい。けれど、同時にきれいな想いだけで満たしているはずの心に、嫉妬や欲望が泥のように溜まって澱んでいく。
そんな醜い嫉妬や汚らわしい肉欲は、今までならば一晩限りの男とのセックスで発散し消し去ってきたが、今年の夏はそこまでには至らずに解消されている。
指定されたファミリーレストランで錆兎を待ちながら、義勇は知らず自嘲の笑みを口元に刻んだ。
錆兎に逢えないから心の澱みも増えずにいるなんて、欺瞞でしかないことに、もう気付いている。逢えなければ逢えないで、今まではやっぱり嫉妬し、真菰の立場に自分がいることを妄想せずにはいられなかった。今年の夏もそれは変わらなかったが、それでも体調を崩しかねないほどに男漁りをする必要がなかったのは、あの店に頻繁に足を運んでいたからだ。
きっと今の自分は、炭治郎の好意に救われている。
炭治郎が義勇に向ける一途な恋心を知りながら、つれない態度で客と店員の関係を強要している自覚はあった。炭治郎はそんな義勇の身勝手な要求を、自慢の鼻で嗅ぎ取っているのか、好きになってもらえるようがんばると宣言したわりには、決して義勇のプライベートに踏み込んではこない。
コーヒーのおかわりを注ぎにきたときや、義勇の帰り間際に少しだけ、義勇の好物を聞いたりお薦めの本などを知りたがりはする。それでも、義勇の仕事についてや好きな人のことなどは、炭治郎は一度も口にはしなかった。
錆兎に逢えない寂しさも、今ごろ真菰と二人で過ごしているのだろうと思うたびに心に少しずつ溜まっていく澱みも、炭治郎の笑顔を見れば薄れていく気がする。
男漁りをせずとも済んでいるいる本当の理由は、結局のところ、炭治郎による浄化である。執筆に追われるということは、つまりは炭治郎に逢う回数が増えることと同義だ。もはやどちらがあの店に行く理由なのか、義勇にもはっきりしない。
それを自覚してはいるものの、炭治郎に対する自分の感情に、義勇はまだ明確な名をつけられずにいる。
他人と関わることに臆病な自分が、炭治郎とは気負うことなく接することができる。炭治郎と他愛ない言葉を交わすのは、嫌いじゃない。炭治郎の気配があるだけで、心が不思議と穏やかさを取り戻す。それはいったいどうしてなのか。
自分がゲイだということを隠す必要がないからだろうか。そう思いはするが、それだけでは心の澱が消えていく感覚の説明にはならない。
ざわめくファミレスではパソコンを開く気にもなれず、手持ち無沙汰に美味くもないコーヒーを啜りながら、義勇はぼんやりと通りを眺めた。
気が付くと炭治郎のことを考えている。義勇はそんな自分を持て余していた。
以前なら、なにを見てもなにを聞いても、連ねて思い浮かべるのは錆兎の顔だった。
錆兎ならこう言うだろう。錆兎に似合いそうだ。錆兎ならそんなことはしない。錆兎、錆兎、錆兎で、義勇の日々は回っている。
それは今もさほど変わってはいないのだが、錆兎の代わりに炭治郎を思い出すことが、ずいぶんと増えた気がする。今だってそうだ。通りがかる高校生のグループを見て、炭治郎はあんなふうに友達と出かけることはあるんだろうか、義勇に対しては敬語を崩すことがないが友達とはどんな口調で話すのだろうなどと、我知らず考えていた。
「悪い、遅れたっ」
錆兎の声に意識を引き戻され、義勇は慌てて席に着く錆兎を見つめた。多忙と猛暑のダブルパンチはさすがの錆兎にも堪えたのか、前回逢ったときよりも、頬のラインがシャープになったような気がする。
「……痩せた」
「ん? いや、そうでもないぞ。ちゃんと飯は食ってる」
近づいてくるウエイトレスにメニューも見ずコーヒーとだけ言うと、錆兎は置かれた水を一気に飲み干した。
「まだまだ暑いな」
「真菰か?」
「ああ、ほっとくとカップ麺ばかりで済ませるからって、最近は毎日飯を作りにきてくれる」
単語だけで会話が成立するものだから、錆兎といるときの義勇は、勢い言葉足らずに拍車がかかる。
それは真菰や鱗滝にも同様だが、錆兎には二人にとは違う甘えが雑じることを、義勇は自覚している。錆兎が義勇の意を察してくれるたび、ほわりと胸が温かくなって、幸せだと思う。
やっぱり好きだ。錆兎が。錆兎だけが。
どれだけ炭治郎に癒されても、やはり自分の恋心は錆兎にだけ向かっているのだと、義勇は好きという言葉を声にはせずに噛みしめる。
炭治郎じゃない。俺が思い浮かべ、想いを捧げるのは、錆兎だ。
もはやそれは自身に言い聞かせる強さを持っていたが、義勇は気づかない。気づかぬふりを続ける。好きな人は一人きりでいい。ほかにはいらない。
錆兎を好きな気持ちは、どれだけ炭治郎が気に掛かろうと目減りすることはなかった。二人を同時に好きになれるほど、自分は器用じゃない。もしも錆兎への想いを諦める日がくることになったとしても、だからといって炭治郎に心変わりするのは嫌だった。
炭治郎は錆兎の代わりなんかじゃない。錆兎が駄目だから炭治郎となんて、そんな代替品のような扱いをしていい子供ではないのだ。
「このところいい天気だったが、明日は雨かもしれないな」
口元から頬にかけて走る傷跡を、かりかりと指先で掻いて錆兎は言う。湿度が高くなると痒いとよく言っているから、錆兎が言うならきっと明日は雨なのだろう。
「そうか」
傷跡を見つめる義勇の視線に、かすかな罪悪感が滲むのを感じ取ったのだろう。錆兎は呆れたように苦笑した。
「義勇?」
「……わかってる」
おまえのせいじゃない、気にするな。何度言われても、何年この遣り取りを続けても、義勇の心から罪悪感が消えることはない。
けれど、それは錆兎が思うように、錆兎の顔に残った傷跡のことばかりではないからこその、罪悪感だ。
錆兎には決して悟られてはいけない、義勇の浅ましさゆえの罪悪感。その傷こそが、義勇に恋心を自覚させたのだなどと、錆兎は一生知らなくていい。
『お母さんにプレゼントしたいの』
そう真菰が言ったのは小学五年の夏休み。
名前は知らない。けれどとてもきれいな花だったからと、真菰はニコニコと笑っていた。
泊りがけで遊びに行った鱗滝の親類の家で、縁側でスイカをご馳走になりながら話していたときのことだった。
前日に、裏山を三人で探検した折に見つけた池に咲いていた真っ白な花を、母親の誕生日にプレゼントしたいのだと、真菰は言う。錆兎も義勇も、もちろん快く了承した。
仕事が忙しいなか、よく道場におやつを差し入れてくれる真菰の母の誕生日なら、二人だってお祝いしたい。池に咲く花を摘み取るのは苦労しそうだが、苦労したほうが祝う気持ちも伝わるだろうと思った。
今から行けば夕方までには戻れるだろう。軽い気持ちで出かけたものの、池は存外深そうだった。けれど、大輪の白い花はやはりきれいで、目にしてしまえば諦めるのは悔しかった。
畔に生えていた木の枝を錆兎が掴み、錆兎の手を義勇が握って池に身を乗り出すことにしたのは、単純に体重の差だ。
真菰は危ないからやめておけと錆兎が言うのにも、義勇だって納得していた。万が一池に落ちでもしたらいけないし、かといって錆兎や義勇の身体を支える力は真菰にはない。
精一杯手を伸ばしても、どうしても届かなくて。もういいよと真菰が言うのに、少し意地になった。錆兎までもうやめようと言い出すから、ますます引けなくなって。もうちょっとと身を乗り出した途端に、ずるりと足が滑ってバランスを崩した。
池に落ちる瞬間に義勇が見たのは、ともに池に落ちた錆兎の頬が、折れた枝に切り裂かれる様。それでも義勇の手だけは放さずに、必死に義勇を引き寄せようとしてくれた錆兎の顔が近づいて。
散った鮮血に刹那頭に浮かんだ言葉は、きれい、だった。
あの日、目に焼き付いた真っ白な花と錆兎の鮮血は、今もまざまざと思い出せる。
「仕事のほうはどうなんだ? 行きつけの店がなくなってから、結局ヘルプ要請なかっただろ」
「クリスマスあたりに新刊が出る」
「そうか、順調ならいい。けど、なにかあったら言えよ? 時間作るから」
「真菰は?」
いつも通りかすかなからかいを含めた声で聞いた瞬間に、不意に錆兎の空気が変わった。手に取ったコーヒーカップをそのまま下ろして、錆兎は居住まいを正し義勇を見つめてくる。真剣な表情には、わずかばかりの緊張があった。
「錆兎?」
「結婚することになった」
そのときがきたら、きっと失恋したあの日のように、傷つくと思っていた。
ドクン、と大きく鼓動が跳ねて、瞬間息が止まったのは想像通りだ。けれど。
「いつ?」
「クリスマスイブ」
「……今年のか?」
それはさすがに早すぎないかと言外に込めた問いに、錆兎は少し目をうつむかせた。
「爺さんがな、来年の春は越せないらしい」
義勇はヒュッと息を吸い込み、目を見開いた。鱗滝の具合が悪いのは知っていたが、それでも早すぎると思った。
呆然とする義勇にほのかに笑って、錆兎は言葉を紡ぐ。
「外出許可がおりるうちに安心させてやりたい。できれば曽孫の顔も見せてやりたいが、こればかりはな。二人で相談して、昨日、真菰の家に行って挨拶してきた。まだ学生だから、反対されるかと思ったんだが」
「……大喜びだった?」
当たりだと言うように苦笑しながら肩をすくめるその姿が、いつもより大人びていた。
「小母さんも小父さんも、錆兎が大好きだから……」
以前なら、からかい言う声が震えぬよう、自分を抑えることに躍起になっただろう。心に滴る穢れに飲み込まれそうになり、叫びだしたくなっただろう。
なのに、とうとうこの日がきたというのに、義勇の心は凪いでいた。
諦めとも違う不思議な感慨が胸にある。
鱗滝を失っても、錆兎は幸せになれる。真菰と一緒に温かな家庭を築いていける。それが嬉しい。きれいな想いが義勇を微笑ませる。
ずっと心の奥底で望んでいたのは、きっとこんな自分だったのだろう。錆兎が好きだという気持ちを欠片も消すことなく、それでも素直に祝福できる。そんな自分になりたかった。
ずっと、ずっと、好きでいるために。
「どこで?」
「気が早いな。昨日決まったばかりの話だぞ? まだ爺さんにも話してないんだ。細かいことはこれからだな」
「そうか……」
そうか。そうなのか。
なぜだか無性に泣きたくなって、義勇はすっかり冷めたコーヒーに口をつけた。飲み干すまでに涙が乾けばいい。カップで隠されている内に。
幸せだ。心の底から、そう思った。
脳裏に思い浮かんだ鮮血が、炭治郎の赤い瞳と重なって見えた。