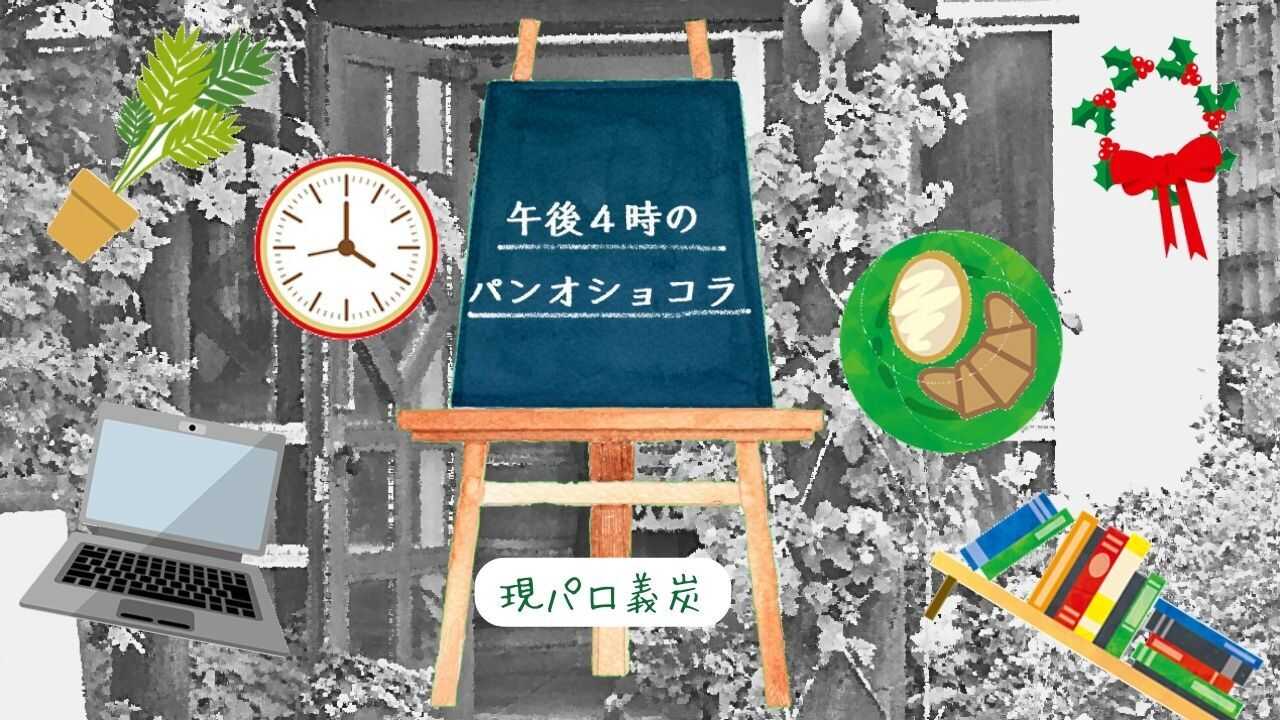真剣な目で義勇を見上げて言う炭治郎は、少し震えている。マズイと直感的に思ったが、炭治郎の言葉を止めることはできなかった。
逢ったことがあるという言葉が、少しばかり気になったこともある。だがそれ以上に、炭治郎の真剣さに気圧された。
「俺は、少し前に父さんが死んだばかりでした。しっかりしなきゃってがんばってたけど、一人でいるときは、つい注意力散漫になることも多くて……そのときも、ぼんやりして人にぶつかっちゃったんです。一所懸命謝ったけど、その人たちは全然許してくれなくって。金を出せって言われました。その日は母さんがどうしても卸先に集金に行けそうになくって、俺が代わりに集金に行ったんです。頑固なお爺ちゃんのやってる洋食屋さんで、現金商売に拘ってる人だったんですよね。それで、俺、何万も持ってたから、絶対に財布を盗られるわけにはいかなくって……」
ぼんやりと思い出したのは、必死に叫ぶ子供の声。ガラの悪い高校生たちに囲まれて、それでも泣き出しもせずに凛とそいつらを睨みつけていた、赤みがかった髪と目をした子供。そうだ、たしかあの子供の耳には、大きなピアスが揺れていた。
「このピアス、父さんの形見なんです。長男として家族を支えるんだって決意表明の気持ちで付けたんですけど、子供がピアスなんてしてるから目立つみたいで、絡まれることもたまにあったんですよね。いつもだったら逃げられたんだけど、その日はすぐに囲まれちゃって、人数が多かったから逃げられませんでした」
失恋したばかりで、苦しくて、つらくて、泣きたくて。グラグラと脳みそが揺れて、胃の腑の底から込み上げる吐き気が止まらなかった。ふらふらと歩いていた自分の目に留まったのは、子供に絡む質の悪い輩。苛立っていた。奴らが上げる下卑た笑いも、下衆な怒鳴り声も、癇に障ってしかたなかった。
「冨岡さんが、助けてくれました。やめろって言ってくれて、あんなにおっかなそうな人たちに睨まれて殴り掛かられても、全然怯んだりしないで、あっという間に悪い奴らをやっつけてくれました」
いっそ殴られ蹴られて、ボロボロになりたかったんだ。苛立ちのままに、誰でもいいから殴ってやりたかったんだ。子供を助けるなんて大義名分すら、あのときの俺の頭のなかにはなかった。
「お礼を言った俺に、冨岡さん、しゃがみ込んで頭を撫でてくれたんですよ? きっと冨岡さんは覚えてないでしょうけど……そのとき、俺、父さんが死んでから初めて人前で泣いちゃいました。初めて、ちゃんと泣けたんです……」
きれいな赤い瞳からポロポロ落ちる涙は、瞳以上に美しく見えて、余計に自分が惨めに思えた。自分のなかの嫉妬や肉欲が、どうしようもなく汚らしく思えて、いっそ俺のほうが泣き出したかった。この子と同じぐらいのころに戻りたい。錆兎への想いを自覚して戸惑いながらも、ただきれいなままの恋心を抱いていられたころに。無性にそう思った。
「優しくて、強くて、憧れました。名前も教えてもらえなくて、すぐに冨岡さんは行っちゃったけど。そのときから俺、ずっと、ずっと、もう一度逢いたいって思ってました。冨岡さんに、もう一度だけでもいいから逢いたいって」
「勘違いだ」
絞り出すように言った声に、炭治郎が戸惑いを露わに首を振る。
「絶対に冨岡さんです! 見間違えたりしません!」
「そういうことじゃない」
言い捨てて歩き出した義勇を、慌てて炭治郎が追いかけてくる。本を買うという目的さえ忘れているのだろう。足早に歩く義勇に必死に追いすがってくる。
「あの、冨岡さん、怒ってますか? ごめんなさい! あんなに人のいるところで俺が、その……」
「……その続きを口にするな。絶対に」
炭治郎を責めるのはお門違いだと、自分でもわかっている。それでも、あの日の自分を美化するのはやめてほしい。ひどく惨めで、ひどく凶暴な感情が沸き上がって、どうしようもなくなってしまう。
炭治郎がいい子なのはもう知っている。あの店の居心地の良さは、炭治郎がいるからこそだと、もう理解している。誰からも愛される子供だ。誰の心にも寄り添う優しさを持った子だ。けれど、義勇は寄り添われたくなどないのだ。
錆兎が好きだ。どうしようもなく好きだ。錆兎を想う気持ちは、ただひたすらにきれいで純粋なものでありたい。だから捨てたのだ、あの日に。炭治郎と初めて逢った、その日に。
「どうして、ですか……? 迷惑なのはわかってます! 俺は男だし、冨岡さんから見たら子供だし……でもっ」
「勘違いだと言った」
どこまでもついてくる炭治郎に、義勇は小さく舌打ちした。炭治郎にも聞こえたのだろう、視線をやればびくりと震えて泣き出しそうに瞳を潤ませている。それでも、義勇を追いかけないという選択肢はないのだろう。義勇の後を雛鳥のように必死についてくる炭治郎が、なんだか憐れに見えた。
足を向けた階段には人気がない。エレベーターやエスカレーターを使う人がほとんどなのだろう。踊り場で足を止め、義勇はようやく炭治郎に向き直った。
「おまえが優しいだの強いだのと言った男は、どこにも存在しない」
「……人違いじゃありません。大好きになった人を見間違えたりしません!」
「あのときの俺は、おまえを助けたかったわけじゃない。ただの八つ当たりだ。失恋して、その憂さを晴らしたかっただけだ。おまえが言うような優しくて強い男なんて、どこにもいない。おまえが見たのは、身勝手で、汚らしい欲を抱えた、惨めな俺だ。そんな男に憧れるのはやめろ」
睨みつけ言ってやれば、炭治郎は小さく息を飲んだけれど、義勇の目から視線を逸らせることはなかった。
「……それでも、俺は嬉しかった。頭を撫でてくれた冨岡さんの手は、優しかった! 冨岡さんが優しい人だって、俺はちゃんと知ってます!」
「それで? おまえはどうしたいんだ。俺と寝たいか。俺に抱かれたいのか、俺を抱きたいのか、どっちだ?」
きっと予想もしていなかった言葉だったのだろう。ぽかんとした炭治郎の顔が、次の瞬間、火のついたように赤く染まった。その純粋さが義勇の苛立ちを掻き立てる。
「したいなら相手をしてやる。どっちでも俺はかまわない。ただし、一度だけだ。俺は同じ男とは二度と寝ないし、二度と逢わない。キスもしない。その代わり、よっぽどアブノーマルなプレイでなければ大概は経験済みだから、どちらでも満足させてやる。それで終わりだ。店にももう行かない」
愕然。今の炭治郎の表情を言い表すなら、まさにそれだ。
義勇と寝ることなど、考えたこともなかった。義勇がそんな不誠実なことを口にするなんて、思いもしなかった。揺れる大きな瞳が語っている。
義勇は視線を逸らせたい衝動をどうにか押しとどめた。炭治郎の悲痛な顔を見つめつづけるには、かなりの気力を要したけれど、今は目を逸らすわけにはいかない。
傷つけたくなどなかったはずなのに、言葉が止められなかった。自分がとんでもない人でなしに思える。失恋したあの日のように。きれいな想いにドロドロとした穢れが滴り落ちて、心が淀んでいく。
もう少し穏やかな言葉を選べばよかった。炭治郎を遠ざけるための言葉に変わりはなくとも、もう少し、炭治郎に優しい言葉を探せばよかった。思っても、口にした言葉は、もう取り戻せない。
けれど、傷ついてしまえと心のどこかで思ったのも、事実だ。
きれいで純粋なだけの恋など、どこにもない。いや、炭治郎が今義勇に向けている想いは、きっと昔の義勇と同じように、キラキラ輝くきれいな想いだけなのだろう。だが、いつかは欲に汚れていく。
それでも、炭治郎は自分とは違うのだ。炭治郎は義勇への恋を諦めたなら、きっとごく当たり前に女性に惹かれるようになるだろう。炭治郎に似合いの優しく愛らしい女の子と恋をして、誰の目も微笑ませる、可愛らしいカップルになるに違いない。
ならば、今自分が目を逸らすわけにはいかない。傷ついて、義勇を軽蔑し嫌悪すれば、炭治郎は戻れる。自分のように男の欲望に塗れるなど、炭治郎には似合わない。この子には、明るく晴れた空の下で優しく微笑み合えるような、誰からも祝福される恋愛が待っているのだ。
今、義勇が傷つけ、嫌われさえすれば。きっと。
それなのに。
「俺、あなたが好きです」
なぜ、そんなに真っ直ぐな瞳で、そんな言葉を言えるのか。記憶のなかの義勇はただの幻で、実際は貞操観念など持ち合わせていない誰とでも寝るような男だと、もうわかったんじゃないのか。
見開かれた義勇の目を真っ直ぐに見つめたまま、炭治郎は静かに微笑んでいた。そんな笑みを浮かべると、存外大人びて見えるのだなと、場違いにも少し見惚れた。
「冨岡さん、自分を悪く言って俺に嫌われようとしても無駄ですよ? だって俺、冨岡さんがとても優しい人だって知ってますから」
なにを根拠にと顔をしかめても、炭治郎は笑みを崩すことはなかった。その眼差しには、いっそ労りと呼んで差し支えない温かみがある。
「それに、ビックリはしたけど、嬉しいです。冨岡さんが男の人とそういうことできる人なら、俺にだってちょっとぐらいはチャンスありますよね? 俺だって男だし、その、冨岡さんとエッチなことしてみたいって思ったことぐらい、あります。よ、よくわかんないから、あの、キス……とか、さ、触ってもらうのとか、それぐらいしか、想像したことないですけど……。だから、もし冨岡さんが俺としたいって思ってくれるなら、俺も、その……冨岡さんと、したい、です」
恥ずかしそうに頬を染め口ごもりながら、それでも炭治郎は視線を逸らさない。
「でもそれは、冨岡さんの恋人としてが大前提です。一度だけじゃ嫌です。二度と逢えないなんて絶対にごめんです。だから、冨岡さんにも好きになってもらえるよう、俺、がんばりますね!」
なんでそうなる。
今度は義勇が愕然とする番だった。まさか自分の淫らな性生活の片鱗を知ってなお、こんなにも実直に告白してくるなど、誰が思うものか。
「……俺は、恋人は作らないし、いらない」
「気が変わることだってあるかもしれないじゃないですか! そのときに俺を選んでもらえるようにがんばります!」
「俺が好きなのは、今までも、これからも、たった一人だ。おまえをそういう意味で好きになることはない」
大きく目を見開いて動きを止めた炭治郎は、もしかしたら、先ほどの義勇の言葉以上にショックを受けているようだった。好きな人、と小さく呟く声にも力がない。
「……冨岡さんは……好きな人がいても、違う人とエッチなことができるんですね……」
「幻滅したか?」
多分に自嘲を含んで言い捨てた声は、それでも常と変わらぬ響きをしていた。表情だってきっと傍目には変わっていないだろう。感情が表に出にくい義勇の心の内側を、過たず悟れる者など、数人しかいない。
だから炭治郎も気づくはずがないと思ったのに。
「冨岡さん、今、悲しいって思いました?」
小さく鼻をうごめかせて、炭治郎はことりと小首をかしげた。気遣わしげな視線を向ける瞳は、それを確信していることを義勇に伝える。
「……なぜ、そんなことを」
「俺、鼻が利くんです。冨岡さんの匂いは淡すぎて、よくわからないことも多いですけど、でも、嬉しそうとか悲しそうなのは、ちょっとはわかります。今、冨岡さんからはちょっぴりだけど悲しんでる匂いがしました」
そんな馬鹿なことがあるものかと切り捨てられなかったのは、同じ特技の持ち主を知っているからだ。剣道の師範の鱗滝がそうだ。まだ錆兎や真菰が義勇の感情を悟り切れずにいたころ、鱗滝ばかりが義勇の言いたいことをちゃんとわかるのが悔しいと、二人が羨んでいたのを覚えている。
だから、炭治郎の言葉は事実なのだろうと、義勇は小さく溜息をついた。
「あ! あの、だから俺、本当は初めて冨岡さんが店に来てくれたとき、冨岡さんが俺のこと嫌がってるの、わかってました。ごめんなさい……。でもっ、やっと逢えたから……あのまままた逢えなくなるのなんて、絶対に嫌で! けど、やっぱり迷惑だったですよね……ごめんなさい」
「……今さら」
「ですよね……。もっと前に、ちゃんと謝らなきゃいけなかったんですけど」
どうしてそうなると、ちょっと眉を寄せるが、しょんぼりと俯いた炭治郎は気づかない。なるほど、言葉にしなければ伝わらないことも多々あるようだ。鱗滝との違いは人生経験の差だろうか。
ともあれ、もう義勇は、炭治郎を傷つけ遠ざける気は失せている。少なくとも、今は。
この子は無理に遠ざければますます追ってくるだろうし、義勇とは違い、性的な欲望にも自浄作用が効くようだ。それなら無下に傷つける必要もあるまい。
「今さらそんなことを謝る必要はない。べつに今はおまえを嫌ってなどいない」
「えっ!? じゃ、じゃあっ」
「だからといって好きだとは言ってない」
「……ですよねー……」
くるくると変わる炭治郎の表情は、もしかしたら義勇の心の底に溜まっていく澱みさえ、浄化する効果があるのかもしれない。そんな馬鹿なことを考えて、義勇は吐息だけで笑った。
途端に炭治郎が顔を真っ赤に染めた理由はわからないが、炭治郎のそんな表情の変化を自分が楽しんでいるのは確かだ。
この子が自然に自分から離れていくまでは、このままでもいいかと、義勇は思う。
無理に傷つけることはない。炭治郎はまだ恋を知ったばかりの子供なのだ。今はまだ、きれいな想いだけ心に抱えて、初恋を堪能すればいい。その相手が自分だというのは、少しばかり申し訳ないけれど。
「……人が来る」
「あ、あの……っ」
階段を上りだした義勇の背にかけられた炭治郎の慌て声に、義勇は少しだけ振り向いて、視線でこないのかと問いかけた。ぱちりと一つまばたきして、パァッと顔を輝かせた炭治郎が駆けよってくる。
「買い物お付き合いしてもいいですか?」
「……好きにしろ」
少しだけ優しい気持ちになって言えば、愛想の欠片もない声であっても、炭治郎は嬉しげに笑う。炭治郎が笑うたび、不思議なことに心の澱が消えていく。
今夜は溝浚いは必要なさそうだ。
身勝手さに浮かんだわずかな自嘲も、炭治郎の柔らかな話し声を聞いている内に、薄れて消えた。