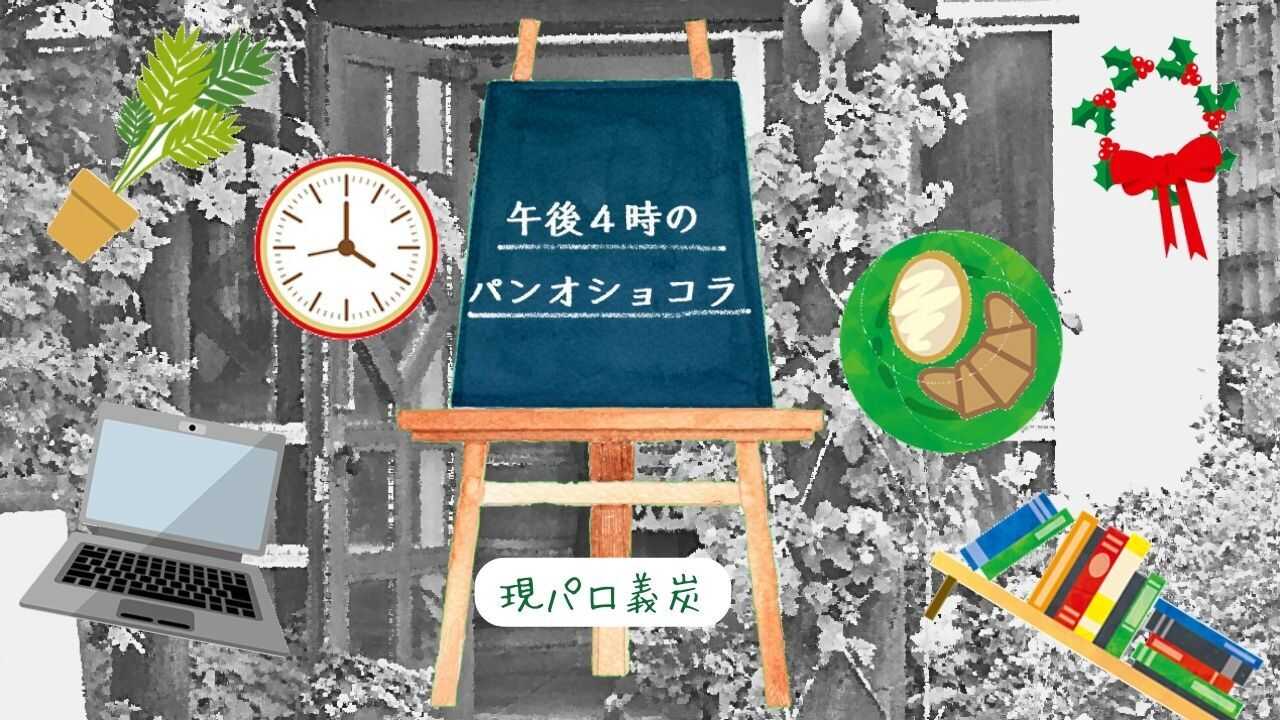それからすでに三ヶ月。もうすっかり義勇は竈門ベーカリーの常連である。パンオショコラのほかにも気に入りのパンはいくつか増えて、季節の移り変わりすら、期間限定のパンで知るほどには、義勇は頻繁に竈門ベーカリーに足を運んでいた。
炭治郎との距離感は相変わらずだ。炭治郎の瞳から義勇への好意は消えることがないし、義勇は気付かぬふりを続けている。
義勇の仕事について、炭治郎は決して詮索してこない。長時間居座りひたすらキーボードを叩く義勇に、いろいろと疑問もあるだろうが、店員と客の節度を保とうとする姿勢を貫いている。
だから、義勇にばかり一方的に、炭治郎の情報はもたらされる。
義勇が炭治郎に聞いたわけではない。炭治郎が高一だとか、父を亡くしているとか、六人兄弟の長男だとか。そんな諸々を義勇が知ることになったのは、ひとえに炭治郎が、常連客達から愛される看板息子だからである。
長く通えば自然と炭治郎とほかの客との会話も耳に入ってくる。聞こえてきた会話の端々を繋ぎ合わせて想像で捕捉すれば、いつの間にやら炭治郎の趣味が掃除であることだとか、好物はタラの芽だなんてことまでも、義勇の知るところとなっていただけのことだ。
聞き耳を立てたことなど断じてないが、炭治郎の声は大きい。いつでも元気いっぱいに、常連客と楽しげに会話する。集中しきっているときには意識に止まることはないのだが、ふと集中が切れた折に聞こえてくるものはしかたがないじゃないか。
そろそろ季節は夏になる。大学生でもある義勇よりほんの少し先に、高校生の炭治郎は夏休みに入る。聞こえてくる会話から、炭治郎は夏休みでも毎日店に出る予定であることを知ったのも、常連客との会話からだ。義勇が店を訪れる曜日は決まっていないので、たまに炭治郎がいないことだって当然あったのだが、夏の間は毎回炭治郎の顔を見ることになりそうだ。
たしかに、そう思っていたのは事実だ。けれどそれは店でという意味であって、まさか偶然にも街中で顔をあわせるなんてこと、想像することすらなかったのに。
「冨岡さんっ! 偶然ですね! あの、冨岡さんも買い物ですか?」
入院中の剣道の師範への見舞いを買おうと、足を運んだ駅ビル内の書店。時代小説の文庫本を物色していた義勇の耳に飛び込んできた炭治郎の声は、やっぱり大きかった。注目を集めるのが苦手な義勇にしてみれば、勘弁してくれと言いたい。
それでも小走りに近寄ってくる炭治郎を無視するわけにもいかず、義勇は視線だけを炭治郎に向けて答えた。
「あぁ」
会話の接ぎ穂を与えない義勇に、炭治郎はめげることがない。それじゃまた、ということにはならないだろうとは思ったが、やはり炭治郎は義勇から離れる気はないようだ。
「時代小説お好きなんですか? お薦めの作家さんていますか? 俺も読んでみたいです!」
「……声が大きい」
静かに言えば、炭治郎はバッと両手で自分の口を塞いだ。恐る恐る窺ってくる目はどうしよう言わんばかりに見開かれていて、元々大きい目が今は真ん丸に見える。なんだか小動物のようだ。思わず小さく噴き出した義勇に、炭治郎はぱちくりとまばたきして、次の瞬間、なぜだか耳まで真っ赤になった。
そろそろと手を下ろしたものの、言葉が出ないらしく、はくはくと唇をおののかせている。
「見舞い用だ」
「え? あ、冨岡さんが読むんじゃないんですね。ご家族の方ですか?」
炭治郎の表情はくるくると変わる。真っ赤になっていた顔は、今は心配げに少し曇っている。
その目に宿る熱さえなければ、たいへん好ましい少年なのだ。竈門炭治郎という少年は。
欲の対象としてではなく、人として好ましいと思う。真っ直ぐな気性も、朗らかな笑顔も、客や時折店に顔を出す弟妹に見せる気遣いも。義勇が目にした店での炭治郎は、ごく普通の、とても優しい高校生だ。
冷静な第三者的感想を述べるなら、容姿のほうも可愛らしい顔立ちをしていると思う。たまに店に顔を出す妹は、誰が見ても美少女と言って差し支えないが、炭治郎も妹とよく似た面差しをしている。
炭治郎は快活な笑顔が印象に残りやすいので、元気だとか朗らかという言葉で褒められることが多いようだが、稀に浮かべる静かな表情を見れば、印象以上に目鼻立ちが整っていることに気づく。額に痣があるのが難点だという者もいるだろうが、義勇からすればその痣も、愛らしいチャームポイントの一つに思えた。
というよりも、炭治郎の性格も外見も、難癖をつけるほうが難しいと思うほどには、もう義勇も炭治郎のことが気に入っている。出逢いの場が違えば、共寝の相手に選んでもいいと思うぐらいには。
だが、そういった目で見るには炭治郎は純粋すぎた。自分の汚い欲の対象におくことなど、想像のなかですら許されないと思えるほどに。
炭治郎が義勇に向ける感情は、もはや恋であることは疑いようがない。だからこそ、義勇は気づかぬふりをするしかなかった。
炭治郎は今のところ、義勇に告白する気はないようだ。見つめていられるだけで幸せだと、大きな赤い目は雄弁に語る。
きらきらと輝いて、義勇を映し嬉しげな微笑みにたわむ、炭治郎の目。その目で見つめられるたび、狡いことをしていると自己嫌悪を覚えるようになったのは、いつからか。
そんな目で見るな。俺に惚れても無駄だ。さっさと諦めろ。そう言ってやれば、炭治郎はきっと泣くのだろう。ひどい仕打ちに傷つくのだろう。けれど、本当はそのほうが炭治郎にとってはいいのだ。今は傷ついたとしても、報われない片恋などさっさと捨ててクラスの可愛らしい女の子とでも当たり前な恋愛をするほうがいい。きっと炭治郎にとっても、炭治郎を愛する人たちにとっても、それこそが幸せだ。
いくら世論がジェンダーフリーを叫ぼうが、GLBTへの理解が進もうが、しょせん市井の人々は狭い世間に生きている。テレビを見ながら、画面に映るゲイやレズビアンのインタビューに好意的な言葉を口にしても、自分の周りの人間がゲイだと知れば心穏やかにはいられないはずだ。
当人たちが幸せなら同性同士であれかまわないじゃないかと、綺麗事を述べたところで、いまだ偏見の目は多く、HIVについての誤解なども消えはしない。フィクションと現実は違うのだ。
わかっているのに、義勇はそれを口にしない。炭治郎がなにも言わないのをいいことに、気づかぬふりで炭治郎の瞳から恋の熱が消えるのを、ただ待っているだけの卑怯者だ。自分で引導を渡す勇気を持たない、臆病者だ。
「先生だ」
「先生……学校のですか?」
問い返す声にはもう答えず、義勇はちらりと炭治郎を見下ろす。おまえの買い物はいいのかと視線だけで問いかけてみれば、炭治郎はすぐにそれに気づいたようだ。
「俺は好きな作家さんの新刊を買いにきました。今日が発売日なんです。真滝勇兎さんって人の本なんですけど……冨岡さんは知ってますか?」
ごふっ、と、思わずむせたのは、致し方ないところだろう。
「冨岡さんっ!? 大丈夫ですか?」
突然咳き込んだ義勇に慌てながら、炭治郎が背をさすってくれたが、正直それどころじゃない。
「おまえ、その名前……」
「真滝勇兎さんですか? あ、もしかして冨岡さんも好きだったりしますか!? 俺、恋愛小説って読んだの真滝さんのが初めてだったんですけど、なんだかすっごく胸に刺さるっていうか、共感できて! 凄くファンなんです!」
赤面しなかった自分の顔を褒めたい。これよりよっぽど気恥ずかしい言葉で綴られたファンレターだって貰ったことがある。けれど、面と向かって絶賛されたのは、錆兎たち身内ともいえる者を除けば初めてだ。烏間からはファンなのだと聞いただけで、感想までは聞かされていない。それだけでもじゅうぶん気恥ずかしく思ったというのに。
そこまで考えて、義勇はふと浮かんだ疑問に、つい眉をひそめた。
「いつだ」
「はい?」
「いつ、読んだ?」
そうだ、烏間は竈門ベーカリーの常連でもあった。ならば、炭治郎に義勇の本を薦めた可能性は高い。まさか義勇が当人だとまでは言ってないとは思うが、もしも炭治郎が烏間同様にエッセイにまで目を通していたなら、義勇が真滝勇兎だと推理するだけの材料はもう揃っている。
「えーと、たしか……中学に上がったころかな」
思い出すためか少し首をかしげて言った炭治郎は、なぜだかそれを口にした途端に、ほわりと頬を染めた。
「す、好きな人ができて、その……最初、初恋だって気づかなかったんですけど……」
訥々と炭治郎の言うことには、偶然出逢っただけの、二度と逢えないかもしれない人への初めての感情に戸惑っていたときに、書店で見かけたタイトルに惹かれ衝動買いしてしまったのだという。『もう一度逢いたい』まさしくそれは当時の炭治郎の気持ちそのままで、手に取らずにはいられなかったのだと。
それまではファンタジーや児童文学ぐらいしか読んだことがなかった。けれど、初めて読んだその恋愛小説に書かれていた主人公の恋心は、自分がその人のことを思い出しているときの心情そのままで、そこでやっと自分が恋をしていることに気が付いた。すぐにほかの本も探して、残りの小遣いをはたいて買ってみたけれど、やっぱり真滝が書く主人公の恋は自分の心そのままだった。それ以来、真滝勇兎の新作が出るたび、必ず買っている。どの作品も自分の気持ちと重なる部分が多くて、何度も読み返しているぐらいには、真滝の作品が好きだ。
ぼそぼそと、常にはない小さな声で語る炭治郎の顔は真っ赤で、初々しい恋心を今も抱えているのだと、言葉にせずとも伝わってくるようだった。
そのタイトルはまさしく義勇のデビュー作だ。高一の炭治郎が中学に上がったばかりというなら、初版であることに間違いはない。しかも、平台に並ぶ新刊ではなく、棚差しの数多ある本のなかから、おそらくはたった一冊だけあった義勇のその本を、炭治郎は手にしたのだ。
偶然にもほどがあるだろうと、義勇は思わず天を仰いだ。
烏間と炭治郎にあらぬ疑いをかけてしまったが、もう疑う余地はない。炭治郎は義勇のデビュー作からのファンなのだ。たいへんめずらしいことに。
それは俺だと言ってやるつもりはないが、ますます邪険にするのが躊躇われることになったなと、義勇は遠い目で虚空を見つめた。こんなにも熱烈に応援してくれている読者だと知ったうえで、手酷い言葉を投げつけ袖にするような人でなしには、どうしたってなれそうにない。これはもう、まかり間違っても炭治郎が告白などしてこないよう、心底祈るよりほかなさそうだ。
だが、そんな義勇の思惑など知らぬ炭治郎は、意を決したようにじっと義勇を見上げてきた。
「あの、冨岡さん。俺、小学校を卒業したころに、冨岡さんに逢ったことがあるんです」