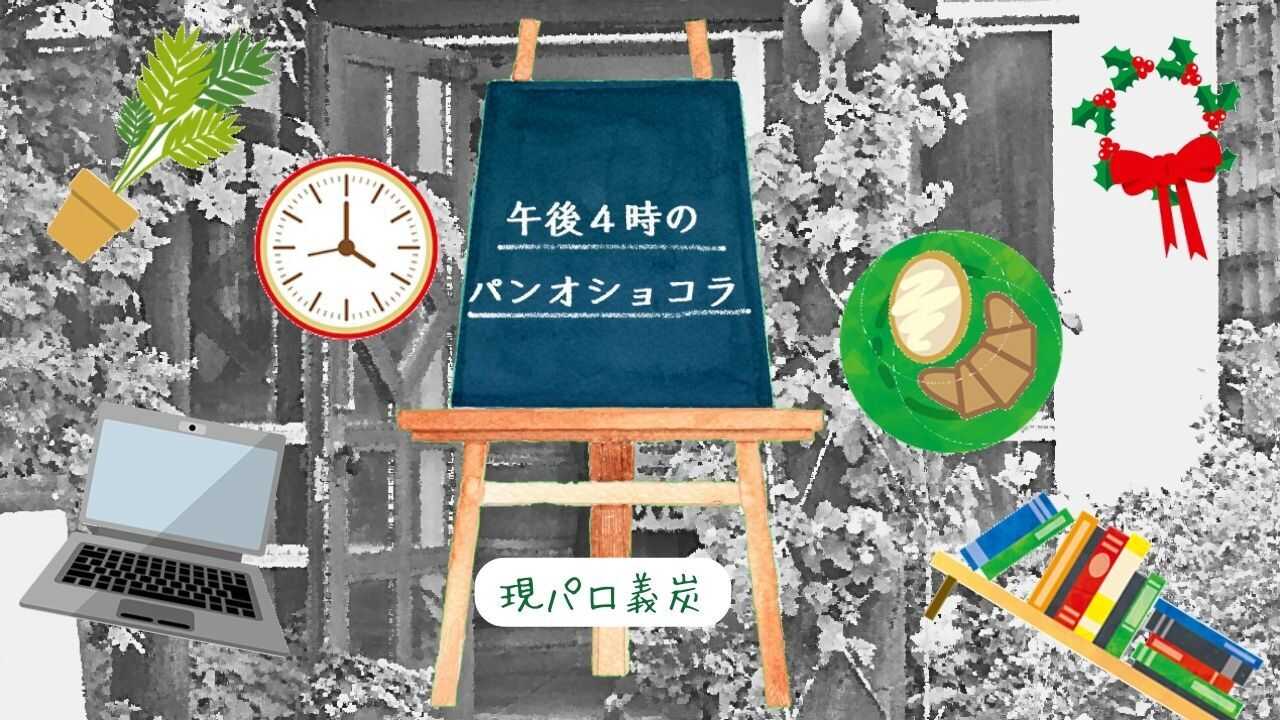過保護だとわかっているが、姉としてはやっぱり妹の想い人がどんな子なのか気になる。妹が恥ずかしがりながら言葉少なく教えてくれたかぎりでは、とても優しくて思い遣りに溢れた元気な子らしいが、一度くらいは自分の目でも見てみたい。ベーカリーの看板息子だというから、お店に行けば逢えるはず。お店自体も評判らしいし、最近マンネリ化している差し入れのレパートリーを増やすにもちょうどいい。偶然にも担当作家と逢う用もあるし、店のカフェスペースで打ち合わせすれば一石二鳥どころか万事解決だ。
そんなことをつらつらと語り、それで冨岡さんはどうして竈門ベーカリーに行きたくなかったんです? そのご様子ならよく知ったお店なんじゃないんですか? と、笑顔で圧をかけてくるしのぶを、どう躱したのか義勇はよく覚えていない。しのぶと別れても戸惑い狼狽えたままだった帰路で、事故を起こさなかったのは幸いだ。
記憶は曖昧ながら、常連だということはもうバレたのだろう。根掘り葉掘りとまでは言わないが、炭治郎のことをやたらと聞かれた記憶はあるから。
帰宅し茶の間にどかりと座り込んだ義勇の口から、もう何度目かわからない溜息がこぼれる。
今は持ち帰った手紙の束にも目を通す余裕がない。申し訳ないが明日以降にでも読ませてもらおうと、紙袋を壁際に押しやって、義勇は知らず頭を抱えた。
しのぶの妹の片想いの相手とは、考えるまでもなく炭治郎以外ありえない。
その事実になぜ自分はこんなにもショックを受けているのだろう。錆兎から真菰との結婚を告げられたときとは比べ物にならないほど、義勇の心は乱れている。
人見知りで引っ込み思案なしのぶの妹に、炭治郎はまったく臆することなく笑いながら話しかけ、なにかにつけて気を遣ってやっているらしい。きっと、不愛想で無口な義勇に対するのと、まったく同じように。
誰の目にも美女であるしのぶの妹だ。たいそう可愛い子であるのは疑いようがない。面倒見がよく思い遣り深い炭治郎と、自分の意思を上手く口にできないというしのぶの妹は、きっと誰の目にもお似合いなはずだ。
誰の目にも微笑ましく映る、初々しい恋人たち。誰からも祝福される炭治郎とその恋人。それを自分は望んでいたんじゃないのか。
炭治郎は自分とは違う。誰にも恥じることのない、ごく普通の、当たり前の恋愛が、炭治郎には似合う。
今はどんなに義勇に向かって恋情を募らせようが、いずれは傷つき疲れ果て、自分が間違っていたことを知るだろう。ならば、その前に道を正してやればいい。そう思っていたはずだった。
だからこそ義勇は、いまだ炭治郎に優しい言葉などかけずにいる。ことさらにそっけない態度を装い、ただの客と店員だと思い知らせるような素振りを続けている。
炭治郎がそのたびに少し切なげな顔をするのは気づいているけれど、優しい言葉をかけて、炭治郎の恋心に燃料を与えてやるわけにはいかなかった。
炭治郎の胸の内で燃える義勇への恋心は、きっと暖かいのだろう。熱く燃え盛ることを当の義勇から許されず、それでも消すことなくゆらゆらと揺れる小さい火だ。小さいけれど頼りなさはなく、震える者を優しく温めるような火だ。
わかっているから、義勇の一言でたやすく燃え上がるだろうその火に、油を注ぐような真似をしてはいけない。
炭治郎は、錆兎の代わりじゃない。
錆兎に対して抱くわけにはいかない劣情を、今までずっと、義勇は一晩限りの名前も知らない男たち相手に吐きだしてきた。口にするのも憚られる不道徳な性生活は、それでも今までの義勇にとっては必要なことだったから、今さら悔やむ気などない。
だが炭治郎にだけは、そんな暗く澱んだ劣情を向けてはいけないと思う。
錆兎から得られぬ温もりを、炭治郎に求めてはいけない。炭治郎を錆兎の代わりにすることも、ましてや誰でもいいと選ぶ相手になんて、したくはなかった。
世間的には性に対する好奇心旺盛な年ごろではあるが、炭治郎は、そういった欲望とは無縁なのではないかと思うほどに初心だ。もちろんそれなりに興味はあるのだろうし、実際、義勇との性的な触れ合いを想像したことがあると、義勇本人にも言っていた。
それでも、それはきっと一般的な男子高校生よりずっと幼く、曖昧とした妄想でしかないだろうと思う。そんな炭治郎に劣情を向けるなど、あまりにも酷だ。
いい機会じゃないか。今度炭治郎に逢ったら、せいぜい笑って言ってやればいい。可愛い女の子から好かれているらしいなと、付き合ってみたらどうだと、無責任な第三者の顔でひやかしてやればいいのだ。
義勇のそんな言葉と態度に、きっと炭治郎は傷つくだろう。義勇にだけはそんなこと言われたくないと、涙を堪えて唇を噛むのだろう。
たやすく想像できるその顔に、自分のほうこそ傷つくなんて、馬鹿げた話だ。
錆兎への想いは、ひたすらにきれいなだけのものにようやく変わってくれた。これからは錆兎の幸せだけを願って生きていく。それだけでいい。
失恋して以来ずっと望んでいた自分にやっとなれたというのに、なぜ今自分の心には、穢れのような苛立ちが滴り落ちているのだろう。
焦燥や嫉妬、肉欲といった、義勇からすれば穢れとしか呼べないそれら負の衝動は、錆兎への想いから生まれる物だった。きれいな想いは上澄みだ。心の底にはそんなドロドロとした澱みがひっそりと溜まっていく。
だからこそ、今までは溝浚いが必要だった。きれいなままでいようと思うなら、ヘドロのような澱みは取り除かねばならない。
炭治郎としのぶの妹が付き合うことになったとして、それを義勇は喜んでやらねばならない。いや、喜ばしいと思うのが当然だ。出逢った当初ならば、なんの迷いも戸惑いもなくそうしていただろう。
なのに、今、義勇の心には抑えきれない腹立ちが渦巻いて、穢れとなって滴り落ちている。炭治郎の隣に立つ見たこともない女の子に、そこはおまえの場所じゃないと吐き捨て、おまえは俺が好きなんじゃないのかと炭治郎をなじってやりたい。そんな衝動が拭い去れず、心の底に溜まっていく。
その狂おしい衝動には、まだ名がない。名付けたらもう、後戻りできない気がして、名をつけられずにいる。もうわかっているはずのその名を、義勇は決して認めない。
記憶のなかでぼんやりとした像を結ぶ、小さな炭治郎のきれいな赤い目からこぼれ落ちる、清浄な涙のきらめき。あれを穢すわけにはいかないじゃないか。
義勇は深く重い溜息をつき、緩慢な動きで立ち上がった。無理にでも動かなければ、溜まっていく穢れに突き動かされ、衝動的にベーカリーに行ってしまいそうで怖い。
とにかく今はなにも考えずに、ルーチンワークのような日常動作だけしていよう。
それとも、久し振りにハッテン場で相手を探そうか。思い浮かんだ瞬間に、義勇はそれを打ち消した。
錆兎の結婚を穢すような気がして、見知らぬ男との即物的で淫らなセックスなど、今日だけはしたくない。
溝浚いすら叶わない澱みは心の底にドロドロと溜まって、今夜はきっと眠れないだろうと義勇は苦く思った。