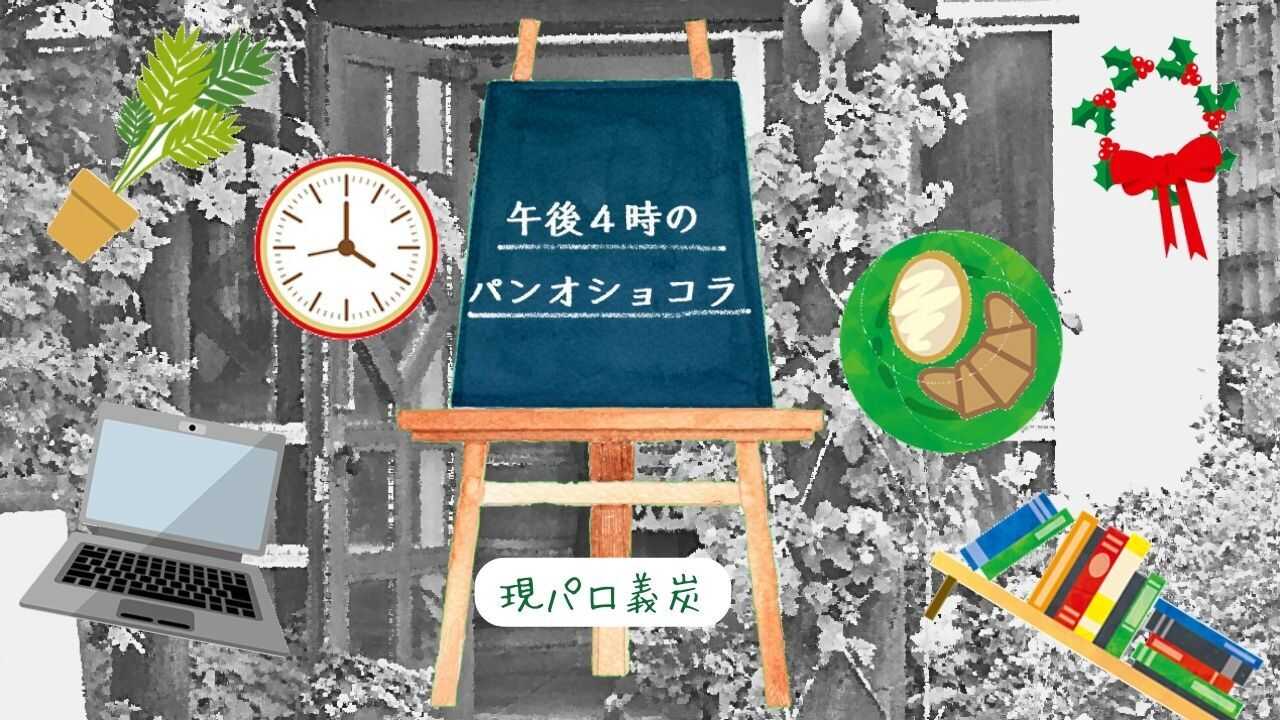ゾクゾクと寒気がする。そのくせやたらと汗が滲み出るのは、熱が上がっているせいだろう。力任せに押さえつけられた脚が痛い。腰もかなり。口にしづらい箇所の痛みは言うまでもない。
自宅の最寄り駅にどうにか着いたものの、運転なんてできる体調ではとうていなかった。よろめきそうになる足で、改札近くにあるコーヒーチェーンに入った義勇は、席につくなり大きく嘆息した。
竈門ベーカリーを出て以来、空きっ腹に流し込んだジンライムのほかに胃に入ったのは、青臭いたんぱく質が少々。不摂生なんて言葉じゃ生温いほど、不健全極まりない食事内容だと、内心で自分を嘲笑う。
胃は空腹を訴えているが、食欲はない。少しでも楽になったらタクシーで帰ろうと、義勇はソファにぐったりと背を預け、口のなかの不快感をコーヒーで胃に流し込んだ。
ひたすらに嫌悪感しか得られないセックスだった。テク無し遅漏のサディストなんて、相手にするもんじゃない。キスされるのを拒否できたのだけが、かろうじて救いと言えるだろう。まぁ、多少拳に訴える必要はあったけれど。
勢い任せの痛みばかり強いセックスも最悪だと思ったが、なにより不快で堪らないのは、うっかり朝まで眠り込んでしまったことだ。
セックスの最中に汗塗れになるのはかまわないが、事後に肌を触れ合わせるのは、全身が鳥肌立つほど気持ちが悪い。抱き締められるのも、抱き締めるのも、浚った澱みをふたたびなすりつけられるようで、不快感しかなかった。
だからいつでも、事が終わればどれだけ相手がねだろうが、さっさと別れて家へと帰っていたというのに、昨夜は苦痛から逃れるように意識を飛ばしたのがまずかった。
朝目覚めて、男の腕に抱きこまれていることに気づいた瞬間の、あの絶望感。思い出したくもないと義勇はきつく眉を寄せた。
痛めつけられた腰が悲鳴を上げるのすら無視して飛び起き、込み上げる吐き気を堪えてトイレに飛び込んだ義勇に、男は不機嫌な声を上げていたが、テク無し遅漏に文句を言う資格などあるものかと言いたい。
胃のなかにはなにもなく、胃液だけが逆流して焼けた喉がまだ少し痛い。キスはしない、セックスも一度だけだと言っておいたにもかかわらず、よろよろと出てきた義勇に、男は次はいつ逢おうかなどと言いながらまるで恋人気取りでキスしてこようとした。男の鳩尾に、力任せに拳を叩きつけたときだけは、気分が良かった。
溝浚いのはずが、まったく気が晴れないのは、体調不良のせいばかりではないだろう。
腹を抑えて呻く男を一瞥すらせず、慌ただしく身支度だけしてホテルを出たものだから、シャワーすら浴びていない。ホテルを出たときに気づいた、奥歯に挟まった陰毛を抜き取るあの情けなさときたら。事後に後始末する気遣いなどあの下卑た男にあるはずもなく、肌に残るべたつきやらごわつきが、今まさに穢れを身に纏っていますと知らしめているようで、なんだか泣きたくなってくる。
病気の一つも持っていそうで生は絶対にごめんだと、ゴムだけはつけさせた自分を、少しだけ褒めたい。なによりも、男の肌の感触と腕の重みがまだ自分の肌に残っているような気がして、叫びたくなるほど気持ちが悪い。
なぜ、こんなにもキスやハグを嫌うのか、理由は明確だ。それらは義勇にとっては、恋人の証のようなものなのだ。
セックスは許してもキスはしないなんて、まるで娼婦のようだと思いはする。けれど、それぐらいは大切にしたっていいじゃないかとも思う。穢れ切った自分にも、恋しい相手に捧げられる初めてがあったっていいはずだ。
そんな日は、決してこないとわかっているけれど。
数えきれないほど男と寝ているくせに、ファーストキスは未経験なんて、なんて馬鹿馬鹿しい笑い話だろう。うっすらと思う間も悪寒は治まらず、これはいよいよまずそうだ。
意を決してタクシー乗り場に向かうべく立ち上がろうとした義勇の耳に、「あれ? 冨岡さん?」という軽やかな声が不意に飛び込んできた。
「あ、やっぱり冨岡さんだ。おはようございます。昨日はうるさくしちゃって、お仕事の邪魔してごめんなさい」
近づいてきたのは、炭治郎の妹の禰豆子だった。私服であるのを見るに、友達と待ち合わせでもしているのだろうか。そう言えば今日は土曜日かと、今さらのように気づいた。
今はあまり顔を合わせたくない相手だが、禰豆子にはなにも罪はない。あぁ、と小さく応えを返した義勇に、禰豆子の顔が曇った。
「冨岡さん、具合悪いんですか?」
だから昨日はあんなに急いで帰っちゃったの? と、心配そうに言う禰豆子は、炭治郎とよく似ている。
「たいしたことはない」
だからかまうなと言外に込めた意は、禰豆子には伝わらなかったようだ。いや、あえて無視されたのかもしれない。
「たいしたことある顔してますよ。これから出かけるなら、やめておいたほうがいいです。今にも倒れそうだもの」
「……帰るところだ。タクシー乗り場まで行けばどうにかなる」
「タクシー乗り場まで歩けますか? 見た感じ無理そうな気がするんですけど」
たしかに、痛みと発熱で萎えた足は立ち上がることを拒否しているが、それでもここにいたってしかたがない。それは禰豆子もじゅうぶん承知しているのだろう。可愛らしい顔を心配げに曇らせている。
「もう少し待てますか? あと十分ぐらいしたらお兄ちゃんのお友達が来るから、肩を貸してもらいましょうよ。男の人だから冨岡さんを支えられると思うし」
「……悪い」
「いえいえ、困ったときはお互い様です」
いや、そうじゃなく。
人と待ち合わせてどこかに行くなら、そんな面倒をかけるのは悪いから。そう言いたかったのだが、錆兎や真菰なら通じても、さすがに禰豆子には通じなかったようだ。言い直す気力はなく、ましてや一人でタクシー乗り場まで行ける体力も今はなく。背に腹は代えられぬと、義勇は小さくありがとうと呟いた。
それに微笑み返した禰豆子は、義勇の向かいの席に座ると、すっと表情を改めまじまじと義勇を見つめてきた。
「冨岡さん、具合が悪いときにお話しするのは申し訳ないんですけど、少しだけ私の話を聞いてもらってもいいですか?」
少し緊張して聞こえる声だが、義勇を見つめる瞳は優しかった。
義勇がかすかに小首をかしげたのを了承ととったのか、禰豆子は一度小さく息を吐くと、ゆっくり口を開いた。
「昨日、冨岡さんが帰った後、お兄ちゃんがお友達に言ってました。その席だけは駄目だって。冨岡さんが座っていてもいなくても、あの席は冨岡さんだけの席だって……冨岡さんのためだけに用意したあの席には、ほかの誰も座られたくないからごめんって、お友達に頭下げたんです。その席だけが、自分が冨岡さんと繋がっていられる唯一の場所なんだって、お兄ちゃん、泣き出しそうな顔で言ってました。冨岡さんと一緒にいられる場所を、俺から奪わないでって……お兄ちゃんのあんな顔、初めて見ちゃった」
お父さんのお葬式だって、私たちを励まそうとして必死に笑ってたのに、冨岡さんと逢えなくなるだけでお兄ちゃんは泣いちゃうみたい。禰豆子はそう言って、少し悔しそうに笑う。
「……お兄ちゃんの気持ち、冨岡さんは知ってるんですよね?」
真っ直ぐに義勇の目を見て言われた言葉に、義勇は目を見開いた。幻聴だと思いたかったが、禰豆子の視線はそんな楽観を許さない。
「……なんで」
「だって、あの席を作った日に、お兄ちゃんから聞きましたもん。好きな人の役に立てそうなんだって、お兄ちゃん大興奮だったんですよ? 我儘だけどあの席はずっとその人の予約席にしてほしいって、お兄ちゃん、お母さんに向かって言ったの。俺の好きな人は男の人で、だからきっとお嫁さんや孫の顔はお母さんに見せてあげられない。好きだって告白したって、男の俺があの人に好きになってもらえるわけないけど、今までもきっとこれからも、あの人のことだけが好きだ。だから、ごめんなさい、って」
親に謝らなければならない恋愛感情なんて、捨ててしまえ。
もし自分がその場にいたら、そう怒鳴っていただろう。そんな一途に思ってもらえるような男じゃない。幸せになれる道が目の前にあるのに、くだらない男に騙されて、むざむざそれを捨てる気か。そう叱り飛ばしていただろう。
顔を歪めた義勇に、禰豆子は困った顔で少しうつむいた。
「こんなこといきなり言われても、冨岡さんだって困っちゃいますよね。でも、お兄ちゃんわかりやすいから、冨岡さんももうお兄ちゃんの気持ちなんて知ってたでしょ? 男のお兄ちゃんに好かれたって、冨岡さんには迷惑でしかないんだろうなって私もわかってます。だから冨岡さんも、お兄ちゃんにはあんまり優しくしてくれないんだろうけど……でも、お店にぐらいは来てあげてください。お兄ちゃんはそれだけで幸せそうだから」
お願いしますと頭を下げる禰豆子に、やめてくれと叫びたかった。
おまえが今頭を下げて懇願している男は、ほんの数時間前まで見ず知らずのろくでもない輩相手にだらしなく足を開いていた、どうしようもなく汚らしい奴なんだ。炭治郎のきれいな想いを捧げられていい奴じゃないんだ。禰豆子に心配される資格だってない。
そんな男に恋なんてするな。炭治郎にはきれいで優しい恋が似合う。それは禰豆子だってわかっているだろうに。
「なぜだ……? 俺が行かないほうが、炭治郎のためになる。昨日一緒にいた子は、炭治郎が好きなんじゃないのか? 男相手に恋なんてしなくたって、あの子のほうが炭治郎には似合う……俺なんかやめろと、反対してやるのが炭治郎の身のためだ」
絞り出すように言えば、禰豆子はこともなげに笑った。
「反対なんてしませんよ。男の人だろうと、お母さんよりずっと年上のお婆ちゃんだろうと、お兄ちゃんさえ幸せなら、私たちはどうでもいいんだもの。いつでも家族のため、私たちのためって、自分のことは全部後回しにするお兄ちゃんが、初めて我儘を言って、冨岡さんがお店に来るたびに凄く幸せそうに笑うんですもん。反対する理由なんてないです」
禰豆子の笑顔は晴ればれとすらしていた。本心から炭治郎の恋を応援しているのが、その笑顔でわかる。呆然とする義勇に、その笑顔はすぐに苦笑めいたものに変わった。
「カナヲちゃんには申し訳ないけど……でも、やっぱり私はお兄ちゃんの恋を応援せずにいられないから。それにね、カナヲちゃん、帰るときこっそり教えてくれたんです。強くなりたかったんだって。お兄ちゃんと一緒にいたら、自分も強くなれるんじゃないかって思ってたんだって……でも、もし今お兄ちゃんが今の自分を好きになってくれても、きっとお兄ちゃんに頼り切って、強くなんてなれなれないままだと思うって、言ってました。自分が強くなってお兄ちゃんに告白できるようになるのが先か、お兄ちゃんの恋が実るのが先か、競争って、カナヲちゃん笑ってた」
泣きだしそうな顔だったけど、それでも笑ってくれたの。そう言って、禰豆子は、じっと義勇を見つめた。
「お兄ちゃんは頑固で融通効かないから、多分、告白してもごめんってお兄ちゃんは言うんだろうなって……カナヲちゃんもわかってるみたい。私もそう思います。お兄ちゃんはきっと、振りむいてもらえなくてもずっと冨岡さんのことが好きなんだろうなって。お兄ちゃんには誰よりも幸せになってほしいから、できれば冨岡さんにもお兄ちゃんのこと好きになってもらいたいけど、そこまではご迷惑になるから言いません。お店に来てくれるだけでいいんです」
もうそれ以上言わなくていい。聞きたくない。勘違いしそうになる。炭治郎の一途な恋心が、いつまでも自分に向けられるなんて、ありえない。炭治郎を錆兎の代わりにするなんて嫌なんだ。あの子はそんなことをしていい子じゃない。俺の穢れに炭治郎を巻き込めるわけがないだろう。炭治郎の恋は勘違いだ。いつか間違いに気づく。
グラグラと頭のなかが沸騰しているようで、思考はまともに働いてくれそうにない。苦しくて苦しくて、いっそ恥も外聞もなく泣いてしまいたい。
「冨岡さん? 大丈夫ですか!?」
「禰豆子ちゃ~ん! ごめんね、待たせちゃった? って、この人昨日の……?」
「善逸さんナイスタイミング! お願いっ、冨岡さんに肩を貸してあげてほしいの! タクシー乗り場まで!」
ぼんやりと霞んでいく思考の片隅で、聞こえてくる禰豆子の慌て声をどうにか理解するが、もう一人の声はよくわからない。聞いたことがある気もするが、誰だったか。
それでも、家まで帰りついたということは、禰豆子と待ち合わせ相手は無事義勇をタクシーに乗せてくれたのだろう。記憶はないが、自分で住所も伝えられたようだ。
霞む目と震える手のせいで鍵を開けるのに手間取ったが、どうにかベッドまで辿り着けただけでも上々だ。
色々と限界を迎えていた義勇は、ベッドに倒れこむなり眠りに落ちた。