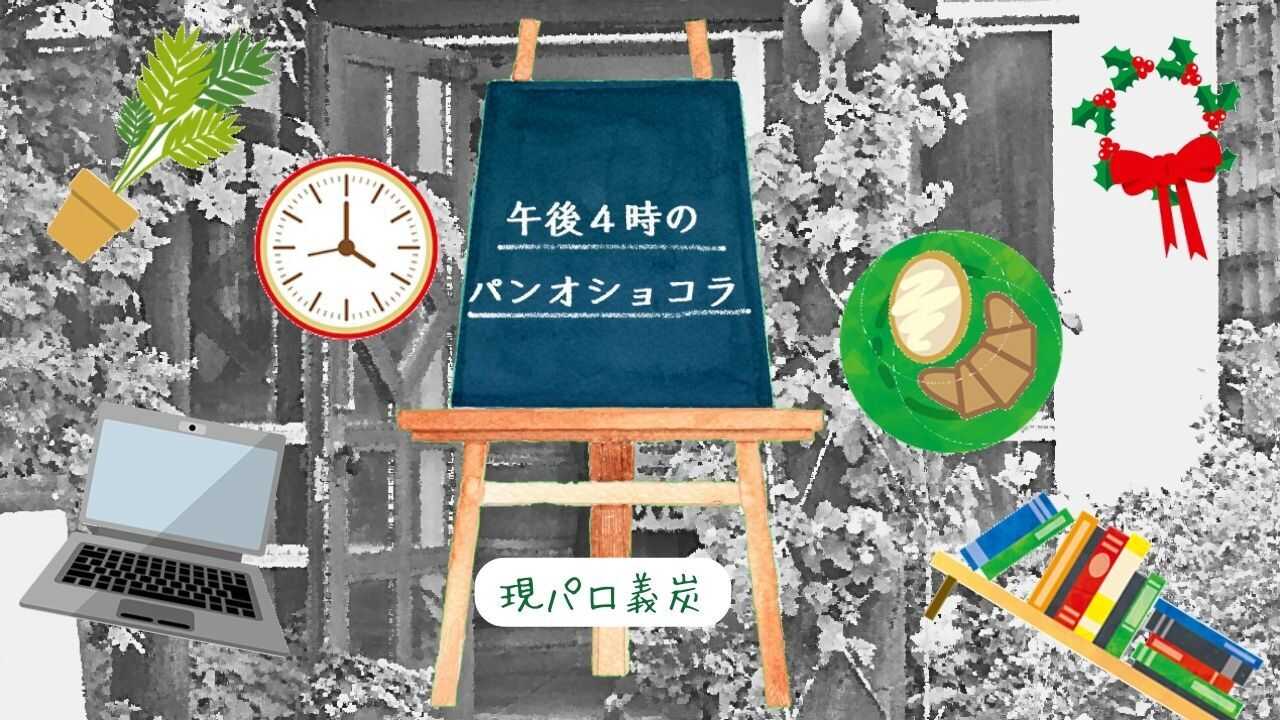義勇の愛車が竈門ベーカリーの駐車場に停まったのは、午後六時になる少し前だった。ドアの横に置かれた立て看板には『20:00close』の文字。窓からちらりと店内を窺えば、どうやらカフェスペースの鉢植えは一週間前と変わらぬ場所にあるようだ。
そして。
「……いたか」
諦めとともに呟いて、義勇は、ともあれパソコンバッグを手にドアを開いた。
「いらっしゃいま…せ……っ」
途中までは元気が良かった声が尻すぼみに小さくなって、ドリンクカウンターでコーヒーを淹れていた炭治郎の顔が、入り口に立つ義勇を目にした途端にみるみる真っ赤に染まった。
まだこんな状態か……。
まいったなと思いつつ、義勇は、炭治郎の視線に気づかぬ素振りでトレイとトングを手にした。目当てのパンオショコラは残り少ない。これで売り切れていたら、かなりがっかりしたことだろう。踏んだり蹴ったりな状況は免れたのだから、それだけでも良しとしようか。
背中に熱烈な視線を浴びながら、義勇はそれを無視してパンオショコラのほかにいくつか気になるパンを夕飯用に選ぶと、意を決してレジへと向かった。
「冨岡さん、いらっしゃいませっ。あの、今日は……」
「イートインで。これと、ホットコーヒー一つ」
嬉しげに見上げてくる炭治郎の言葉を遮り素っ気なく言えば、炭治郎は少し眉を下げたが、それでも店員としての愛想はどうにか保っていた。
会計を済ませてパンとコーヒーカップの乗ったトレイを手に、義勇が向かったのはあの席だ。背中に感じる炭治郎の気配に歓喜が漂うのは感じたが、この際開き直ってしまえ。ようは自分が相手にしなければいいのだ。
炭治郎の義勇に向ける感情が、恋情でもそうでなくても、炭治郎が口にしないかぎり、義勇は気づかぬふりをするだけでいい。告白されてしまえば断るほかないので、この店に来ることはさすがに控えるしかないだろうが、その時はその時だ。それまでは気に入ったパンも堪能できるし、執筆作業もこなせるはず。
思いながら席に着き、義勇はノートパソコンをテーブルに置くと、コーヒーに口をつけた。
この店はカフェスペースにも力を入れているようで、コーヒーも結構美味い。義勇自身はあまりコーヒーの味にはうるさくないのだけれど、錆兎がわりと拘るほうだから、つい頼むのはコーヒーになる。錆兎が気に入りそうだと思えば、錆兎や真菰を誘ってまた訪れるのだが、この店は合格点であっても誘えないなと、少し残念に思った。
閉店は夜八時。さて、どこまで進められるかと頭のなかで構成を考えつつ、義勇はまずはクロックムッシュにかぶりついた。温められたクロックムッシュはチーズのとろりとした味わいが堪らなく、この店はどんなパンでも美味いなと少し感嘆する。
楽しみにしていたパンオショコラは最後の楽しみにとっておき、書きかけの小説の続きを打ち込みながら、ときどき思い出したようにパンとコーヒーを口に運ぶ。
烏間の喫茶店よりと比べれば人の気配は段違いに多いが、客層が良いのか、決して気に障るようなものではなかった。鉢植えの観葉植物で隔てられた空間は、薄皮でできたシェルターのように、義勇の身を取り巻く静けさを守ってくれる。
「あ、あの……冨岡さん」
かけられた声にハッとして、慌てて顔を上げれば、炭治郎がすまなそうに立っていた。
「すみません、ラストオーダーなんですが、ご注文ありますか?」
言われて初めて義勇は、自分がかなり集中して執筆していたことに気づいた。烏間の店や錆兎とともにいる茶の間ですら、ここまで集中できたことはない。驚きに言葉をなくした義勇に、炭治郎は困り切ったように慌てだした。
「ごめんなさいっ、お仕事中なんですよね。えっと、どうしよう……少し閉店時間を遅らせて……」
「いや、もう出る。遅くまですまなかった」
炭治郎の提案にギョッとして、義勇も慌てて炭治郎の言葉を遮ると、皿に置かれたままになっていたパンオショコラに噛り付いた。
やはり美味い。美味いのだが……。
初めて食べたときの衝撃的な美味さに比べたら、なんだかちょっと拍子抜けというか、あのときほどの美味さは感じられず、義勇は我知らず手にしたパンオショコラをまじまじと見つめてしまった。
「あ、もしかして前と味が違いますか?」
「あ、あぁ。いや、これも美味いんだが……その……」
口ごもる義勇に、炭治郎は合点がいったようにうなずいて、少し困り顔で笑った。
「パンオショコラは焼き立てが一番美味しいんです。もちろん、うちのは冷めても美味しいように拘って作ってますけど、やっぱり焼き立ての美味しさには敵いません。イートインのお客様には温めてお出ししますから、もう少し焼き立てに近い味になるんですけど……その、かなり時間が経っちゃってますから……」
なるほど、そういうものなのか。そう言えば、初めて来たときにも常連客が焼き立てはあるかと確認していたなと、義勇は納得しつつ少ししょんぼりと肩を落とした。
「そうか……」
「あのっ、パンオショコラは午前十時の開店と一時と四時の三回焼くんです! その時間に合わせて来てもらえれば、焼き立てを食べられます! えーと、あの……できれば四時に来てくださると、その……俺もいるんで、だから、その……」
だんだんと力なくうつむいていく炭治郎に、義勇の罪悪感が刺激される。初めてこの店を訪れたときも今日も、義勇は炭治郎に対していっさい優しい言葉などかけていない。元々の不愛想に拍車をかけた不機嫌な態度を、隠そうともしなかった。
なのに炭治郎は、義勇に対していまだに悪感情を持ち合わせてはいないようだ。もしも一目惚れされたのだとしても、前回だけでも印象は悪くなっただろうし、ましてや一週間も音沙汰なしという不義理もしている。嫌われないまでも、好意はかなり目減りしてもおかしくはないというのに。
つい溜息がこぼれたら、びくりと炭治郎は肩をすくめた。大きな目が泣き出しそうに潤んでいる。
「……四時だな」
「え……?」
「焼き立てが並ぶ時間に来る」
残ったパンオショコラを急いで食べきり、義勇は保存を済ませるとパソコンの電源を落とした。
この店のパンは美味い。コーヒーだって悪くない。執筆場所としては最高だ。またこの店に来る理由はそれだけでじゅうぶんだ。
四時に来るのは、ほかの時間より都合がいいから。炭治郎がいたとしても、今日のように集中していたら会話をすることもないだろうし、いずれは炭治郎も、取り付く島もない義勇に見切りをつけるだろう。
席を立ってドアに向かう義勇に、先ほどの義勇の言葉を噛みしめていたらしい炭治郎が言った「またのご来店お待ちしております!」という声には、抑えきれない嬉しさが湛えられていた。