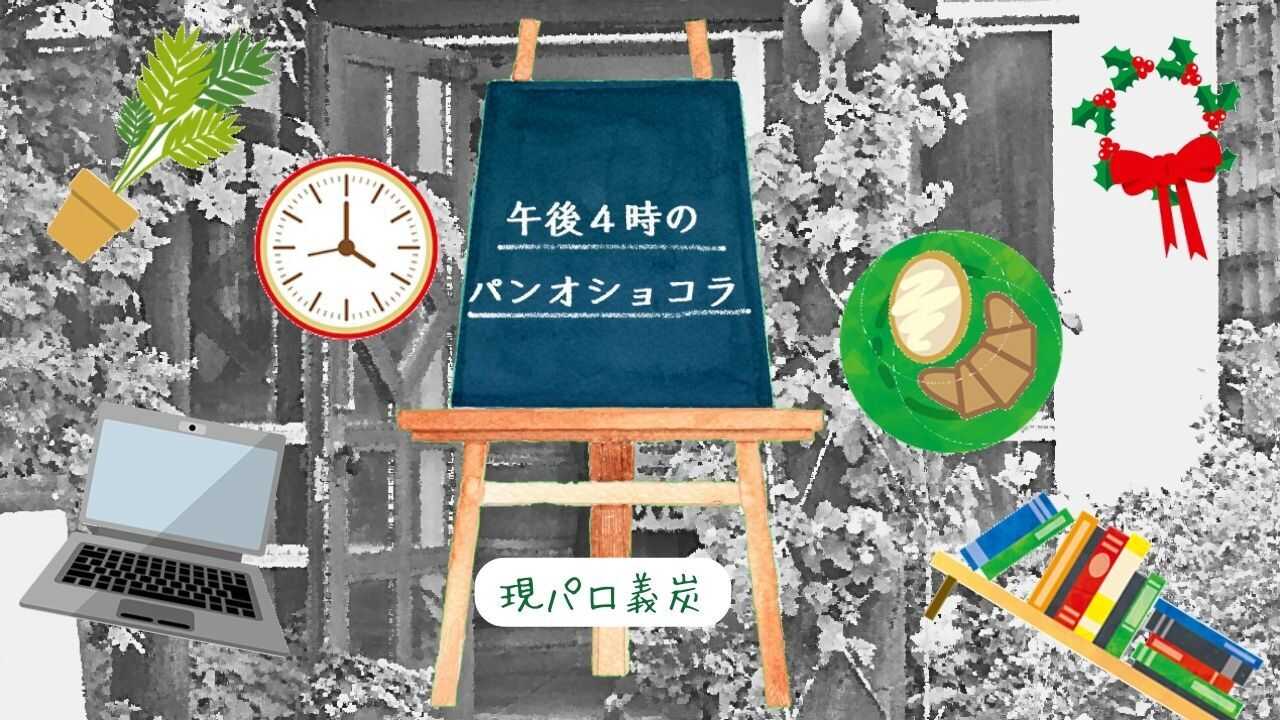義勇の行きつけの喫茶店から車で十五分ほどの住宅地に、そのベーカリーはあった。
「竈門ベーカリー……ここか」
閑静な住宅街にはめずらしく、割合広い店構えではあるが、いかにも地域で愛される街のパン屋さんといった佇まいのベーカリーだ。大きな窓から店内を窺えば、たしかにそこそこ広めのカフェスペースがあり、満席とまでは言わないがかなり客が入っているのが見えた。
マスターの気遣いは嬉しいが、さて、パンの味はともかくこんなに客の多い店で長時間居座ることなどできるのか。はなはだ心許ないなと、義勇は内心溜息をつく。
その点、あの店は良かった。いつ行っても常連が数人いればいいほうで、締め切り前に五時間居座ってしまったことがあるが、その間に来た客は義勇を除けば二人だけだったりもした。
だからこその店じまいだと思えば、客の少なさを喜ぶわけにもいかないが。
自宅で執筆することに否やはないが、いかんせん義勇の家は静かすぎる。暮らしていくにはその静けさこそを愛しているが、不思議なことに小説を書いているときには、人の気配があるほうが筆が進む。
『結局のところおまえは人が好きなんだよな』
そう笑って言った宍色の髪をした親友の言葉は、うなずきかねる部分もある。だが、実際ある程度、人の話し声やら生活音やらが聞こえるほうが、ストーリーに入り込みやすい。
テレビやラジオなどではまったく効果がない。だからといって、自宅に他人がいるのは、落ち着かないことこのうえなかった。
義勇のパーソナルスペースは広い。できうる限り一人で過ごすのが性分にあっている。傍にいて気にならない者など、片手で足りるほどしかいない。だというのに人がいないと書けないとは、我ながら難儀な性格だ。
ともあれ、店の前で立ち尽くしているわけにもいくまい。ひとまずパンだけは買っていこうかと、義勇は店内に足を踏み入れた。
カランコロンとドアベルの軽やかな音に混ざって、いらっしゃいませと快活な声がひびいた。
声の主はパンの補充をしていた少年であるようだ。高校生ぐらいだろうか。振り返った顔は、まだ幼さを残している。飲食関係だというのに大振りのピアスをしているのが少し気になったが、店主が許しているのなら、義勇が文句を言う筋合いはない。
とくに気にも留めず足を進めようとした義勇は、少年がピタリと動きを止めたままこちらを凝視しているのに気づき、思わず眉根を寄せた。
不審な恰好をしているつもりはないのだが、今日の服装はなにか変だっただろうか。
思わず視線だけで自分の服を確認したが、Tシャツに青いパーカー、ブラックジーンズと、いたって普通の格好のはずだ。伸ばしっぱなしの髪が気になるのだろうかとも思うが、見苦しくないよう結んでいるし、不潔感はないと思うのだが。
つい怯んでしまった義勇を見つめる少年の眼差しに、嫌悪や嘲りの色はまったくない。どちらかといえば、驚愕に染まっているように見受けられる。
いずれにせよ、あまりじろじろと眺められるのは気分のいいものではない。とにかくさっさと買って帰ろうと、義勇は少年の視線から逃れるように、トレイとトングを手に取った。
マスターは居心地の良い店だと言っていたが、こんなふうに客を不躾に見る店員がいる店では、とうてい店内で飲食する気にはならない。いくら美味かろうが買いにくるのもごめんだなと、義勇は内心で溜息をついた。
喫茶店で食べ慣れたクロワッサンとバターロールだけをいくつか取り、さっさとレジに向かう。棚には気になるパンも多かったが、背中に強すぎる視線を浴びながらでは、落ち着いて悩むこともできない。
レジ前に立った義勇に、少年がハッと姿勢を正し慌ててレジカウンターに入った。
どこかぎこちない様子でレジを打ち商品を袋に詰める少年は、先ほどまでの凝視っぷりが嘘のようにうつむきがちで、今度は義勇の顔を見ようとしない。
もしかしてバイト初日だとかで、初めて対応する客に緊張していただけなのだろうか。だとしたら自分のように不愛想な客なのは、かえってかわいそうなことをしたかもしれない。
そんな義勇の好意的な解釈も、入ってきた客への少年の対応に消え失せた。
「炭治郎ちゃん、パンオショコラ焼き立てあるかい?」
「あ、佐伯さん、いらっしゃいませ! はい、ちょうど焼けたところですよ」
……常連と名前で呼びあうぐらいには慣れている。ぱっと上げた顔はにこにこと愛想が良い。ならばやっぱり、こんな対応をするのは自分に対してだけということか。
「タイミング良かったなぁ。コーヒーもよろしくね」
言いながらトレイにパンを乗せる客に、はいと元気よく返事したと思えば、ハッと義勇を見上げ慌てだす。
「あ、ごめんなさい! えっと、あの、六四八円になります。あ、あの……」
無言で千円札を取り出しカウンターに置いた義勇に、炭治郎と呼ばれた少年は、なぜだかおろおろと視線をさまよわせている。
不躾に見つめられるのにも困惑したが、こんなふうに挙動不審になられるのも困る。いったい自分がなにをしたというのだと少し苛立ちだした義勇を、炭治郎は意を決したように見つめてきた。
なにをそんなに真剣な顔で見てくるのかと、うろたえる義勇に向かって、炭治郎が口にしたのは。
「あの! うちは三百円お買い上げごとにポイントが付くんですけど、ポイントカード作られますか?」
思わず拍子抜けした。なにを言い出すかと思えば、ポイントカードときたか。商売熱心なのは結構だが、そこまで真剣にならずともよかろうに。思いつつ、義勇はそっけない声で断りを入れた。
「いや、結構です」
「え、で、でもですね、十ポイントで三百円分の商品と取り換えられてお得ですよ!」
「いりません」
もう来る気はないし。とは、さすがに言葉にはしなかったが、取り付く島もない義勇の声に、炭治郎が見るからにしょんぼりと肩を落とすのには、少しばかり気が咎めないでもない。
もうさっさと帰りたいのだが、炭治郎は、でも、あの、と必死に言い募る。
「……釣りを」
「あぁ! すいませんっ、ごめんなさい! えっと、三五二円のお返しになります」
義勇が差し出した手に、小銭を置いた炭治郎の指先が、ちょんと触れた。その途端に真っ赤に顔を染めて、炭治郎は慌てた様子で手を引き、商品の入った袋をぐいっと差し出してきた。
いぶかりながらもそれを受け取った義勇は、さっさと踵を返した。
残念だが今日買った分が終わったら、あのモーニングのパンは二度と食べられないことが決定したなと、諦めの溜息を噛み殺す。居心地の良い執筆場所も開拓しなければならないだろうが、新しく店を探すのも億劫だ。
しかたない。しばらくは自宅にこもって、それでも駄目なら、錆兎にヘルプを願うことにしようか。
夜型でなくて良かったと思うのはこういうときだ。泊りは困るのだ。主に義勇の心情として。
昼間ならば、錆兎の気配が近くにあるのは喜ばしい。茶の間の卓袱台での執筆中、ふと集中が途切れたときに感じる、錆兎の気配。視線を上げれば瞳に映る錆兎の姿。静かに本を読んでいるだけでも、レポートに励んでいるだけでも、向かいに座っている錆兎が目に入るだけで、義勇の心は安らぐ。
義勇の視線に気づいた錆兎が笑ってくれるだけで、幸せだと思う。
幼馴染で親友の錆兎に、恋をしている。ずっと、ずっと、前から。
……駄目だな。鱗滝さんの具合も良くなさそうだし、真菰が手伝いに行ってるのに、呼び出して邪魔するわけにはいかないか……。
小さな溜息を噛み殺してドアを開けようとした義勇は、思い直しドアの近くの棚へと移動した。背中に感じる視線が鬱陶しい。噛み殺しきれずに溜息が落ちそうになったころ、ふたたび入り口に向かいドアを開ける。
「あ、すいません。ありがとうございます」
入ってくるベビーカーを押した若い主婦に軽く会釈して、表に出たときにはなんだかひどく疲れていた。もう来るつもりはないのだから、どうせなら棚にあったフレンチトーストも買えばよかったかなと、ちらりと思ったが、またレジに並ぶ気には到底なれない。しかたがないかと愛車へと近づいたとき。
「おや、冨岡さん。早速いらしてくださったんですね」
「あぁ……烏間さん」
行きつけだった喫茶店のマスターが、義勇の愛車の隣に停車した車から降りて、義勇にニコニコと笑いかけてきた。
タイミングが悪いなと、少々バツ悪く思う義勇とは裏腹に、烏間は至極嬉しそうだ。
「どうでしたか、いい店でしたでしょう? パンの味もさることながら、店員の感じがとてもいい店ですから」
「……いえ、今日は時間がないので」
言外にだから飲食はしていないのだと滲ませれば、烏間は納得したようにうなずいた。義勇にしてみれば、どこが感じがいいだって? と苦虫を噛み潰したような顔になりそうな烏間の言だが、烏間はそれをまったく疑っていないようだ。
「あのっ!」
二度と来る気はないなど言うわけにもいかないし、どう誤魔化せばいいだろうかと思案する義勇の背に、もう聞くこともないと思っていた声がかけられた。
「おや、炭治郎くん。お久しぶりです」
「烏間さん、お久しぶりです! 閉店、本当に残念です。あの……こちらのお客さんと、お知り合いなんですか……?」
慌てて出てきたのだろう。少し息を切らしながら言う炭治郎の声を背中で聞きながら、義勇は思わず遠い目で虚空を見つめた。
本当にタイミングが悪い。せめて店内から見えないところでの会話なら、この感じの悪い店員にも気づかれなかっただろうに。
この少年が、義勇のことをこれほど気にするのはなぜだろう。気になるのは確かだが、それを問いただすより、二度と関わらないほうが楽だ。実際、そうなるはずだったというのに……。
そうは思うが、話題に出されてはしょうがない。
烏間の顔を潰すのも忍びなく、義勇はゆっくりと振り向いた。愛想のないことでは定評のある己の顔は、きっといつも以上に無になっていることだろう。そういう顔をするからみんな話しかけづらくなるのだと、苦笑いする親友と幼馴染の顔が浮かんだが、この場ではその太鼓判がありがたい。きっと炭治郎も、自分の不愛想っぷりにドン引きするに違いないと、ほとんど義勇は確信していた。
けれど、炭治郎の義勇への関心は、一筋縄ではいかぬようだ。
「ああ、この方が私が言っていた冨岡さんですよ。ほら、うちの喫茶店でお仕事をされることが多い常連さん。こちらならきっと冨岡さんも、ゆっくりと落ち着いてお仕事ができるでしょうから、いらしたら懇意にして差し上げてくださいとお願いした……」
「あぁ! この方のことだったんですか! 冨岡さんっていうんですね……あ、あの、下のお名前はなんですか? あ、俺は竈門炭治郎って言います! この店の長男です!」
ニコニコと言う烏間の言葉や表情には善意しか見当たらないが、義勇にしてみれば、余計なことをとしか思えない。赤い顔をしてきらきらと目を輝かせ言う炭治郎に、義勇のほうがたじろいでしまう。
思わず眉を寄せた義勇の戸惑いと不快感に気づいたのか、炭治郎は途端にしゅんと肩を落として、モジモジとしている。しかし、これぐらいでへこたれるような性格ではないのだろう。キッと顔を上げると、義勇へと詰め寄ってきた。
「カフェスペースでお仕事されるんですよね? どの席がいいですか? 窓際のほうがいいですか? 気に入った席があったら予約席にします! あ、でもさっきはテイクアウト商品しかお買い上げいただいてないから、どの席がいいかわかりませんよね。良かったら今からカフェのほうに来てください! さっきうちで自慢のパンオショコラが焼き上がったんです、ぜひ食べてみてください! 俺、ドリンク奢りますから!」
コーヒーがいいですか? それとも紅茶? ホットドリンクと合わせるほうがお薦めですけど、コールドドリンクもありますよ。甘いのがお嫌いならクロックムッシュはどうですか? と、怒涛のように紡がれる言葉に、口を挟む隙を見つけられないまま義勇が茫然としていると、烏間が苦笑した。
「炭治郎くん、冨岡さんが驚いてらっしゃいますよ。冨岡さん、お時間がないのはわかっておりますが、少々お付き合いいただけますでしょうか」
嫌だ。即座に脳裏に浮かんだ否定の言葉は、結局義勇の口から発せられることはなかった。
義勇は押しに弱くて流されやすいから。
頭のなかで錆兎と真菰が呆れた顔で言ったような気がしたが、今回ばかりは、自分だけが悪いんじゃないと義勇は思う。
炭治郎の押しの強さもさることながら、烏間にはそれなりに恩を感じているのだ。義勇のように金にならない長っ尻な客にも嫌な顔一つせず、いつもにこやかで丁寧な対応をしてくれたマスターのお陰で、今まで邪魔されることなく執筆作業ができたわけだから。
しかも、このたびのことだって、あくまでも義勇に対しての厚意からだ。本心から義勇の執筆状況を案じてくれているのは疑いようがない。そんな烏間をがっかりさせるのは、恩を仇で返すようなものじゃないか。
諦めの境地で小さくうなずいた義勇に、炭治郎の喜びようは激しかった。こっち! こっちへどうぞと、はしゃぐ様を見ていると、手を引かれないだけでもマシかと思ってしまう。
カフェスペースは席と席の間隔を広くとっていて、飲食するだけなら確かに居心地はよさそうだ。椅子も客の長居を拒むような硬いものではなく、落ち着けるようにと選ばれたことがよくわかる。実際、カフェスペースにいた客のなかには、じっくりと腰を据えて読書中といった風情の者もいる。
だが。
「……申し訳ないが」
烏間と二人、炭治郎に案内された奥の席に着き、お薦めだというパンオショコラとコーヒーを目の前に、義勇は烏間に向かって小さく断りを入れた。炭治郎と会話したら最後という気がしてしかたがないので、あくまでも、烏間に。
「落ち着かれませんか……? やはり、当店で気に入ってくださっていた席のように、ほかの席からは隔離されているような感じをお求めで?」
こくりとうなずいた義勇に、烏間は残念そうな顔はしたが、重ねて薦めてはこない。義勇の意思を尊重する姿勢は、義勇の著書のファンだからだろうか。これで話が終わるのは義勇にとってもありがたい。
「じゃ、じゃあここに、あそこの鉢植えを移動します。えっと、ずらっと並べて壁みたいにしたら、個室っぽくなりますよね? それならどうですか? 冨岡さんの予約席にして、ほかのお客さんは座れないようにします!」
なんでそんなにも必死なんだと問い質したくなるほど、炭治郎は義勇をこの店にこさせたいらしい。
ちらちらと義勇を窺う視線や赤く染まった頬に、もしかしてと思いはするが、炭治郎からは義勇と同じ性的指向は感じられず、義勇はとにかく困惑するしかなかった。
自分がゲイだと自覚して以来、なんとなく相手がゲイかどうかわかるようになった。説明はしにくいのだが、同じゲイなら、まとう空気がノンケとは違って見える。炭治郎からはそんな空気は微塵も感じられない。なのに、義勇を見つめる瞳には、隠しようのない恋慕の色があるのだ。
まさかノンケが男相手に一目惚れというわけでもあるまい。もちろん、炭治郎がまだ自分の性的指向に気づいていないだけという可能性はある。けれども、それにしたってなんの困惑も混乱も見せずに、義勇への恋愛感情をすぐさま受け入れるというのは理解しがたかった。ありえないとも思う。
義勇だって、錆兎への想いを自覚し、自身の性的欲求が同性にしか向かないのだということに気づいたときには、ひどく困惑し、自己嫌悪と戸惑いにしばらく悩みつづけたのだ。一目惚れされることがないとは言わないが、それはゲイの自覚がある男か、女性に限定されるはずだった。
気になりはするが、探りを入れて藪蛇になっても困る。このまま自分が答えなければ否定の意だと炭治郎も悟るだろう。それでこの話も流れて、二度と炭治郎と逢うこともないはずだ。それがお互いのためだと、義勇は炭治郎の提案に答えることなくカップを手に取った。
そんなふうに楽観していた義勇に、烏間の言葉など予想できるはずもなく。
「なるほど、いい案かもしれませんね。ちょっとやってみますか? 私も手伝いますから、炭治郎くん、鉢植えを移動してみましょう」
「はい! 冨岡さん、ちょっと待っててくださいね!」
飲み込み損ねたコーヒーを、噴き出さなかっただけでも褒めてほしい。
老齢の烏間が、炭治郎に心配されながら重い観葉植物の鉢植えをいくつも移動するのを、義勇は呆然と見ていた。
いや、止めようとは思ったのだ。しかし、烏間の行動は完全に善意である。しかもここで止めたら、執筆に向かない状況を受け入れることになるか、もしくはこの店には二度と来ないという意思を伝えるかの選択を、余儀なくされる。
おまけに、店の看板息子であるらしい炭治郎が、常連客らしい老齢の烏間と一緒になって、重い鉢植えを移動し始めたことで、店内にいた客の視線を一身に集めてしまっているのだ。今までの会話だって声を潜めていたわけではない。炭治郎の声はすこぶる大きい。事情は店内の客たちに筒抜けに違いなかった。これで義勇が断れば、義勇が白眼視されるだけでなく、この店でも馴染みらしい烏間の顔は、完全につぶれるだろう。
いずれにせよ、烏間の善意に溢れた厚意の行動を、当人の目の前で無碍にするようなことを、義勇が出来るわけもない。
義勇は押しに弱くて流されやすいから……。
ふたたび脳裏に再現された声に、義勇はもはや反論する言葉を持たなかった。