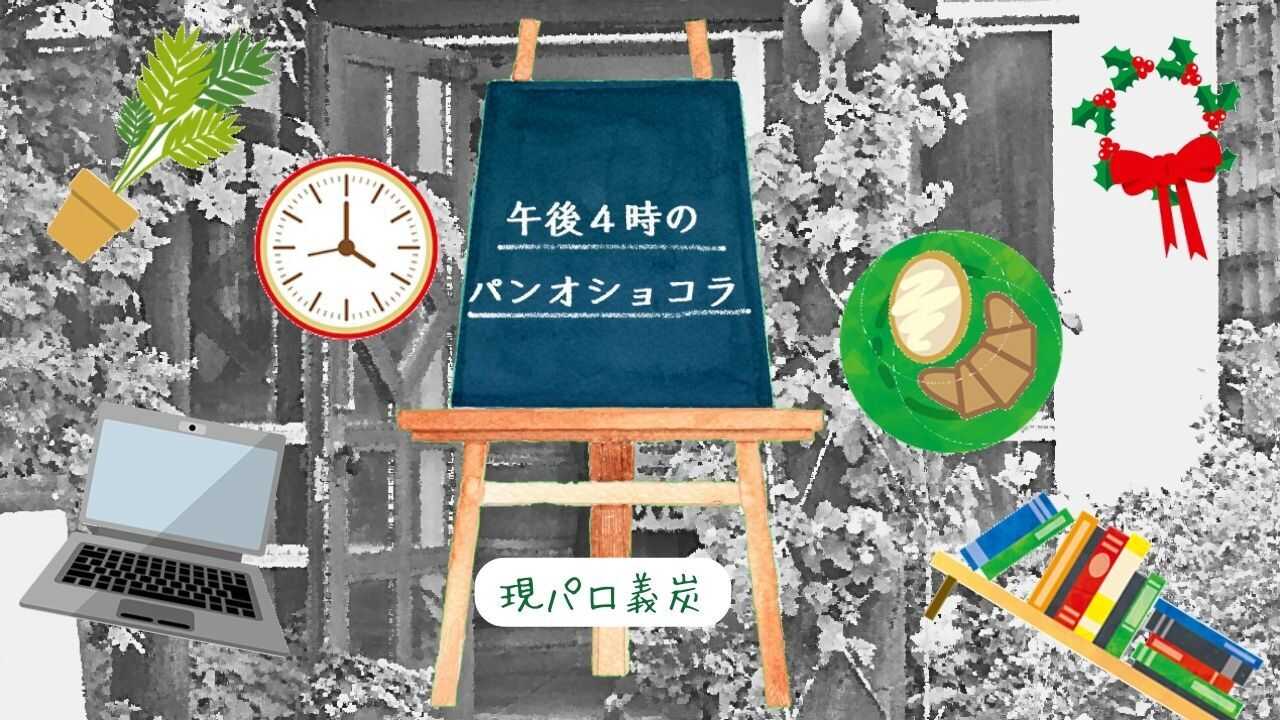次に義勇が目を覚ましたのは、玄関のチャイムの音によってだった。
チャイムに混じって雨音が聞こえる。朝は晴れていたが、いつのまに降り出したのだろう。というよりも、いったい今は何時なのか。家に帰りついたのはおそらく昼ごろだと思うが、室内はもう暗い。
夜までぐっすり眠っても、痛みはまだ体に残っていて、熱も下がってはいないようだ。ポケットに入れっぱなしだったスマホを取り出して時間を確認すると、夜の九時だった。
倒れこんだまま眠っていたので、引きかけだった風邪が悪化したのかもしれない。寝起きから頭痛がするし、まだ悪寒も続いていた。目が熱いのは熱が上がっているのだろう。このぶんだと三十八度は超えているかもしれない。締め切りが近いというのに、なんてザマだ。
やっぱりマスターの忠告に逆らうべきじゃなかった。亀の甲より年の劫、自分のような若造とは比べ物にならない経験を積んできただろうマスターの言葉に、今後は決して逆らうまいと誓う。
あぁ、シャワーが浴びたい。喉が渇いた。けれどどうにも動きたくない。
目覚めたときの体勢のままでグズグズと考えていると、ふたたびチャイムの音がした。予定はないはずだが宅配便だろうか。申し訳ないが居留守を使わせてもらおうと、また目を閉じかけたが、チャイムは連続して鳴らされだして、義勇は苛立ちながらようよう起き上がった。
宗教の勧誘やセールスだったらどうしてくれよう。物騒な苛立ちを抱えるのは発熱ゆえか。フラフラとしつつ義勇が玄関に辿り着くまで、チャイムは鳴り続けていた。
うるさいと怒鳴ってやろうと、玄関の引き戸を開いた義勇の目に飛び込んできたのは、炭治郎の泣き顔だった。
「冨岡さんっ! 良かった、生きてたぁ……!!」
人を勝手に殺すなと言いたいが、それよりなにより、なぜ炭治郎がここにいるのかが理解できず混乱する。しかも炭治郎はずぶ濡れだ。雨足はかなり激しい。だというのに、なんで炭治郎は傘もささずにいるのか。
熱に浮かされた頭では考えはまとまらず、それでも一つだけはっきりしていることがある。
「何月だと思ってるんだ! そんなに濡れたら風邪を引くだろうっ!」
「来る途中で降ってきちゃって……それまでは晴れてたから傘持ってなかったんです」
なるほど、炭治郎が持っているのはコンビニのビニール袋だけだ。
髪がぺたりと額や頬に張り付くほどに濡れている炭治郎に、気が気じゃなくて、義勇は思わず炭治郎の腕を掴むと玄関に引っ張り込んだ。掴んだ腕もぐっしょりと冷たく濡れていて、熱に紅潮していた義勇の頬から血の気が引いた。
自身の体調不良は後回しだ。とにかく温めなければと、炭治郎が靴を脱ぐ間すらもどかしく、風呂場へと炭治郎を連れて行く。
「タオルと着替えを用意するからシャワーを浴びてこい」
「あのっ、俺は大丈夫ですから、それよりも冨岡さんのほうこそ寝てください! あ、俺が起こしちゃったのか。ごめんなさい! でも具合悪いんですよね? 禰豆子に聞きました。俺、看病しますから!」
「話はおまえがちゃんと温まってから聞く。いいからさっさと入れ!」
必死に言い募る炭治郎から有無を言わさず上着をはぎ取り、義勇は、俺が戻るまでに入ってろよと言い置き、急いで自室へと向かった。
自分のスウェットとバスタオルを取り出し風呂場に戻ると、シャワーの音が響いている。ちゃんと言いつけを守ったようだと安堵の溜息が出た。
「タオルと着替えを置いておく。きちんと温まるまで出るなよ」
それだけ浴室に向かって言うと、返事を待たずに茶の間に向かい、エアコンのスイッチを入れる。後は湯を沸かして、茶でも飲ませてやればいいかと考えたところで、火事場の馬鹿力めいた気力は果てたらしい。不意に足が萎えて、倒れこみそうになる。
きっと安心したのがまずかった。もう少し。せめて炭治郎が出てくるまでと気力を振り絞るが、やかんを火にかけたところで、いよいよ限界がきた。
冷たい台所の床に座り込み、義勇はシンク下の収納に寄り掛かるとそのまま動けなくなった。頭のなかでは、駄目だ、炭治郎が風邪を引く、動けと、繰り返し自分に言い聞かせるのだが、手酷いセックスで酷使したうえ風邪を引いたらしい体は、義勇の意思などまるで聞き入れてはくれない。
シュンシュンと湯が沸く音がしだした。座り込んだまま立ち上がれずにいると、バタバタと忙しない足音が聞こえ、次いで炭治郎が自分を呼ぶ声がした。
「冨岡さんっ!! 大丈夫ですかっ!?」
風呂から上がっても義勇の姿が見えないので探していたのだろう。慌てて走り寄ってきた炭治郎は、ガスの火を止めるとしゃがみ込み、義勇の腕を肩に掛けた。
「立てますか?」
すまないと言いたかったが、声にはならない。荒い息だけが忙しなくこぼれる。
「部屋はどっちですか?」
「……奥」
どうにか呟けば、炭治郎はきちんと聞き取ってくれたようだ。ゆっくり義勇の足取りを気遣われながら進む廊下は、日ごろより長く感じる。独り暮らしには広すぎる日本家屋は、こういうときには少々つらい。
義勇の頬に触れる炭治郎の髪は湿っている。体は温まっただろうが、このままではやはり風邪を引きかねない。炭治郎の濡れた髪ばかり気にかかって、無理矢理絞り出すように「髪、乾かせよ」と強く言ったのを最後に、義勇の意識は途切れた。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
義勇さん。義勇さん。誰かが呼ぶ声がする。優しい声だ。温かく、幸せそうな声だった。
義勇さん。義勇さん。繰り返し名を呼びながら、誰かがそっと頭を撫でている。慈しむように、優しく。
「……義勇さん、好きです……義勇さんが、好き」
不意に浮かび上がった意識がとらえた囁きは、炭治郎のものだった。ゆるゆると目を開ければ、心配そうに義勇の顔を覗き込みながら、そっと義勇の頭を撫でている炭治郎と目が合った。
「あ……ご、ごめんなさいっ!」
慌てて引かれる炭治郎の手を、引き留めたいと思った。けれど手を上げることすらつらくて、義勇は代わりに小さく呟いた。
「……もっと」
「え……?」
そのまままた目を閉じた義勇の呟きは、ちゃんと炭治郎に届いたようだ。掌が一度額に当てられて、まだ高いですねという声とともに、その手はまた優しく頭を撫でだした。
このまま、ずっと触れられていたい。抱き締めて、自分も優しく撫でてやりたい。
ふたたび眠りに落ちていく意識の片隅で、そんなことを考えた気がする。