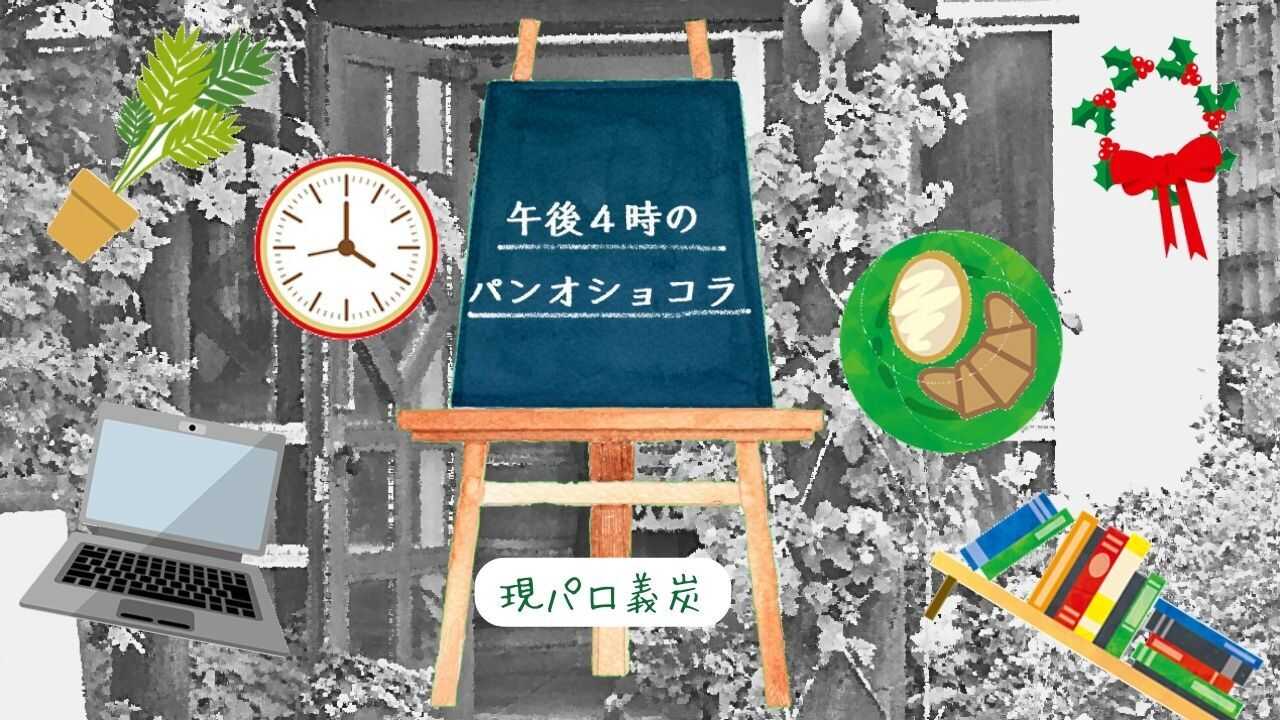しのぶの言葉を聞いてから、気が付けば心を占めそうになる陰鬱な感情に、義勇は十一月も半ばになろうかという今日まで、すこぶる寝不足な日々を続けていた。今までは溝浚いと称する男漁りで吐きだしてきたそれも、その原因が炭治郎だと思うと躊躇いが生まれ、ただ悶々と眠れない夜を一人のベッドで過ごしている。
竈門ベーカリーにも、当然のことながら行けずにいる。どんな顔をして行けばいいというのだ。感情が読めないと言われる義勇の顔だが、義勇自身が意図してのものではない。怒りや不機嫌さなどは割合表情に出やすいらしいし、万が一、炭治郎としのぶの妹が一緒にいるところなど見てしまったら、自分はいったいどんな顔をするのやら。想像するだけでもマズイ気がする。たとえ無表情を貫けたとしても、炭治郎は鼻が利く。寝た子を起こすような真似などできるものか。
そうはいっても、義勇の仕事に最適な場所は今や竈門ベーカリーのほかになく、義勇は今月末に一本締め切りを抱えている。しのぶのところとは違う出版社からの依頼で書いた連作の短編が、意外なほど好評で文庫化が決定したのはいいのだが、巻末に収録される書下ろしを月末には書きあげなければならなかった。
だからずっと家から一歩も出ることなく、茶の間でひたすらにパソコンと向かい合っているのだが、遅々とした進捗状況には、もはや頭を抱えるほかなかった。
デビューから世話になっている産屋敷出版と違って、この連作が初めての仕事になった出版社なので、あまり融通が利かないのが厄介だ。担当編集者も物言いがネチネチとしつこくて、あまり義勇とは馬が合わない。締め切りを伸ばしてほしいなど言おうものなら、またぞろ嫌味を言われまくるだろう。だからと言って、嫌っているわけではないから、担当を変えてほしいとは思わないが。
その連作は義勇にしては軽いタッチのほのぼのとしたもので、こんな鬱々とした気分のままではまったく筆が進まないだけでなく、内容も先方の依頼に沿うものになるとは思えない。そのうえ、あのカフェスペースの専用席に行けないとなれば、ほかの仕事にも影響は多大で、いい加減どうにかしなければベストセラーなどには縁のない義勇など、早晩干されるだろうことは想像に難くなかった。
よしんば小説家を続けられなくなったとしても、食っていくには困らない。けれども小説家を辞めたなら、義勇はおそらく自分を見失うだろう。
錆兎の幸せを願いながら、性欲が高まれば適当な男とセックスして、なにを生み出すわけでもなくただ息をして生きる。そんな生き方を受け入れることは、もうできそうにない。
義勇の小説を待っていてくれる子供がいる。自分の恋と義勇の書く主人公の恋を重ね合わせ、勇気づけられていると感謝してくれる名前も知らないあの子を、裏切るようなことはしたくない。
口下手な義勇が自分の言葉で誰かを勇気づけられることなど、小説でしか果たせないのは自認している。ほかの読者にも感謝しているけれど、義勇に書き続ける力をくれたあの子は特別だ。あの子に届けるためにも、プロとして書き続けたかった。
しかたがない。いい加減覚悟を決めて店に行こう。義勇はパソコンを手にノロノロと立ち上がった。
できれば炭治郎がいないといい。思う端から炭治郎の明るい笑顔が脳裏に浮かぶ。
今までならば癒された炭治郎の笑みは、義勇を苦しませるだけだった。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
ドアベルの軽い音とともに聞こえてきた「いらっしゃいませ」という炭治郎の元気な声は、なぜか義勇の顔を見た瞬間に尻すぼみになった。
いつもだったら義勇の姿を認めた途端に顔を輝かせるのに、今日は表情までもが戸惑いが露わで、すぐにうつむいてしまっている。
九月以来不義理をしてきたからだろうか。それとも、もうしのぶの妹と交際を始め、義勇の顔を見るのはバツが悪いのか。
思いついた理由は義勇を苛立たせ、つい眉間に皺が寄った。
勝手な憶測でしかないことは自覚しているが、それでもそんな理由を思いついただけで、義勇の機嫌は一気に下降する。
想像上の炭治郎の心変わりをなじりたくなって、義勇は小さく深呼吸した。
自分のことなど諦めろと、炭治郎に詰め寄ったのはまだ記憶に新しいというのに、あまりにも身勝手な自分に反吐が出そうだ。
苛ついたままお気に入りのパンオショコラを食べる気にもなれず、夕食代わりになりそうなパンをいくつかトレイに取る。とにかく今日中に脱稿の目途が立つぐらいには書き進めなければならない。長時間居座ることになりそうだと、ちらりといつもの席に視線を向ければ、あの観葉植物の鉢植えはまだ移動されることなくそこにあった。
我知らず安堵して、義勇はレジカウンターに向かった。俯いたままの炭治郎は視線だけで義勇を窺い見たものの、表情は浮かないままだ。
「……ホットコーヒー」
「はい……」
いったい俺がなにをした。どうして俺の顔を見ない。いつもみたいに笑わないのはなぜだ。
問い詰める言葉ばかりが脳裏に浮かんでは消えるが、義勇の口からそれらが出ることはない。そこまで恥知らずになるつもりは義勇にだってなかった。
炭治郎には炭治郎の生活があって、義勇中心に回っているわけではないのだ。そもそも足を遠のかせていたのは自分のほうだ。ただの客と店員だと、自分達の関係を位置づけ無言の強要を強いていたのも、ほかでもない自分自身なのだから、義勇に炭治郎を責める資格などない。
これでいい、これが当然の関係だと自分に言い聞かせている内に、レジを打ち終えた炭治郎が金額を告げる。札と一緒に渡したポイントカードは、あと一つですべて埋まる。結局作ってしまったポイントカードも、もう五枚目だ。いつもなら、あと一つですねと嬉しげに笑う炭治郎は、今日は無言で釣りとともにそれを返してきた。
またじわりと腹立ちが胸を焼いたが、どうにか堪えて義勇はトレイを手にいつもの席に着いた。
パソコンを開きストーリーに没入しようとするが、うまくいかない。
店内に溢れる温かみのあるざわめきは、いつもなら集中への導入剤のようなものなのに、今日はやけに耳につく。
客の話し声一つひとつを拾っては、そこに炭治郎の名が出ないことに苛ついたり安堵したりを繰り返しているのに気づいたとき、義勇は思わず天を仰いだ。
執筆のために来たというのに、気が付けば炭治郎の近況を常連たちの会話から探ろうとしている自分は、いったいなんなのだ。なにを考えている。
どうしてこんなにも炭治郎のことばかり考えてしまうのか。その答えをおそらく義勇は知っている。
だが、それを認められるかと言えば、否としか言えない。義勇にとって恋愛感情とは、錆兎だけに集約されるもので、誰かに代替わりさせられるようなものではないのだ。
たしかに、錆兎への想いから恋の一文字は昇華されたのだろう。今はただ深い愛だけが錆兎に対してはあるのだと思う。友情より重く、恋情ほど生々しくはない、深い深い愛情だ。
では義勇の胸にあった恋はどこに行ったのか。義勇はそれに気づきたくはない。気づこうとも、認めたくはない。
深い溜息を吐いて、義勇は開いていたワードを保存した。この席ですら集中できず、遅々として進まないのなら、もうどこで仕事しようが同じことだろう。炭治郎のことばかり気になってしまうぶん、ここにいるほうがかえって仕事にならない。
食事だけ済ませて帰るかと、置きっぱなしになっていた皿に手を伸ばしたとき、ドアベルがけたたましい音を立てた。
「権八郎、来てやったぞ!」
「馬鹿っ、デカい声出すなよ伊之助! 迷惑だろっ!」
ワイワイと騒ぎながら店に入ってきたのは、数人の高校生たちだった。
義勇がよく訪れる時間帯は学校帰りの高校生が立ち寄る時間と重なるので、それ自体はめずらしい光景ではないが、今日の奴らはいかんせんうるさい。思わず視線を向けると、観葉植物の葉の間から垣間見える一行のなかに、見慣れた顔があった。
「ごめんねぇ、禰豆子ちゃ~ん。お店で騒いだら迷惑だよね」
「うーん、ちょっと声のトーン落としてくれると嬉しいかな。あ、お兄ちゃん、ただいま」
炭治郎に手を振る少女は、やはり炭治郎の妹の禰豆子だ。たまに炭治郎と一緒に手伝いをしているので、義勇も少しは馴染みがある。
「おかえり、禰豆子。伊之助たちもいらっしゃい。カナヲも一緒なんてめずらしいな!」
義勇のいる席からでは姿は見えないが、炭治郎の声は明るい。義勇に向けた憂いや戸惑いなどまったく感じさせない元気な声だ。
禰豆子と一緒に来たのは、炭治郎の友人なのだろうか。禰豆子はまだ中学生だと聞いたが、炭治郎たちが通う学校は中高一貫だというから、それなりに仲は良いのだろう。
「あ、あの、禰豆子ちゃんが一緒に行こうって……」
緊張していることが義勇にも伝わる女の子の声に、炭治郎が優しい声でゆっくりしていくといいと返すのが聞こえた。瞬時に浮かんだのは、炭治郎に片想いしているというしのぶの妹のことだった。
直感的に、この子だと思った。きっと今の声の主が、しのぶの妹だ。
わずかに見える少女の姿は、葉の陰で顔が見えない。一行はそれぞれパンを選び出したようだ。おそらくはカフェスペースに来るのだろう。そう思った途端に義勇の鼓動は速まり、頭のなかで警告音が鳴りひびいた気がした。
見たくない。炭治郎に恋する少女の顔なんて。
そう思うのに、義勇の視線は動かなかった。
重なり合う葉の隙間を凝視する自分の顔は、不機嫌そうだろうか。それとも、青ざめ頼りなげにでもなっているか。どちらでもなく、常の無表情であればいい。どちらの顔も炭治郎には見られたくない。
義勇は無理矢理視線を逸らせた。目を伏せてうつむけば、自分がひどく惨めな気がした。
会計を告げる炭治郎の声がする。離れた席を選んでくれと我知らず願った。きっと炭治郎は彼らの元に近づいていくだろう。そうして笑いかけるのだ。自分に恋する少女に優しく、労り深く、もしかしたら少女と同じ想いを乗せた瞳で。嬉しげに頬を紅潮させて義勇を見ていたその瞳で、きっと少女を見る。
「あの秘密基地みたいなとこにしようぜ!」
「え? あ、そこは駄目だ、伊之助!」
大きな声に続いて聞こえた炭治郎の慌て声に、ゆるゆると義勇が視線を上げると、観葉植物の陰からひょいと見知らぬ顔が覗いた。
「ごめんなさいっ、冨岡さん! ほら、伊之助、あっちの席が空いてるからあそこに座れ!」
「ちっ、先客がいるんじゃしかたねぇな」
慌てて飛んできた炭治郎が袖を引くのに、先の少年が不満そうに舌を鳴らした。
ちらりと義勇に向けられた炭治郎の視線に、義勇は隠しようのない腹立たしさを覚えた。
もう俺のことなど迷惑な常連客ぐらいにしか思っていないだろうに、おためごかしに気遣うような視線を向けるのはやめろと、吐き捨ててしまいたくなる。
簡単に心変わりする奴だと思われたくないのか。今さらだろう。義勇の言葉に従っただけだと開き直ればいい。そうしたらきっと自分も、ドロドロと心に溜まるばかりの澱みから解放される。
このままでは炭治郎を責める言葉ばかりが口をつきそうで、義勇はパソコンを閉じると、まだろくに食べてもいないパンが乗ったままのトレイを手に立ち上がった。
「いい。もう出る」
「えっ!? で、でもあの、まだお仕事中ですよね? 食事だって終わってないし……大丈夫です、伊之助たちはあっちに座ってもらいますから!」
いつものように必死な様子で引き留めようとする炭治郎に、少しだけ心が揺らぐ。ちゃんと義勇の目を見て言い募る炭治郎は、今までと変わりなく見えた。義勇に恋していると、真っ直ぐに伝えてきたときのままの炭治郎だ。
現金にも浮上しかけた義勇の機嫌は、炭治郎の背後で心配そうに佇んでいる少女が目に映った途端、苛立ちに取って代わられた。
「……友達なんだろう? 俺にかまわず話してくればいい」
返却口にトレイを返すときには、ほとんど手を付けなかったパンに罪悪感を覚えたが、それでも席に戻る気にはなれなかった。
一度として買ったものを残したことなどなかった義勇が、大半を食べ残したことがショックなのだろうか。義勇とトレイを交互に見遣る炭治郎の顔は、幾分青ざめていた。
「あの、冨岡さん……俺、なにかしましたか? 冨岡さんを怒らせるようなことしちゃいましたか?」
炭治郎の声は小さく震えている。義勇の不興を買うことに怯えているように見えるのは、多分義勇の気のせいではないだろう。
言いがかりでしかない義勇の不機嫌さに不安を露わにする炭治郎は、変わらず義勇を想っているように見える。それでもそれは、店員としてと置き換えることだってできる反応だ。客が注文した料理に手もつけぬまま退店しようとすれば、店員なら当然示す態度で義勇に接しているだけのこと。
義勇は炭治郎の様子をそう決定づけた。無理にでもそう思わねば、自分がなにを言いだすかわからない。
「こちらの都合だ、店に落ち度はない」
「そ、それじゃあの、パンは袋に入れますから、持って帰って食べてください! 冨岡さんの夕食だったんでしょう? 今、今すぐやりますから、ちょっとだけ待っててください!」
言いながら炭治郎が返却口に置かれたトレイに手を伸ばしたが、その手は聞こえてきた大きな声にぴたりと止まった。
「おい、権八郎、空いたならここいいよな! 紋逸、早く座れよ! 腹減った!」
「声がデカいって言ってるだろっ。でも、個室みたいでいい感じだよな、この席。あ、禰豆子ちゃん、俺の隣においでよ!」
「駄目だっ!!」
炭治郎の怒鳴り声に、飛び上がったのは少年たちだけではなく、義勇もまたびくりと肩を揺らした。店内の客もみな、炭治郎が上げた突然の大声に驚きを隠せないのか、ざわめきがやんだ。
「そこは……その席だけは駄目だ!」
かたくなな炭治郎に、義勇は思わず眉を寄せた。それは炭治郎の誠意なのだろうが、今は喜ぶ気になどなれそうにない。
「かまわない。もうあの鉢植えもどけていい」
素っ気なく言って、義勇はドアへと向かった。炭治郎が呼び止める気配に先んじて、食欲がないからパンもいいと言い捨てれば、炭治郎ももうかける言葉を見つけられなかったのだろう。背中に感じる炭治郎の視線を振り払うように、義勇は足早に店を出た。
帰り際見えたのは、炭治郎を見つめる少女の心配そうな顔だった。
確認せずとも、あの美少女っぷりならしのぶの妹で確定だ。義勇は愛車に乗り込みながら、胸の奥で独り言ちる。
儚げな風情の美しい子だった。案じる眼差しを一心に炭治郎に向けていた。
これでいい。これでもう終わりにしてしまえばいい。もううんざりだ。醜い嫉妬など、抱え込むのはもうごめんだ。
考えた刹那、義勇は自然に脳裏に浮かんだその言葉に、知らず目元を歪ませた。自嘲の笑みが震えながら口から零れ落ちる。
嫉妬。そうだ、嫉妬した。もう気付かぬふりはできない。いまだかつてない狂おしい衝動に、もう名はついてしまった。
憶測でしかない炭治郎の心変わりよりも、自分は今、あの少女にこそ嫉妬していたのだ。
可愛らしい、炭治郎の同級生。誰に恥じることなく真っ直ぐに、きれいな恋心を炭治郎に捧げることを許された、あの美しい少女に。
炭治郎と恋しても、祝福だけを得られる、あの少女に……みっともないほどに、嫉妬している。
嫉妬なんて、もう二度とするはずがなかった。錆兎への想いが愛へと変わった以上、もう嫉妬なんて感情は、自分の胸に生まれるわけがないと思っていた。だから決して名付けてはいけなかったのに。気づくわけにはいかなかったのに。
あの可憐な少女に見苦しく嫉妬するほどに、炭治郎へと向かう感情は恋に近づいていると、認めなくてはいけなくなるから……気づきたくなどなかったのに。
でも、もういい。恋は始まる前に終わった。終わってくれて良かった。錆兎の代わりを炭治郎にさせなくて済む。あの清純で健康的な炭治郎には、自分の穢れは毒にしかならない。
あぁ、もう行かないと。いつまでもここにいたら炭治郎に気づかれる。炭治郎のことだから、きっと義勇が車を出す前に、紙袋を持ち息せき切ってやってくるだろう。いや、それならもうとっくに出てきているか。
自嘲の笑みは先ほどよりは幾分軽かった。
もう炭治郎にとっても終わったことなのだろう。きっともう、炭治郎の心に義勇への恋の火は灯されてはいない。それはすでにあの少女を温めるためにあるのだ。だから炭治郎は今までのようには義勇を見つめたりしない。明るく朗らかに、嬉しいと、見つめられるだけで幸せだと、義勇に笑いかけたりなんてしない。
その証拠に、もう何分も動けずにいる自分の元へ、炭治郎はやってこないじゃないか。
義勇は歪んだ笑みを浮かべたまま、エンジンをかけた。家に帰る気にはなれなかった。溜まった澱みは心を埋め尽くさんばかりで、きれいな上澄みなど望めないほどにどろりと濁っている。
溝浚いが必要だ。すべて捨て去り、忘れるためにも。
アクセルを踏み車を発進させながら、義勇の目はそれでもバックミラー越しに店のドアを見つめていた。
けれど、遠ざかる店が見えなくなるまで気にし続けても、ドアが開くことはなかった。