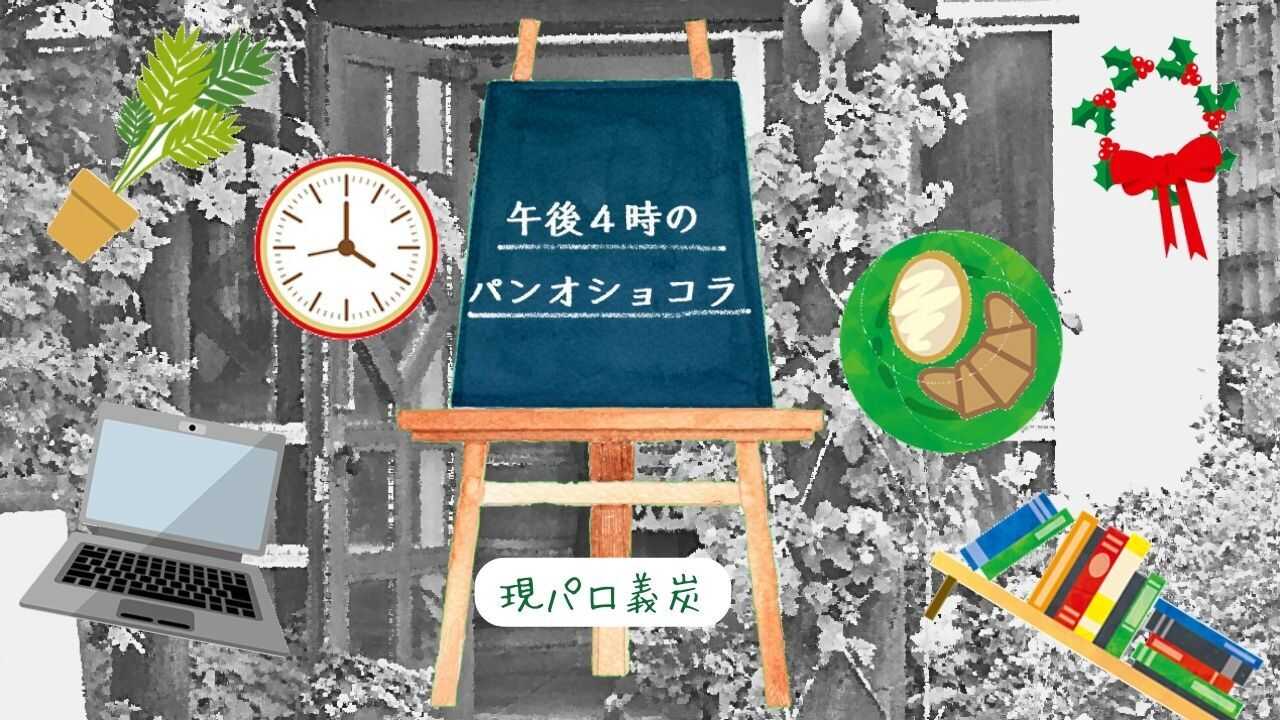「閉店、ですか」
「はい。私も年ですし、店を継いでくれる者もおりませんので」
冨岡さんにはご贔屓いただいてましたのに申し訳ございません。そう言って頭を下げるマスターに、義勇は内心の動揺を押し隠し、鷹揚に頷いてみせた。
「いえ、私のほうこそいつも長居してしまって、ご迷惑をおかけしてすいませんでした」
「いえいえ、迷惑などととんでもない」
マスターは少し慌てたように手を振った。ほかには客もいない店内で、声を潜める必要などないだろうに、そっと義勇に顔を近づけ言うことには。
「……実は、内緒にしてましたが、私は冨岡さんの著書の大ファンでして。憧れの作家さんが私の店で執筆されているというだけで、年甲斐もなく興奮してたんですよ」
ロマンスグレーのマスターが見せた悪戯っ子のような表情に、義勇は目をしばたかせた。
「……ご存じだったんですか」
「申し訳ございません。パソコンの画面が見えてしまったことがございまして……去年発売されたご本に、そっくりそのままの文章があったもので、気づいてしまいました」
義勇は日ごろ著者近影を断り続け、インタビューも写真を乗せないことを条件にしている。なのに、なぜ気付いたのかと思えば、そういうわけか。
客のプライバシーの詮索など一度もしたことがないマスターのことは、それなりに信用している。目に入っただけだという言を疑う気はないが、それにしても並外れた記憶力だと、腹を立てるよりも先に感嘆してしまう。
義勇の感心の眼差しに気づいたものか、マスターは面映ゆそうに苦笑した。
「そんなわけで、冨岡さんの執筆のお役に立てていたことが、私の密かな誇りでしたので、店じまいはたいへん心苦しく思っております」
なるほど、ファンだというのはお愛想というわけでもないようだ。義理があり断り切れずに書いた雑誌のエッセイで、行きつけの喫茶店での執筆が一番筆が乗ると書いた記憶がある。
デビュー四年目の義勇は、小説家としてはまだまだ駆け出しといっていい。著作もそれほど多くはない。売上ランキングなどにはあまり縁のない、知名度も人気もそこそこの作家だという自覚はある。
そんな自分の本を、小説のみならず、一度書いただけのエッセイにも目を通しているとは。思いもよらぬことに、義勇は少しばかり気恥ずかしさを覚えた。
「そこでですね、じつは当店の代わりにお勧めしたい店がございまして。ご本のなかで、当店のモーニングをたいへん気に入ってくださっていると書かれてましたでしょう?」
「ええ、まぁ」
たしかにそんなことも書いたなと、記憶を探る。事実、和食派の義勇だがこの喫茶店のモーニングはお気に入りで、とくに日替わりのパンは毎日食べても飽きがこないぐらいには好いている。
正直なところ、気に入りの執筆場所がなくなること以上に、あのパンが食べられなくなることのほうが残念なくらいだ。
「モーニングで提供しているパンなんですが、あれは懇意にしているベーカリーから仕入れているものなんですよ。そのベーカリーにはカフェスペースもございまして、私も店が休みのときに寄らせてもらうのですが、きっと冨岡さんにも気に入っていただけるのではないかと……」
午後4時のパンオショコラ