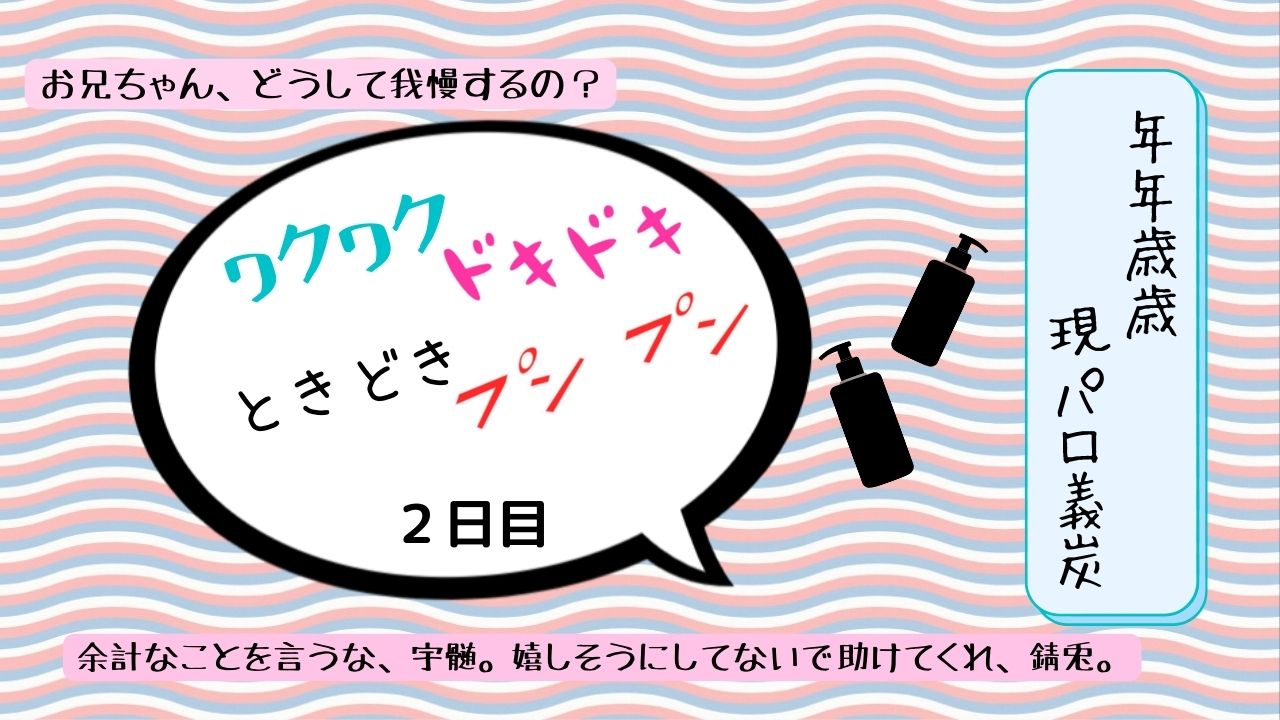炭治郎
「義勇さん大丈夫かなぁ……禰豆子一人で、本当に看病できるかな」
浴場に向かう廊下を元気なく歩きながら、しょんぼりと言った炭治郎に、錆兎や真菰もしゅんと肩を落としたまま顔を見合わせた。
「やっぱり戻ったほうがいいんじゃないか? せめて二人ずつぐらいでついてたほうがいいと思うんだが……」
「一人だとおトイレとか行きたくても行けないかもしれないし、もう一人くらいはいたほうがいいよね」
勢い込んでうなずきあい義勇がいる座敷に戻ろうとした三人を、宇髄のあきれ声の一言が止める。
「だぁかぁらぁ、おまえらが戻ったら冨岡がよけいに気に病むだろうがっ」
その言葉に炭治郎たちは、また顔を見合わせ、深い深いため息を吐いた。
わかっているのだ、炭治郎だって。もちろん、錆兎や真菰だって同じだろう。
義勇がとても苦しそうにしながらも、炭治郎たちに申し訳なさげな目を向けていたことぐらい。自分の体調よりもずっと、炭治郎たちを気遣っていたことなんて、みんなしっかりわかってはいるのだ。
義勇はやさしいから、きっとはしゃぐ自分たちに気を遣って、体調が悪いと言えずにいたんだろう。どうにかウェアは自分で着たし、宇髄が抱き上げようとするのに断固拒否の姿勢を見せはしたけれど、本当につらそうだった。煉獄に肩を借りてとはいえ自分の足で休憩所には行けたものの、限界だったのか、ふらふらと横になって苦しそうにしていた。
そんな義勇を一人で置いていけるわけもなく。もうはしゃぐような気分でもない炭治郎たちだったけれど、義勇の傍にいると言ったら当の義勇からとても悲しい匂いがしたから。悔しい、哀しい、申し訳ないと、潤んだ瑠璃の瞳が言っていたから。
義勇が悔やむような休日など過ごしたくない炭治郎たちが、逆らえるわけがない。
「俺たちも悪かった。冨岡がまだ俺たちにそこまで気を許したわけではないことぐらいわかっていたのだが、つい浮かれてしまってな……」
もっと気配りしてやるべきだった。未熟ですまんと、本当にすまなそうな顔で煉獄に頭を下げられてしまえば、同じく気づけなかった炭治郎たちだってなにも言えなくなる。
むしろ、煉獄よりも親しい自分たちこそが気を配るべきだったのだ。
「ったく、しょうがねぇなぁ。派手に元気出せ! おまえらがそんな顔してたら、冨岡だってガッカリするだろうが」
ぐしゃぐしゃとまだ濡れた髪を順繰りに撫でまわされ、錆兎が決心した顔でうなずいた。
「……天元の言うとおりだ。禰豆子がついててくれてるんだし、義勇のとこに戻ったときに楽しかったって言ってやれるよう、ほかも入って回るぞ」
「まずは予定どおりツリーハウスだよね。禰豆子ちゃんも遊ばせてあげたいし、十五分くらいで交代しよう」
真菰も義勇に楽しい報告をするのが自分の役目と決意したようだ。遊ぶ計画を話しているとは思えない真剣な顔で言う。
義勇と家族同然で自分より年下の二人がそう決めたのなら、炭治郎だって我儘は言えない。炭治郎だって義勇が喜ぶ顔が見たいのだ。
「じゃあ、すぐツリーハウスに行こう! どんなだったか義勇さんに教えてあげなくちゃ!」
「おうっ!」
中庭に続くドアへと駆けだそうとした錆兎と真菰の頭を、宇髄がガシッと掴んだ。
「待て待て、まずは髪を乾かしてこい! 風邪ひいたらどうすんだ」
そこで炭治郎ははたと気がついた。そういえば禰豆子も髪を乾かしてないし、義勇だって濡れたままだ。錆兎や真菰もそこに気づいたらしく、またまた炭治郎と顔を見合わせる。
「やっぱり一度義勇の元に戻ってからにしよう!」
「義勇が風邪引いちゃう!」
「タオル持ってくる!」
「おまえら俺の話理解してっか!? 先に自分の髪を乾かせって言ってんだろうが!」
さっきの決意はどこへやら。一斉に走り出そうとした炭治郎たちが宇髄に叱られしゅんと肩を落とすと、愉快そうに煉獄が笑った。
「俺が冨岡と禰豆子にタオルを届けてこよう! 竈門少年たちが戻っては、遊ばせてやりたかったのにと冨岡もガッカリするだろうしな!」
そう言われてしまえば、もうなにも言えない。タオルを手に休憩所に向かう煉獄の背を見つめ、ハァッとため息をついた炭治郎たちだった。
ともかく髪を乾かしてしまおうと、脱衣所に戻り備え付けのドライヤーで髪を乾かし合う。気が急いて生乾きのまま口々に「もういいよなっ?」「乾いたよねっ?」と、お目付け役となった宇髄にお伺いを立てれば、あきれた顔でドライヤーを取り上げられた。
「俺が乾かしてやっから、ちったぁ落ち着けっての。おまえらに風邪でもひかせたら、俺らが冨岡にも鱗滝さんにも合わせる顔がねぇっての。冨岡に楽しかったって笑ってやるんじゃねぇのかよ」
「わかってる! だけど、のんびりしてたら十五分なんてすぐに過ぎちゃうだろ!」
「あのなぁ、十五分おきに交代してたら冨岡だって休めねぇよ。禰豆子だって、自分を気にしねぇで炭治郎に遊んでほしいって考えて、自分が残るって言ったんだと思うぜ? すぐに戻ってちゃ、ガッカリするんじゃねぇの?」
おまえは遊ぶより冨岡と一緒にいるほうがうれしいのかもしれないけどな、と、炭治郎に向かって苦笑した宇髄に、目をパチクリとしばたかせる。
「そうなのかな……禰豆子が一緒でも、俺、楽しくなかったことなんてないのに……」
義勇とくらべると少々乱暴な手つきで髪を乾かされながら、困ってしまった炭治郎は、錆兎と真菰をうかがい見た。少しでも早く乾かそうとタオルで髪を拭っていた二人にも、こくりとうなずかれてしまえば、ますます眉尻が下がる。
「天元に言われて気づくのは癪だけど、たしかに残るって言ったときの禰豆子、やたら張り切ってたみたいだからな」
「禰豆子ちゃん、早く炭治郎に頼りにされるようになりたいんだよ。炭治郎はいつも禰豆子ちゃんや竹雄くんたちを優先するから、たまには『お兄ちゃん』を休んでほしかったんだと思うなぁ」
そう言われても、炭治郎にとって禰豆子は、絶対に守らなくちゃいけない大切な妹だ。逆に守られたり頼りにするなんてこと、考えてもみなかった。物心ついたころから『お兄ちゃん』で、禰豆子たちの世話を焼かない日なんて一日たりとない炭治郎にしてみれば、宇髄や錆兎たちの言葉はどうにもピンとこない。
炭治郎に続いて真菰の髪を乾かしだした宇髄が、首をひねる炭治郎をチラリと見下ろし、わずかに口角を上げた。苦笑というにはささやか過ぎる表情とともに、ふわっと炭治郎の鼻をくすぐったのは、どことなし悲しいような、少し怒っているような、複雑な匂い。
錆兎か真菰なら、きっと自嘲と言い表すであろうその匂いが、炭治郎をますます悩ませる。
俺が禰豆子を頼りにしないと、宇髄さんまで怒らせちゃうんだろうか。そんなにいけないことなのかな。
どうしたらいいのかわからずにじっと宇髄を見ていたら、炭治郎の視線に気づいた宇髄は、今度ははっきりと苦笑した。
「……チビッ子どもにそんなに急いで大人になられちゃ、そりゃ冨岡も焦るわな」
「焦る? 義勇さんがですか?」
思いがけない言葉に、そうなのか? と確認するように錆兎へ目を向ける。ガシガシと乱暴にタオルで髪をこすっていた錆兎は、虚を突かれた顔で手を止めていた。真菰も目を見開いて宇髄を見上げている。
「義勇……私たちが大人になろうとするの、嫌なのかな……」
かすかに震えている真菰の声。錆兎もグッと唇を噛みしめてうつむいていた。
まさかの反応に、炭治郎はポカンとして、ちょっと不安にもなった。だって、錆兎や真菰は、義勇のことならなんだってわかると思っていたのだ。それは炭治郎にとってはあまりにも当たり前すぎて、宇髄のたった一言に二人がこんなにも動揺するなんて信じられない。
炭治郎が困っていると、軽く肩をすくめた宇髄が、真菰の頭にポンと手を置いた。
「俺が初めて教室で見た冨岡は、なんにも興味なんてないし、それこそ自分自身のことだってどうでもいいって顔してたぜ。自分で考えて行動してるわけじゃなく、言われるままに動くだけでいいって感じでよ。感情なんてどっかに失くしてきたって面で、ぼぅっとそこにいるだけだった」
実際そうだったんだろうけどなと、かすかに眉を寄せ少し硬くて、でもやさしい声で宇髄は言う。続いた「でも」の一言は、なんだかとても強く響いた。
「今の冨岡は違うだろ。いろいろ自分で考えて、うれしがったり派手にビックリしたり、悲しがったりもしてんだろ? 俺にだってわかるぐらいによ。焦るのだって、ちゃんと心があって、自分で考えてるからこそだ。おまえらにかまわれるのを嫌がってるわけねぇだろうが。おまえらが大事だから、自分もしっかりしようって焦るようになってきたんだ」
喜んでやれよと言って、宇髄は薄く笑う。その小さな笑みに、炭治郎の胸がそわりとうずいた。
なんでだろう。宇髄さんはいつもどおりに笑ってるのに、やっぱり少しだけ、怒ってるし悲しんでるみたいな匂いがする。
なにやら落ち込んでいる錆兎と真菰も気掛かりだし、宇髄の匂いも気になるし。当然、禰豆子や義勇のことだって心配でたまらない。いろんなことがいっぺんに頭のなかにあふれて、どうしたらいいのかわからない。
炭治郎がどうしようと困っていると、煉獄が足早に戻ってきた。絶好の助け舟だとホッとしたのもつかの間、なぜだか辺りを見回した煉獄は、笑みを消し眉を寄せている。
「おう、冨岡大丈夫そうだったか?」
煉獄に声をかけた宇髄はもう完全にいつどお通りだ。でも笑ったその顔は、煉獄の少し焦った声にすぐに固まった。錆兎と真菰も目を見開いて煉獄を凝視する。もちろん、炭治郎だって同じこと。もしかしたら一番ビックリしたかもしれない。
「禰豆子は来てないのか? タオルを取りに戻ったらしいんだが……」
まさか(よもや)、迷子? 全員の頭に浮かんだのはそんな言葉だった。