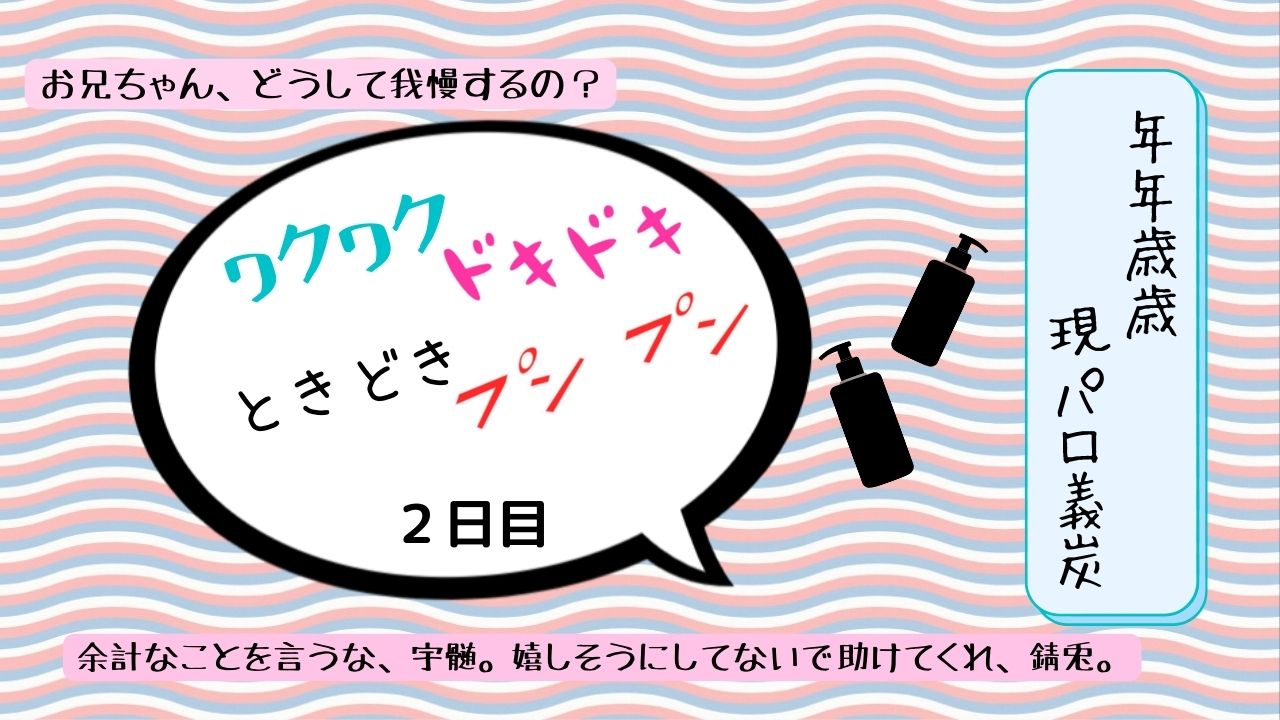禰豆子
駅から送迎バスで十分ほどの場所にある、リニューアルオープンしたばかりのスーパー銭湯は、ゴールデンウィークということもあってかなりの盛況っぷりだ。
大浴場も混雑していたが、座敷造りの休憩所でも老若男女がそれぞれくつろいでいる。とはいえ時刻は午後四時で夕食には少し早いし、漫画などが読めるラウンジにくらべれば、テーブルと座布団があるだけの休憩所は静かなほうだと言えるだろう。
そんな休憩所の一番奥のテーブルの横で、オレンジ色の館内ウェアを着た禰豆子は、懸命に団扇を動かしていた。
小さな手で風を送る先には、苦しそうな息遣いの義勇が横たわっている。
義勇の額にはいくつも汗が浮かんでいて、禰豆子はそれが心配でしかたがない。禰豆子よりもずっと大きいのに、つらそうに目を閉じて横になっているさまは、やけに頼りなく見えてしまう。団扇を振る手にも力がこもるというものだ。
露天風呂にみんなで入ってる最中に、突然ずるりと湯に沈んだ義勇に一同が大慌てしたのは、今から三十分ほど前のこと。
湯あたりしたのか義勇はとても苦しそうだった。宇髄に抱えあげられて脱衣所に運ばれるまでは、軽く気を失ってもいた。錆兎と真菰が体を拭いてやっているうちに目を覚まし、自分でウェアを着た義勇は、煉獄に支えられてとはいえ自分の足で休憩所まで歩いたけれど、それが限界みたいだった。頭痛がひどくて起きていられないらしい。
煉獄に医務室に行くかと聞かれても首を振り嫌がるから、とにかく横になれる場所へとここに来たけれど、本当に寝ているだけで大丈夫なのか禰豆子は不安だった。でも、錆兎や真菰もそうしてやってくれと言うなら、禰豆子が反対するわけにもいかない。
炭治郎の不安は禰豆子以上だ。「俺が重かったからだ……俺のせいですよね、義勇さんごめんなさい!」と泣き出しそうな顔で心配していた。真菰と錆兎だって赤く上気していた顔から一気に血の気が引いてしまっていた。
そんな子供たちにここで寝てるだけでいいと言って、義勇は少し震える手で炭治郎の頭を撫でてくれたけれど。その後はもう口を開くのもつらいのか、なにも言わずに横になっている。
「……風邪をひく」
「ぎゆさん、寒いの? 団扇しないほうがいい?」
唐突にぽつりと言われた一言に慌てて手を止め聞いたら、義勇は横になったまま小さく首を振った。
潤んだ瞳が向けられた先で、いくつもの水滴が畳に染みを作っている。それを見た禰豆子の目の前で、また一滴、禰豆子の髪から水滴が畳に落ちた。
禰豆子の髪が濡れたままなのに気づいたのだろう。一所懸命仰いでいた禰豆子はそんなこと気にしなかったのだけれど、義勇は気遣わしげに禰豆子を見上げていた。
苦しいのは義勇のほうなんだから、私の髪なんて気にすることないのに。思えども、義勇はそういう人なのだ。そんなところは、炭治郎によく似ている。
だから禰豆子はとても心配してしまう。禰豆子のお兄ちゃんでありヒーローでもある炭治郎は、禰豆子や竹雄たちのことばかり心配して、自分のことはいつだって後回しだ。遊びに行くときも、いつでも禰豆子たちを連れて遊ぶ。
オモチャもお菓子も炭治郎は後回し。いつだって禰豆子たちが先。禰豆子が覚えているかぎり、炭治郎が一人で友達と遊びに行ったことなんてない。
禰豆子にはそれがちょっと悲しいのに、炭治郎は気づいてくれない。禰豆子だってもう小学一年生だ。竹雄と花子の世話だって一人でできるのに、信用されてないみたいでちょっぴり悔しくもある。炭治郎がとてもやさしいことも、禰豆子たちを大事にしてくれていることも、ちゃんと知っているけれど、それでもやっぱり禰豆子には少しだけ炭治郎のやさしさが悲しくて、悔しかった。
義勇のやさしさは、炭治郎と同じに禰豆子には見える。今も苦しそうなのに、禰豆子が風邪をひかないか心配してる。それにさっきだって、一緒にいると言い張る炭治郎や真菰たちに、悲しそうな顔をした。
自分の心配をするよりも、炭治郎たちが楽しく遊び続けてくれるほうがいい。禰豆子にだって義勇がそう思っていることがわかるくらい、義勇は悲しそうに炭治郎たちを見ていた。
だから禰豆子はみんなに言ったのだ。
「禰豆子がぎゆさんのお世話する! だからお兄ちゃんたちは遊んできて!」
禰豆子はみんなから見れば頼りないチビッ子だ。みそっかすのお荷物だなんて誰も言わないでくれるけど、禰豆子にだってそれくらいわかっている。背だって一番小さくて、うまく舌が回らないから義勇の名前だって一人だけ舌足らずになるのだ。本当はときどき錆兎や宇髄のことも『ちゃびとくん』だの『うじゅいしゃん』になりかけたりもする。今朝の剣道の稽古だって、一番先に疲れてしまった。そんな禰豆子が具合の悪い義勇の世話をするなんて、誰もが不安を覚えるだろう。
でも! 重ねて言うが禰豆子だってもう小学一年生なのだ。炭治郎が一年生のときにはもう、ちゃんと禰豆子たちの面倒を見てくれていた。禰豆子が風邪をひけば、お母さんがお店に出ているあいだ炭治郎が、おでこのタオルを取り換えてくれたり水を飲ませてくれたのだ。
禰豆子だって炭治郎のようにできるはず。だっていつでも炭治郎のすることを見てきたんだから。いつだって炭治郎の真似をしてきたんだから。
「……わかった。では禰豆子に任せよう!」
みんなが不安そうにするなかで、そう言ってくれた煉獄には大感謝だ。
「禰豆子はちゃんと手伝いだってできるし、弟や妹の面倒を見るのも慣れているんだろう? 冨岡の介抱を任せようじゃないか!」
ふん! と拳を握って宣言した禰豆子に、煉獄はそう言って笑ってくれた。フロントに置かれていた団扇やら水やらを持ってきた宇髄も、軽く笑ってうなずいた。
「冨岡はここで寝てりゃいいって言うんだし、たしかに介抱は禰豆子で十分だな。逆上せただけなら、水分とって休んでりゃそのうち治るんだし、禰豆子、冨岡を頼むぜ?」
「うん! がんばる!」
炭治郎たちはまだ心配そうだったけれど、宇髄に大勢でいたら義勇が休めないと後押しされ、やっとうなずいてくれた。後で交代するねと言いながら、煉獄たちに連れられお風呂に戻っていった顔は、まだまだ不安そうだったけど。
なんとか納得してくれたみんなと違って、最後まで反対していたのは当の義勇だ。だけれども、なにしろ義勇は口下手なうえに、今は具合も悪い。拒む言葉を口にする代わりに不満と不安と申し訳なさを浮かべている瑠璃の瞳を、見て見ないふりした禰豆子だった。
「大丈夫だよ。禰豆子寒くないし、髪だってすぐ乾くもの」
そう言って不安げな義勇の頭をよしよしと撫でてみれば、義勇の髪は禰豆子以上に濡れている。禰豆子はビックリして慌ててしまった。
そういえば義勇は頭まで湯に沈んでいたんだっけ。横になる前にさっと真菰に拭われているけれど、ポニーテールに結ばれた髪は、まだぐっしょりと濡れている。
枕代わりに畳んだタオルは置いてあるけれど、そのタオルもかなり湿っているようだ。投げ出された髪の束が、畳に染みを作っている。
このままだと、義勇のほうこそ風邪をひいてしまうかも。濡れてるのにさっきまで団扇で扇いじゃったし。
「ぎゆさんも髪の毛乾かさなきゃ! 風邪ひいちゃう!」
言うなりすくっと立ち上がった禰豆子は、義勇ににこっと笑いかけた。禰豆子が心細くならないよう、炭治郎がいつも笑顔をみせてくれるように。
「タオル持ってくるね。ぎゆさんはお水飲んで待ってて!」
もの言いたげな義勇の視線を振り切って、禰豆子はとととっと小走りに座敷を出た。大浴場はどっちだったかなと辺りを見回す。義勇を心配してたから、道順をよく覚えていない。
「んっと……どっちだったっけ?」
「お嬢ちゃん、どうしたの?」
迷子だとでも思ったのだろう、首をかしげている禰豆子に、やさしそうな小母さんが声をかけてくれた。
「あの、大浴場はどっちですか?」
「あぁ、それならこの廊下を進んで突き当りを右よ。大きな暖簾がかかってるからすぐわかるわ」
「ありがとうございます!」
教えてくれた小母さんに、きちんと頭を下げてお礼を言う。小母さんが一緒に行こうかと言ってくれたけど、禰豆子は大丈夫と笑い返し一人で歩き出した。
禰豆子だってお姉ちゃんなんだもん。一人でも迷子になんてならないもん。
それに、禰豆子には義勇の介抱をするという重大な使命があるのだ。早くタオルを持って義勇のところに帰らなくちゃ。意気軒昂に禰豆子はずんずん進んでいく。
廊下の突き当りを言われたとおりに右に曲がると、暖簾が掛かった入り口が見えた。
臙脂色の暖簾にちょっと首をかしげる。
みんなで入ったときは紺色じゃなかったっけ? 不思議だったけれど、でも小母さんはここって言ったはず。禰豆子はあまり気にせずとことこと暖簾の下を入っていった。
禰豆子は銭湯にくるのは初めてだったし、暖簾に書かれた『男』や『女』という文字も、まだ習っていない漢字だったから。
脱衣所にいるのが女の人ばっかりなことにも、疑問を感じなかった。いつも入るお風呂だっていつも炭治郎や竹雄とも一緒だし、お父さんと禰豆子や花子が一緒に入ることだってある。さっきだって義勇たちと一緒だった。
だから知らなかったのだ。男の人と女の人は、別々のお風呂に入るなんてこと。
見回しても炭治郎たちはどこにも見当たらない。きっとお風呂場にいるんだろう。わざわざ声をかけなくてもいいよねと決めて、禰豆子は壁にずらっと並んでいるロッカーに近づいていった。
フロントで貰ったリストバンドと同じ番号のロッカーに、禰豆子の着替えとタオルが入っているはず。青いリストバンドに書かれた数は87。真菰が花って読めるね、禰豆子ちゃんにぴったりと、真菰のほうこそかわいいお花のように笑っていた。真菰はもう漢字も読めるのだから、本当にすごい。
お花お花と言いながら見つけたロッカーに、リストバンドに付いている鍵を差し込む。
「あれ? なんで開かないの?」
禰豆子は知らない。男性用のロッカーと女性用のロッカーでは、リストバンドの色も違うなんて。宇髄たちと一緒だからと、男性用のロッカーの鍵を渡されていることなんて、思いもよらない。
困ってしまってきょろきょろと周りを見回した禰豆子は、さっき入ってきた入り口とは別に、奥へと続くドアを見つけた。
服を脱いでいたときに錆兎が、あれがツリーハウスのある中庭に続いてるみたいだと言っていたドアに似ている。そういえば露天風呂の後はみんなでツリーハウスに行こうとも言っていたっけ。
ホッとして禰豆子はドアに駆け寄った。
「ツリーハウスって書いてある! ここだぁ」
きっと炭治郎たちもツリーハウスにいるだろう。そしたらロッカーを開けてもらってタオルを出して……と、考えながら向かったツリーハウスには、遊んでいる子供たちが何人もいてにぎやかだ。思わず禰豆子は、わぁ! と目を輝かせた。
大きな木の上にはかわいいお家。太い枝にはいくつも縄梯子やロープがぶら下がっていた。子供たちがそれを競争するように登りあっている。直接木登りに挑戦している子もいた。
お家の周りにはぐるりとテラスがついていて、下で見ている大人たちに手を振っている子がいた。みんな笑顔で、楽しそうだ。テラスには木の階段もあって、小さい子はそこからツリーハウスに上がるんだろう。ツリーハウスの裏側にはすべり台まである。順番待ちしている子供がテラスに並んでいた。
公園にあるのよりずっと大きいすべり台を、キャアキャアと声を上げて子供たちが滑り降りてくる。あんまり楽しそうで禰豆子も少しそわっとしたけれど、大事な用があるから遊ぶのは後回しだ。
「お兄ちゃんたちどこかなぁ……」
木の周りにあるブランコやハンモックにも、大人たちが座っているベンチにも、炭治郎たちの姿はない。お家のなかにいるのかなと階段を登ってみたけれど、やっぱり誰もいなかった。テラスから見まわしても、宇髄や煉獄の姿だってどこにも見えない。
「みんなどこ行っちゃったのかな」
もしかして、炭治郎たちはお風呂にいるんだろうか。でもロッカーが開かなくちゃウェアをしまえないから裸になれない。服を着たままお風呂場に行っていいのか、禰豆子にはわからない。
「どうしよう……」
しょんぼりと肩を落として階段を降りると、あれ? と声がした。
「やっぱり竈門だ。竈門も遊びに来たのか?」
男の子の声に振り向くと、同じクラスの不死川就也が立っていた。双子で隣のクラスの弘も一緒だ。
「就也の友達か?」
「うん、俺と同じクラスの竈門禰豆子」
就也たちに炭治郎よりちょっと大きいモヒカン頭の男の子が話しかけた。就也たちのお兄ちゃんだ。就也や弘と一緒に学校へ来るのを見たことがある。三年生だし、就也たちは春休みに引っ越してきたので、禰豆子はまだお話したことがない。
ふーん、と、ちょっと怖い顔で禰豆子を見る男の子の顔には、大きな傷があった。痛そうだと禰豆子は思わず眉を下げた。でも炭治郎だって痣があるけど痛くないよって笑う。このお兄ちゃんも痛くないといいなと思いながら、じっと見つめていると、就也たちが近づいてきた。
「どうしたんだ? 誰か探してんのか?」
モヒカン頭のお兄ちゃんは、禰豆子よりちっちゃい女の子の手を引いている。花子と同じくらいの子だ。後ろをついてきた女の子は二人。仲良く手をつなぎ合っていた。
「ここな、俺たちの母ちゃんと実弥兄ちゃんが働いてるんだぜ。今日は玄弥兄ちゃんと一緒にみんなで遊びにきたんだ。こっちが妹の寿美。こっちはことと貞子」
どこか誇らしげに弘が言うのに、禰豆子はこんにちはと頭を下げた後、玄弥を見上げてこっくりとうなずいた。
「あのね、お兄ちゃんたちがいないの。禰豆子、早くぎゆさんのとこに行かなくちゃいけないのに……」
「なんだ、迷子になったのか。兄ちゃんのくせに妹置いてくなんて、しょうがねぇヤツだな」
少し怒った声で言う玄弥に、禰豆子は思わず眉をつり上げた。
「違うもん! 禰豆子はぎゆさんのお世話してたのっ、お兄ちゃんが置いてったんじゃないもん!」
禰豆子がプンッと頬をふくらませたら、玄弥はちょっとビックリしたみたいだった。それでも。
「悪かったって。けど、一人じゃ兄ちゃん探すの大変だろ。一緒に探してやるよ」
そう言って笑ってくれる顔は、最初の印象よりもずっとやさしい。
きっと炭治郎と同じで、玄弥もやさしいお兄ちゃんなんだろう。就也たちも笑って「行こうぜ」と言ってくれたから、禰豆子もプンプンとふくらませたほっぺを笑みに緩ませた。
よかった、これでぎゆさんも風邪ひいちゃわないよね!
禰豆子の頭を撫でてくれた玄弥は、炭治郎と同じ『お兄ちゃん』の手をしていた。