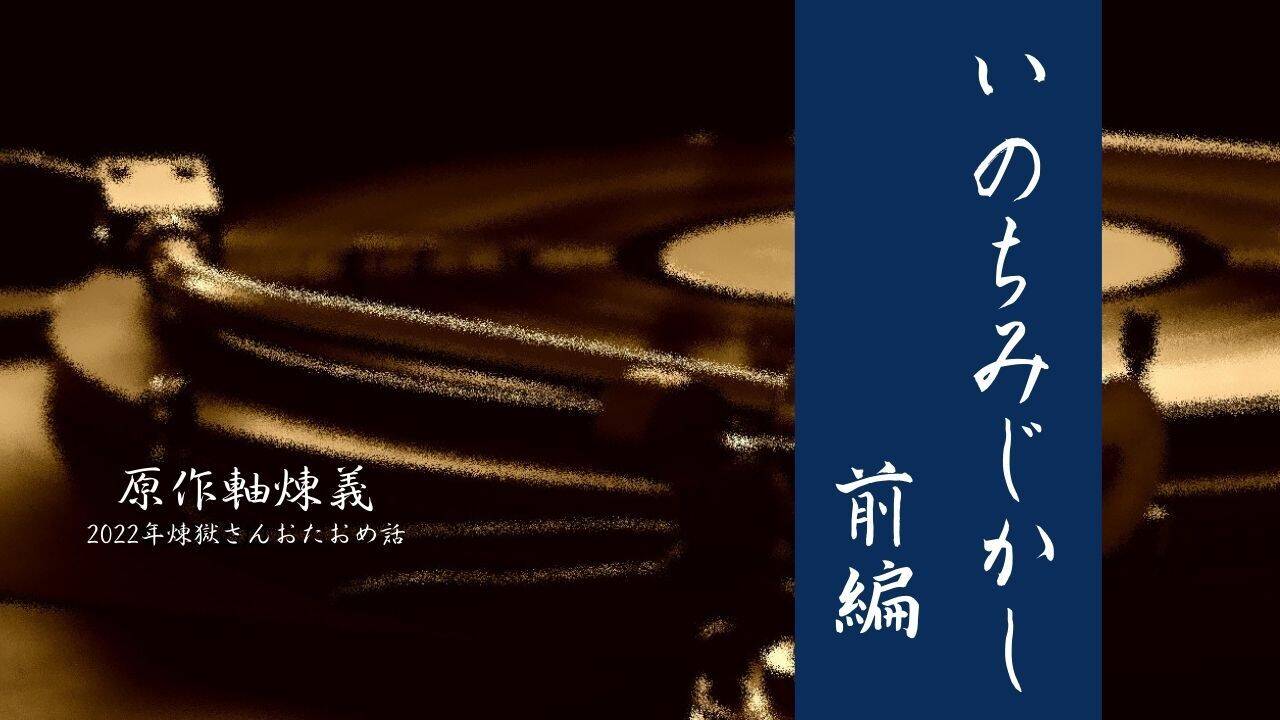薄暗い館内から一歩表に出れば、青空のまばゆさが目を焼く。暗がりから光のなかに出たときの常で、義勇の視界が一瞬、白く染まった
フフッと、いかにも喜悦に富んだ忍び笑いが傍らから聞こえた。ちらりと視線を投げれば、幸せをかき集めたような顔で煉獄が笑っている。声は抑えているものの、笑みがこぼれるのを止められないといった風情だ。
「今日は本当にいい日だ。冨岡に逢えたばかりか、こうしていつか一緒に来たいと思っていた花屋敷にもこられた。一生忘れられない素晴らしい日だ」
向けられた笑みはやはりとろけんばかりで、声も多幸感に満ちている。
そういえば、今日は煉獄の誕生日だったか。
先の会話を思い出し、義勇は知らず視線を泳がせた。
どうして自分なぞと行動することに、煉獄がこんなにもうれしそうな顔をするのか、義勇にはてんで理解できない。それでも煉獄が素晴らしい日だと言うのなら、水を差すような言動は戒めるべきだろう。なにせ煉獄は誕生日なのだ。誰からも寿がれるべき、佳き日である。そんな日を自分の迂闊な言葉や態度で台無しにしてしまっては、申し訳ないにもほどがある。
ちゃんと祝うべきだろうか。だが、どうすればいいんだろう。
煉獄は祝いと思って手をつないだままでいてくれと言ったが、たかがこれしきのことを祝いとするのは、どうにも気が引けた。
せめてなにか気の利いたことでも言えればいいのだが。思ってみても、口下手な義勇には無理難題が過ぎる。
どうにか煉獄が楽しめるような会話を……。
「能」
「ん?」
義勇のつぶやきに小首をかしげ、浮かんだ笑みはそのままに顔を覗き込んできた煉獄に、胸中でしまったと冷や汗をかく。
思いついた言葉を考えもせず口にしてしまった。なんでもないと黙り込むのは簡単だが、それではいつもと同じことの繰り返しになるだけだ。煉獄を寿ぐ気持ちは、義勇にだって十二分にあるのだ。祝いの品など用意がなく、煉獄が喜ぶことをしてやりたいと思っても、見当もつかないありさまではあるが、少しでも楽しんでほしい。
せめて煉獄が興味を持ちそうな会話をと、必死に話題を探し求めた挙げ句が、これか。本当に俺は不甲斐ない。落胆にガクリと肩が落ちそうになるが、落ち込んでばかりもいられない。
「観るだけじゃないのか」
焦る気持ちとは裏腹に、義勇の言葉は唐突が過ぎ、そっけなくも感じられたろう。
けれど煉獄は、そんな義勇の無愛想っぷりなど、まるで気にならないようだ。それどころかいっそう顔をほころばせ、まさしく浮かれているとしか言いようのない声で笑ってくれさえした。
「あぁ、それか。父上から指南を受け始めたころに、全力で止まれというのが、どうにも理解できなくてな。鍛錬の一貫として能を習わされた」
「全力で止まる……」
能が鍛錬になるのかという疑問はさておき、その文言は義勇にも理解できる。
「俺も、先生によく言われた」
「冨岡もか! あれは、初めて剣を握ったばかりの身には理解に悩む要求だったな!」
義勇は深くうなずいた。錆兎と二人して意味がわからないと頭を抱えたのが懐かしい。先生に何度も「違う!」と叱り飛ばされたものだ。
「初めは能がなんの役に立つのか、さっぱりわからなかった。だが、能楽は神事から始まっただけあって、武士のたしなみだと言うからな。実際、習ってみるとなかなかに厳しいぞ」
「そうなのか?」
「うむ! 能の『構え』は、まさしく全力で止まるという行為を体現しなければならない技だ!」
足を止めた煉獄が、じっと義勇を見つめてくる。笑んだままなのに、不思議と真剣さが伝わってくる顔つきだ。
「能は、静止する『構え』に説得力がなければならないと習った。全速力で走る体でもって全身全霊で止まり続ける。そんな状態が『構え』だ。だが力みを観客に悟られてもいけない。力が入っていると感じ取られることなく、自然体で静止しているように見せなければいけないんだ」
「それがむずかしい」
体感したことがなければ、理解のおよばぬ言葉だったろう。けれど、能の経験などない義勇にも、その状態の困難さはありありとわかった。実感を伴い打った相槌に、煉獄が強くうなずく。
「あぁ。剣も同じだ。刀を振るうのと同じだけの力で、刀を止められなければ話にならないと、父上によく叱られた! 鬼は卑劣だからな、入れ替わりの術を使う鬼がいれば、仲間の頸を切り落とす羽目にもなるんだぞと。だが、止めるだけでは足りない。刀を止めても振り抜く力はそのまま保て、振りかぶり直す暇などないと心得ろ、止まっていても動いているのと同じ状態でいなければ次の手が遅れる。遅れはすなわち死だ。繰り返しそう叱られた。全力で動いている状態を保ちながら止まるんだと言われても、なかなかできずに苦労したものだ! しまいには拳骨を落とされて、頭がコブだらけになったな!」
「俺も、力任せに刀を振り下ろすたび、びしょ濡れになった」
「ん?」
「先生に滝壺に落とされた」
淡々と言った義勇に、煉獄が破顔した。カラリと明るい笑い声を立てる煉獄は、至極楽しげだ。
「冨岡の育手も厳しいな!」
煉獄には悲嘆などどこにも見当たらない。自分とはなにもかもが異なると思っていた煉獄も、子供のころには同じように悩んだのだと思えば、なんだかこそばゆいようなうれしさを覚えた。
「能を舞うようになってから、少しずつ体の使い方がわかってきた気がする。剣術と違って練達の域にはとうてい及ばない、手遊び程度のものだが、気晴らしにもなるしな。今もたまに舞うことがある」
「そうなのか?」
どこかいたずらっ子めいた笑みで言う煉獄に、義勇の心も浮き立つ。自然とやわらかくなった問いかけに、煉獄はいよいよいたずら小僧のような顔でうなずいた。
「うむ。千寿郎に見られないよう、コッソリとだが」
「弟か?」
聞き慣れぬ名に思わず問えば、煉獄はなぜだか一瞬、盲点を突かれたかのように真顔になった。すぐに破顔し強くうなずく様は、いかにもうれしげだ。
「うむ! そういえば、俺も冨岡に家族の話をしたことはなかったな。すまない、浮かれてつい周知のことのように名を出してしまった。我が弟ながら、千寿郎は本当にいい子なんだ。冨岡も逢えば気にいると思う!」
きっと仲の良い兄弟なのだろう。微笑ましく思っていれば、煉獄はフフッと面映げな笑みをもらした。
「冨岡は俺のことになどなんの関心もないと思っていたが……そうか、俺に弟がいるのを知ってくれていたんだな。ありがとう」
礼を言われる意味が、義勇にはわからない。煉獄がなぜこんなにも幸せそうに笑うのかも。
関心がないと思われていたのは心外だが、では興味があるのかと問われても困る。詮索好きだと思われ避けられたくもない。弟の存在を知っていただけでこんなにも喜ばれるなど、なんだか妙に恥ずかしかった。
「見られるのは嫌か」
うまく話をそらせる術など知らず、義勇が返した言葉は、我ながらそっけない。けれども、煉獄は気に留めた様子もなかった。
「剣ならば自信を持って教えられるが、舞いは我ながら下手の横好きだからな。兄としては、あれを見られるのは恥ずかしくてたまらん」
カラカラと笑う顔には、言葉ほどの羞恥は感じられない。とはいえ嘘はないのだろう。
「煉獄なら、能も達者にこなせそうだが……」
剣と能では、たとえ力の入れ具合などの類似性はあっても、やはり勝手が違うのだろうか。浮かんだ疑問を素直に口にすれば、煉獄の頬がまた淡く染まった。
「土っ」
勢い込んで裏返った声音に義勇も驚いたが、当の本人である煉獄の動転は、義勇の比ではないようだ。言葉を飲み込み、んんっ、とめずらしくも空咳などする煉獄を、義勇はポカンと見つめた。
「そ、その……土蜘蛛なら、見た目も派手で、能楽に親しんでいなくても楽しめると思う。あ、衣装や面はないが、蜘蛛の糸ならあるぞ! 能を習った先生からいただいたもので、いくつか投げてしまったが、まだ残ってるんだ! うまく広がるように投げると本当に痛快で、すっきりするぞ! 冨岡も投げてみれば気晴らしになると思う!」
ワッとまくし立てるのは照れ隠しだろうか。かわいいところがあるのだなと微笑ましさを覚えたが、同時に蜘蛛の糸を投げる煉獄の心境を想像し、義勇の胸が小さくうずく。
煉獄の笑みはどこまでも明るい。けれどもその明るさこそが、義勇にはなにがなし悲しかった。
「……土蜘蛛……源頼光か」
「うむ! 有名な演目だからな、冨岡も知っているか! 鬼退治ものの代表格だな。能を習いだしてから、歌舞伎や浄瑠璃にも興味が湧いて観るようになったが、鬼退治を題材にした演目は意外と多いぞ。初めて土蜘蛛の精が舞台中に糸を撒き散らしたのを見たときにも、心弾みもしたが、もしもあんな血鬼術を使う鬼と出遭ったらどう戦えばいいかと悩んだものだ。実際の鬼とはまるで違うし、俺の舞いでは得られるものも少ないだろうが、その……冨岡さえよければ、一度、うちにこないか……?」
端正な顔に恥じらいを浮かべ伺いを立てる煉獄に、義勇は、我知らず眉をひそめた。
「なぜ?」
弟にすら見られるのは恥ずかしいと煉獄は言ったではないか。なのになぜ自分を誘うのだろう。
たちまち落ちる煉獄の肩に落胆っぷりを見てとり、義勇は少々慌てた。また言葉を選びそこねたのかもしれない。自己嫌悪に義勇はわずかにうつむいた。
きっと煉獄は鍛錬の一環として、義勇のためにもなると思い誘ってくれたのだろう。有り難い申し出だと感謝すべきだし、煉獄の舞いに関心があるのも確かだ。だが、気後れするのは否めない。仮初の柱でしかない自分が、代々炎柱の屋敷としてある煉獄家に、さも煉獄と肩を並べる水柱として招かれるなど、どうにも罪悪感が刺激されてしかたがなかった。
「埒もないことを言ってすまなかった」
答えあぐねているうちに煉獄の落ち着いた声がして、義勇はそろりと顔を上げた。煉獄は笑っている。けれどその笑みには、かすかな寂寥が感じられた。
「……ようやく君と過ごせる遊興の時間を持てたというのに、どうしても鬼狩りの話になってしまうな! 行こうか。姉上とは山雀の芸も見たんだろう? 俺たちも見よう!」
言われ、義勇は小さくうなずいた。煉獄の笑みはいつだって日輪の如くにまばゆいのに、悲しいだなどと感じる日がくるとは、思いもしなかった。
一人、誰の目にもつかぬように舞い蜘蛛の糸を投げる煉獄を、義勇は思い浮かべる。鬱屈を人に見せることなく、己の胸だけに押し込めて、煉獄は笑うのだ。
いったいいつから、どんなときに、一人で舞っていたのだろう。つらくはなかったか。寂しくないのか。聞いてはならぬことだとわかるから、義勇はただ静かに煉獄を見つめ返す。
不憫だなどと思う自体が、煉獄を侮辱している。思い上がりもはなはだしい。自嘲が義勇の口をつぐませた。
姉を殺されて鬼殺の道を目指した自分と違い、煉獄は、物心ついたころから鬼狩りという過酷な道を歩んできたのだ。義勇よりもずっと幼いころから煉獄は、柱による指南のもとに鍛錬に励み、己も柱となるのを運命づけられている。義勇からすればそれは、うらやましいのと同時に、わずかばかり憐憫をも覚える環境だ。
『俺は君と違って普通の暮らしがよくわからん』
煉獄は、どんな心境であの言葉を口にしたのか。義勇には、分別もつかぬころから覚悟を求められる生き方など、想像もつかない。
「我が家には小鳥がやってくることなど滅多にないからな。山雀も、母と初詣に行ったおりに、神社でおみくじを引くのを見たきりだ」
「……カルタ取りや、鐘つきもしていた。たしか、弓も引いたはずだ」
小鳥のこない庭。理由はすぐに知れた。鎹鴉だ。鴉がいつく庭に、獲物となる小鳥はこない。
「そんなこともできるのか! すごいなっ、楽しみだ! 早く行こう!」
義勇の手を引き足を早める煉獄の顔は、いつもより少し幼かった。もう先ほどの寂しげな色はどこにもない。
子供のころ、姉の手を引き早く早くとせかした自分も、きっとこんな表情をしていたのだろう。『母と』と煉獄は言った。ならばそれは随分昔の、ほんの幼子のころであったろう。そのときも煉獄は、母の手を引き幼い顔をほころばせていたに違いない。ワクワクと浮き立つ気持ちを小さな体いっぱいにみなぎらせ、大好きな人の手を引き急かす幼さは、煉獄も自分も同じだったのだ。思い義勇は、煉獄の白く広い背を見つめ、少し目を細めた。
握る手にキュッと力を入れてみる。振り返りパチリとまばたいた煉獄が「すまん、またやってしまった」と照れ笑うのに、小さく首を振ってみせる。
少しはにかんだ子供っぽい煉獄の笑みは、微笑ましいのと同じぐらい、義勇にはどうにも物悲しい。煉獄が真実こういった場所に不案内であるのが見て取れ、悲哀めいた感傷は、胸から消え去りそうになかった。
憐憫など煉獄に対して失礼だ。何度思い振り払おうとしても、家族そろっての行楽になどまるで縁がなかっただろう煉獄の子供時代は想像に難くなく、胸の奥が切なくうずく。
子供のころから煉獄は、今と変わらず明るく公明正大で、将来を嘱望されていたに違いない。次代の炎柱との期待を背負って生まれ、そうあるべく育てられるなど、義勇にしてみれば想像を絶する環境だ。
不満や疑念はなかったのだろうか。今の煉獄はそんなものを超越して見えるけれども、幼いころには、心の奥に寂しさや閉塞感を抱いたこともあったのではないだろうか。
義勇を振り返り見る煉獄の、まぶしい笑顔を見つめながら、義勇が思い描くのは幼い煉獄の姿だ。
苦もなく想像できる小さな煉獄は、小鳥一羽こない庭で真剣な顔に汗をちらしながら、一心に竹刀を振っている。きっと、現実と義勇の想像に差異はないだろう。だからこそ義勇は、少し悲しい。
先代炎柱である煉獄の父の柱在籍歴は、今も存命の鱗滝や元鳴柱に比べれば、半分にも満たないと聞く。それでも、歴代の柱たちのなかでは群を抜いて長い。煉獄が生まれたときにはすでに柱だったはずだ。
となれば、家族との団らんに費やせる時間など、ろくになかったことは明白だ。煉獄の記憶のなかには、家族総出での遊覧など存在しないだろう。父親との思い出は鍛錬ばかりだと言われても、納得せざるを得なかった。
それでも母親がいるうちは、不満など微塵もいだいたことはなかったかもしれない。幼い煉獄はきっと、父への尊敬と憧憬を一心にいだき、鬼狩りへの道を邁進するばかりだったろう。だが、母を亡くしたのちは、どうだったのだろうか。
初めて出逢った柱合会議でしか、義勇は、煉獄自身の口から先代炎柱の現況を聞いたことがない。実際に義勇が知る先代の様子も煉獄の言葉を裏付け、噂は真実であることを示していた。
しだいに気力を失い酒に溺れていく父を、どんな目で幼い兄弟が見つめてきたのか。柱の責務を放棄した先代への口さがない言葉に、傷つけられることも少なくはなかったろう。隊士になってからは、なおさらかもしれない。
それでも煉獄は一人竹刀を振り続け、誰にも見せぬ能を舞い、隊士になって後は柱にまで登りつめた。
傍からすれば予定調和とひがまれかねない道程を、煉獄は脇目も振らずにひた走ってきたのだろう。背負った運命のなかで、悲嘆も焦燥も孤独感も、一度も覚えずきたなんて思えない。それでも煉獄は、泣き言一つ漏らさず飲み込んで、人前では快活に笑ってみせながら柱になったのだ。
改めて、炎柱の雅号を継ぐ家という重さを、義勇は深く考える。
帯刀禁止令が施行されてから随分と経つ。貧富の差はあれど、刀になど縁のない家に生まれた者が大多数を占めるのが現在の鬼殺隊だ。義勇だって鱗滝に保護されるまで、刀など一度も見たことがなかった。剣一振りに己の命運を賭ける時代はもう遠い。
今の鬼殺隊では、煉獄の存在は思えば異質だ。また義勇の脳裏に浮かんだ孤高という言葉は、今度は言いようのないやるせなさを伴っていた。
自分とは、やっぱり違う。己と煉獄との違いは、先までとは異なる悲しさで、義勇の胸を締めつけた。
姉に溺愛され育ったから、義勇が、両親がいない寂しさを感じたことはほとんどない。思い出の場所に行くたび、どれだけ両親が義勇をかわいがっていたのかを姉が語り聞かせてくれたから、両親の愛情を疑うこともなかった。
煉獄が愛されず育ったとは思わない。煉獄の為人を見ていればわかる。だが、義勇のような子供らしい思い出は、煉獄のなかにあるのだろうか。
しかたのないことと割り切るにはどうにもやりきれず、とどのつまりは無惨という鬼に煉獄の人生は定められたのだという事実に、改めて無惨への憤りも感じた。だが。
『覚えていてね、義勇。お父様とお母様にはもう逢えないけれど、忘れなければ消えることはないの。だからいっぱい思い出してあげて。約束、ね?』
姉と小指を絡めあって交わした約束を、思い出させてくれたのは煉獄だ。煉獄自身にはそんな意識はないかもしれないが、借りは返さねばならない。
いや、そうじゃない。
煉獄の輝く笑みのまぶしさに目を細めながら、義勇は、心の底から湧き上がってくる本音を認めた。
ただ笑っていてほしいのだ。煉獄は今日が誕生日だと言ったではないか。無粋で面白みなど皆無な自分が連れでは申しわけないかぎりだが、それでも知ったからには祝いたい。
煉獄が生まれたことをただ寿ぎ、生きる喜びに顔をほころばせるのを見ていたかった。忘れえぬ思い出になれたらなどと、思い上がったことは願わない。それでもせめて今日だけは、置き去りにしてきただろう子供時代を取り戻させてやりたい。無邪気な子供のように、今日だけは、煉獄に笑っていてもらうのだ。義勇は決意に唇を引き結んだ。
憐れみや怒りはいらない。煉獄が望むものなど想像もつかないが、少なくとも同情を与えられることを良しとする男ではないのは、知っている。
力不足は重々承知の上だが、抑えがたい使命感に突き動かされ、義勇の口数も多くなる。今日ばかりは煉獄を楽しませねばと、煉獄に問われるたび、義勇は懸命に姉との思い出を語った。
小さな山雀がピョンピョンと飛び跳ね芸をする様に相好を崩し、うちで飼えればさぞ千寿郎が喜ぶだろうと言うのに、俺も飼いたいとねだって姉を困らせたと答えれば、煉獄はいっそう幸せそうに笑う。あれだけ利口なら鴉にも慣れてくれそうだ、指に止まったらかわいいだろうなと、童心をあらわに笑う煉獄の顔には、なんの憂いもなかった。
花園(植物園)だった名残りか繚乱と咲く春牡丹に目を輝かせるのには、芍薬との見分け方を姉から習ったと告げ、ひとしきり質問攻めにあった。香るのが芍薬、あまり香りがしないのが牡丹。単純な見分け方にも、煉獄はやたらと感心するから少し照れくさい。
香りの話題ついでに母の形見に父から贈られた舶来ものの薔薇の香水があり、姉がこっそりとつけていたことを教えれば、煉獄は少しだけ遠い目をして、俺も母上に贈ってみたかったなと、微笑んでいた。母上には薔薇よりも百合のほうが似合いそうだ、母上はいつでも凛としてまるで百合の花のようだったから。どこか誇らしげな笑みで言った煉獄に、きっと喜ばれたと思うと義勇がうなずくと、いっそう破顔する。
自慢に聞こえねばいいがとヒヤヒヤしつつ紡ぐ義勇の言葉に、煉獄は、楽しげな笑みを崩さない。口下手な義勇の物言いは、声の小ささも相まって要領を得ないものも多かろうに、煉獄はただ幸せそうに笑うのだ。その笑みを向けられるたび、義勇の胸にも、少しの寂しさがまじる甘やかな歓喜が、ふつふつと湧き上がる。
楽しいと、素直に思うことも何年ぶりか。両親と姉の思い出に、煉獄の今日の笑顔が重なって、幸せな記憶がいっそう彩られていく。
思い出さぬよう努め続ければ、記憶も薄れる。両親や最愛の姉、唯一の友である錆兎の顔さえ、思い出せぬようになっていたかもしれない。姉との約束すら忘れていた自分だ。思い出を語らずにいれば誰の心からも消えてしまう、彼岸に住まう人たち。今も愛しくてならないのに、この世から消えてしまう。覚えている自分が忘れてしまえば、誰も彼らを知る者などいなくなる。それなのに、思い出さぬようにしてきた。約束を忘れ、非道なことをしているとすら、気づけずに。
今日は、俺にとってこそ、素晴らしい日になるかもしれない。義勇は瞳を揺らめかせながら、屈託のない煉獄の笑みを見つめた。
忘れたくない自身の思い出をたどるなかで、煉獄の思い出もまた知っていく。鬼狩りの道を歩まなければ重なることのなかった二人の軌跡が、思い出が重なり合い、まるで幼いころからともにそばにいたような気さえする。それはひどく幸せに思えた。
煉獄へと向ける義勇の目は、常にはないやわらかな光を帯びていた。