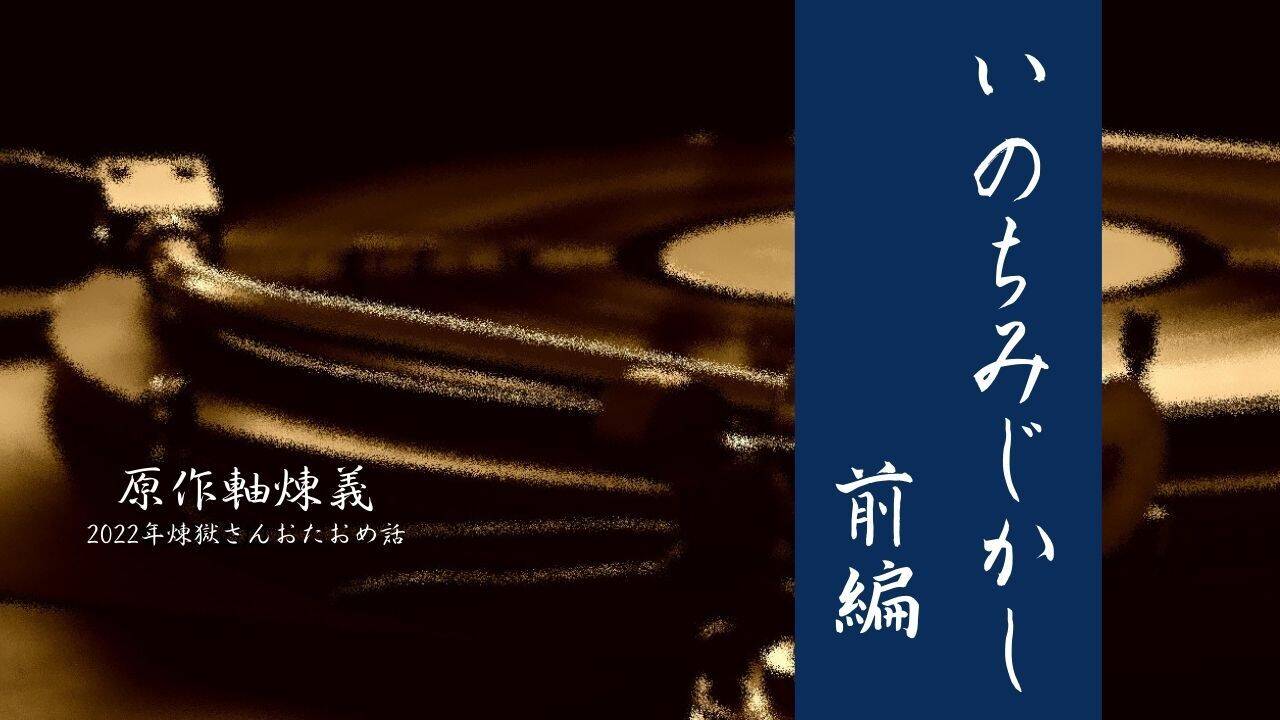無惨と遭遇した場所と聞けば、柱たちが浅草六区への危惧を深めるのは当然の成り行きだ。
「あの狡猾な鬼が、いまだにこの界隈をうろついているとは思えんがな」
傍らを歩く煉獄は屈託のない太い声で言い、大きく口を開けて笑うが、目には消えぬ警戒が宿っている。それはべつにいい。義勇にとっては理解の範疇だ。
だが。
「……なぜ、花屋敷へ?」
わからないのはそこだ。
浅草と一口に言っても、それなりに広い。浅草寺を有する浅草公園内のうち、演芸場やら活動写真が立ち並ぶ六区に、無惨は出没したと聞く。
残念ながら、浅草六区は義勇の担当地区ではない。煉獄も同様だ。
たとえ自身の管轄でなくとも、無惨が出没したと聞けば落ち着かぬのも当然だ。わずかたりとでも情報を得られればと、ほかの柱たちも一度は足を運んでいるとも聞く。
炭治郎が無惨に遭遇したとお館様から告げられたのは四月の末。今はもう端午の節句も過ぎた。
義勇だって、任務が立て込まなければ、すぐにも向かいたかった。果たせず今日になったのは偶然だ。
煉獄とたまたま任務帰りにかち合わせたのも、今日こそは浅草へ行ってみようと双方が思い定めていたのもまた、示し合わせた結果ではない。たまさかお互いに任務が早くに終わり、めずらしくも次の任務が控えていなかった。体力気力、時間にも余裕がある。多忙な柱同士、そんな日が重なるのはたいへん稀ではあるが、ありえないと言うほどのことでもない。
だけれども、重ねて言うが無惨が現れたのは、浅草六区だ。煉獄が先に立ち迷わず足を進めた花屋敷は、五区にある。
平日ながらも周囲にはそれなりに観光客がおり、続々と花屋敷の門をくぐっていく。大看板を掲げた大仰な門を見上げ、内心の困惑を隠しきれずに聞いた義勇に、煉獄はカラリと笑った。
「六区からそう離れているわけでなし、くまなく探査するに越したことはないだろう?」
「それは、そうだが……」
言わんとすることは理解できるが、それにしたって今は昼日中である。同じ歓楽地であっても暗がりが多い六区や凌雲閣周辺と違い、花屋敷に鬼が潜む場所など、そうそうあるとは思えない。
義勇はふたたび門を見やった。刹那、陽炎のようにゆらりとよぎった記憶に、ドクリと鼓動が跳ね息を呑む。
大看板の奥に見えるは五重塔の奥山閣。左手を見れば五月の爽やかな青空を背に、凌雲閣がそびえている。昔より凝った造りに建て替えられた門をくぐっていく人々は、みな笑顔だ。
賑やかな光景は昔とくらべ少し様変わりしたが、奥山閣と凌雲閣は変わらない。あのころのままだ。二度と戻れない在りし日のまま。自分だけが、遠くへ来た。
「……と、いうのはじつは建前だ。すまん!」
黙り込んだ義勇の変化に気づかなかったのか、煉獄が唐突に頭を下げた。
いきなり謝罪され、無表情の裏側で義勇は困惑したが、それでも驚愕のおかげで息が軽くなったのは確かだ。遠い日の思い出はやさしすぎて、息が詰まる。煉獄にはそんな意図など微塵もなかっただろうが、空気が変わったことに義勇は安堵した。
「本当の理由は別にあるということか」
「ん、まぁ……そうだな」
頭を上げ、少しだけ視線を泳がせながらも義勇を見やった煉獄は、すぐに大きな目をパチリとまばたかせた。
「冨岡? どうした、気分でも悪いのか?」
「なぜ、そんなことを?」
動揺は一瞬だ。突然の謝罪に息苦しさも消えた。常と変わりなくいるはずだと義勇自身は思うのに、煉獄はいかにも心配そうに眉をひそめている。
「いつもより少し顔色が悪い。瞳も……君の瞳はいつでも凪いだ海を思わせるのに、先ほどは、雨に打たれ波立っているかのように見えた」
「……煉獄は詩人だな」
揶揄したわけではなかったが、煉獄はサッと頬に朱を走らせた。悲しみとも苛立ちともつかぬ様子でグッと口を引き結び、淡く染まった頬はそのままにじっと義勇を見据えてくる。
「茶化さないでくれ。体調が悪ければ遠慮しないでほしい。つらいのなら無理をさせたくはない」
真摯な声音は、一切の裏表を感じない。煉獄は心の底から案じてくれている。少なくとも義勇には、煉獄の心根のまっすぐさを疑う理由などなかった。
「どこも悪くない」
「俺に気を使っているわけではないんだな? それならいいんだ! 君が健やかならそれにこしたことはない!」
快活に笑う煉獄は、まるで真夏の晴天に輝く太陽のようだ。まぶしすぎて、義勇はいつも正視できない。つい目を伏せてしまう。
「では、もしかしたら花屋敷が嫌なのだろうか。どこかほかへ行くか?」
「調査するんだろう? ほかにも無惨が潜む場所に心当たりが?」
「いやっ、そうではないが……」
そういえば建前と言っていたか。無惨の手がかりを探る以外にも、煉獄には花屋敷に入りたい理由があるのだろう。
無言で答えを待てば、常にはない逡巡を見せた煉獄は、すぐに意を決した顔をして口早に言った。
「冨岡と入ってみたかったんだ。俺のわがままだ。君の意思を尊重すべきなのに、騙し討のような誘い方をしてすまなかった。不快な思いをさせて申し訳ない」
まっすぐに義勇を見つめ言う煉獄の頬は、いまだ赤い。朱に染まった目元が、なんだか初々しくすら見える。
そういえば、煉獄は年下だったな。ふとそんなことを思い、なんとはなし義勇はうつむいた。
目が潰れそうにまぶしい笑みから逃れるいつもの仕草と違い、我ながらそれは、照れくささが勝る行動だった。けれども、なぜ気恥ずかしさを覚えたのかは、よくわからない。うれしいような、もどかしいような、不思議な心持ちがする。
「いや……少し、昔のことを思い出しただけだ。なぜ俺となのかはわからないが、煉獄が入りたいと言うのならそれなりにわけがあるんだろう。俺はかまわない」
花屋敷が嫌だというわけではない。感傷にゆらぐ己の心こそが不甲斐ないと、義勇は内心の鬱屈を抑え、努めて冷静に言った。
おかしな台詞ではないはずだ。だが、煉獄はなぜだか目を見開き、義勇をいっそう凝視してくる。呆然として見えたのは数瞬で、すぐに煉獄は泡を食った様子で義勇に詰め寄ってきた。
「むっ、昔とは、よもや冨岡は以前にもここに誰かと来ているのか!? どんな女性なんだ? その人とはどのような関係なのだろうかっ!」
なぜ女性だとわかったのだろう。煉獄は千里眼か。
驚きは、義勇にはめずらしく、はっきりと表情に出てしまったらしい。するとどうだろう。煉獄はさらにうろたえだした。
「すまん! 詮索するつもりは……いや、嘘だ。気になってしかたがない。君が言いたくないのなら、追求しないと誓うが……」
オタオタと狼狽したと思えば、肩を落としてうなだれている。尻すぼみに消え入る声も、やけに力ない。てんで煉獄らしからぬ反応だ。
「姉だ」
いつも威風堂々として自信に満ちて見える煉獄の、らしくない挙動に呆気に取られつつ、義勇はポツンと呟いた。たちまち威勢よく煉獄の顔があげられた。こぼれ落ちんばかりに目を丸くして、また義勇をまじまじと見つめてくる。
「姉?」
「あれはたしか、俺が十のころだ。姉に連れられて来たことがある。ここにくるのは、今日で三度目だ。一度目は、覚えていない。三つのときに、両親と姉と一緒にきたらしいが……」
家族総出できたのは記憶にないが、姉と訪れた日ならば覚えている。脳裏に知らず浮かび上がった記憶は、今も鮮やかだ。空の青さも、風の爽やかさも、姉のやさしい笑みとつないだ手のぬくもりだってすべて、ありありと思い出せる。それが義勇には少しつらい。
平静を心がけたつもりだったが、義勇の声には、わずかな寂寥がにじんでいた。煉獄の顔がたちまちくもる。
「冨岡のご家族の話は、聞いたことがなかったな。ご両親と姉上は……」
「両親はコレラだ。俺は五つだった」
それだけで悟るものがあったに違いない。煉獄はそれ以上たずねてはこず、静かにうなずき、ふたたび頭を下げた。
「不躾なことを聞いた。重ねがさね申し訳ない」
「かまわない。……昔の話だ」
隊士の大半は、鬼に家族を殺されている。義勇もまた、その一人であるに過ぎない。声高に仔細を語り悲しみを吐露する気は毛頭ないが、かたくなに答えるのを拒むたぐいの話でもなかった。
それでも姉のことを思い出せば、心が揺れる。どれだけ月日が流れても、自責の念は消えない。
だが煉獄を責めるのはお門違いだ。いまだ心乱される自分を恥じるだけである。
と、義勇は不意に思い至ったそれに、ゆっくりとまばたいた。
煉獄の家族について聞いたことはなかったが、先代炎柱は、義勇が入隊するより前に奥方を病で亡くしたと聞いた。つまりは煉獄の母だ。
義勇より年若であるのをかんがみれば、母を亡くしたときの煉獄は、相応に幼かったはずである。大切な人を失った状況は異なるが、煉獄もまた、かけがえのない人との別れを幼いうちから経験しているのだ。その気づきは、奇妙な感慨を義勇に懐かせた。
煉獄はまだ、義勇をまっすぐに見つめている。義勇もまた煉獄の眼差しをひたと受け止め、見つめ返した。
無言で瞳を見交わしていたのは三分にも満たないが、大の男が二人して人波で立ち止まったままでいれば、邪魔以外の何物でもなかろう。気づけば周囲から迷惑げな視線が集まっていた。
これはいけない。ただでさえ帯刀を見とがめられることも多いのだ。政府非公認の組織は、こういうとき厄介だ。
注目されていることに煉獄も気づいたのだろう。精悍な顔には苦笑が浮かんでいた。
「このままではほかの客の迷惑になるな。冨岡、君が嫌でなければ、今日のところは俺につきあってもらえないだろうか」
目元をやわらげた煉獄は、それでもどことなし緊張して見える。
緊張? 馬鹿な。煉獄の物怖じしない性格を、義勇はもう知っている。義勇に語りかけてくれるときの煉獄には、いつだって屈託がない。それなのにどうしてだろう。今日はなぜだか、見知った煉獄ではないような気がする。
思った端から、義勇は内心で自嘲した。緊張など気のせいだ。煉獄が自分に対してそんな反応をする謂れはない。
なぜ自分を誘うのかはわからないままだが、煉獄が固執するからには、それなりの理由があるはずだ。義勇は小さくうなずいた。
途端に煉獄の顔がパアッと輝く。その笑みに胸の奥がそわりとさざめいた所以もまた、義勇自身考えもつかない。それでも不快さはどこにもなかった。まばゆい煉獄の笑みに、ただ心が揺れる。
「行こう! 俺は初めてだ、案内してくれ!」
煉獄の声は弾んでいる。差し伸べられた手が義勇の手をつかむ。羽織をはためかせて足早に歩きだした煉獄の背を、義勇は呆然と見つめるばかりだ。なぜ手をつなぐのかと問うことも、離せと拒むこともできない。
無言のままついていく義勇を、煉獄はどう思っているのだろう。ギュッと握りしめられた手に戸惑い、義勇の目がパチパチと忙しなくまばたいた。
幼い子供でもあるまいし、成人男性が手をつなぎあって歩くなど、そうあることではないだろう。けれども煉獄は、ちっとも気にした様子がない。
もしかしたら自分とは初めてなだけで、ほかの柱たちと行動するときには、手をつなぐことが多いのだろうか。考えた途端、なぜだかチリリと義勇の胸は痛んだ。
柱の資格などない自分にさえ、煉獄はほかの柱と同様に接してくれる。ありがたいと感謝こそすれ、同じ扱いを悲しむなんて、思い上がりも甚だしい。自分のさもしさが嫌になる。
けれどもやはり義勇は、手を離してくれとは言えなかった。
誰かと手をつなぐなど何年ぶりか。最後に手をつないだのは……そうだ、錆兎だ。
思った瞬間、義勇はまた、喉の奥に大きな塊を詰め込まれたかのような息苦しさを感じた。
錆兎の手は、煉獄よりもずっと小さかった。自分の手だってそうだ。お互い、子供の手だった。
煉獄の手のひらは、あのころの錆兎よりもずっと固く、大きい。長年、刀を握り続けてきた者の手だ。義勇の手も、今では錆兎よりはるかに大きくなっている。刀胼胝や古傷だらけな固い手のひら。それだけの月日はとうに過ぎた。
煉獄は義勇より少し体温が高いのだろう。大きくてたくましい大人の手なのに、子供めいた体温だ。いっそ汗ばむほどに熱くすら義勇には感じられる
誰とでも手をつなぐのだとしても、今この瞬間に煉獄が手をつないでいるのは、自分だ。この熱さと力強さを、今は自分だけが与えられている。
義勇の心臓がドクリと大きな音を立てた。離さないでほしい。心の片隅に、不意にそんな言葉が浮かぶ。
なぜそんなことを思うのか。なぜこんなにも自分の鼓動はドキドキとうるさいのだろう。自分で自分がわからずに、義勇の瞳が困惑に揺れた。
戸惑いが勝る願いは長くはもたず、料金所についたと同時に煉獄の手は離れていった。
落胆はほんの一瞬だ。二人分と告げる煉獄に、義勇はひとつ深呼吸すると話しかけた。
「払う」
「いや! 俺が無理に誘ったのだから、俺に出させてくれ!」
攻防にもならないやり取りは、ふたたびしっかと手を握られ終わりだ。
年下の同僚に支払いを任せてしまうなど、不甲斐ないにもほどがある。けれど、自己嫌悪すること自体、思い上がりでしかないのだろう。煉獄はすべてにおいて上位の存在なのだ。意固地になっても始まらない。そんな卑屈な感情が、多少なりと義勇のなかには存在していた。
せめてなにか言わなければ。思うけれども言葉は出てこない。己の口下手さを義勇は嘆いた。
口が重いのは自覚している。義勇が語る言葉は、なぜだか人を苛つかせ、呆れさせもする。けれど、煉獄はいつでも明るく話しかけてくれるのだ。
君は声が小さすぎだなと笑いはしても、もういいと話を切り上げようとはしない。義勇が返す言葉はいつだって、ほんの短い相づち程度だ。会話が弾んだことなど一度もない。それでも煉獄は見限ることなく、顔を合わせるたび明るく声をかけてくれる。
煉獄に握られている己の手へと、義勇はなにげなく視線を向けた。自分とさして変わらぬ大きさと固さをした、剣士の手。煉獄の手だ。改めて思い、心臓がトクンと弾んだ。
もしかして花屋敷を巡る間中、煉獄は手をつなぎ続けるつもりなのだろうか。先まで以上に湧き上がる当惑は、不可解な甘さを含んでいる。
姉や錆兎、鱗滝に手をつながれたときだって、義勇は安堵と多幸感に包まれた。けれども煉獄の手はどこか違う。今まで義勇の手をこうして引いてくれた人たちは、年齢の差はあれどもみな義勇が甘えられる人ばかりだ。煉獄は、違う。仮初でしかない義勇とは異なり本物の柱だとはいえ、立場上は上下などない。ましてや、入隊したのも柱を任じられたのも、義勇のほうが先だ。歳だって煉獄は下だし、甘えるなどとんでもない話ではないか。
そうだ、年下なのだ。思いながら、義勇はひるがえる煉獄の羽織の白さに目を細めた。
初めて柱合会議に現れた煉獄は、まだ甲だった。
俺が炎柱になれば問題ないと堂々のたまった煉獄に、自分がなにを思ったのか、義勇は覚えていない。けれども正式に炎柱としてふたたび煉獄が現れたその日、絶えずの藤咲く庭に舞い込み肩口に落ちた桜の花びらは、不思議とはっきり覚えている。
であればあれは、四月だったのだろう。歳を問われ十八だと宇髄に答える声を聞くともなく聞き、二十歳になって間もない義勇は、あいつは俺よりも歳を重ねるのだろうなと思ったものだ。
桜の季節に炎柱の羽織をまとった煉獄は、お館様の言を借りれば鬼殺隊の運命を変える一人だ。自分なぞとは格が違う。だというのに、煉獄は義勇に対して常に笑いかけてくれた。
あれから、一年が経った。煉獄はもちろんのこと、義勇も今なお生きている。
先に立ち歩いていく煉獄の背は、爽やかな五月の日差しを弾いて真白い。煉獄はいつでも、義勇の目にはどうしようもなくまぶしかった。