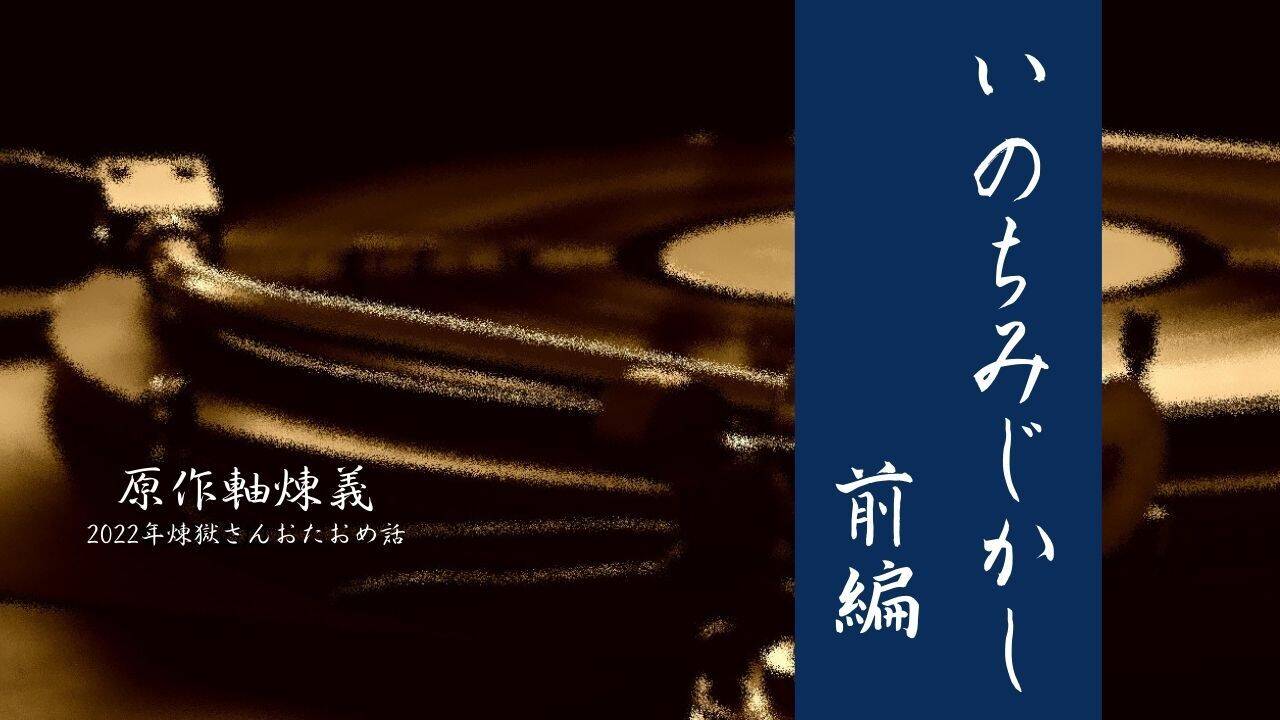操り人形たちが俳優もかくやと言わんばかりに演じる滑稽な芝居にも、煉獄はキラキラと目を輝かせた。ほぼ初見と変わらぬ義勇も、人形たちのイキイキとした動きには目を見張ったが、煉獄の興奮は義勇の比ではない。
「西洋の糸操りは、人形浄瑠璃とはだいぶ違うな」
「そうなのか?」
先の会話からも垣間見えたが、煉獄は歌舞伎などへの造形が深いようだ。義勇の口下手や無愛想さも相まって個人的な会話などろくに交わしたことがなかったから、こんなことすら初めて知る。なんだか胸がまたソワソワと甘くざわついて、義勇は、煉獄ほどには芝居に集中できずにいた。
もしかしたら煉獄は幼いころにも目を輝かせ、今日のように浄瑠璃人形に釘付けになっていたのかもしれない。夢中で人形を見つめる小さな煉獄を思い浮かべ、義勇はほんの少し頬をゆるめた。
「浄瑠璃は語り物だから聞く芸だろう? 主役たる義太夫が、人形繰りや三味線三位一体で演じる。人形自体も一体を黒子が三人がかりで操るし、あんなふうに人形の全身が自由に動くわけでもない。演者一人では成立しない芸だ。語りや音楽があってこそ人形も活きる。もちろん、だからといって優劣をつけるのは無意味だと思うがな。どちらも素晴らしい芸だ」
観劇中だからか、煉獄の声はささやくような小声だ。手を握り大声をたしなめる機会はない。ちょっぴり残念だと落胆する自分に気づき、義勇は胸のうちで少々慌てた。
そんな義勇の狼狽には気づかぬまま、煉獄は視線を舞台に据えたまま、なおも言う。
「五代目菊五郎も、糸操りを絶賛していたらしいぞ。歌舞伎に『操り三番叟』という演目があるんだが、人形と人形繰りを演じる縁起物な舞台なんだ。西洋の操り人形に着想を得た菊五郎はその人形を演じた際に、舞踊の幕でゴム糸をつけ空に浮いてみせたらしい。名人にそれほど影響を与えるものなら、ぜひ一度西洋の操り人形を観てみたいと思っていたんだ。花屋敷で興行していてよかった」
もともと話好きな質ではあると思うが、いつも以上に煉獄は饒舌だ。声音は抑えていても、弾んだ調子は隠しきれていない。
ろくに会話を盛り上げられぬ聞き手では語り甲斐がないだろうに、煉獄は気にならないのだろうか。煉獄のことを知れるのはうれしくもあるが、そこはかとなく申し訳なくもなる。
明るく気安い煉獄は、ほかの柱たちとの交流だって深いだろう。それでも、趣味の話で盛り上がるのがむずかしいことぐらいは、義勇にも想像がついた。観劇を好む者がいたとしても、柱がそうそう時間を取れるわけもない。余暇を過ごせる日が重なるなど奇跡的だ。めったにない機会とばかりに、煉獄の弁舌には熱がこもっている。
多感な時期からずっと鬼狩りのみに時を費やした義勇と違い、煉獄は柱としてのみならず、私人としても充実した日々を送っているのだろう。煉獄は行楽には不慣れだと言うが、それでも余暇を無為に過ごすことはないに違いない。時間の使い道ひとつとっても、自分とは雲泥の差だ。義勇は知らずため息をつきそうになった。
自分とは違う。思い浮かぶたび、胸の奥がチリリと痛む文言だ。だが、端からわかりきったことではないか。今さら落ち込むほうがおかしい。だというのに自分は煉獄の傍らに立つには不釣り合いだとの見解は、凪いで揺れ惑わぬのが常となった義勇の心に、どこか悲しいさざ波を立てた。
鬱々と沈みかけた義勇の心のうちなどまるでおかまいなく、人形芝居は佳境に入っていた。観客がドッと沸いて、館内が笑い声に包まれ拍手が鳴り響く。どうやら終幕のようだ。
「おもしろかった! じつに見事な動きだったな!」
照明が煌々と灯り、楽しげに笑いながら観客が続々と客席を後にする。人々の流れを見るともなしに見つめていた義勇に、煉獄はたいそう満足げに笑いかけてきた。
「冨岡は浄瑠璃を観たことがないようだが、よければ浄瑠璃も一度見てみないか? 君が好みそうな演目をやっているか調べておくから、一緒に行こう。あぁ、もちろん浄瑠璃に興味がないなら、能や歌舞伎でもいいぞ。能なら俺もいくらか舞えるし、わからないことがあればなんでも聞いてくれ!」
「なんで?」
社交辞令にしては熱のこもった煉獄の誘いに、義勇は小首をかしげた。
俺と行ってもなんの得にもならないだろうに。煉獄は観劇には慣れているようだし、声を注意する必要もない。舞台について熱く論を交わしたいのなら、義勇では役に立たないのだ。誘われる理由がわからない。
義勇からすれば当然の反応であり、いつもと変わらぬ仕草と言葉だったが、ずいぶんとそっけなく感じられたのかもしれない。途端に煉獄の笑みがくもった。ありありと伝わってくる落胆が、義勇の疑問と困惑をますます深める。
きっとまた自分は、なにか間違ったことを言ってしまったに違いない。義勇は焦燥を押し隠すようにうつむいた。
いつでもこうだ。不死川や伊黒などは、義勇が口を開くたび苛立った顔をする。胡蝶や宇髄には呆れ顔をされることも多い。
煉獄にもいよいよ失望されただろう。だがそれも、しかたのないことだ。自分はほかの柱たちとは違い、本来ならば隊士にすらなれる器ではない。事実を知れば柱たちのみならず、今は敬意を払ってくれている隊士たちにだって、厭われるに違いない。
それぐらい、わかっているけれど。義勇は軽く唇を噛んだ。
浅ましいと己を戒めても、煉獄にだけは軽蔑されたくないと願ってしまう。嫌われたくない。見損なったと煉獄に切り捨てられるのを想像するだけで、刺し貫かれる如くに胸が痛む。
「やはり、俺では駄目だろうか」
悲しげな声に、義勇は慌てて顔を上げた。煉獄の顔には笑みがある。寂しげで自嘲の色濃い苦笑だ。煉獄には似合わない。
「俺は君と違って普通の暮らしがよくわからん。年下だし、君の目には経験の浅い子供に見えてもしかたがない。頼りなく思われているんだろうが」
「違うっ!」
自己卑下する文言など、煉獄の口から聞きたくない。俺では駄目だとは、煉獄ではなく自分こそが言うべき言葉だ。なのにどうしてそうなるのだと、義勇は勢い込んで煉獄の声をさえぎった。
頼りないだなんて、なぜそんな真逆なことを思うのだろう。煉獄は常に堂々としていて、交流下手な自分なぞよりはるかに頼りがいもあり、世慣れた男ではないか。
「俺が一緒では、おもしろくないと思う。煉獄が楽しめないのは嫌だ」
ただそれだけなのだ。煉獄を否定したわけじゃない。伝えたくて必死に紡いだ義勇の言葉は、どこか子供めいている。
なんだそうかと笑ってくれると思ったのに、義勇の言葉を聞くなり煉獄は、カッと目を見開いて声を張り上げた。
「楽しいに決まっているだろう!? 冨岡、君と一緒にいられるなら、それがどこだろうと俺にとっては桃源郷だ!」
大音声に思わず肩を跳ね上げらせながらも、義勇は、反射的にキュッと煉獄の手を握った。サッと煉獄の頬に朱が走る。
戸惑いをあらわに閉ざされた唇。わずかにそらされた視線。手はつないだままだ。すぐに力を抜いた義勇の手を、どこかすがるような強さで煉獄は握ったままでいる。
花屋敷に姉ときたときに、自分もこんな顔をした気がする。覚えずよぎったささやかな記憶に面映ゆさを感じ、義勇も視線を泳がせた。
十だった。はぐれぬようにと言われ手をつなぎはしたが、十歳にもなれば人前で幼子扱いされるのは恥ずかしい。歳の離れた姉から見ればまだまだ幼くとも、高等小学校にだって上がっていたのだ。そんなに自分は危なっかしいのだろうかと、ちょっぴり不満でもあった。大人ぶろうとしていた自分の幼さは、今となっては赤面ものだ。
活人形にビクついて、姉の足にしがみついたときもそうだ。怖いならもう出ようかと心配げに言う姉に、きっと自分は、今の煉獄のような顔をした。
恥ずかしくて、ちょっと自分に苛立って、でもどこかうれしくもある複雑な気持ち。子供扱いを不満がっていた自分と今の煉獄が同じだとは思わないが、この反応はよく似ている気がした。
そういえば、錆兎にもこんな態度を取ったことがあったな。
次々に思い起こされる記憶は、義勇の胸をさざめかせる。
初めて得た親友がうれしくて、どうしても追いつけないのが少し悔しくて。頼りにされたいと張り切っては失敗を重ね、羞恥と不安に顔を赤らめたあのころ。厭わず笑って手を差し出してくれた錆兎は、もういない。
義勇はこっそりと煉獄の様子をうかがい見た。
もしかしたら煉獄は、あのころの自分と同じ気持ちを抱いているのだろうか。親友だと思ってくれているのだとしたら、うれしい。あんなにも友情をはぐくめる相手には、もう二度とめぐり会えないだろうと思っていたけれど、錆兎と同じように自分を好きになってくれる人がいるなんて。しかも相手は煉獄だ。
ありえないと思いながらも、義勇の鼓動は早まっていく。早馬の足音のようにドキドキと高鳴る胸が、甘苦しい。
親近感と歓喜は面映ゆく、逃げ出したいよないたたまれなさを感じもする。なんだか妙に恥ずかしい。子供のころとはそこはかとなく異なる羞恥が、義勇の頬にも熱を集めていった。
「桃源郷は、ない」
照れ隠しを多分に含んだぶっきらぼうな口調に、ほぞを噛む。また責めているように思われるかもしれない。迷惑になる大声をたしなめるだけでよかったのに、よけいなことを言ってしまった。
馬鹿にしたわけでも、嫌がっているわけでもないのだ。ただ恥ずかしいだけ。けれど、それをうまく伝える術など義勇にはない。
周章狼狽しつつもさほど表情が変わらぬ義勇よりも、煉獄の反応はよっぽど顕著だった。
含羞に淡く染まっていた頬は、すっかり熱を帯び、いまや林檎の如くに真っ赤だ。耳や首筋までもが赤い。
全集中常中を保ちつづける柱は、そうそう冷や汗などかくことはない。汗で刀が滑るなど論外なのだから、自然と汗を抑制するのが習慣づけられている。だというのに、赤面する煉獄の額には汗が光っていた。
「そ、その……今のは」
こんなふうに口ごもり、煉獄が言葉を探しあぐねる様も、義勇は一度として見たことがなかった。
やっぱり自分はしくじったのだ。ズンと落ち込みかけた義勇を浮上させたのもまた、煉獄だ。
キリッと顔つきを改めた煉獄は、赤く染まった頬もそのままにまっすぐ義勇を見つめ、強い声で言った。
「浮ついて聞こえたのなら、すまない。だが紛れもなく本心からの言葉だというのは、信じてくれ。冨岡、俺は、君といると楽しい」
生真面目な声音と眼差しには、誇張や嘘などいささかも感じられなかった。煉獄は紛うことなく本音で義勇に接しているのだ。信じられるからこそ、義勇の頬も赤みを増していく。
館内はすっかり客が減った。先の煉獄の声で集まった不躾な視線も、もうほとんど感じられない。人形を片付けている劇団員だけが、チラチラとこちらをうかがい続けている。
「俺も……煉獄といるのは、楽しい」
義勇がようやく口にできたのは、そんな一言だ。端的過ぎる文言は、義勇自身物足りなさを感じた。だが、胸のうちにさんざめく感情の数々を、言語化するのはむずかしい。
喜びがあるのは確かだけれど、それは姉や錆兎から寄せられる親愛に対して抱いたものとは、どこか違っている。うれしいのになぜか切なくて、煉獄のまっすぐな熱い眼差しを見つめ返せば心浮き立つのに、どうしてだか涙が出そうにもなった。けれど悲しくはない。ただただ胸がざわざわと揺れまどい、まるで心臓がゴム毬のようにポンポンと弾んでいる気がする。
これはいったいなんだろう。自分になにが起こっているのだろうか。こんなの知らない。錆兎にだって感じたことのないなにかが、胸のうちで息づいている。つかめそうでつかめない己の感情がもどかしかった。
大の男が二人して赤く染まった顔を見合わせて立ち尽くしているなど、糸操りの芝居以上に滑稽だ。思っても体は動いてくれそうになかった。
そろそろ出ようと自分から言えばいい。理性が、劇は終わったのだから早く出なければ迷惑だと促す。けれども義勇の心の片隅には、このままでいたいと主張する幼い自分もいる。一歩でも動いたら、切なく苦しいけれどもひそやかに甘くやわらかいなにかが、散り散りに消えていってしまいそうで……動けない。
言語化されない感情に揺り動かされる困惑は、依然としてある。だがそんな困惑さえもが、なんだか心地よいのだ。
動け。もう少しこのままで。相反する意思が天秤のように揺れる。逡巡はそれでもたいした時間ではなかったろう。煉獄の赤らんだ顔が不意にやわらかく微笑んだ。
いかにも幸せそうなとろけんばかりの笑みは、キラキラとした金の髪も相まって、上等なはちみつのようだ。義勇の胸がさらに高鳴る。
さっぱりとして男らしい性格の煉獄を蜜に例えるなど、人に知られれば呆れられるかもしれない。煉獄だって怒りはせぬまでも困惑するだろうし、多少なりと不満は覚えそうだ。不快がらせたくなどない。それでもやはり義勇の目には、煉獄の笑みはどうしようもなく甘く感じられた。
「ありがとう、冨岡」
ついぞ聞いたことのない甘やかな声音で言われてしまえば、義勇の頬はますます熱くなった。
やさしい仕草で手を引かれた。そろそろ行こうと微笑む煉獄に、コクリとうなずく。このままでと願っていたはずなのに、残念だとはちっとも思わなかった。
不可解に甘く切ない空気は消え失せることなく、それどころか濃度を増したようにすら感じられる。本当にはちみつみたいだ。とろとろと甘くて、少し喉が焼ける、あの感じ。似たような甘さでも水飴とは違って、煉獄がもたらす甘さはやっぱりはちみつに似ている。
煉獄という蜜に溺れそうだなんて、またもや詩歌めいた感慨が心の隅に浮かび、義勇は少しうつむいた。まわりくどい隠喩は聞くも言うも苦手だ。歯に衣着せられぬのは世知にうとい証拠かもしれない。
なのにどうしてだか煉獄のことを考えるたび、言葉が勝手に浮ついてきらびやかな色をまとう。そんなのは煉獄にだけだ。煉獄に対してだけ、なぜだか自分は詩人めくらしい。
摩訶不思議な現象だと義勇はつい首をひねりたくなったが、羞恥はあれど、声に出さねばなんということもない。煉獄に呆れられなければ、それでいい。
「冨岡?」
知らず笑いそうになって、さらにうつむき顔を隠す。そんな義勇に、煉獄はキョトンとした視線を向けていた。前髪の隙間からそれを盗み見て、義勇はほんの少しだけ弾んだ声で、なんでもないとささやいた。