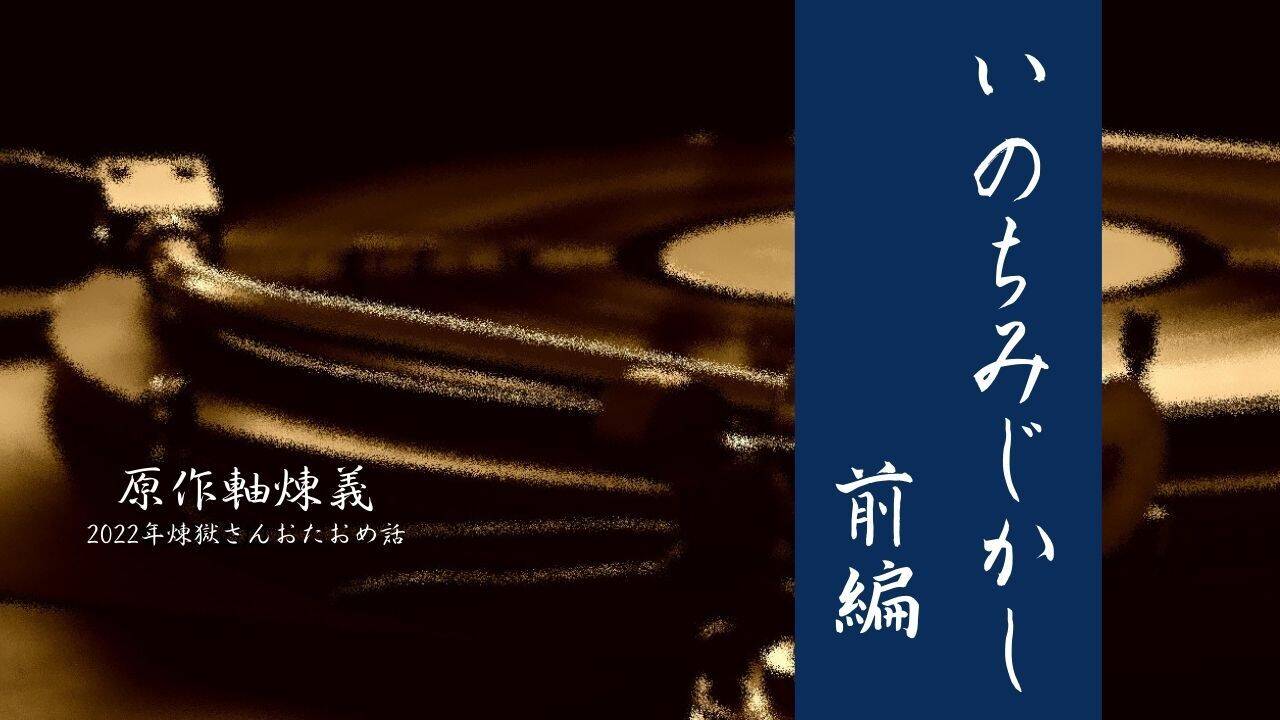展望台をあとにして、活人形館へと向かう。残念ながら煉獄が期待した歌舞伎ものは空振りだ。それでも、名前のとおり生きた人そのままに見える精緻な人形は、見ごたえがあった。
とはいえ、その精巧さこそが、幼子の目には空恐ろしく映るのだろう。興味津々に身を乗り出す父親の足にしがみつき、しきりにもう出ようよと訴える幼女の声は、いかにも怯えている。
そんな親子連れの様子を目に止め、義勇は思わず追想に目を細めた。
「俺も、あの子のように姉の足にしがみついた」
「ふむ、たしかに幼子には恐ろしいかもしれんな。今にも動き出しそうだ」
納得顔でうなずいた煉獄が、クスリと小さく笑う。
「冨岡が前に来たのは十だったか? さぞかしかわいらしかっただろうな。そのころに出逢っていれば、俺の足にもしがみついてもらえたのに残念だ!」
煉獄はすこぶる上機嫌だが、義勇にしてみれば、心外なことこの上ない。
「俺が十なら、おまえは八つだろう。俺より小さな子にしがみついたりしない」
少々へそを曲げた義勇の声は、覚えず子供じみて、すねたひびきをしていた。ねめつけるような視線をちらりと投げれば、煉獄はキョトンと目をしばたかせている。
「八つ?」
「俺は二十一だ」
「それは知っているが……あぁ、そうか! 炎柱を拝命したときに、宇髄に歳を聞かれ十八だと答えたな! 冨岡は二月生まれだろう? たしかにあのときは二つ違いだったな」
楽しげに破顔した煉獄は、すぐに笑みを穏やかなものに変え、じっと義勇を見つめてきた。
「冨岡、俺は今日で二十歳になった」
今度は義勇がキョトリとする番だ。不意打ちとしか言いようのない予想外の言葉に、義勇は少しばかり呆然とつぶやいた。
「今日……」
「うむ! 今日、五月十日で満二十歳だ!」
なるほど、それならば四月の柱就任時には、十八で間違っていない。だが、翌月には一つ歳をとるのなら、十九だと答えればよかろうものを。どうやら、煉獄が変に生真面目さを発揮したが故の勘違いだったらしい。
年下であることに変わりはない。二つ違いが一つになっただけのことだ。それでもなんとなく、その差は義勇を奇妙に戸惑わせた。
「君より年下なのは変わらないからな。だからどうしたと言われそうだが……」
苦笑の気配をわずかににじませた煉獄の、たわんだ目がひどくやさしい。昔、姉がいつでも義勇に向けてくれていた笑みに、少し似ている。姉と同じくらいやさしく義勇を見つめる煉獄の瞳には、けれども、いまだかつて誰からも注がれたことのない、焼き尽くされそうな熱があった。
赤と金に彩られた煉獄の瞳は、燃え盛る炎を思わせる。この瞳に見つめられ、恋に身を焼く者もいるのだろうなとふと思い、義勇は、知らず視線をそらせた。
なぜそんなことを思ったのだろう。ツキリと胸が痛んだ由は、義勇にもわからない。
内心でうろたえはしても、義勇の表情はさして変わりはしなかったはずだ。それでもなにがしか察するものがあったのかもしれない。煉獄の苦笑が深まった。
「しがみついてくれとは言わんが、手はつないだままでもいいだろうか。祝い代わりにと言ったら、図々しいか?」
「……かまわないが」
自分と手をつなぐことが祝いになるなど、到底思えるわけもなく、義勇は眼差しを煉獄に戻すと小さく首をかしげた。
大声を注意するだけなら、方法はいくらでもある。大の男が童のように手をつなぎあうなどめったにない事態だと思うのだが、やはり煉獄にとっては普通のことなのだろうか。
義勇の困惑は消え失せることがなく、不可解な痛みの理由も知れぬままだ。だが、あまりにもうれしげな煉獄の笑顔を見ていると、べつにいいかと思いもする。
深く考えるのは、後でいい。手をつないでいてほしいとは、義勇こそが願うところでもある。姉との思い出を一人でたどれば、心に刻まれた傷跡がいまだにジクジクと痛むのだ。熱い煉獄の手が自分の手を握っていてくれるから、目を背けていたあたたかい記憶から逃げ出さずにいられる。
「よかった! ありがとう、冨岡!」
大きな声で言い笑う煉獄の手を、義勇はキュッと握りしめた。すぐに煉獄の口が閉じられ、精悍な顔に照れくさげな苦笑が浮かぶ。目はやわらかくたわんだままだ。瞳の奥にはまだ炎の如き熱がある。
煉獄の大声に驚いたか、先の少女はますます父親の足にしっかとしがみついている。少女の視線は、もはや活人形よりも煉獄に釘付けだ。父親も目を丸くしてこちらを見ていた。
「どうも驚かせてしまったようだな。冨岡が教えてくれて助かった」
煉獄の物言いはいたって素直だ。義勇は思わず言葉に詰まった。
こういうときには、なんと言って答えるのが正解なんだろう。
錆兎にならば、まったくだとからかい、笑ってみせることもできた。けれど煉獄にそこまで気安く振る舞うのはためらわれる。かといって、これしきのことを謙遜するのも妙な気がして、義勇は黙ったままそっとうつむいた。
思えば幼いころからこんな具合だ。両親の遺産で暮らしている義勇と、家業の手伝いに忙しい農家の子供たちでは、時間も話もなかなか合わない。おかげで尋常小学校の級友とは、ほとんど遊ぶこともなかった。虐められることはなかったが、友と呼べる者には恵まれずにいた。改めて考えてみれば、ずいぶんと侘しい子供時代だ。
けれど、姉がいればそれで十分義勇は満たされていたし、不満や反発はなかったように思う。義勇が心から友情を感じたのは、生まれてこの方、錆兎だけだ。
だから、煉獄の友好的な笑みや言葉には、うれしい反面、いつも少し困ってしまう。まばゆすぎる太陽は、目がくらんで、いたたまれなくなる。あけっぴろげな好意には慣れていないのだ。積極的に嫌われてはいないと思うが、なかなか周囲に馴染めない自分の性格ぐらい、義勇とて自覚している。
不死川や伊黒が知ったのなら、こめかみに青筋を立てそうな義勇の自己認識ではあるが、指摘できる者などこの場にはいない。沈黙する義勇と、ほんの少し寂しげに眉尻を下げた煉獄のそばには、驚きに目を丸くした親子がいるだけだ。
うつむいたままでいると、煉獄がふっと小さく息を吐きだす気配がした。かすかな吐息に淡い寂寥を感じ取り、慌てて義勇が顔を上げれば、煉獄は明るく笑っている。わずかに感じとったやるせなさなど、気のせいだとしか思えぬほどに朗らかな笑みだ。
「そろそろ行くか。姉上とは、奥山閣と活人形のほかにも見て回ったんだろう?」
「あぁ……西洋の操り人形や山雀の芸を見た記憶がある。最後に動物の檻を見て回ったはずだ」
歩き回った順をはっきり覚えているわけではないが、最後に虎を見たのは記憶している。
幼児の背ほども大きなペリカンや、二本足でピョンピョンと飛び跳ねるカンガルーとやらにも驚いたし、豪奢な羽を広げる孔雀にも目を見張ったが、もっとも印象深いのは虎だ。
親子連れに驚かせた詫びを告げた煉獄が、行こうと手を引き、義勇に笑いかけてくる。笑んだその目にふと懐かしさを感じ、義勇は、ゆるくまばたきした。
あぁ、そうか。あの日見た虎の瞳にも、煉獄の目は少し似ている。
金に光る虎の瞳。赤みが強い煉獄の目との共通点は黄金のきらめきだけだが、なぜだか妙に腑に落ちた。
義勇の脳裏に、檻のなかから義勇を見つめてきた虎の姿が、鮮やかに浮かび上がる。人に囚われてなお、密林の王者としての風格を感じさせた虎の瞳は、屈しはせぬと燃えるようであった。
煉獄も、義勇の目には王者然と映る。決して服従を良しとせぬ、孤高の王だ。
屈託なく気安い煉獄の周りには常に人が集まるのに、どうして孤高などという文言が浮かんだのだろう。疑問の答えはすぐに思い至った。
お館様の言のとおりならば、煉獄はきっと、鬼殺隊にとって明けの明星だ。暁に燦然と輝き、夜明けを告げる星である。
炎のような朝焼けのなか、あまたの星明かりが消え失せても輝きを放ちつづける明け星は、まさに煉獄を思わせた。鬼が跋扈する夜を終わらせる力強き星。柱なのだ。改めて思い、義勇はわずかに息を震わせた。
自分とはまるで違う。きっと錆兎ならば、煉獄の隣りにいても見劣りなどしないだろう。けれど、柱どころか隊士を名乗る資格すらない自分では……。
義勇はつながれた手を見つめた。視線が無意識に揺らぐ。不釣り合いだ。そんな言葉が頭をめぐる。
わかりきったことなのに、どうしてこんなにも胸が痛いんだろう。煉獄にかぎらず、柱たちはみな、自分なぞとは違う。自覚しているから、邪魔にならぬよう努めてきた。なのに、煉獄にだけは、なぜ。
隊士すべてが純直で高潔だなどと、義勇とて思ってはいない。高額な俸給が目当てであったり、大義名分を掲げて刀を振るうためだったりと、下賤な理由で鬼殺隊に入った者たちがいることぐらい、承知している。柱合会議でもたびたび隊士の質が落ちていると議題に上るのだ。義勇がどれだけ柱であることを否認しようと、力の差は歴然としており、水柱を継げる者はいまだ現れない。
義勇自身の意向はともあれ、義勇が水柱であることに変わりはなく、立場上は煉獄と同格だ。それでも、似つかわしくないとの卑下は、義勇の胸から消えそうになかった。
まぶしすぎて目がくらむ太陽。強く輝く孤高の星。そんな煉獄の手には、自分よりずっと似合いの手があるはずだ。なのに振り払えない。離さないでほしいと願う心は、いずこからくるのだろう。
「次は操り人形だなっ。そういった見世物を見るのも初めてだ。子供のようにはしゃいでしまったらまた教えてくれ!」
振り返り笑う煉獄はまぶしくて、離したくない、その願いだけが義勇の心臓を強く打ち鳴らしていた。