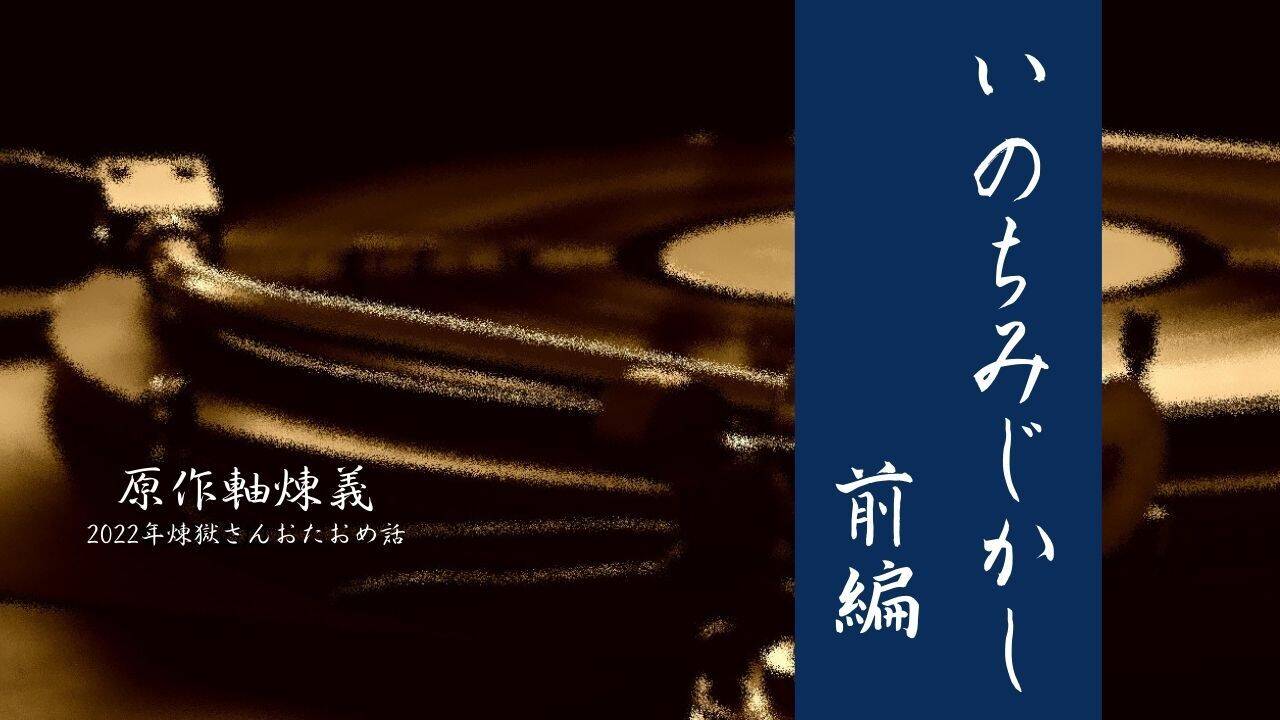「姉上ときたときには、どこから見て回ったんだ?」
「……たしか、奥山閣に」
「よし! ではまずは奥山閣だ!」
花屋敷を象徴する五層の楼閣へと足を向ける煉獄は、義勇の手を離そうとはしない。たびたび義勇を振り返り見る顔には、輝かんばかりの笑みがある。いかにもうれしげで、声も喜々として弾んでいた。
十二階からなる凌雲閣の威容には及ばぬまでも、鳳凰閣の異名も名高い奥山閣もまた、浅草名所だ。
幼いころにはフゥフゥと息を切らせて登った五階建ての楼閣の最上階には、以前と変わらず、蓄音機が置かれていた。
姉ときたときには人が群がり、蓄音機の様子はまるで見えやしなかった。それでも、まるで目の前で人が演奏しているかのように聞こえてくる音楽に目を丸くもしたし、興奮で小さな胸はドキドキと高鳴った。あの日の衝撃と感動を、義勇は今も覚えている。
国産の蓄音機が販売されるようになった今では、そこまで物めずらしくもないだろうが、庶民には高嶺の花であるのに違いはない。まだまだ客寄せに一役買っているようで、当時ほどではなくとも蓄音機の周りには人垣ができていた。
「人が多くて近づけんな。よく見えん」
「……昔は、まるで見えなかった」
あのころは大人の背に阻まれて、どんなに背伸びしても蓄音機の姿はちらりとも見えなかった。けれどもう、ほかの観光客から頭一つは優に抜け出るほど背も伸びた。今では蓄音機の金のラッパもちゃんと見える。
抱っこしようかと言う姉に、もう大きくなったんだからいいよとブンブンと首を振った自分が、今の自分を見たらなんと言うだろう。こんなに大きくなれるんだと目を輝かせるかもしれない。姉を守れるぐらい大きく強い男になるのだと、無邪気に願っていた幼い日々。遠くへ来た。また思い、義勇はわずかに目を伏せた。
守れなかった。あんなにも守りたかった人たちは、もういない。
「お、始まるぞ冨岡!」
煉獄の弾む声で義勇が我に返ると同時に、シィッ! と、とがめる声が聞こえ、傍らの煉獄がピシッと姿勢を正した。
謝罪しようとしたのか口を開きかけたが、また叱られるとでも思ったのだろう、すぐに口を閉ざす。それでも唇は弧を描いていて、横目に見ていた義勇は、沈みかけていた心がフワリと軽くなるのを感じた。
ほんの少しバツ悪げに義勇に向けられた視線は、それでもワクワクとした気配がほの見える。なんだか子供みたいだ。こんな煉獄も初めて見る。
キラキラと子供のように目を輝かせる煉獄が傍らにいるだけで、義勇の胸にも、理由の知れない歓喜がわいてくる。甘いのに、泣きだしそうに苦しくもあり、そのくせフワフワとした多幸感に笑いたくもなった。かすかな痛みを伴う不思議な喜びは、ラムネの泡のように心でパチパチと弾けて、鼓動は早まるばかりだ。
明確に言語化されない感情の渦は、いったいどこからくるのだろう。戸惑いは不快では決してなく、当惑さえもがどことなし心地よかった。
流れだした西洋音楽は、姉と一緒に聞いた曲とは異なる。以前に聞いたのはオーケストラだったが、今日のレコードはピアノ曲だ。やわらかく穏やかなピアノの調べに、義勇はまたグッと息を詰まらせた。
――あぁ、この曲は……。
記憶が鮮やかによみがえる。枯れはてたと思っていた涙が熱を持って溢れそうになるのを、義勇は唇を噛みしめこらえた。
西洋の技術への感嘆はあれど、まだまだ聞き馴染みのない西洋的な音色と曲調は、耳に合わぬ者のほうが多いとみえる。出だしこそ観客もワッと沸いたが、すぐになんだか釈然としない顔をしたり、あからさまに顔をしかめる者が出始めた。落胆めいた気配に義勇の胸がシクリと痛んだ。
「きれいな曲だな」
だから、煉獄のささやきに、義勇は少しだけ驚いた。
「……夜想曲だ。たしか、ショパンのノクターンと、姉は言っていた。姉が弾くときは何度もとちっていたから……ちゃんと聞くのは初めてだ」
なにげなさを装っても、声はかすかに震えた。義勇にとっては懐かしく、今となっては物悲しくもある曲だ。
耳によみがえる素人奏者によるノクターンは、こんなにも流暢ではなかったけれど、やさしかった。むずかしいわと照れ笑う姉に、でも俺は姉さんのピアノが一番好きと笑い返せば、ありがとう義勇はやさしいねと、あたたかな腕が抱きしめてくれた。
「姉上はピアノを弾かれるのか。冨岡は上流の出なんだな」
「両親が洋行帰りだっただけだ。母がドイツで買い求めたピアノが家にあった」
母の形見となったピアノを、姉はひどく大事にしていた。嫁入り道具の一つとして、婚家でもやわらかな音色をひびかせるはずだったあのピアノも、もうない。姉の血にまみれた、小さな古いアップライト。赤く染まった鍵盤が、やさしい調べを生むことは二度とない。
聴衆をはばかり交わす会話はひそやかだ。つながれたままの手が、ギュッと握りしめられた。煉獄は、無言で前を見据えている。義勇の胸を去来する悲哀など知るわけもないのに、重ねての問いも慰めも口にせず、煉獄はただ強く手を握ってくれていた。
悲しみが、スッと薄れていく。ピアノの美しい旋律が、やさしく義勇の心を震わせた。
不思議なものだ。己の覚悟を示す羽織以外には、姉や錆兎の思い出を呼び覚ますものなど遠ざけてきたというのに、煉獄とともにいるだけで痛みは和らぎ、幾ばくの切なさとともに懐かしく思い出せる。
義勇は視界の端で煉獄の横顔をそっとうかがった。凛々しい横顔は、ゆるく微笑んでいる。つないだ手の力強さも変わらない。義勇は静かに目を閉じた。少しだけ強く、自分からも手を握り返してみる。
「……一番、好きな曲だった」
たどたどしくピアノを弾く姉の姿が、恥ずかしげな笑みが、瞼の裏によみがえる。幸せな記憶は、やはりかすかな痛みを伴っていて、罪悪感ゆえか喉の奥には苦さが少し。それでも、今は思い出していたかった。
煉獄と手をつなぎ合う今ならば、苦しみの底に沈むことなく、やさしい曲に耳をそばだてることもできる。だから大丈夫。思い出しても胸を掻きむしることはない。
「そうか……初めて聞く曲だが、俺も好きだ。君と聞けてよかった」
煉獄はどんな顔をして言ったのだろう。見たいとの欲求に突き動かされそうになったが、義勇は目を開けられなかった。こぼれ落ちる涙が、このやさしい時間を連れ去ってしまいそうで、まぶたを押し上げることはかなわなかった。
ひそやかに落とすやさしいため息が、夜の静寂にふわりと解けゆくかのような、繊細な調べ。
今この瞬間の己が心を音色にしたのなら、まさしくこんな曲になるのかもしれない。
文雅にはとんと縁がないのに、こんなガラにもない感傷的な言葉が浮かぶとは。義勇はかすかに苦笑した。
切なくて悲しくて、けれどもどこか心ゆるび安堵感に包まれるこの心地は、なんなのだろう。遠い日に置き去りにしたはずの幸せという言葉が、胸で揺らめいている。静かに波打つ春の海のような心のさざめきは、きっと隣に煉獄がいるからだ。
夜想曲……夜に想う。そんな日は、おそらく自分には二度とこない。夜とは戦いの時間であり、血の臭いと泣き声に包まれる刻限だ。無惨を斃したあとに訪れるはずの、穏やかな夜のなかにいる自分の姿など、義勇は思い描けない。
それでも、願う。いつか安穏とした夜に月明かりの下で、煉獄がこの曲を聞いてくれたらいいと。
儚いばかりの願いは、祈りに似ている。彼がふたたびノクターンを聞くとき、傍らには誰がいるだろう。美しい細君か愛くるしい子か、それとも心許した友人だろうか。誰であれかまわない。ただ願わくばほんの一瞬でもいい、自分を思い出してほしいとあさましく願う。叶えばどれほどうれしく、誇らしいことだろう。初めてこの曲を聞いたときに手をつなぎ合っていたのは冨岡だったなと、少しだけ微笑んでくれたのなら、それ以上は望まない。
万が一、自分が生き延びたときにも、思い出には煉獄の笑顔があるだろう。姉が弾くたどたどしいノクターンを耳によみがえらせながら、ひとりの夜に思い浮かべる姉のやわらかな笑みには、きっと今日このときの煉獄のぬくもりや微笑みが混ざりあうに違いない。握り合う互いの手が、それを義勇に確信させる。
こうしてまろい心持ちでいられるのは、彼の手が、熱くやさしいから。煉獄が隣りにいるから、懐かしい音色にも悲しみだけに引き込まれずいられる。
義勇はゆっくりと目を開けた。浮かびかけていた涙はもう乾いている。
うかがい見れば、煉獄もまた音色に身を委ねるように目を閉じていた。唇はやっぱりやわらかく弧を描いている。義勇の唇にも、ささやかな笑みが浮かんだ。
沈黙のなかで、ノクターンが静かに流れていた。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
「蓄音機というのは凄いものだな。まるで目の前で人が演奏しているみたいだった」
「俺も、初めて聞いたときには同じことを思った」
ざわめきを取り戻した人々が、三々五々散っていく。最上階に設えられた展望台に向かう者もいれば、ほかの展示を見るために階下へと足を運ぶ人もいる。周囲の目を気にしてか、煉獄の声はまだ少し控えめだ。
「冨岡もか! 同じように感じられたのなら、うれしいかぎりだ!」
前言撤回だ。なにがそんなにうれしいのか、興奮しきった声は常と変わらず大きい。
周囲を驚かせるに十分な声量に、とがめだての視線が一斉に二人へと向けられた。
義勇が注意するまでもなく、煉獄も注目を浴びているのに気づいたらしい。また少しばかり恥ずかしげに笑うと、照れ隠しめいたそぶりで頭をかいている。
煉獄にしては見慣れぬ仕草だが、妙に様になっている。男らしい顔立ちをしているだけに、少々子供っぽい仕草や表情をすると、どことなく愛嬌があってかわいらしくすらあった。
とはいえど年下ながらも煉獄は、義勇からすれば柱とはかくあるべしという見本の如き男である。かわいらしいなどという感想を知れば気を悪くするだろう。思い上がらぬようにせねばと、義勇はさり気なく呼吸を整えた。
どうも今日は感情の揺れ幅が大きくていけない。ノクターンのせいだろうか。感傷に惑わぬよう常々努めているというのに、思い出にひたるなど何年ぶりだろう。
「こういう場には慣れていないので、どうもいかんな。大きな声を出してはいけないとわかってはいるんだが」
「声が大きすぎたら、教える」
余計な世話だろうかと思いつつも、わずかに視線をそらせ義勇が言うと、煉獄の笑みが深まった。
「ぜひそうしてくれ!」
弾んだ声がひびいて、義勇はつないだ手に力を込めた。意図は過たず煉獄に伝わったらしい。煉獄は言葉を重ねることなく、小さく忍び笑った。喜びを抑えきれない。そんなふうに感じられる笑みだ。
口下手な自分が言葉で注意すれば、煉獄を不快にさせてしまうかもしれない。故に選んだ方法だったが、煉獄の反応は予想外だ。
喜色あらわな煉獄に、義勇は気恥ずかしさを隠しきれず、つい手を引きそうになった。途端に手を握り返され、視線を上げると、生真面目な顔がまっこうから見つめている。煉獄の頬はほんの少し紅潮していた。
「このまま手をつないでいてくれないだろうか。俺は行楽には縁がなかったから、まるで経験がない。いたらぬところがあれば、さっきのように君が教えてくれ」
「俺だって慣れてるわけじゃない」
謙遜ではなく事実だ。貧しいほどではなくとも、本来なら女学校へと通う歳の姉と幼かった自分の二人暮らしはつつましやかだった。頻繁に行楽するお大尽な生活だったわけではない。
両親が亡くなってすぐに、以前には数人いた手伝いも、姉が暇をやった。毎日台所で立ち働き、たらいで洗濯するようになった姉の手には、いつからかあかぎれが目立つようになっていた。ピアノを習い弾き、女学校で習ってきたコロッケを母とともに作った以前の手は、白魚の如きたおやかさであったのに。
つましく暮らすぶんには、ばあや一人ぐらい雇っていられただろう。けれども、ばあやがどんなにお嬢様と坊っちゃまを置いて故郷になど帰れませんと泣いても、姉の決心は固かった。今ならばわかる。姉は両親の遺産を減らさぬよう努めていたのだろう。理由など考えるまでもない。
――俺の将来のためにと、姉さんは、苦労を買って出てくれていた。
義勇が望むのならば高等学校(現在の大学相当)や大学(同、大学院修士課程相当)にだって進めるようにと、姉が決意していたのは想像に難くない。両親が亡くなった当時は、官立(国立)の帝大でさえ授業料は年二十五円、私学ともなれば三十六円もしたはずだ。ただでさえ幼い義勇と二人きりとなった暮らしだ、気丈な姉にも不安はいくらでもあっただろう。けれど姉は、義勇の学費のためにと頼りにしていたばあやにまでも暇をやり出費を抑え、苦労を重ねようともいつでも笑ってくれていた。
尋常小学校を修了したらどこかに奉公すると告げたときにも、姉は、お金の心配などしなくていいのと義勇を懇々と諭し、高等小学校へと進学させたものだ。無償である尋常小学校と違い、高等小学校には授業料がかかる。だというのに、姉は齢十歳の義勇が働きに出ることを、頑として許さなかった。自分は新しい着物も買わずにいたくせに。あかぎれのある細い指先を思い浮かべ、義勇は小さく唇を噛む。
それでも姉は、ときおり義勇を行楽へと連れ出した。行くのはいつも、義勇がもっと幼いころに、父や母と行った場所だ。帰宅すると姉は、楽しかったねと笑い、必ず同じ言葉を口にした。
『――いてね、義勇。――――約束、ね?』
細い小指を差し出して姉が笑うから、義勇も笑って小さな指を絡めてうなずいた。声をそろえて指切りげんまんと歌った日々。義勇の目がゆっくりと見開いた。
そうだ、約束した。何度も、何度も、指切りげんまんと約束したのに。
義勇は煉獄の目をじっと見つめ返し、もう一度手に力を込めた。
「わかった」
「本当かっ? よかった、ではこれが合図だな! ありがとう、冨岡!」
ギュッと握り返される手に、小さくうなずく。煉獄は満面の笑みだ。とろけるように幸せそうな笑みは、やっぱりまぶしい。
礼を言わねばならないのは、俺のほうだ。思いながらも言葉にはせず、義勇は静かに口を開いた。
「次は、どこへ行く?」
「君が姉上と回った順にしよう。俺にも君の思い出を共有させてくれ!」
明るく朗らかな声と笑みが思い出の笑顔と重なり、また涙を誘われる。懸命にこらえて、義勇は日差しの差し込む展望台を指さした。
「……あそこだ。二人で並んで、十二階を見た」
「よし、なら出てみよう!」
子供のように手をつないだまま、そろって日差しのもとへと足を踏み出す。
階下の広い展望台と違い、最上階に設えられているものは周り廊下とさして変わらぬ幅しかなく、人がひしめきあっている。幼いころも、大人たちに押され姉の手を離さぬように必死になったものだが、体格のいい二人連れが手をつないで楽しむには、どうにも狭苦しい。だが煉獄はとくに気にした様子もなかった。
「おぉ! まさに千里の展望だな! 上天気でよかった、十二階もいっそう間近に見える。下から見上げただけでも目を回しそうに高いが、こうして見ると、雲を凌ぐとの名称が伊達ではないのがよくわかるな!」
青空を貫かんとばかりにそびえ立つ赤煉瓦の塔に、煉獄は至極満足げだ。子供みたいだとまた思う。
「十二階は?」
「階下で任務にあたったことはあるが、登ったことはないな」
言葉足らずな問いにも戸惑うことなく快活に答えた煉獄に、義勇は相づち代わりにコクリとうなずいた。
「いつかあれにも登ってみるとしよう。五階でさえこの見晴らしだ、十二階ともなれば、世界を一望するような素晴らしい眺めだろう!」
そのときには、煉獄は誰と手をつなぐのだろう。思いつつキュッと手を握れば、煉獄は輝く笑顔を義勇へと向けてきた。
「すまん。またやってしまったな。冨岡、十二階でもこうして教えてくれ」
声をひそめて笑う煉獄に虚を突かれ、義勇は思わず目をしばたたかせた。
義勇の反応は、煉獄にとっては予想外だったのかもしれない。笑みを消しわずかばかり眉尻を下げた顔は、どことなく不安げにも見えた。
「駄目だろうか。あぁ、もちろん君に頼りっきりになるつもりはないぞ。ちゃんと場所柄をわきまえるよう、俺も注意する」
「いや……十二階は、俺も行ったことがない。案内できないが」
「かまわないとも。道案内が欲しいわけではない。冨岡、君と行きたいだけだ」
静かな声音で言われ、ドキドキと心臓が騒ぎ出す。
ではまた煉獄と手をつなぎ、市井の人々と同じように娯楽に興じられるかもしれないのか。昔、姉の手を引いて、姉さんこっちと笑ったあの日々のように。それはひどく魅惑的な想像だった。
けれど、馬鹿なと自嘲する自分もまた、義勇のなかには存在している。
鬼狩りに休日などない。たまさか無惨が出没した場所が歓楽街だっただけで、そんな事情でもなければ、任務でもなしに浅草に繰り出すことなどないだろう。だからこんなのは、果たされることのない徒言だ。煉獄だってきっと、約束の意味で口にしたわけではないに決まっている。わかっていても、義勇の胸は騒いだ。
「君に無理をさせたいわけではないんだ。都合が悪ければ、俺に遠慮せず断ってくれてかまわない。だが……君が嫌でなければ」
「おいっ、兄ちゃんたち邪魔だよっ。見終わったんならどいてくんな!」
煉獄の言葉に被せて背後からかけられた声に、思わず義勇は肩を跳ね上げた。煉獄も同じ仕草をしたのを見れば、驚きは同様だったらしい。
慌てて二人同時に振り返ると、年嵩の男がいかにもイライラと睨みつけていた。男の後ろにも展望台に出る順番を待つ者が、同じような顔つきで並んでいる。気配を消しているわけでもない一般人相手に、なんという失態か。
「すみませんっ! 冨岡、どうする?」
落ち込みかけた義勇と違い、煉獄はすでに堂々としたものだ。本物の柱はこんなところからして違うなとほんの少し自己嫌悪が増すが、素直な羨望もまた、義勇の胸にわく。
「煉獄が満足したなら、移動したほうがいいと思うが」
「俺は君といられるなら、どこでも」
ためらいがちの問いに返されたのは、そんな言葉だ。声音はどこか甘い。耳に顔を寄せてのささやきは人が多いからだとわかっているのに、心なしか陶酔しているようにも聞こえた。
ビクリと怯んだ義勇を見つめる煉獄の顔が近い。なんなのだ、これは。これではまるで睦言ではないか。
目を見開いた義勇になにを思ったのだろう。煉獄はまたかすかに眉尻を下げたが、すぐにいつもと同じ闊達な笑みを浮かべた。
「ほかを回る時間がなくなっては困るな。行こう冨岡」
ムッと睨んでいる男に軽く会釈して、煉獄は義勇の手を引き歩きだした。一人ならば義勇とて慌てもしないが、どうにも今日は勝手が違って反応が遅れる。まごつく義勇と違い、煉獄は平常心を保っているようだ。これではどちらが案内しているのだかわかりゃしない。
「姉上とは次にどこへ行ったんだ?」
「あのときは展示が骨董だったから、ほかを回ろうと……。あぁ、活人形を見に行ったんだと思う」
「そんなものもあるのか。楽しみだな。歌舞伎の一幕があればいいんだが。冨岡は歌舞伎は好きだろうか。俺はわりと観るほうなんだが、去年、歌舞伎座が市村座や帝国劇場と『勧進帳』を競演していただろう? 運良く市村座のを観られたんだが、吉右衛門の富樫は初役とは思えぬ素晴らしさだった。残念ながら、肝心の弁慶と義経は今ひとつだったがな。冨岡はどれか観たか?」
「いや、歌舞伎は観たことがない」
父や母が存命のころは義勇が幼すぎて、家族での行楽に観劇のたぐいは含まれていなかったのだろう。姉に誘われるのは両親との思い出の場所ばかりだったから、観劇の経験はろくにない。ここ花屋敷でも、せいぜいが操り人形の劇を観たぐらいだ。流行りの活動写真だって、義勇は一度も目にしていない。
隊士となり俸給を得るようになってからも、娯楽など目もくれず、ただひたすらに鬼狩りと鍛錬の日々を送ってきた。負傷し休養を命じられても、せいぜいが詰め将棋を問いて過ごすぐらいで、我ながら面白みなどまるでない男だ。
わずかばかり気後れしつつ言った義勇に、煉獄は呆れるどころか、どこかうれしげに顔をほころばせた。
「それなら、俺が冨岡に教えられることもあるんだなっ。十二階だけでなく、歌舞伎にも一緒に行かないか? だがその前に、君が姉上と行った場所をめぐるのが先だな。冨岡の思い出をたどれるのが楽しみだ!」
なにがそんなに楽しいのだろう。煉獄が自分なぞの過去に興味を持つ理由は、義勇には想像もつかなかった。
水を差すのも申しわけなく、さりとて、たやすく約束などできる立場にはお互いない。こんな日は稀なのだ。偶然が重なり合ったからこそこうして花屋敷になどきているが、もともとは調査が目的だ。そんな用向きでもなければ、任務がない日には鍛錬に励む。隊士となって以来、義勇はそうして日々を過ごしている。
煉獄は義勇と違い、甲のころから継子を迎えていたと聞く。あいにくと煉獄の稽古は厳しすぎて脱落者続出という話だが、面倒見のいい彼らしい一面だ。弟も隊士を目指しているようだし、稽古をつけてやっているのなら、任務や自分の鍛錬以外にも忙しいことだろう。俺をかまう暇などなかろうにと、義勇は戸惑いを深くした。
義勇がろくな返事をできずにいても、煉獄は気を悪くするでもなく、にこやかなままだ。手もずっとつないだままでいてくれる。ならば、約束はできずとも今日ぐらいは。
子供のように手をつないでいるうちは、ほかのことは考えまい。姉との約束を果たすには、痛みを伴う。それでも煉獄の熱い手が、あたたかな笑顔が傍らにあれば、耐えられそうな気がした。