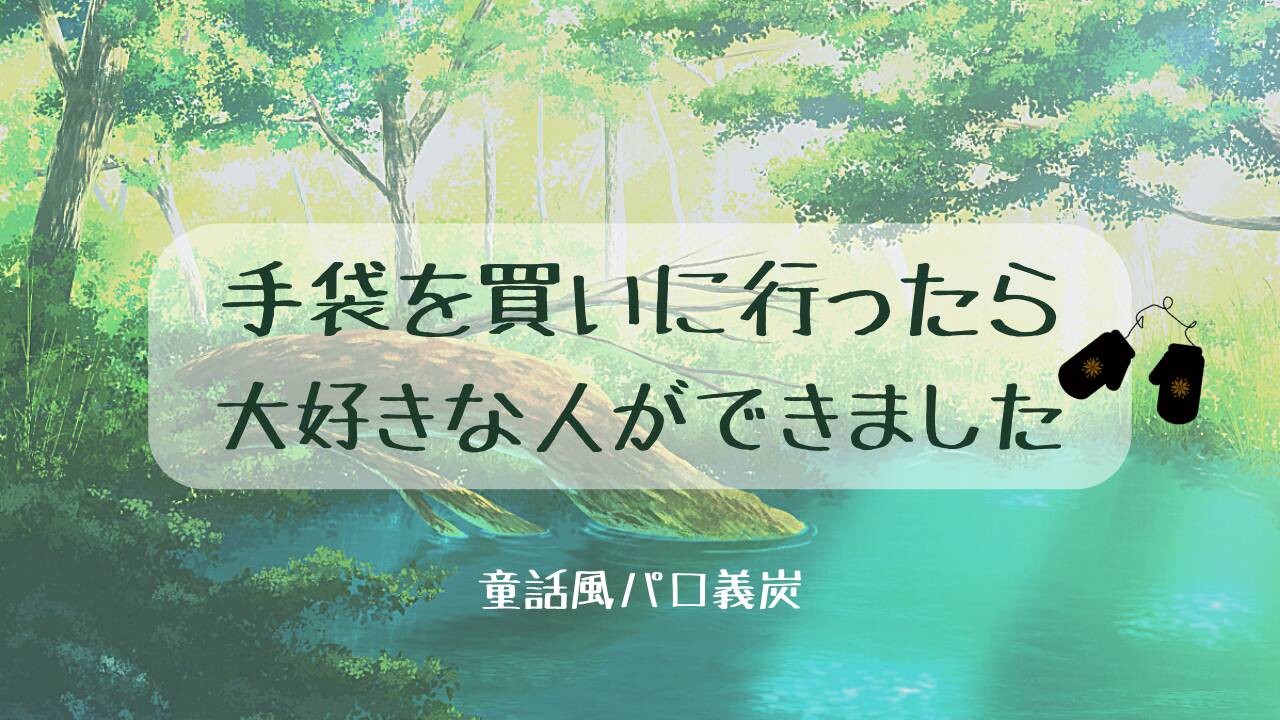「お前たち、ちょっと待ちなさい」
くたくたになった炭治郎たちが、それでもどうにか足を動かして岩山を下りようとしたところ、岩柱様が炭治郎たちを呼び止めました。
「なんだよ、数珠のおっさん」
「馬鹿っ! 岩柱様になに言ってんだよお前! 見ろよ、あの太い腕っ。おっきな手! あんなので叩かれたら大怪我しちゃうぞっ」
怖いもの知らずな伊之助に、善逸はビクビクしっぱなしです。炭治郎も失礼なことを言うのはやめてほしいなぁと、思わず眉を下げてしまいました。
「なんでしょうか、岩柱様」
「自分の足で山を降りるのは感心だが、それでは遅くなる。近道を作ってやろう、そこを通っていくがいい」
言うなり岩柱様は、むんっと力を込めて地面を強く殴りつけました。ゴンッと大きな音がして、たちまち岩盤にぽかりと穴があいたものだから、炭治郎たちはあんぐりと口を開いてしまいました。
穴は真っ暗で、底がまったく見えません。なんだかつるつるとしても見えます。滑っていけば、きっと麓までまっしぐらに行けるのでしょう。
「うわぁ、すごいなぁ! これならすぐに麓まで行けそうだ! ありがとうございます、岩柱様」
「これで夜になる前に帰れます。ありがとうございます!」
炭治郎と禰豆子はお礼を言いましたが、善逸はすっかり怯えてしまったようです。
「やだやだやだやだ! きっと真っ逆さまに落ちちゃうんだって!」
「うるせぇなっ、早く行け!」
「いやぁぁあああぁぁぁあぁぁっっ!!」
伊之助に背中を蹴られて、悲鳴を上げながら善逸が穴に滑り落ちました。伊之助もすぐに飛び込んで、キャハハハハと楽しげに笑い声を響かせながら滑り降りていきます。あっという間に二人とも見えなくなってしまいました。
炭治郎と禰豆子は顔を見合わせ苦笑すると、もう一度岩柱様に頭を下げました。最後まで大騒ぎでちょっぴり申し訳なかったのです。
「さようなら、岩柱様」
笑って手を振った禰豆子が穴を滑っていき、炭治郎も続こうとしたのですが、岩柱様がなぜだか呼び止めてきました。
「狐の子供よ……なぜ最後に頭突きなどしたのだ?」
「もしかしたら、『あの方』がここに加護をくれたかもしれないと思ったので!」
そう言って炭治郎は、ちょっぴり赤くなってえへへと笑いました。
それを見て岩柱様も、少し笑ってくれました。初めて見せてくれた岩柱様の笑みは、とてもやさしい笑みでした。
「小さき狐の子供よ。お前なら、あの者の憂いを晴らせるかもしれないな」
真っ暗な穴を滑り降りると、そこは岩山の麓でした。先に降りて待っていた善逸は怖かったよぉと泣いていましたが、伊之助はご機嫌で、もういっぺん滑りてぇと大はしゃぎでした。
岩柱様用のお弁当を朝ご飯にして、炭治郎たちは帰り道を走ります。眠っていないので体はやっぱりくたくたでしたが、急がなければお店に着くのが遅くなります。
炭治郎たちは駆けて、駆けて、駆け続けました。疲れた体ではいつものように速くは走れませんでしたが、炭治郎も禰豆子も、伊之助や善逸も、みんな懸命に走りました。
途中でお腹が空いて怒りっぽくなった伊之助が文句を言ったので、二日目用のお弁当を食べて一休みしましたが、そのあとはもう、まっしぐらに洋服屋さんのお店へと急ぎます。
そうしてみんなで走り続けて、お日様がまた赤く染まるころ、炭治郎たちはようやくお店へと帰り着きました。
トントントン。炭治郎はいつものように戸を叩き、元気にただいまと言うと戸を開きました。
「おかえり」
洋服屋さんは炭治郎の元気な笑顔を見てそう言うと、炭治郎の頭をいつもどおりにやさしく撫でてくれました。
テーブルにはもう四人分の夕ご飯が並んでいます。テーブルに着いた炭治郎たちの頭を順繰りに撫でて、洋服屋さんは「これでお遣いはおしまいだ。よくやった」と言うと、いつものようにお仕事机へと行ってしまいました。
急いでご飯を食べると、炭治郎も洋服屋さんの隣に並びます。
「お仕事を見ててもいいですか?」
やっぱりいつものようにうなずいてくれた洋服屋さんは、手にした水晶にふぅぅっと息を吹きかけました。
息を吹きかけられたところから、水晶のヒビが見る見る青く染まっていきます。細かなひび割れから青い色が行き渡り、じわじわと水晶全体が青く染まっていきました。やがてすべて染まった水晶は、まるで水柱様のお住まいの泉の水を固めたような、きれいに澄んだ深い青色をしていました。
洋服屋さんは、その水晶をパンッと両手で挟むように叩きました。するとどうでしょう、水晶は真っ二つに割れてしまったではありませんか。
ビックリして目をパチパチとまばたかせた炭治郎の前で、洋服屋さんは藍鼠色のリストバンドを二つ取り出すと、半分になった水晶の欠片をそれぞれしっかりと貼り付けました。
「これをあいつに」
視線の先にはパンを口いっぱいに頬張りながら、こちらを気にしている伊之助がいます。炭治郎がリストバンドを持っていくと、伊之助は善逸や禰豆子と顔を見合わせました。
「やいっ、なんで俺なんだ? 権八郎はまだなにももらってねぇんだぞ?」
「そ、そうだよっ。炭治郎だけなにもなしなんて……」
「洋服屋さん、なんでお兄ちゃんにはなにもくれないの?」
口々に言うみんなの言葉はうれしいのですが、炭治郎は少し慌ててしまいました。だって炭治郎は、なにももらえなくてもかまわなかったのですから。
みんなが洋服屋さんを嫌いになっちゃったらどうしよう。やめないかと言いながら、炭治郎はオロオロと洋服屋さんを見ました。
「この子にはもう加護がある」
そう言って洋服屋さんは、炭治郎の耳飾りをそっと撫でて、みんなを見回しました。
「……もうじき年が替わる。おそらく明日の夜には、お館様から森に住む者すべてにお達しがあるだろう。お前たちはもうここに来るな。お達しに従い家でおとなしくしていろ」
洋服屋さんの言葉に炭治郎たちは驚きました。
お館様のお達しがあることを洋服屋さんが知っているのは、もう誰も驚きません。人間にしか見えない洋服屋さんですが、とても不思議なことができるのですから。
驚いてしまったのは、もうここに来てはいけないという言葉です。
「どうしてですか? 俺はもっと洋服屋さんと一緒にいたいです」
さっき炭治郎がただいまと言ったら、洋服屋さんは初めて、おかえりと言ってくれました。炭治郎はそれがうれしくて、ただいまと帰るお家が洋服屋さんのお家ならどんなにいいだろうと思いました。
洋服屋さんがおかえりと迎えてくれるお家。炭治郎と洋服屋さんが一緒に住んで、一緒にご飯を食べて、一緒に眠るお家。想像するだけで、それは夢のように素敵なことに思えます。
もちろん、ここは洋服屋さんのお家で、炭治郎のお家ではありません。それでも「おかえり」と言ってもらえて、とってもとってもうれしかったのに。
悲しくなった炭治郎に、洋服屋さんは小さく首を振りました。
「年が替わる夜……柱達はみな『災い』と戦うことになるだろう。『災い』の首魁は強い。柱全員の力を合わせても勝てるかわからない。もしかしたら全滅するかもしれない。それほど首魁は強いんだ。柱でも……神でも、命を落とすことはある」
ヒュッと息を吸い込んで言葉を失った炭治郎に、小さくうなずくと、洋服屋さんは炭治郎たちを見回して静かに言いました。
「今日は泊っていくといい。最後の夜だ」
洋服屋さんの言葉に、いつもは騒がしい善逸や伊之助も黙り込んでしまって、それぞれ考え込みながらベッドに入ります。
伊之助の手首には、結局藍鼠色のリストバンドがはめられました。洋服屋さんから最後の贈り物です。もうお代としてお手伝いをすることはないのですから。
今日も炭治郎は、洋服屋さんに抱っこされてベッドに入りました。洋服屋さんは自分のことについて、やっぱりなにも言ってはくれません。けれどみんな、洋服屋さんが何者なのか、なんとなくわかっていました。
少なくとも、炭治郎と禰豆子は、あの方を思い浮かべずにはいられませんでした。
洋服屋さんの、やさしくて悲しくて、寂しい匂いに包まれて、炭治郎の大きな目がじわりと涙で潤みます。洋服屋さんはそっと炭治郎の頭を撫でてくれました。
そして、炭治郎にだけ聞こえるように、小さく囁いてくれたのです。
「炭治郎……俺の名前は義勇だ。もしも俺を呼ぶときが来たら、そう呼びかけろ」
そんなときが来なければいいがと言う洋服屋さんの声は、少しつらそうでした。
けれど、炭治郎の小さな胸には喜びがいっぱい溢れて、とうとう涙が零れました。
初めて名前を呼んでもらって。初めてお名前を教えてもらえたのです。
本当にこれで最後な贈り物。
それを大切に噛みしめて、炭治郎はゆっくりと眠りに落ちていったのでした。