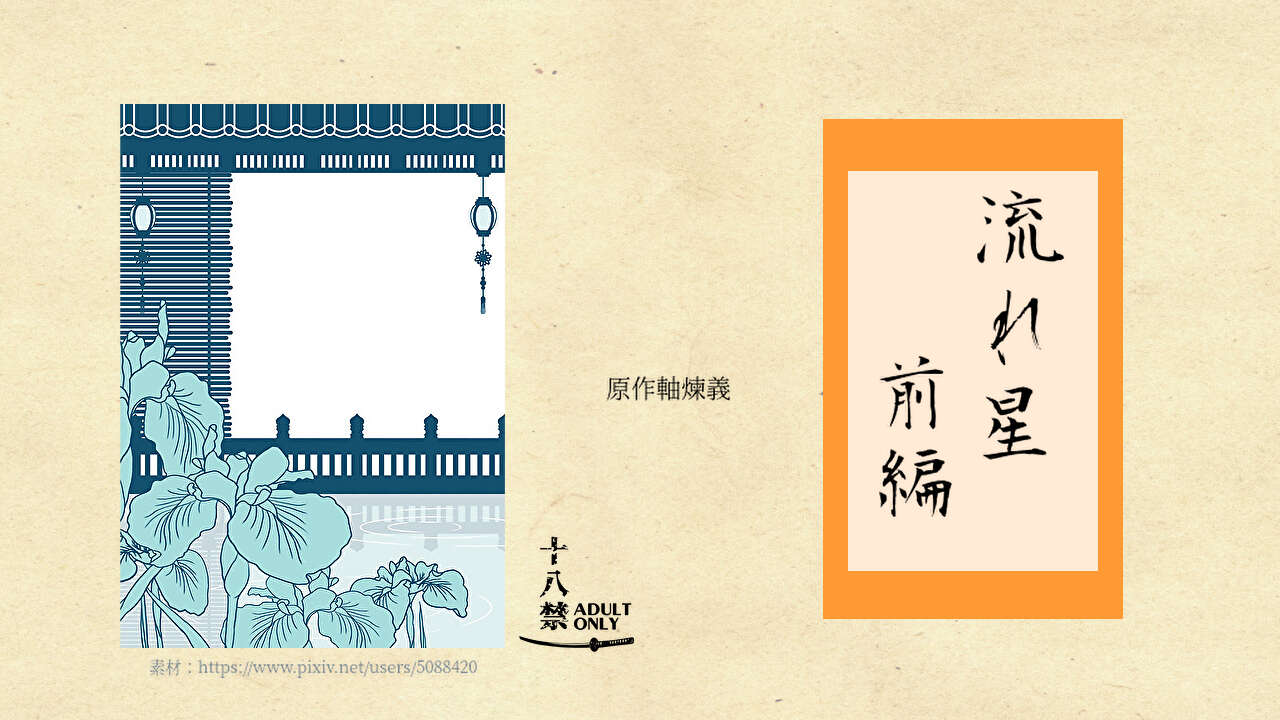「……俺の、隊服の内ポケット」
「え?」
「錆止めの……小瓶」
錆止め、と声には出さず繰り返した煉獄の脳裏に、ポンと浮かんできたのは、煉獄自身も慣れ親しんだ代物だ。慌てて丼を卓に戻すと、煉獄は脱ぎ捨てられた冨岡の制服を手にとった。
探るまでもなく、目当てのものはすぐに見つかった。
「そうか、丁子油か! 稚児の草紙にも出てきたな。たしか、僧の寝所に向かう前に稚児が準備するのに使っていたんだったか」
「べつに、そういう意味で持っていたわけじゃないっ。刀は、なるべく早く手入れしておきたいからだ。もし刀を折ったら先生に骨を折られる」
稚児が準備のために使用する記載はあったが、ほかの書物では見かけることがなかったので、すっかり失念していた。背を向けたまま口早に言う冨岡の声を聞きながら、煉獄は、小さな茶色い薬瓶に入れられた液体をチャプリと揺らしてみる。使いさしだけあって量は多くはないが、行為には十分足りそうにも見えた。だが。
「冨岡の育手は過激だな! しかし……このまま使っても大丈夫だろうか。以前、うっかり傷口に垂らしてしまったことがあったが、かなり刺激があったぞ」
虫歯など一本もない煉獄は使用したことがないが、よく効くと評判の歯痛薬にも丁子油は使用されている。効くのはいいが、とにかく刺激が強いのが難点だとも、柱になる前に一緒に任務に着いた隊士たちが言っていた。鎮痛作用や殺菌作用があるのは最適と言えなくもないが、使用する場所が場所だ。
はたして粘膜に使用してしまっても、大丈夫なものなんだろうか。冨岡の体を害するのはまっぴらなのだが。
煉獄がどうすべきかと思案していると、冨岡がちらりと振り向いた。
「食い物なぞを使われるよりマシだ。なにごともやってみなければわからないと言ったのは、おまえだろう」
挑むような声音や眼差しとは裏腹に、冨岡の肩はかすかに震えていた。虚勢の態度で隠した怯えは、この先の行為へのものか、それとも煉獄に拒絶されることへなのか。いずれにしても、煉獄の目にはどうしようもなく健気に映る。
「そうだな。男に二言なしだ」
自然と煉獄の顔に浮かんだ笑みは、今度は虚ろな空笑いではない。冨岡も、こんな事態になってもなお、望んでくれている。応えねば男がすたるというものだ。
「それなら、さっさとしろ。俺にも二言はない。……煉獄の好きなようにしてくれ」
強がる声音は、それでも少し掠れている。ゴロリと潔く仰向けになり足を広げるものの、冨岡の顔は、ふたたび両腕で覆われ見えない。抑えようとしても不安は打ち消せないのだろう。四肢も、胸や腹も、微細ではあるが震えていた。けれども欲望の象徴は、まだ力を失いきってはいなかった。
性と恋の興奮は、まだ冨岡の身のうちにもあるのだ。
喜びと決意に背を押され、言葉ではなく、煉獄は行動で応えた。
キュポンと音を立て、小瓶の蓋が開けられる。そんな些細な音にも、冨岡の肌はヒクリと震えを大きくした。
手のひらに落とした油はサラリとしている。冨岡が見ていないのを確かめ、煉獄は手にした油にそっと唾液を垂らした。これしきで刺激が薄まるとは思えないが、気は心。そのまま使うよりはマシだろう。煉獄は無言で一つうなずくと、両手を擦り合わせ、手のひら全体に油をなじませた。
油が乾く前に、ことを進めなければ。だが焦るな。初めてなのだから、冨岡の反応を見落とさぬようにしなければ、苦痛ばかりを強いてしまう。胸の内で繰り返し自分に言い聞かせながら、煉獄は冨岡の脚を立たせた。
冨岡は逆らわない。かすかに震える膝頭に、チュッと小さな口づけを落とすと、煉獄は油をまとった手をすべらせ、少し浮いた双丘を押し広げた。
小さく固い蕾は、押し開く手に逆らい、なおもキュンとすぼまろうとしている。よしよしと子をあやしでもするように、かたくななそこをそっと撫でると、蕾はヒクンと反応を返し、煉獄の指の腹に口づけるかの如くに吸い付いてきた。力を込めると、先ほどよりもすんなりと煉獄の指先が飲まれていく。
「うっ」
「痛いか?」
グッと押し込んだ瞬間に、冨岡がもらしたあえかな呻きは、意図せぬものだったのだろう。煉獄の問に、フゥッと息を整えると、大丈夫だと存外しっかりとした声音で返事があった。
我慢するなと言ってやることはできなかった。ここで引けば、冨岡の苦痛や羞恥がいや増すだけだ。
第一関節までしか入らなかった指先を、ゆっくりと押し進めていく。フゥゥと長く息を吐きだす音がする。吐き出される息にあわせて、冨岡の体からわずかばかり力が抜けるのを感じた。呼吸に合わせて指を押し込み、冨岡が息を詰めるたびに煉獄は、震える膝に、波打つ腹にと、唇を落とした。
官能を掻き立てる愛撫など、煉獄は知らない。まだ。だから煉獄の唇や肌をたどる舌は、愛撫というよりも、大丈夫ここにいる、一緒だと、冨岡に知らせるものでしかなかった。それでもそのたび冨岡はほのかな安堵をにじませて、脱力しようと健気に応えてくれる。
すっかり収めきった人差し指を、小さな口はキュウキュウと食んでいる。冨岡に締めつけようという意思はないのだろうが、異物を拒む本能的な動きはいかんともしがたいようだ。まだとうてい快感など得てはいないことは、経験のない煉獄にも残念ながらハッキリとわかる。
「すまない、冨岡。苦しいだろうがもう少し我慢してくれ」
「……大丈夫だと、言っただろう」
そっけなさを装った声で冨岡は答えるが、うっすらと汗をかいた肌は痙攣するように震えて、冨岡が感じている苦痛を隠せてはいない。顔を見せてもくれやしないのは、恥ずかしいからだけではないのだろう。まだ自分さえ耐えればと考えているに違いない。
馬鹿だな、と、煉獄の顔に小さな苦笑が浮かぶ。ほのかな笑みは少しの切なさをたたえていた。
「うん、だが、君に無理を強いるのは俺がつらい。一人で快楽を貪るのでは意味のない行為だ」
だから、迷うことはなかった。
「っ! れ、煉獄、それはやめろと言っただろ!」
とうとう腕がほどかれ、冨岡は煉獄の肩を強く掴むと押しやろうとしてくる。
「ほほはる」
「んっ、く、咥えたまま喋るなっ! ひゃっ! あ、やっ、馬鹿ぁ……っ」
グイグイと押してくる手にかまわず、強く吸い上げ、同時に揺れたふくらみを握ってやれば、冨岡の腰が大きく震え、手の力が抜けた。手のなかで双珠がキュッと固く縮こまった気がする。
どれだけ鍛えようと、急所を握り込まれると力が抜けるのは冨岡も変わらぬらしい。胡桃のようなそこは、怯えてすくんでいる。口のなかの男刀はまだ硬度を保っているが、打ちあわせたときとくらべ勢いがないように感じた。
痛くしてごめんとの詫びもこめて、煉獄は口に含んだ肉棒に舌をすべらせつつ、やんわりと手のなかのふくらみを揉み込んだ。煉獄の肩を掴む冨岡の手は、もう押しのけようとはしてこない。むしろ指に込められた力はすがるようだった。
意図せずこぼれた煉獄の笑みに、冨岡のその手が拳を作り、ポカリと肩をたたいてくる。キュッと頬がすぼまるほどに吸い上げれば、またすがってくる、冨岡の手。愛おしさが胸を打つ。
「君に馬鹿と言われるのは、なんだかいいな。母を思い出した」
一度口を離し、横笛を吹くみたいに唇で触れながら言って、煉獄は視線だけで冨岡の顔をうかがった。真っ赤に染まった顔のなかで、瑠璃の瞳が濡れて光っている。涙の膜をまとった瞳は、日差しを弾いて星のようにキラキラときらめいて見えた。興奮にうるみながらも怪訝げに細められている目に、煉獄はまたほのかに笑う。
「ずっと幼いころの話だ。なんの話をしていたのかは覚えていない。父が母になにかを言って、母は咎めるように、パチンと父の肩をたたいた。俺は喧嘩かと思い慌てたんだが、父も母も笑っていた。馬鹿、と。母がそんな言葉で誰かをなじるなど、初めて見たが……やけにやさしい声で、母は幸せそうに少し頬を染めていた。きれいだったんだ……今まで見た母のなかで、一番。馬鹿と父に言った母の顔は、ドキドキするほど、きれいだった。たたかれ馬鹿と言われた父も、幸せそうだった……」
竿に触れたままの唇で綴られる言葉を、冨岡は、息を詰めたまま聞いていた。懐かしい記憶は、煉獄にとってはやさしいものではあるが、こんな場で語るものでもあるまい。郷愁にかられる心の奥で自重して、煉獄の笑みが苦笑に変わる。
すまないと、煉獄が口にするよりも早く、煉獄の髪がくしゃりと掴まれた。
「……馬鹿」
「……うん、そうだ。悪いな、冨岡。俺は君のことになるとどうにも馬鹿になるようだ」
浮かんだ苦笑に、幸福感が添えられた。また、胸が痛い。幸せな痛みは、煉獄の胸をギュッと掴んで離さない。
横向きに咥え、舌をそっと押し当てながら顔を動かせば、あ、あ、と音階を替えて控えめに声が上がる。どんな名匠の手による笛よりも、冨岡の声のほうがよっぽど妙なる音色に聞こえて、たまらない。二本目の指は、先よりも抵抗なく入った。
「おな、じ……ぅんっ」
「ん? あにか言っはは?」
「だからっ、咥えたまま喋るなと、あっ! は、ぁ……んぅっ」
「冨岡、さすがに痛いんだが……禿げそうだ」
掴みしめられた髪は、何本かちぎれ引き抜かれたようだ。地味に痛い。
「そんなものを咥えたままで話すからだっ、馬鹿っ」
「うん、馬鹿だと言っただろう?」
朗らかに笑って、見せつけるように先端に滲んだ蜜を舐め取ってみせた煉獄を、冨岡は濡れた瞳で睨みつけてくる。けれども手は、髪を握りしめるのではなく、煉獄の頭を包み込むものへと変わっていた。
「馬鹿だ……」
「もっと言ってくれ。冨岡に言われるのはなんだかうれしい」
「違う」
なにが? と、問う口は舐めしゃぶるためにふさがっている。視線だけで問えば、冨岡の右手がまた視線を遮るように顔に乗せられた。
「みっともない、のに……こんな、の……あぅん! はっ、見苦し、のに、うれしい……からっ、俺も、馬鹿、ああっ、あっ!」
あぁ、たしかに馬鹿だ。かわいそうなほどに。深まる笑みを抑えきれずに、煉獄はさらに口中で育っていく花芽を唇で強くしごいた。
そんなことを言えば、俺が止まれなくなることぐらいわかりそうなものなのに、生真面目に答えようとするなんて。なんて馬鹿真面目で、なんて、可愛くて……どうしてこんなにも、愛おしいのだろうか。
こらえようなく差し込んだ三本目の指を、解けた花弁が包んでいる。冨岡のなかは熱く、狭い。けれどもまだ、煉獄の指は冨岡の肉体にとってはただの異物だ。うねる肉筒は排除の動きをしていた。直接的な快感と初めての痛みや違和感のせめぎあいに、冨岡は懸命に耐えている。
早く楽にしてやりたい。もっと味わいたい。相反する欲望に押され、煉獄が口の動きに合わせ、なかを押し広げるように指を蠢かせていると、冨岡の立てられた脚がブルブルと大きく震えだした。
「れ、煉獄っ、変だ。あ、痒いっ。むず痒くて、んんっ、あ、無理っ」
切羽詰まった声音は涙混じりだ。耐え難いのか、脚はいつのまにかかかとが浮き、足趾が布団を掴みしめていた。
「嫌だ、もう、無理っ! あ、擦ってくれ、もっと強くっ」
叫ぶように言って、冨岡が唇を噛みしめるのが見えた。丁子油の作用か。思い至り、煉獄は知らず識らず生唾を飲み込んだ。
強烈な痒みは拷問となり得る。陰間の仕込みに丁子油が使用される所以はこれなのだろう。むず痒さが痛みよりも勝るがゆえに、受け入れることを快楽と捉えやすくなるのに違いない。
愛撫による快楽にも、羞恥や痛みにも、崩れ去ることのなかった冨岡の理性が、ピシリと音立ててひび割れていくようだ。それでも煉獄が言った、痛いという言葉は覚えているのだろう。煉獄にすがることはなく、冨岡の両腕が溺れる者の必死さに似て空を掻いた。その腕は、激しさを増した煉獄の指では足りぬのか、自身の髪を掴みしめ、かき乱している。意思ではままならない感覚を逃したいとでも言うように、冨岡は首を打ち振った。
掻痒感と性感の区別など、もはや冨岡にもついていないのは間違いない。煉獄の口のなかに広がる潮はどんどんとあふれてくる。育ちきった淫棒は太刀のように反り返っていた。このままふたたび絶頂へと追いやってしまいたい気はあるが、煉獄自身も限界が近い。冨岡に負けず劣らず天を衝く熱は、痛いほどに張り詰めている。
煉獄がそろりと口を離すと、外気に触れた剣先がピクピクと震えた。小さな口がハクハクと、酸欠でもあるかのように空気を食んでいる。なんだかいじらしく見えて、チュッと軽い音を立てて口づけたら、冨岡の背が仰け反った。脚はいよいよつま先立ち、腰が浮いている。
ぬくぬくと締めつけてくる心地よい秘所から指を引き抜き、煉獄は、冨岡の震える脚を肩へと担ぎ上げた。
こんなにも痒みを訴える冨岡に、挿入の助けとはいえ油をさらに塗り込めるのは、気が咎める。固く閉じていた初心な蕾は、指を含まされていたせいかしどけなく解け、早くとねだる如くにひくついていた。テラリとぬめって見えるのは、油によるものだけではあるまい。煉獄の口から漏れこぼれた唾液や冨岡の蜜液が、そこを淫猥に濡らしているのは明らかだ。
煉獄は荒ぶる息はそのままに、猛る自身を握りしめ軽くしごいた。冨岡にのしかかり、熟れきる前の白桃のような尻の間に、己の欲をすべりこませる。伺いを立てるように突いてみれば、煉獄自身の欲液のぬめりも手伝い、存外たやすく陰花は開いた。
だが、やはりそこは狭い。指とはくらべものにならぬ体積を含まされ、内壁が退散を促すようにうねった。肉の蠢きは、拒みながらも絡みつくようで、煉獄は思わず息を詰めた。
指だけでもキツイと感じてはいたが、こんなにも締めつけられるとは。ゾクゾクと背を快感の電流が走る。
「あ、はぁ……あっ、あっ、入って、くるっ。気持ち、い」
恍惚とした声と蕩けた瞳や、口をついた文言は、慣れた淫売のようだというのに、この身はまだ誰の足跡もついていないまっさらな白雪と同じなのだ。悦楽にゆらゆらと揺れる瑠璃の瞳から、ひとしずく、涙が伝い落ちた。あぁ、星が流れる。手の届かぬ天空で輝く星が、この手に落ちてきてくれた。そんな言葉が、また脳裏に浮かんだ。
清楚な印象の冨岡と、脚を割り開かれ男の欲望を身のうち深くに飲み込んだ目の前の冨岡との不整合は、違和感よりもなお、途方もない興奮を煉獄にもたらした。
誰も……親友も、育手も、家族だって見たことのない、冨岡の姿を目にしている。自分だけに許された。体が感じ取る悦楽を、心を満たす喜悦が追い越していく。やっとだ。やっと、繋がりあえた。快感よりも大きな感動に、知らず目の奥が熱くなる。泣き出しそうに瞳を揺らせ、煉獄は胸に湧き上がる幸せのままに笑った。
「やっと……君と繋がれた」
腰を振りたててしまいたい衝動は、早く解放へと向かえと急かすが、煉獄はどうにか抑制した。今はむず痒さのほうが勝り、苦痛を忘れているようではあるが、冨岡も初めてなのだ。油もだいぶ薄まっている。いきなり激しく攻めたてれば、痛みに萎縮してしまうかもしれない。
深く息を吐き、煉獄は、まとわり締めつけてくる肉襞の感触に耐えた。
グシャグシャにかき乱された髪が、汗で湿る冨岡の頬や額に張り付いている。過ぎる快感を耐え震える指で、煉獄は精一杯やさしく冨岡の頬に触れた。
「大丈夫か?」
「ん……煉獄」
「なんだ?」
「俺は、平気だから……動いてくれ」
冨岡の手も震えながら持ち上がり、煉獄の頬に触れてくる。見上げてくる瞳には、理性の光がわずかながら戻りつつあった。
「だが、もっとなじまないとつらいだろう?」
「大丈夫だ。まだ痒みが残っているうちに、動いてくれたほうがいい。あの、でも、その前に」
おずおずと指先が唇に触れてくる。甘える指がうれしくて、煉獄はその手を取り、指先に口づけた。不満げに小さく尖らせた唇に微笑み、望みどおりに唇を落とす。
チュッ、チュッと、可愛らしい音を立てて繰り返す子供じみた接吻に、冨岡の腕がためらいを残しながら煉獄の首に回されてきた。予想以上の必死さで、腕はしがみついてくる。
引き寄せられ、深く唇を噛み合わせる。舌先で前歯の裏側をたどり、上顎をくすぐる。冨岡の歯はつるりとして、心地いい。控えめにおとなしくしていた冨岡の舌が、遊ぶなと言いたげに煉獄の舌に絡んできた。冨岡の舌は、どこか甘い。
挑み合うように互いに先を競って舌を絡めても、慣れぬことであるのに違いはなく、息苦しさに口が離れた。
ハァッ、と、互いに空気を吸い込んで、また唇を合わせる。なんだか呼吸を覚えたてのころのようだと、少しだけおかしくなった。
ツン、と髪を引く指先に、促されていることを知る。逆らわず、煉獄はゆるゆると腰を揺らめかせた。まだ大胆に動く気にはなれなかった。様子見のような動きにも、冨岡は、んっ、んっ、と、くぐもった声をもらし、必死に舌を絡めてくる。腰を支える手を滑らせて、張りのある丸みを揉んでみると、冨岡の手がポカリと頭をたたいてきた。
「ひどいな」
「変なこと、するな。あっ、ぅんっ」
「変なことではないだろう? 君の尻は、まるでむき玉子みたいで触り心地がいい」
腰を揺すりあげながら笑って言えば、冨岡の目が潤みながらかすかにすがめられた。
「馬鹿っ、はぅんっ! あ、あ、なんで……また、おっきくな、あぁっ!」
「冨岡の口から馬鹿と言われるのはうれしいだけだなっ」
言いながら、先よりも大きく腰を動かしてみる。とたんに掠れた悲鳴が冨岡の口からあがった。
「あ、駄目、だ。ごめん、煉獄」
「痛いか?」
「痛くは、ない。だが、あの、大きく動かれると、腸が引きずり出されるような感覚がして……その」
怯える瞳に、煉獄は小さくうなずいてみせた。小刻みに、つんつんとつつくように腰を揺らしてみせれば、冨岡は、ホゥッと安堵に似た吐息をもらした。
「これなら、大丈夫か? 苦しくは?」
「ん、へい、き……あっん、煉獄、は? 気持ち、いいか?」
健気に問うてくるから、煉獄はたまらなくなる。
「当然だ。こんな喜悦があったとは、知らなかった。君のなかは、とてつもなく気持ちがいい」
「よかった……はぅっ! あ、あっ、まわす、なぁ!」
いたずら心でグルリと腰を回してみせれば、冨岡の首が仰け反った。無意識にだろう、煉獄の動きを追って動く冨岡の腰に、痛くさせてしまったかとの焦りは笑みに変わった。
「こうされるのが、君は好きなんだな。だんだんわかってきたぞ」
「やぁっ、ちが、ああっ! ぐるぐる、しない、でっ!」
大人だからこその行為をしているのに、冨岡が口走った文言は子供じみている。
淫蕩な腰つきとは真逆のいとけなさは、ひどく艶かしく感じられた。素のままの、なにもまつろわぬ冨岡は、幼い子供の素直さを残してあどけない。刀を握り、鬼を狩るため東奔西走する柱としての冨岡の根源に、今、煉獄は触れている。
もっと。もっとだ。もっと奥まで触れたい。冨岡の奥深くで包まれたい。
熱望に突き動かされて、煉獄は腰を深く突き入れた。
「あ……っ」
ほとばしりかけたか細い悲鳴を、冨岡が喉の奥で寸前にとどめたのがわかった。耳が拾ったのはガラリと戸が開く音。店主の声。客が入ってきたようだ。とっさに視線が向かったのは、薄汚れた窓だった。
日はまだ高い。だが太陽は先よりもだいぶ上空にある。階下の気配は多くはないが、昼時であることを考えれば、こんな店であっても人はそれなりに入ってくるかもしれない。
確認の視線は、冨岡も同様だった。日が差す今は鬼は出ない。けれども鬼が人を手先として使う事例がないわけではないのだ。万が一刺客が差し向けられたのなら、一番危険なのはきっと情事の最中であろう。警戒は怠れない。
こんなときでも我を忘れることができぬ互いを恨むより、むしろ誇らしい心持ちがして、声を控えるために呼吸を整えだした冨岡に倣うように、煉獄は、深く息を吐き出した。
見つめ合い、ゆっくりとまた動き出す。快感を拾い上げはしても、達するには至らないのだろう。煉獄の首にしがみつき、んっ、んっ、と短く意味のない音をもらすだけの冨岡をじっと見下ろしながら、冨岡の腹の上で揺れる淫茎を握った。そこはもうしとどに濡れていた。
「冨岡、いいか?」
喉を震わせてコクリとうなずいた冨岡の唇を、己の口で塞ぐと、煉獄は手にした熱をしごき立てながら腰を突き動かした。
目は、閉じない。冨岡の視線も、煉獄の瞳に据えられたままだ。目合うという意味を、知った気がした。抑えきれない恋情を、互いの瞳が伝えあう。好きだ。好きだ。声にならぬまま、眼差しが伝えあう。冨岡の眦から、ポロリ、ポロリと、星が流れた。
いつまでもこうしていたい。望めども、そんなことは不可能だ。終りが近い。警戒を忘れぬ理性を芯に残し、思考が白く掠れていく。フッ、フッと、短く荒ぐ息をもらしながら、二人は舌を絡めあい、腰を振りたてた。足並みをそろえるようにして、高みを目指す。
「んんっ!」
ギュッと冨岡の眉間が寄せられ、ビクビクと腹が波打った。とたんにブシュリと音立てて噴き上がった白い濁流が、冨岡の顔に降りかかる。硬直し痙攣した冨岡の締めつけは、痛いほどだ。
「ぐぅっ!」
思わず煉獄の口からも呻きがもれた。それでも、自制心を総動員し、煉獄は絡みついてくる肉襞から己を引き抜いた。いっそ凶暴なほどの欲に追い立てられ、自身を握り乱暴にしごく。時をおかずして、灼熱の迸りが冨岡の顔めがけて噴出された。
「……は、ぁ」
腰が震える。感極まった溜息がおののく煉獄の唇からこぼれ落ちた。冨岡はどこかぼんやりと、うつろに見える瞳で虚空を見つめていた。
まとったままの白いシャツはしわだらけで、髪も乱れきっている。力を失いくたりとうなだれた肉茎の先から、とろりと白い粘液が滴り落ちているのを目にし、煉獄の背がゾクリと震えた。冨岡の顔を汚す白濁を見てしまえば、欲は隠しようなく身を焼く。だが、衝動のままにふたたび挑みかかるわけにはいかない。
二度も達したというのに、まだ足りぬとばかりにいきり立つ自身を、煉獄は強靭な意志でもって鎮めた。
冨岡の脚をそっとおろすと、隊服を手繰り寄せ懐紙を取り出す。頬を濡らす欲液を拭き取ってやれば、冨岡の目が緩慢にまばたいた。
「冨岡、体はつらくはないか?」
我ながらやけに甘い声だ。少しだけ不安げにも聞こえる。なにしろ初めての交合だというのに、潤滑剤すら満足に用意せず及んだのだ。傷つけはしなかったようだが、媚薬めいた効果が過ぎ去れば、痛みはきっとあるだろう。心配は顔にも出ていたらしい。
「大丈夫だ。俺だって鍛えているんだ、そんなにやわにはできていない。それに」
冨岡の声には、少々呆れたような気配がにじんでいた。
「それに?」
丁寧に肌を拭ってやりながら、言葉の先を促した煉獄に、冨岡はちょっとばかり恥ずかしげに顔をそらした。
「……やさしかったから、平気だ」
声は、蚊の鳴くような小ささで、冨岡の羞恥を示していた。たまらなくなって抱きしめれば、ポカリとまた頭をたたかれた。今日はなんど冨岡にたたかれればいいんだろう。まるで痛くはないし、なんだか愛らしくすらあるからかまわないけれども。
「汚れるだろうっ」
「なに、今さらだ! 隊服を着てしまえば見えないしな」
「でも、臭い、とか」
落ち着かぬ様子で恥じらい言う冨岡に、煉獄は肩をすくめてみせた。煉獄にしてみれば、冨岡と交わった証のようでいっそ誇らしいぐらいだが、冨岡はいたたまれないだろう。それに、もしも千寿郎に問われても、煉獄とて説明はできない。
できればもっと甘い空気のなかで戯れあっていたいが、しかたがない。起き上がり、ふたたび冨岡の肌を濡らす情交の印を懐紙で拭う。自分でやると拒むかと思われたが、冨岡は、意外なことに素直に身を任せ、されるがままになっていた。
まだ紅潮したままの肌に無尽に走る傷跡にも、煉獄はそっと触れた。明るい日差しの下で見る傷跡に、生き延びてくれたことへの感謝が胸に満ちていく。
いつか、鬼の出ないやさしい宵闇のなかで、慈しみと愛を込めてゆっくりと、この傷跡一つひとつを癒やすのだ。自分に残る傷にも、触れてほしい。戦ってきたその証を、生き延びともにいる感謝を、尽きぬ恋情にこめて互いに触れて触れ合う夜。それはどんなにか甘いことだろう。
そうして互いを抱きしめ、窓の外を流れる星に、二人笑って願いを託すのだ。夜更けになっても離れることなく共寝して、穏やかで眩しい朝をともに迎える、そんな日を、いつか。今はまだ、夢物語でしかないけれど。
「さぁ、これで大丈夫だろう! だいぶ騒がしくしてしまったな。店主には悪いことをしてしまった」
さすがに秘所の汚れは自分で拭くと譲らぬ冨岡と、なぜ、嫌に決まっていると言い合い、少々揉めたり。しぶしぶ引き下がり自身を拭いていた煉獄に、冨岡が、お返しに拭いてやろうか? などとからかいでもない口調で言ってきたのに真っ赤になったり。抱き合うことはできないまでも、それなりに逢い引きらしい戯れを堪能できたことに、煉獄は満足していた。
だがしかし、では帰ろうかというわけにもいかない。
身繕いを終え笑いかけた煉獄に、冨岡の眉がなんとも言えぬ具合に下がった。その視線を追った煉獄もまた、いくぶん情けない顔で、うぅむと小さくうなってしまう。
卓の上には、汁がこぼれすっかり冷めて伸びた二人分の蕎麦が置かれたままだ。
「……どうする?」
「食べ物を粗末にするわけにはいかんな……」
おまえがそれを言うかと言いたげな眼差しを感じたが、冨岡も蒸し返す気はないのだろう。フゥッと疲れた溜息をこぼし、めずらしくノロノロとした動きで卓の前に座した。
「食えないわけじゃないだろう」
「まぁ、そうだな。……食うか!」
向かい合い、いただきますと互いに手を合わせ箸を取る。
ズルっと一口啜り込んだ蕎麦は、まったくコシを感じられずグニャリとしている。天かすの油は固まりだしていた。
「うむっ、不味い!」
「…………声が大きい」
「おぉ、すまん! だがこれは、じつに不味いなっ」
モソモソと蕎麦をすする冨岡の顔は、すっかり無だ。だが、なんとはなし頬がまだ赤い。それになにやらモジモジとしている。
「どうした? まぁ、これでは食う気が失せてもしかたないからな。残してもいいぞ。食えないのなら俺が食おう。飯には足りんかもしれないが、ここを出たら甘味でも食いに行くことにしよう」
「いや……たしかに不味いが、そうじゃなく……その、なんだかまだ、おまえのが挟まってる感じがして、落ち着かない」
「ん゛ん゛っ!」
思わずむせそうになったが、冨岡の猛攻は止まらない。
「慣れれば、きっと大丈夫だと思う。あんなに大きいものが入るとは、思ってもみなかったが……一度入ったんだから、次はきっと、もっと煉獄が気持ちよくなれるようにできると思う。それまで張り型で練習して」
「それはやめてくれ」
やっぱり、宇髄は一発殴っておこう。
真顔で言った煉獄にキョトンとしつつも、わかったとうなずいてくれた冨岡にホッと胸をなでおろし、煉獄は伸び切った蕎麦をかきこんだ。
青臭さとカビ臭さが入り混じった室内に、日は燦々と差し込み、埃がキラキラと舞っている。卓に乗ったままのアヤメは少ししおれていた。二十歳になった祝いの膳とはとうてい言えぬ、冷えて固まった油の浮いたたぬき蕎麦は、伸びきってコシもなく、つゆは喉が渇くほど塩辛い。初めての目合いは、とんだ大騒ぎだ。たぶん、人に話せば笑い話としか思われないだろう。
けれど。
「冨岡、俺からも言わせてくれ。俺と出逢ってくれて、ありがとう」
帰ったら、仏壇に手を合わせ、母に生んでくれてありがとうございますと告げよう。冨岡と出逢うことができた感謝を込めて。
ほのかに頬を染めてうなずいてくれた冨岡と一緒に、どうにか食べきった蕎麦は、不味いけれどもどこか幸せな味がした。