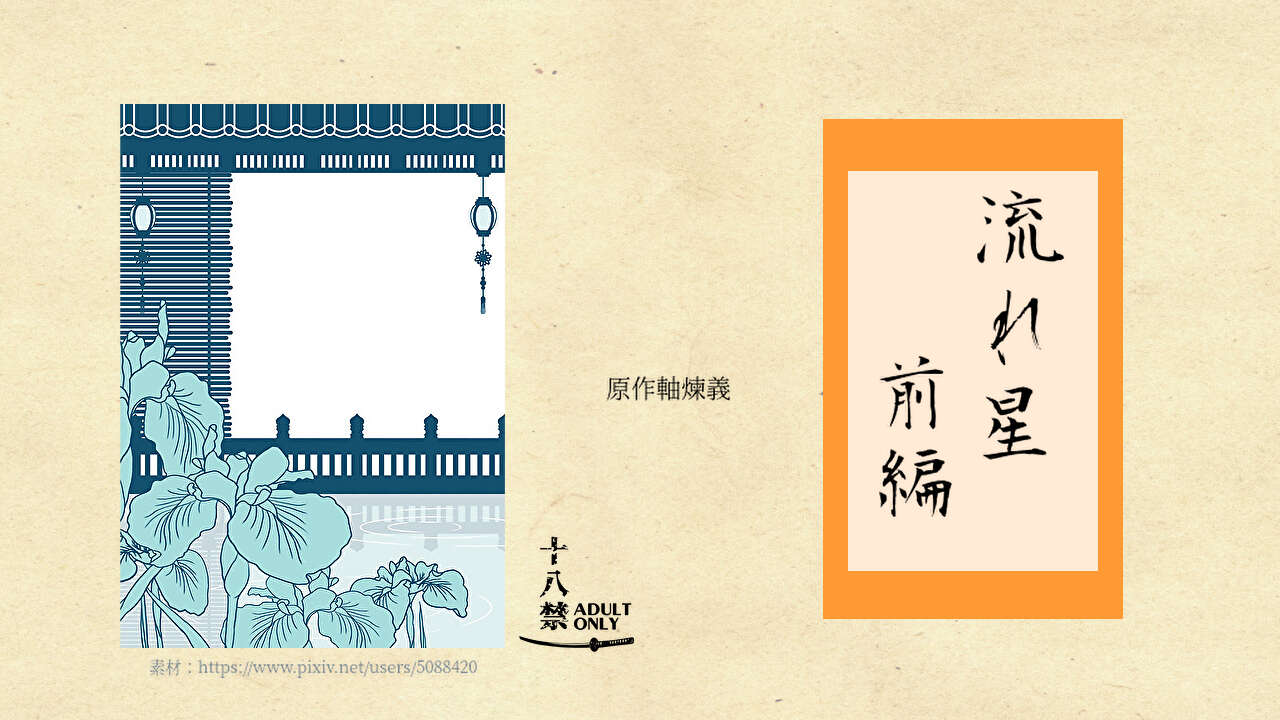大股に店内を横切り、ごゆっくりとの店主の声を背に階段を上る。戸惑う気配をにじませながらも拒みもせずついてくる冨岡に、少しだけ苛立ちが胸に湧いた。
諦める気などない。冨岡には、やさしくゆっくりと自分の想いを染み込ませるように伝えていきたいとも、思っている。ともにいるのが当たり前になったら、そのときこそ言うのだ。君が好きだと。そう心に誓ってもいた。
興味などなかった将棋を覚え、棋譜を買い求めもした。冨岡が好きそうな店を探す癖もついた。姿を見つければ駆け寄り声をかけ、誘いにうなずいてもらえればその日は一日中うれしくて。
冨岡と親しくなるために使った時間も金も、それなりだ。だがそんなものなんだというのか。迷惑でなどあるものか。無駄だと? 君がそれを言うのか。無駄な努力だと。いや、違う。冨岡の言葉はきっとそんな意味じゃない。わかっている。
無言のまま煉獄は、胸の奥に浮かぶ冨岡の一言を、懸命に打ち消した。けれど、苛立ちは消えなかった。
無駄なんて言葉で、済ませてほしくないのだ。冨岡と過ごす時間は、煉獄にとって、幸せなひとときだ。殺伐とした、血にまみれた任務の日々。怠惰になり酒に溺れ、ろくに声もかけてくれなくなった父。懸命な努力が実らぬ千寿郎の悲嘆。苦しく切ない想いが、胸をしめつけることだってある。けれどそれでも、冨岡といるときだけは、幼い子供のころのように温かな思いだけで幸せだと笑えるのだ。恋とはこんなにも素晴らしいのかと、胸が熱くなる。
廊下を見回し、襖の開けられた部屋へと迷わず進む。締め切られた部屋から、あえかなすすり泣きに似た声がした。声を荒らげぬようにしよう。考えるともなしに煉獄は思う。
冨岡を怯えさせたくないからなのか、逢い引き中の恋人たちの邪魔にならぬようなのか。自分でもどちらとも判断がつかない。
部屋はさほど広くはなかった。料亭のように装飾が施された欄間など望むべくもない、質素な部屋だ。窓枠にはうっすらと埃が積もっていた。ガラスも磨かれていないのだろう、曇っている。けれども、差し込む日差しは十二分に眩しかった。
「座ってくれ。話をしよう」
努めて静かに声をかけ腕を離せば、冨岡は、寄る辺ない子供のようにどこか悄然として、部屋に据えられた卓の前に座した。
卓を挟んで向かいに腰を下ろし、煉獄はつくづくと冨岡を見つめた。
冨岡はわずかにうつむいている。目も伏せられ、煉獄を見つめ返すことはない。叱られるのを覚悟した子供のような風情だ。
フゥッと息を吐けば、ピクリと冨岡の肩が揺れた。
「怒っているわけではない。冨岡、頼む。顔を上げてくれ」
おずおずという言葉がふさわしい様で、冨岡の顔が上げられる。
「一つだけ、確認してもいいだろうか」
かすかに首をかしげ、それでも小さくうなずいた冨岡を、煉獄はじっと見る。なにひとつ見逃したくはなかった。
「君は、無駄なことはやめろと言ったわけではない……そう思っていいか?」
パッと冨岡の表情が変わった。目が大きく見開かれ、奇想天外な出来事に出くわしでもしたような顔をしている。
「なんで?」
「それは、どういう意味の『なんで』だろう。なぜ無駄なことを続けようとすると」
「違う!」
煉獄の言葉をさえぎり言った冨岡に、煉獄はパチリとまばたきし、ついで満面の笑みを浮かべた。
「君が大きな声を出すのを初めて聞けたな」
「……すまない」
冨岡はまたうつむいてしまった。こんな冨岡は初めて見る。感情がわかりやすく表面に出る冨岡など、きっと鬼殺隊で知る者は、自分ひとりだ。
「謝る必要などないなっ! 俺は喜んでいるのだから」
「……なんで?」
「ふむ、その『なんで』はわかりやすい! もっと君のことが知りたいと言っただろう? 君とはあれからいろいろと話しもしたが、まだ足りない。全然足りないんだ。俺はもっともっと君を知りたい。だから、教えてくれ冨岡。君がなぜ、無駄などと言ったのかも」
パチリとまばたいたのは、今度は冨岡のほうだった。その顔はどこかあどけなく見えた。
わずかに目元が赤らんでいる。視線がさまよう。ふとその眼差しが卓に落ちた。意を決したように口を開いた冨岡は、少し首をすくめていた。緊張が伝わってくるようだ。
「あれは……尋常小学校のころだ。級友に、俺と遊ぶのはつまらないと言われた」
今回は尋常小学校ときたか。ずいぶんと遠回りになりそうだ。思い、煉獄の唇に浮かんだのは、面白がるものでもあり、慈しみでもある微笑みだった。
「小学校にあがる前に、両親が死んで……違う。すまない。これは、前に話したんだった」
「覚えているとも。君の言葉を俺が忘れるわけがない。だが、かまわない。全部聞く。話してくれ。冨岡、君の話なら、俺は全部聞くし、聞きたい」
どれだけ遠回りだろうと、冨岡の声を、言葉を、聞くことは、煉獄にとって幸せ以外のなにものでもない。小さいけれども耳馴染みの良い声で語られる当時の冨岡を想像すると、微笑ましくて、恋しさが募る。布団で母や父が話してくれるおとぎ話を聞いた子供のころのように、もっと聞かせてほしいとねだりたくもなる。心地がよくて、ワクワクとするのだ。煉獄と出逢う前の冨岡の人生を、ともに歩んででもいるような気にもなれた。
わずかな逡巡をたたえた目でちろりと上目遣いに煉獄を見やり、冨岡は、また言葉を紡ぎ出した。
「その、両親が亡くなってから、俺は姉に育てられた。父が生きていたのなら、もしかしたら違ったのかもしれないが、人に乱暴してはいけないとか、生き物をいじめてはいけないと、姉に教えられてきたんだ」
「うむ、当然のことだな! 君の父上がご存命でも、きっと同じようにおっしゃられていただろう!」
「だが……つまらないと言われた。夕方に、コウモリが飛びまわるだろう?」
「うん? そうだな。よく見かけるな」
「級友たちは、棒で叩き落として遊ぶんだ。かわいそうだった。戦争ごっこも嫌いだった。おもちゃでも、人に鉄砲を向けるのが嫌で、サーベル代わりの木の枝で、友達に斬りかかるのも嫌いだ」
「……うん。冨岡らしいな。意味のない暴力や殺生は、俺も好かん。それにコウモリは稲を駄目にする虫を食べてくれる! 殺してしまうなど滅相もないことだ!」
煉獄自身は、物心ついたころから竹刀を握っている。炎柱の名を背負うことを託され続けてきた家系に生まれたのだ。なんの疑問も差し挟む余地はなかった。父が鍛錬する姿や、鬼狩りに向かう頼もしい背を誇らしく見上げ、自分も父上のように強くなるのだと誓いこそすれ、刀をとるのを躊躇したことなどない。
けれど、冨岡は違うのだ。心やさしく、おとなしい子供だったのだろう。姉の言いつけをよく守る、真面目な子でもあっただろう。棒切れを振り回すのすら嫌うぐらいだ。刀など、本来であれば一生握ることはなかっただろうに。
だが、天の定めとやらがあるとしたら、それは冨岡に鬼殺の道を命じたのだ。人に嫌われがちな生き物でさえ殺すのを嫌がる冨岡に、鬼を滅せよと命じられた。そして冨岡は、自分の意志で、刀を手にとったのだ。
なんとも痛ましいことだと煉獄は思う。けれども同時に、無駄な殺生を嫌う冨岡の性質を、なお好ましく思いもしたし、自分と同様だとうれしくもなった。苦しくつらい思いをしても、それでも鍛錬を怠らずに、冨岡は柱にまで上り詰めた。それだけにとどまらず、新たな型を生み出してさえいる。そんな冨岡の努力を、深く尊敬もした。
「嫌じゃ、ないのか?」
「なにがだ?」
そろっとあげられた冨岡の顔が、ようやくまっこうから煉獄に向けられた。うつむかれているよりも、ずっといい。深まる笑みはそのままに、煉獄が少しだけキョトンとして首をかしげると、冨岡も心もち首をかたむけた。まるで鏡写しのように。
「コウモリ。嫌いな人のほうが多いと思っていた」
「あぁ、なるほど! いや、嫌いだとか嫌だとか思ったことはないな。言っただろう? コウモリは農家の方にとってはありがたい生き物だ。人を襲うわけでもない。可愛がろうと思ったことはないが、嫌がる筋合いはないな!」
「そうか……」
冨岡がどことなしホッとしたように見えるのは気のせいだろうか。それきり黙ってしまったものだから、煉獄は思わず苦笑した。
「つまり、君はやさしいがゆえに級友たちから嫌われたと、そこまではわかった。だが、それがどうして俺との時間が無駄だなどという話に繋がるんだ?」
「ち、違うっ。煉獄と過ごせるのは、うれしい。だが、迷惑だろう?」
慌てているのか子供のように首を振ってみせる冨岡も、初めて見る。今日はいったいどういう日なんだろう。初めての大盤振る舞いだ。
喜ばしくもあるが、それでも迷惑という言葉はいただけない。思わず眉根を寄せた煉獄に、また冨岡の顔がうつむきかけた。
「それだ、冨岡。俺にはなぜ君が、迷惑だなどと言い出したのかがさっぱりわからん。無駄と言われるのも勘弁願いたい! ……話してくれ。全部聞くと言っただろう?」
少し曇った窓から差し込む日差しが、常になく頼りなげに見える冨岡を照らしている。窓の外に広がる春の空は穏やかに青い。
恋を自覚したあの日は、冬だった。積み重なる動物たちの亡骸を見つめた冨岡は、悲しげで、どことなし寒そうにも見えた。頑健に鍛え上げられた肉体ではなく、心が凍えていたのだろうと、今は思う。
だから煉獄は、静かに冨岡をうながした。
自分の声もまた、穏やかなあの空のように冨岡を温め癒せるものであればいい。炎柱の名に恥じぬ熱き想いでもって、冨岡を温められたらいい。凍え震える愛しい人を、温められる火となれたなら、どんなに喜ばしいことだろう。
そうしていつか、この肌身でも。
さすがにそれは気が早すぎるなと、煉獄は胸中で苦笑した。まだ想いを告げることさえかなわずにいるのだ。同衾できる日などいつになるやら。焦る気はないが、少々溜息をつきたいような気にもなる。
だから、まさか。
「つまらないと……煉獄に思われるのは、苦しい」
そんな言葉が冨岡の口から出るなど、煉獄は思ってもみなかった。
「冨岡……それは」
呆然としたせいか、いつになくかすれた声になった。それをどうとらえたものか、冨岡は、ギュッと自分の隊服の胸元を握りしめ、叱られた子供のように目を閉じてしまっている。
いけない。これではまた冨岡は黙り込んでしまう。煉獄は焦ったのだが、あにはからんや。冨岡はまたもやめずらしいことに、ふたたび問いかけようとした煉獄の言葉をさえぎり、少し早口で言った。
「俺と一緒にいれば、煉獄の鍛錬や休息の時間が減ってしまうと、わかっている。煉獄はやさしくて責任感が強いから、村長の息子みたいに俺をかまってくれたんだということも」
「いや、ちょっと待て冨岡っ」
せっかく会話を続けてくれたのだから、煉獄とてさえぎりたくはない。ないが……。
「誰なんだ? 村長の息子?」
いきなり出てきた男に、先よりもさらに慌てたのもしかたないと、煉獄としては思いたいところだ。鬼殺隊に入ってなお、つきあいが続いているとは思えないが、とにかく口が重く自分のことをまったく話してくれずにいた冨岡のことだ。煉獄が知らぬだけで故郷の知り合いや友人と、今も親密な交流がある可能性は否めない。
それ自体はいいことなのだろう。だが、恋敵が増えたのだろうかと思うと、気が気でなかった。
「コウモリを殺すのはやめてほしいと訴えたら、意気地なし、つまらない奴だと言われたんだ」
「それが村長の息子か?」
聞けば冨岡は子供のようにふるりと首を振る。
「みんな遊んでくれなくなったが、村長のところの息子だけは、遊んでくれた」
「そっ、それでっ? それで冨岡はそいつのことが好きだったのか? 今も好きなのか!?」
またふるりと首を振り、嫌いではないが好きだとは思ってないかもしれないと、冨岡にしてはやけに煮え切らない言葉で言う。
「そのころは唯一の友だちだと思い、好きだった。だが、級友たちと話しているのを聞いてしまって……。俺の父は医師で、村医者ではなかったんだが休暇の折にはよく、相談に来る村の者たちを診てやっていた。だから、村長に冨岡の坊っちゃんの面倒を見てやれと言われて迷惑していると」
「……そういうことか」
煉獄の肩から思わず力が抜けた。
遠回りな冨岡の物言いは微笑ましいが、こういうときには、ずいぶんとやきもきさせられるものだ。
「俺のことが好きで遊んでくれていたわけではなかった。悪い子じゃない。責任感もあるし、やさしい奴だったと思う。そういう子を嫌うのはよくないだろうが、あんまり悲しかったから、好きだとは言えない。煉獄も、柱としての責任感から俺に話しかけてくれて、こんなふうに誘ってもくれるんだと理解している。だから、迷惑だとかつまらないと思われないよう、少しでもおまえみたいになれたら、一緒にいることが許されるかと思った」
目を閉じたまま冨岡は、いかにも一所懸命に言葉を紡いでいた。日ごろからは考えられない言葉数の多さは、冨岡の焦燥ゆえだろうか。だとしたら、その所以はどこにあるのだろう。
ともあれ、聞き捨てならない文言については否定しなければと、煉獄は迷わず手を伸ばした。
「冨岡」
初めて、冨岡の白い頬に触れた。ピクリと首をすくめるから、なんだか少し悲しい。できることなら、初めて冨岡の顔に触れるときは、お互いに甘やかな気持ちでありたかった。そうあるようがんばってもきた。
だが、触れた手を引く気にはなれなかった。せめて終わりよければすべてよしと言えるようにせねばと、煉獄は努めて穏やかにもう一度、名を呼んだ。
「冨岡。俺は迷惑だなどと思ったことはない。そんなふうに君に思われていたことすら心外だ。君は覚えていないかもしれないが、俺は以前、君に『その才能が羨ましい』と言ったことがあった。あのとき、俺は言葉を間違えた。言い直させてくれ」
「……初めて、煉獄と行った任務の」
ようやく開かれた目が、煉獄を映す。澄んだ瑠璃色の瞳に映った恋する男の顔は、笑んでいた。
あぁ。俺はいつも、こんな顔をして君を見つめていたのか。
少し気恥ずかしく、どこか誇らしそうな笑顔。そして、たとえようもない愛おしさをたたえた男が、冨岡の瞳のなかにいる。
凪いだ海のようでもあり、晴れた空のようでもある、冨岡の瞳。ときに凛と咲く竜胆の花のようだと思いもしたその瞳も、煉獄をまっすぐに見つめてくれていた。
「覚えてくれていたのか。それはうれしい。あのときは、すまなかった。俺はこう言うべきだったのだ」
一度深く息を吸い込み、煉獄は、冨岡の目をまっすぐに見つめ、言った。
「冨岡、俺は、君の努力を尊敬する。炎柱、煉獄杏寿郎として。そして……俺、煉獄杏寿郎は、冨岡義勇を、心の底から好いている」
告白は、もっと先になるだろうと思っていた。こんな逢い引き中の客の喘ぎがかすかに聞こえてくるような、薄汚れた蕎麦屋の二階などではなく、巷で聞く浪漫のある場所でだ。そう、たとえば、秋の穏やかな日が降り注ぎ、爽やかな風の吹く、竜胆の咲く草原で。君が好きだと、手折った竜胆を一輪手渡して言うのだ。そんな日を、夢見ていた。
だが現実はこれだ。理想ほどうまくはいかないものだと、煉獄の眉がはからずも下がる。
理想からはほど遠い。それでも、言わずにはいられなかった。冨岡がたまらなく恋しくて、心は抑えられぬほどに燃えていた。
冨岡は、なにも言わない。うっすらと開かれた唇の端に、まだ天かすがついていた。本当に、子供みたいだ。親指をすべらせ口に触れれば、また冨岡の肩が小さく揺れた。
幼子のようだとか、子猫のようだとか。思えば微笑ましくなるけれど、煉獄の胸にある恋の炎は、愛らしくいとけないものを慈しむ想いだけではない。
柱としての雄々しく凛々しい冨岡も、共闘した浅草での婀娜めいた姿の冨岡も、全部、冨岡義勇という男の一面である。幼子のように不器用な冨岡を愛おしく思うのは、尊敬すべき一人の男としての冨岡が見せる、素の一面だからこそだ。
「好き……?」
「あぁ。だから迷惑だなどと思ったことはない。無駄な時間だなんて思うわけがない。君と過ごす時間は、俺にとっては至福の時だ」
どうか、受け入れてくれ。願う心が煉獄の眼差しを強くする。もっと近づきたいのに、卓が邪魔だ。いや、卓があってよかったのかもしれない。膝を突き合わせていれば、冨岡の意思を顧みず、抱きしめてしまっていただろうから。
じわりと冨岡の目元が花の色に染まっていく。友人としての好意ではないと過たず理解してくれたのならなによりだが、さて、冨岡のことだから油断はできないなと、煉獄は目を苦笑にたわませた。
「君は、俺につまらない奴だと思われるのは苦しいと言ってくれたが、それはなぜだか聞いてもいいか?」
声は、煉獄自身にもやけにやさしく聞こえた。冨岡にもそう聞こえればよいのだけれど。思っていれば、冨岡は、また隊服の胸元をギュッと握りしめた。
「村長の息子が、俺と遊んでくれていたのは親に言われたからだと知ったときは、悲しかった」
「うん?」
「不死川に怒られたり、伊黒に悪口を言われたときもだ。とても悲しくなる」
「……そうか」
これはまた遠回りになるだろうか。少しばかり焦らなくはないが、急かす気もない。手のないときは端歩をつけだ。相手に委ねることも大事だろう。うながすように相槌を打ち、煉獄は、冨岡を見つめつづけた。踏み込む好機をなにひとつ見落とさぬように。
「錆兎に嫌われたかもしれないと思ったときも……悲しかったし、苦しかった」
「君の親友だな。友に嫌われるのがつらいのは当然だ」
おそらくは最も手強い恋敵になり得た人物の名に、ムクリと頭をもたげかけた悋気を、煉獄はしいて抑えつける。以前、冨岡は、煉獄と錆兎はいい友達になれたと思うと言っていた。信頼されているということだろう。腹を立てれば狭量がすぎる。
「だが……」
ふと言いよどみ、冨岡は、グッと眉根を寄せた。胸元を握りしめる手にも、いっそうの力が込められて見える。
「煉獄に嫌われたり、迷惑だと思われるのは……ここが、痛い。痛くて、苦しくて、息ができなくなる」
今、煉獄を襲った暴力的なまでの歓喜を、なんと言い表せばよいのだろう。きっと百万語言葉を連ねても、身震いするほどに内からこみ上げる喜びには、とうてい足りないに違いない。
「冨岡……それは」
「わからない。なんで……煉獄にだけ、こんなにも嫌われたくないと思うのか、自分でもわからないんだ。自分の心すら理解できないなど、呆れるだろう? だが、本当にわからないんだ。……未熟ですまない」
冨岡の瞳のなかの煉獄の顔が、揺らめいていた。きらめく星を散りばめた夜空のように深い瑠璃の瞳が、涙の膜をまとっている。初めて見る冨岡が、また一つ増えそうだ。
「俺が、その答えを言ってしまってもいいのか?」
冨岡の答えはなかった。けれど、瞳が訴えかけている。教えてと。
「冨岡、俺は今、幸せで胸がはちきれそうになっている。どうやら俺と君は、同じ想いを抱いているようだ」
「同じ……」
「言っただろう? 君が好きだ。冨岡」
緩慢なまばたきとともに、きれいな涙がひとしずく、冨岡の目尻から静かにこぼれて落ちた。初めて見る冨岡の涙。流れ星。そんな言葉がふと煉獄の脳裏に浮かぶ。
流れ星に願いをかけることを教えてくれたのは、誰だったか。神仏に手を合わせはしても、煉獄は一度たりと、神頼みなどしたことはない。けれど、このしずくには願いたくなった。
どうか、この美しく凛々しく、けれど誰より愛らしい人が、いつか幸せだと微笑んでくれますように、と。
「好き……え、あ……」
冨岡の目元を染めていた朱が、じわじわと広がっていく。以前に、二人の足元を染めていた鮮血よりも清々しく、温かな、花のように鮮やかな赤。あの日には白く凍りついていた頬が、恋の色に染まっていく。
まっすぐに見つめてくる瞳は揺れていた。見開かれた目のなかで、煉獄を映して揺れる、深い瑠璃。紅葉に赤く染まる草原に、一輪咲いた竜胆のように、その瞳は手折られ愛でられるのを待っているように感じた。
「冨岡、先ほどのたぬき蕎麦のカスがついてるぞ」
「え? あ、あぁ。ありがとう」
あえて軽口めかして親指で冨岡の唇についた食べかすを拭ってやれば、羞恥にだろう、冨岡の顔がいっそう赤らんだ。
「答えを聞かせてはくれないのか?」
「答え……え? 答え?」
潤んだ目をパチパチとしばたたかせるたび、冨岡の長いまつげが涙の粒をまとっていく。
「俺は君に告白しただろう? 君は俺をどう思っているのか、聞かせてほしい」
「……俺、は」
煉獄の指が触れたまま、冨岡の唇が震えながら言葉を紡ごうとしたそのとき。
「だめっ、死んじゃうっ!」
サッと冨岡のまとう空気が一変した。腰の日輪刀に手をやり、早くも腰を浮かせる冨岡に、煉獄の手のひらは置き去りになった。
呆然。絶句。人の事情を与しないのは、鬼だけではなかったか。
「待てっ、冨岡! あれはそういうのではない!」
「殺されかけている」
なにをボサッとしていると言わんばかりに、冷静さをすっかり取り戻した眼差しを向けてくる冨岡は、これっぽっちも状況を理解していないようだ。うといとは思っていたが、まさかこれほどとは。
本当に、よく男娼役など引き受けたものだ。呆れもするが、それよりもなお、煉獄は笑いたくなった。心の動きに逆らわず、煉獄は破顔する。怪訝に眉を寄せる冨岡に首を振ったところで、鴉の鳴き声がした。
「伝令! 伝令! 煉獄杏寿郎、新宿へ迎え! 悪鬼滅殺せよ!」
「冨岡義勇! 高尾に鬼の出現の噂あり! すぐに向かえ!」
窓の外で羽ばたく鴉たちに向けた視線は、二組とも険しい。鬼殺隊の柱の顔がそこにはあった。
「まったく、鬼というのは無粋がすぎる。人の恋路を邪魔するからには、馬に蹴られても文句は言わせん」
言いながら立ち上がり、煉獄は取り出した紙幣を確かめもせず卓に置くと、窓に向かって足を踏み出した。冨岡はちらりと紙幣に目をやり眉間を寄せたが、なにも言わなかった。なぜ階段に向かわないのかと問いかけてくることもない。
ガラリと窓を開けた煉獄は、窓枠に足をかけると、無言のまま外へと飛び出した。地面につくと同時に声を張り上げる。
「主人、急ぎの用ができた! お代は部屋に置いてある、釣りはとっておいてくれ!」
言い終えるより前に、冨岡も音もなく地面に降り立っている。早くも走り出そうとしている冨岡に一拍遅れ、音高く蕎麦屋の戸が開かれた。
「く、食い逃げかっ」
「部屋を確かめてくれ! 足りないということはないはずだ!」
店主の怒鳴り声はもう遠かった。人並みを避けながら駆ける煉獄の傍らを、同じように走る冨岡が、視線を向けてくる。その眼差しにはささやかながら咎める色があった。
「冨岡?」
「……品書きには、六銭と書いてあった」
なるほど。煉獄が置いてきた金が気になっていたようだ。速度を緩めることなく、煉獄は大きな声で笑う。
「部屋代込みだからな! 足りないということはあるまい!」
「五円もする部屋などあるわけがない。追加で注文したわけでもないのに」
それはそうだが、煉獄としては十円払ったところで惜しくはない。
「なに、おかげで君の気持ちがわかったのだからな! 礼には足りなかったかもしれん!」
言って、煉獄は思わず、ん? と、黙り込んだ。傍らを駆ける冨岡の、少し赤く染まってうつむき気味な顔をまじまじと見る。
「いや……まだ、答えを聞いたわけではなかったな」
「隣の部屋の人だがっ!」
聞かせてくれと続けるより早く、いきなり冨岡がいつもより大きな声でさえぎってきた。
「隣?」
「殺されかけていたようだが、本当に大丈夫なのか?」
「あぁ……気にすることはない。あの部屋でなら、まぁ、ああいう言葉を口走ることもあるんだろう」
「あの部屋……蕎麦屋でいったいなにを……」
駆ける足はちっとも遅れることがないが、冨岡は、すっかり思案に沈んでしまったらしい。煉獄はもはや苦笑するよりない。経験のない煉獄でも、女性が情事に感極まってあげた声だということぐらいはわかる。だが冨岡にはまるっきり想像もつかないようだ。おそらくは、巷の人々が蕎麦屋の二階をどのように使用しているのかなど、一度として耳にしたこともないのだろう。
十字路が前方に見えてきた。行き先が分かれる。一瞬だけ煉獄に視線を向け、そのまま走り去ろうとする冨岡に、足を止めた煉獄は声をかけた。
「冨岡! 一つだけ、約束してほしい。誰に誘われようと、一緒に蕎麦屋の二階には行かないでくれ」
「……わかった」
やはり寸時足を止めた冨岡の顔は、もうすっかり元通りだ。いつもの鉄仮面の如き無表情。けれどもどことなし、その顔にはわけがわからないと書いてある気がする。
なにを言われているのか理解できないまでも、煉獄がそう言うならと、了承してくれたのだろう。うれしいような、なんとはなし切ないような。少しばかり複雑な気分になりながらも、煉獄は、小さく苦笑するにとどめた。
「杏寿郎様! お早く!」
「あぁ、わかっている、要」
浮かんだ苦笑を急かす鎹鴉にそのまま向け、煉獄は、気持ちを切り替えるように深く息を吐いた。
「では、行くか! 冨岡、終わったらまた一緒に飯を食おう!」
冨岡の答えを聞くのはそれまでおあずけだ。残念至極ではあるが、あの反応ならば色好いとまでは言わぬまでも、煉獄のことを色恋の対象になりえるのだと理解してくれただろう。意識してくれたのなら儲けものと思わねば。
駆け出そうとした煉獄の背から聞こえた声は、小さかった。
「俺も、同じだ……」
「え?」
即座に振り返ったが、もう冨岡は走り出していた。揺れる黒髪からわずかに覗いた耳が、赤い。
煉獄が呆けたのは一瞬だ。すぐに走り出し、ぐんぐんと速度を上げていく。己でも信じられないほど力がみなぎっていた。
「本当に……鬼という奴は度し難いな。人々の幸せを壊すだけでなく、冨岡の告白さえまともに聞かせてくれんとは」
苦々しい言葉とは裏腹、煉獄の顔には、抑えきれぬ笑みがある。
想いが通じた。それどころか、自分の心も煉獄と同じだと、冨岡は言うのだ。好き。好きなのだ。自分が冨岡のことを好いているだけでなく、冨岡もまた、自分を好いてくれている。
走り出したからにはもう任務は始まっている。浮かれてはならない。そう心にいい聞かせても、勝手に鼓動は跳ね回ろうとする。笑みが抑えられない。
恋の甘やかな喜びに浮き立つ煉獄の足は、常になく軽い。今ならば、百万の敵にだって負ける気がしなかった。
往来の人々が呆気にとられるほど、疾風の速さで駆ける煉獄の頭上には、桜の花びらが舞う青空が広がっていた。