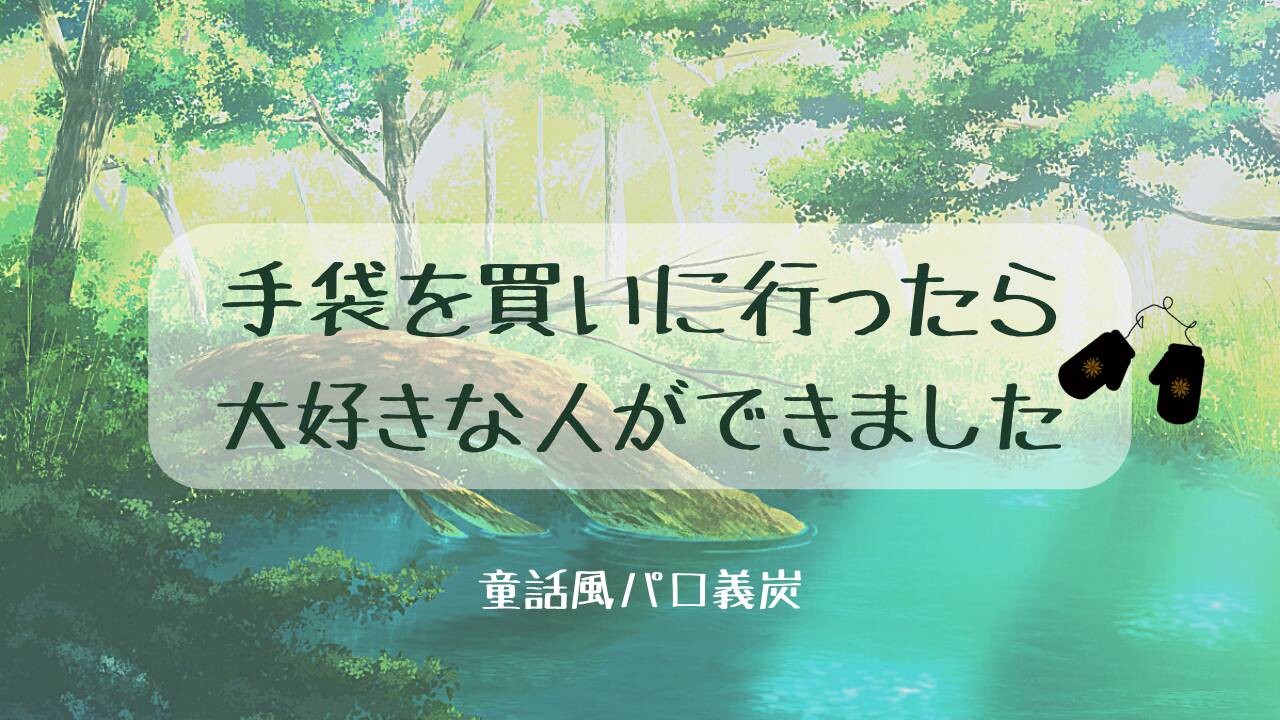楽しくお話しながらご飯を食べ終えた炭治郎たちは、急いで舟に乗ろうとしました。
「早くしなきゃ、雨が降ってきちゃうっ」
「ちょっと待ちなよ。舟で行くよりも早く、向こう岸に行けるようにするから」
言うなり霞柱様はバンザイするように両手を広げました。するとどうでしょう。霞がシュルンと集まって、真っ白な橋が川に架けられたではありませんか。
「うわぁ、すごいや! これならすぐに向こう岸につけるぞ!」
「ありがとうございます、霞柱様!」
霞でできているというのに、橋はみんなで乗ってもびくともしません。驚く炭治郎たちに霞柱様は「また遊びにおいでよ」と笑って手を振ってくれたので、炭治郎や禰豆子も「また来ます!」と手を振り返して元気よく駆けて行きました。
森の木々の合間を走って、炭治郎たちはどんどん進みます。懐にしまった霞の鞠を落とさないように気をつけながら、一所懸命に走りましたが、空にはどんどんと黒い雲が増えてきていました。今にも雨が降り出しそうです。
「急がないとだいぶ暗くなってきたぞ。禰豆子、もうちょっと早く走れるか?」
「禰豆子ちゃん、疲れたら言ってね? 俺、おんぶするから!」
「大丈夫、まだ走れるよ」
みんなよりちょっと遅れがちな禰豆子を気遣いながら走っていると、道の先にしゃがみ込んでいる人を見つけました。なんだかとっても苦しそうです。
その人はとてもきれいな女の人でした。傍で男の人が心配そうにしています。
「た、炭治郎! あれって……」
耳をそばだてた善逸が、ビクリと震えて立ち止まりました。炭治郎も立ち止まると、鼻をふんふんと引くつかせて、ちょっと眉根を寄せました。
「お兄ちゃん、善逸さん、どうしたの? あの人なにか困ってるんじゃないの?」
そう言って禰豆子が進もうとするのを、善逸が怯えた顔で引きとめます。伊之助も怖い顔をして、女の人たちを睨みつけていました。
「大丈夫、ちょっと待ってて」
炭治郎は、決心して一つうなずくと、女の人たちに近づいていきました。善逸と伊之助が慌てて止めようとする声も振り切って、女の人たちに声をかけます。
「どうしたんですか? どこか痛いんですか?」
「なんだ、お前。珠世様に軽々しく声をかけるんじゃない!」
「おやめなさい、愈史郎。大丈夫ですよ、かわいい子狐さん。早くお行きなさい、雨が降り出せば『災い』が出てきますよ」
炭治郎を睨みつける男の人をたしなめて、女の人はやさしく炭治郎に言いました。苦しそうに眉を寄せているのに、それでも笑いかけてくれる女の人の顔は、声と同じくとてもやさしそうでした。蟲柱様もたいへんおきれいな方でしたが、この女の人もとっても美しくて女神様みたいです。
「でも、とってもつらそうですよ。俺がお手伝いできることはありますか?」
「……お前、変な奴だな。なにをたくらんでる?」
「なんてことを言うの、愈史郎! せっかく声をかけてくれたのにごめんなさいね。この子は私を心配してくれているだけなの」
「大丈夫です! 愈史郎さんが心配してるの、匂いでわかりますから。珠世さんがつらいのも匂いでわかります。俺は山犬さんや狼さんよりも鼻が利くんです」
炭治郎が笑うと、珠世と愈史郎はとても驚いた顔をしました。まじまじと炭治郎を見つめる珠世の声も、戸惑いがあらわです。
「それなら、私たちが森の動物ではないこともわかりますね……? なのになぜ、あなたは私たちに声をかけたの?」
「だって珠世さんはとってもつらそうだし、愈史郎さんも心配そうですから。それに珠世さんからはすごくやさしい匂いがします! だから怖くなんてないですよ」
炭治郎が笑うと、善逸たちを振り切った禰豆子もやってきて、珠世に心配そうに聞きました。
「大丈夫ですか? なにかお手伝いしましょうか?」
炭治郎と同じことを言う禰豆子と、禰豆子を追ってやってきた善逸と伊之助の怯えたり怒ったりしている顔を見比べて、珠世は少し困ったように笑いました。
「妹さんかしら。よく似てるのね。大丈夫ですよ、私たちのことはいいから、雨が降る前にお行きなさい」
「でもとっても苦しそう……寒いのかしら。今日はとくに冷えるもの。そうだ!」
禰豆子は手袋を外すと、珠世に「はい」と差し出しました。
「この手袋、森の外れの洋服屋さんが売ってくれたんだけど、とっても暖かいんです。これをはめてたら寒いのもへっちゃらなの。おばさんにあげます」
「貴様、珠世様におばさんだと!?」
「愈史郎!! かわいい狐のお嬢さん、それを私にくれたら、あなたが寒くなってしまうわよ?」
禰豆子たちの話を聞いていた炭治郎も、禰豆子に首を振って、自分の手袋を外しました。洋服屋さんが売ってくれた大切な宝物だけど、人助けには代えられません。
「そうだよ、禰豆子。それに、禰豆子の手袋じゃ珠世さんには小さいよ。俺の手袋をあげます、使ってください」
「炭治郎の手だって大人の女の人より小さいだろぉ。うぅ、俺の耳当てで良かったら……」
「……しかたねぇなぁ! ほらっ、俺様のマフラーなら大丈夫だろ。感謝しろ!」
炭治郎たちが手袋や耳当て、マフラーを差し出すのに、珠世だけでなく愈史郎も唖然としてしまったようです。
「駄目? 寒いんじゃなくてやっぱりどこか痛いの? それともお腹が空いてるんですか?」
首をかしげて聞く禰豆子に、善逸がビクンと飛び上がりました。
「おおおおおお腹空いてるのっ?」
ビクビクと怯える善逸に、珠世は困った顔で笑います。愈史郎が小さく舌打ちして、善逸を睨みつけました。
「珠世様をそこらの『災い』と一緒にするなっ! 珠世様も俺も、動物たちを襲って食べたりはしない。それより、お前らあまり珠世様に近づくな!」
ふんふんと鼻を引くつかせた炭治郎は、困った顔で珠世を見ました。
「……お腹が減ってる匂いがちょっぴりしますよ? 動物を食べないなら、なにが食べられますか? 俺、探してきます!」
愈史郎や炭治郎の言葉で、禰豆子も、ようやく珠世たちの正体がわかったみたいです。けれど、珠世を心配する気持ちのほうが大きいのでしょう。
「私も探してきます! なにが食べられますか?」
怖がる様子もなく珠世の顔を覗き込んで、心配そうに言う禰豆子に、珠世の目が少し濡れたように見えました。
ふぅっと溜息をついて、愈史郎が言いました。
「俺たちは神の力の欠片を食べて生きている。だが、そんなものが、おいそれと手に入るわけもない。『災い』の首魁からの支配を逃れて久しいが、このままでは力を使い果たして、珠世様がまた『災い』の首魁に捉えられてしまうかもしれない。もしも柱の力を持つものがあれば、珠世様も力を得ることができるんだが……」
そう言うと、愈史郎はじっと炭治郎たちを眺めまわしています。その目はなにもかも見透かすようでした。
「おやめなさい、愈史郎! この子たちから柱の加護を奪ってはなりません!」
愈史郎を叱る珠世の顔は、それでもとても苦しそうです。きっと長いことなにも食べていないのでしょう。このまま放っておくこともできず、炭治郎たちは顔を見合わせました。
「柱の加護って、柱様たちからもらったもので作ったこれのことかなぁ?」
耳当てを触りながら善逸が言えば、伊之助もマフラーをまじまじと見つめます。
音柱様の鈴をつけた耳当てと、炎柱様の火の花で仕上げたマフラーです。柱様の加護の力があるとしたら、これぐらいしかありません。
受け取れないというのなら、炭治郎たちにあげられるものなんてあるでしょうか。
「あ! そうだ、これがあった!」
思いついたそれを、炭治郎は急いで懐から取り出しました。
「霞柱様のお住まいにたなびいていた霞です。これなら珠世さんも食べられませんか?」
せっかくいただいた霞ですが、珠世を助けられるのなら、洋服屋さんも怒ったりしないのではないでしょうか。
もしも怒られて嫌われてしまったら、とってもとっても悲しい思いをするでしょう。それでも、珠世たちが助かるなら、炭治郎にためらいはありませんでした。洋服屋さんには何度だって謝って、許してもらえるまでいっぱいお手伝いをするつもりです。
「いいのかよ、炭治郎。洋服屋さんに頼まれたお遣い物なんだぞ?」
「洋服屋さんには一所懸命謝るよ。珠世さん、よかったらこれをどうぞ!」
珠世は泣き出しそうな顔で笑うと、霞の端っこをちょっぴり摘まみとりました。
「ありがとう、これだけで十分よ。なにかお礼をしなくては……」
「いえいえ、お礼なんていりません。困ったときはお互い様です。それよりも、そんなちょっぴりで大丈夫ですか? 愈史郎さんもお腹が空いていませんか?」
笑う炭治郎に、愈史郎は少し戸惑っていたようでした。けれどもすぐに、背に腹は代えられないからなと、珠世と同じくらいちょっぴりと霞を摘まんで口に入れました。
それを見た炭治郎と禰豆子は、心の底からうれしくなって、ニコニコと笑いました。
「かわいくてやさしい子狐さんたち、本当にありがとうございました。とても強い柱の加護を持つあなたたちに『災い』である私たちがあげられるものはないけれど、代わりに教えてあげましょう。おそらくは森の護り神も感じ取っているでしょうが、年が替わる夜にお気をつけなさい。『災い』の首魁が、キメツの森を我がものにするために動こうとしています。新しい年が来る前に首魁を討ち取らなければ、この森の動物たちはみんな『災い』の餌にされてしまうでしょう」
元気を取り戻した珠世が言った言葉に、善逸は飛び上がって震えましたし、禰豆子も怯えて炭治郎にしがみつきました。伊之助もゴクリと喉を鳴らして黙り込んでしまっています。
キメツの森に現れる『災い』は、人や動物に似ているけれど、とても恐ろしい化け物です。『鬼』と呼ぶ者もいます。お日様の光が届かない時間、届かない場所に突然現れては、動物たちに襲いかかり食べてしまう、恐ろしい災厄なのです。
それを祓えるのは、柱様たちだけでした。
けれども柱様たちだって、すべての動物を救うことはできません。森は広くて、『災い』はいきなり現れて襲ってくるのですから。
炭治郎と禰豆子のお母さんや弟妹たちも『災い』に襲われて、命を落としました。水柱様が救けに来てくださらなかったら、きっと炭治郎と禰豆子も『災い』に食べられていたことでしょう。
伊之助のお母さんも、伊之助を生んですぐに『災い』に食べられてしまったそうです。『災い』に家族や友達を食べられてしまった動物は大勢いるのです。
「どうしたら『災い』の首魁を止められますか? 森には友達がいっぱいいます。みんなを助けるために、俺ができることはありますか?」
「首魁は本拠である無限城から出てきません。護り神や柱を恐れてはいませんが、とても慎重で狡猾なのです。無限城は強い結界に覆われて、柱は誰も入ることができません。柱が無限城に討ち入るには、なかから誰かが呼んで迎え入れなければならないのです。けれど子狐さん、無限城の場所は護り神でもなければ見つけ出すことはできないし、あなたのように小さな子供では、とても危険で入ることなどできませんよ。あなたたちの身を守る力を、私たちも少し授けてあげられたらいいのだけれど、『災い』である私たちの気配を身にまとえば、柱達の疑いを招き、かえって危険なことになりかねません」
でも、もしかしたら……と、珠世は少し口ごもりました。
なにかできることがあるのかなと、じっと見つめた炭治郎に、珠世は小さく首を振ると「さぁ、もうお行きなさい」と笑っただけでした。
今にも雨が降り出しそうな空の下、走る炭治郎たちは元気がありませんでした。それもしかたのないことでしょう。珠世が教えてくれた恐ろしい出来事に、みんな怯えていたのです。
「なぁ、炭治郎。珠世さんたちに逢ったことは、洋服屋さんには内緒にしとこうぜ。だってあの人たち、そのぉ『災い』……だろ? 洋服屋さんは柱様と付き合いがあるみたいじゃんか。珠世さんと知り合ったって聞いたら、疑われちゃうんじゃないかなぁ」
心配そうに言う善逸の言葉は、もっともです。
不思議な力を持っているらしい洋服屋さん。もしかしたらと思うことは、いっぱい、いっぱい、ありました。珠世さんの気配を感じ取られたら、もしかしたら嫌われてしまうかもしれません。
「霞もちょっとしかあげてないし、黙っていればきっと気づかれないって! なぁ、そうしようぜ!」
善逸が言うのに、炭治郎は答えられませんでした。炭治郎は嘘をつくのが嫌いです。嘘をついてもすぐに顔に出てバレてしまいます。だからもし洋服屋さんに嘘をついたとしても、きっと洋服屋さんにはバレてしまうでしょう。
それよりなにより、炭治郎は、洋服屋さんに隠し事をしたり、嘘をついたりしたくはありませんでした。
お店に戻っていつものように、洋服屋さんにお遣い物の霞をわたした炭治郎は、思い切って言いました。
「洋服屋さん、ごめんなさいっ! 霞の端っこを少し、困っていた『災い』さんにあげてしまいました!」
「ちょっ、炭治郎っ! なんで言っちゃうんだよぉぉっ!」
善逸が真っ蒼な顔で騒ぎましたが、洋服屋さんは小さく目を見開いただけで、じっと炭治郎の言葉を聞いてくれました。
『災い』だけれど、珠世さんと愈史郎さんは、炭治郎たちを食べようとはしなかったこと。本当につらそうだったこと。それから、珠世が教えてくれた恐ろしい『災い』の首魁のことも、炭治郎は、懸命に洋服屋さんに話しました。
洋服屋さんはなにも言わず、炭治郎の言葉を聞きながら、少しだけ怖い顔で何事か考えているようでした。不安な目で炭治郎が見つめても、それすら気がついてはいないようです。
「洋服屋さん、やっぱり珠世さんと愈史郎さんに霞をあげるのは、いけないことでしたか? 洋服屋さんのご迷惑になっちゃいましたか……?」
ちょっぴり怯えた声になった炭治郎に、洋服屋さんは険しかった目元をようやく緩めると、やさしく炭治郎の頭を撫でてくれました。
「大丈夫だ」
「でも、霞は少し減っちゃいました」
「これだけあれば十分だ。いいから夕飯を食べてこい」
今日もテーブルに用意されたご飯は、ホカホカと湯気を立てておいしそうな匂いがしています。炭治郎と同様に不安そうだった禰豆子たちも、洋服屋さんの言葉にホッとしたのか、テーブルについてご飯を食べ始めました。
「洋服屋さん、今日もお仕事を見ていていいですか?」
霞を丸めた鞠を手にお仕事机に向かった洋服屋さんに、今日も炭治郎はたずねました。洋服屋さんはやっぱり今日も小さくうなずいて、鞠になった霞をほどくと、織機を取り出しそこに仕掛けました。
シャッシャッと洋服屋さんが織機を動かすたびに、霞は布地へと織り上がっていきます。やがて織り上がった布は、淡い桃色をしていました。その布をスイスイと切ったり縫ったりして、仕上げにフッと息を吹きかけると、洋服屋さんはかわいいマントを作り上げました。
「禰豆子に着せてやれ」
「え? 私?」
炭治郎と洋服屋さんの様子を気にしていたのでしょう。名前を呼ばれた禰豆子が、すぐに振り向きました。
「よかったなぁ、禰豆子!」
「いいの? 洋服屋さん」
ととっと近づいてきた禰豆子に、洋服屋さんはうなずいて、ちょっとだけ困って見える顔をしました。
「……もっと、かわいい柄のほうがよかったか? 花とか……」
女の子が好きなものはわからないと洋服屋さんが言うのに、禰豆子はちょっぴりおかしそうにウフフと笑います。マントを羽織って、禰豆子はくるりと回ってみせました。マントの裾が広がると、まるで桃色のお花のようです。
「これがいい! とってもかわいい桃色のマントをありがとう、洋服屋さん!」
「禰豆子ちゃん、すっごく似合うよ! お花みたいだねぇ。かわいい禰豆子ちゃんにぴったり!」
「あったかそうだな。よかったじゃねぇか、これで雪が降っても寒くねぇ」
善逸や伊之助も喜んでくれて、炭治郎もとってもうれしくなりました。
「マントのお礼にお手伝いをします。洋服屋さん、次はなにをもらってくればいいですか?」
「……風柱の住まいにいる鳥の羽根を一本、もらってきてくれ」
「わかりました! でも洋服屋さん? なんでそんなに困ったような顔をしてるんですか?」
いつもと違ってちょっと言いにくそうな洋服屋さんに、炭治郎は思わず首をかしげました。
「……俺は、よく風柱を怒らせる」
「なんだ、嫌われてんのか」
「俺は嫌われてない」
伊之助の声に即答した洋服屋さんに、みんなは思わず笑ってしまいました。
『災い』の首魁は怖いけれど、今の炭治郎にできることは、洋服屋さんのお手伝いだけです。みんなでこんなふうに笑っていられるように、明日も頑張ろうと炭治郎は思ったのでした。