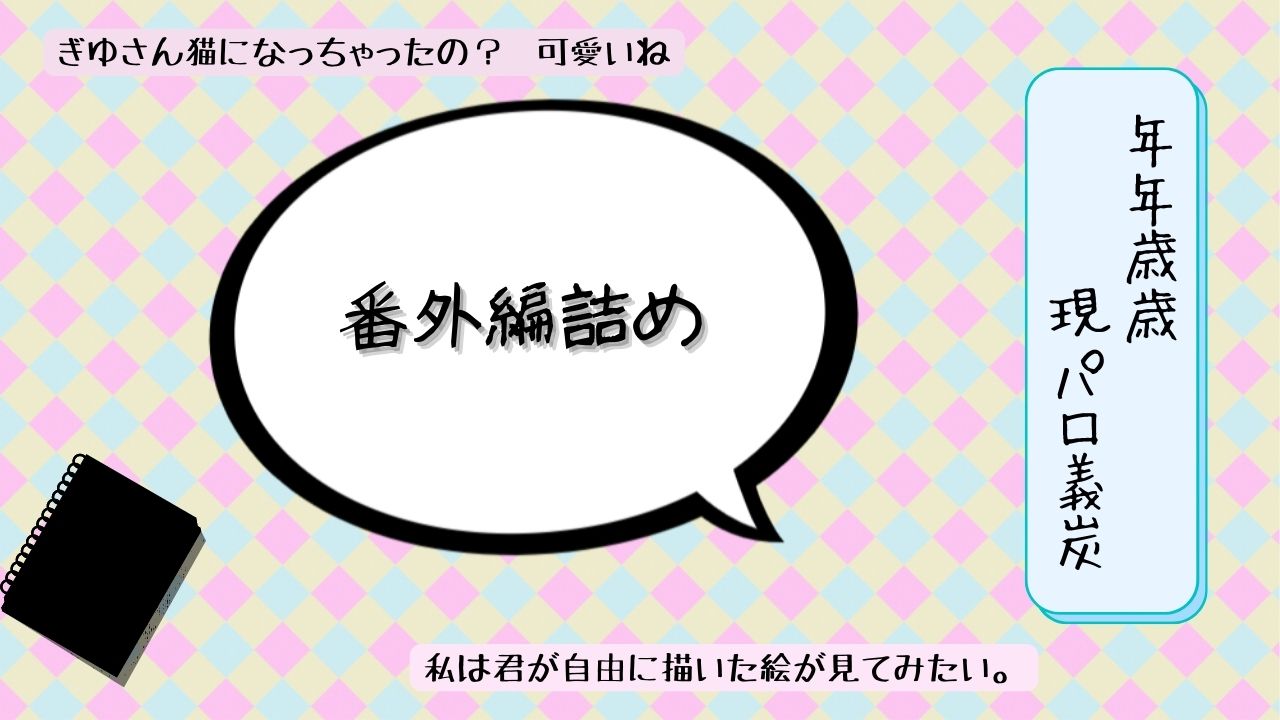◇天元 11歳◇
新作を描きあげたばかりのスケッチブックをしげしげと眺めていた天元は、ようやく満足げにうなずいた。今回はなかなかいい出来だ。色の取り合わせに悩んだけれど、これで正解。派手でいいねぇと、天元はニヤリと笑う。
さて、次はどんなモチーフにしようか。わくわくしながらスケッチブックのページをめくったとき、ノックの音がひびいた。
素早く画材の上に布をかけ、机の引き出しにスケッチブックをしまい込む。代わりに参考書を広げたと同時にドアが開き、弟が顔をのぞかせた。セーフ!
「兄さん、父さんが呼んでる」
「あぁ? 俺はなんにもしてねぇぞ」
帰宅してから今の今まで天元は自室から出ていない。ずっと描きかけの絵にかかりっきりで、父に小言を言われるような覚えはなかった。
「お客様。言葉づかい気を付けて」
声音も視線も冷め切った弟の言葉に、チッと舌打ちする。
二つ下の弟は、顔だけは天元によく似ている。だが似通っているのは顔立ちだけ。表情豊かな天元にくらべ、弟はといえば、表情筋が活躍するのは父の客の前だけで、家のなかではまったくの無表情である。言葉にも無駄がなく、必要なこと以外話す理由などないだろうと言わんばかりだ。
学校では相手ごとに表情を使いわけて、それなりに子供らしくしてみせているようだが、そんな必要のない自宅では、感情を表に出すことさえ無駄だと思っている節がある。
天元は、ドアの前に立つ弟の感情をそぎ落とした冷たい顔を眺め、げんなりと肩を落とした。
我が弟ながら親父そっくりで嫌になる。顔は天元と同じく母譲りの秀麗さだが、中身はまるっきり父のコピーだ。
天元は地元では有名な代々続く資産家の長男だ。曽祖父の代からは政界にも進出している。亡くなった祖父も市議会議員で、父はその跡を継ぐ形で何期か当選を続け、今は県会議員だ。そろそろ国会への進出を考えているらしく、天元たちにも品行方正を求めてくる。
曰く、もめ事を起こすな。何事にも地味に、悪目立ちはするな。しかし人に埋もれるな。常に人の上に立つことを意識せよ。文武両道を旨とし成績を残せ。
ド喧しいわっ!!
べつに父がどんな野望を抱こうとかまわない。天元にまでそれを求めさえしなければ。
いくら親子といえども、自分は父の所有物でもなければ、ましてや父のコピーではないのだ。父が求める理想の子供象など知ったことか。
父は母に対しても天元たち同様に政治家の妻としての理想像を求め、快活だった母は、いつの間にか暗くうつむきがちになり、他人の前でしか笑みを見せなくなった。
明るい笑顔もたあいない日常会話もない家庭。リモコン操作のロボットのように、父の定めた言動を行ってみせるだけの家族。
それが家庭円満を謳う宇髄家の本当の姿だ。
「早くして」
それだけ言い残しドアを閉めた弟は、父の支配をなんとも思っていないようだ。もはや自我などないようにすら見える。
先ほどまでの上機嫌など消え失せて、天元は、苛立ちのままにまた舌打ちした。
父にとって有益な客が来るたびに、兄弟は客の前に引き出される。家庭人としても最上の人物だと思われるために、父は天元たちに優秀で理想的な子供を演じさせるのだ。
じつに将来が楽しみなお坊ちゃんたちだと客にお愛想を言わせるためだけに、天元は笑いたくもないのににこにこと笑ってみせなければならない。まったくもって馬鹿らしい。
だが、行かなければ母が責められる。お前の教育が悪いと父から説教されるたびに、母のなかから柔らかななにかが削られ壊され消えていく。今ではもう、天元の描いた絵を見て上手と笑ってくれることもない。
しかたねぇな。天元はため息とともに立ち上がり、部屋を出た。父の求める馬鹿馬鹿しい三文芝居をするために。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
弟と並んで立つ天元に、やぁ、と笑いかけたその人は、今までの客とはどこか違っていた。柔和な笑みと、心地好い声。けれどただ温和なだけの人物ではないはずだ。滲み出るようなカリスマ性をその人物から天元は感じずにはいられなかった。
「キメツ学園理事長の産屋敷耀哉さんだ。ご挨拶なさい」
産屋敷をぼぅっと見ていた天元は、尊大な父の声に意識を引き戻され、あわてて取りつくろった笑みを浮かべてみせた。
天元と弟が続けて自己紹介すると、産屋敷はにこやかに二人を見つめながら質問してきた。その声に、やっぱり頭のなかがふわふわとするような心地好さを感じる。
「天元は小学六年生のわりにはずいぶんと体が大きいね。なにかスポーツでもしているのかな?」
「合気道をしているんですよ。これでなかなか才能があるようでしてね。先の大会でも準優勝でした。そうだな? 天元」
天元が答えるより早く笑って答えた父に、天元は冷めた反感をおぼえた。準優勝の『準』に責める色を感じ取ったのは気のせいじゃないはずだ。大会成績を問われて答えたときに、優勝じゃないのかと顔をしかめられたことを、天元は忘れてはいない。
だが、顔にはそんな反発は出さない。褒められてはにかむ謙虚な少年の笑顔を作って、次は優勝できるようにがんばりますと元気な声で答えてみせる。
猿芝居だ。自分は猿回しの猿でしかない。ああ、息が苦しい。溺れそうだ。
「凄いね。将来は武道の道に進むの?」
「まさか。心身を鍛えるためにやらせていますが、このまま合気道を続けたところで、将来的な成功を得られるとは思いませんよ。天元は私の地盤を継ぐ政治家にします。合気道は趣味ですね」
勝手に決めるなと叫びたい。政治になんて興味はない。俺の将来は俺が決める。将来的な成功? そんなものいらない。俺は、俺は……!!
カッと身の内を焼く熱は、けれど表に出る前に冷めた。
反論してどうなる。反発したところでどうにもならない。母が責められるだけだ。
どれだけ心のなかで父を拒み反発を繰り返そうと、現実には天元は父に逆らえない。天元の溺れそうな苦しさなど、誰も気づいてはくれない。父の望む理想の子供としての天元しか、人は求めてくれない。天元自身の望みも夢も、塵芥のように払い除けられておしまいだ。
「いえ、私は貴方ではなく天元に聞いてるんですよ。天元、君自身はなにになりたいのかな?」
昏い水底に沈んでいくような息苦しさのなかで聞こえたのは、そんな声。
それはカンダタの目の前に降りてきた蜘蛛の糸のように、細く光り輝いている。掴んでいいのか。救われてもいいのか。葛藤のなかで、天元は少し震えながら口を開いた。
「あの、俺は……っ」
「天元!」
強い声に阻まれて、天元の言葉は喉の奥で止まって消えた。
「おまえ、まさかまだくだらない絵を描いてるんじゃないだろうな。小学生とはいえ、おまえは宇髄家の長男なんだ。そろそろ将来のことも考えなさい」
蔑むように言われ、天元はびくりと肩を震わせた。
咄嗟には答える言葉を見つけられなかった天元に、父は呆れたと言わんばかりのため息をつく。
絵を描くことを許してくれとは言わない。言っても無駄なことぐらいわかってる。だから大人しく従ってるじゃないか。お前の言う通りに生きてやってるじゃないか。それなのに、密かに絵を描くことすら奪おうとするな。絵を描けなくなったら、俺は本当に俺じゃなくなる。弟みたいに、ただのコピーになっちまう……っ!!
焦燥と怒り、消失への恐怖、叫び、喚いて、すべて吐き出してしまいたい。それでも天元が感情を抑えたのは、母への思慕ゆえだ。これ以上母を苦しめるわけにはいかない。それだけが、天元を戒める鎖だった。
母が父をみかぎってくれたなら、自分も自由になれるけれど。母はもはや唯々諾々と父に従うことしかできないから。歯向かう強さをもう持てないから。
己を抑え込んだ天元を見てなにを思ったのか、父は弟に視線をやり顎先でドアを指し示した。それだけで父の意を酌み退出する弟を、気持ちが悪いと天元は苛立ちとともに思う。
完全な父のコピー。なんて哀れで、なんておぞましい、自分の弟。
自分は決してそうはならない。母が苦しむから、悲しむから、従ってみせているだけだ。
ぐっと唇を噛んだ天元は、じっと自分を見つめる視線には気づかなかった。
五分とかからずに聞こえたノックの音に続いて、弟が母とともに部屋に入ってきて、天元は思わず息を飲んだ。
また母を責める気かと思わず眉を怒らせたが、母の手にある物に気づき、天元の顔から一気に血の気が引いた。
「天元、あなたまだこんなものを描いていたのね」
咎める母の声と、掲げられたスケッチブック。眉をひそめて首を振る母。無表情に佇む弟。尊大さを隠そうともしない父。
全部が芝居じみている。
「こんなただ絵の具を塗りたくっただけの変な絵ばかり描いて……あなたにはもっとやらなければいけないことが沢山あるでしょう? どうしても絵を描きたいなら、せめてもっとまともな絵を描きなさい。これじゃお父様が恥をかいてしまうわ」
嘘だ。そう思った。なんで、とも思った。
耳によみがえる母のやさしい声と、非難のひびきで放たれた目の前の母の声が、あまりにも違い過ぎて。
天元の絵を見ても母が笑ってくれなくなったことは、もう諦めている。けれど、まさかすべてを否定されるなんて。
『凄いねぇ、天元にはこんなふうに見えているのね。天元が見ている世界はとってもきれいね』
そう言って笑ってくれていたのに。いつだって、笑ってくれたから。天元を抱きしめて、笑ってくれたから。母が与えてくれたそんなやさしい笑みを、言葉を、全部覚えているから。
だから。だから俺は……!!
絶句して震えた天元の視界の隅、父の冷たい顔が小さく嘲笑を浮かべたのを、天元は見た。
そうか。そんなにも俺から希望も救いも奪いたかったのか。そこまで俺の自我は邪魔なのか。
ぐらりと地面が揺れたような気がする。ガラガラと崩れて、昏い水の底へと沈んでいく。
もう、なにを守っていたのかさえ、わからない。沈んで、溺れて、息もできない。
「天元、少し私と話をしようか」
不意にかけられたその声は、決して大きくも強くもなかった。けれど、その場を支配する力を持っていた。
天元のみならず、父たちもハッと覚めたような顔をして、視線をその声の主へと向けた。黙って一同を見つめていたその声の主は、穏やかな笑みを絶やさぬまま、ゆっくりと立ち上がった。
「産屋敷さん、申し訳ありません。お恥ずかしいところをお見せしまして……」
「お気になさらず。それより天元くんと話をしたいのですが、少し外に出てもよろしいですか? あまり遅くならぬように送り届けますので」
狼狽を押し隠しながら言う父に対する産屋敷の声は、あくまでも静かで穏やかだ。
「いや、それは……」
「ああ、そうそう。先ほどのご提案ですが、前向きに検討させていただこうと思います」
父に最後まで言わせることなくにこやかに告げると、産屋敷は父の答えを待つことなく天元に微笑みかけた。
「さぁ、行こうか。天元」
その微笑みと柔らかな声に、天元はただうなずいた。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
「君のお気に入りの場所はあるかい? そこで話をしたいな」
微笑みとともに言われ、天元は産屋敷を伴い近所の神社へと足を運んだ。
細く急な階段を上ると、木々に囲まれた小さな社がひっそりと建っている。
「こっち、です」
鳥居をくぐることなく木々の合間を縫って社の裏手に回る。やがて木立が途切れて、視界が開けた。
「ああ、これは凄いね。いい眺めだ」
産屋敷の声には真実感嘆のひびきがあった。
視界を埋める青空。流れる雲。遠く見える山の稜線。ミニチュアのような家々。全部が天元のお気に入りだ。
誰にも教えたことのない秘密の場所に、なぜ産屋敷を案内しようと思えたのか、天元にはわからない。産屋敷に逆らう気力もなかったのか、それとも、産屋敷に見てもらいたかったのか。今はなにも考えたくなくて、天元はぼんやりと目の前の光景を見ていた。
いつもなら心が晴れるお気に入りの光景も、今日は天元の心になんの感慨ももたらさない。ここでならいつでも自由になれたのに、今は縛られたまま溺れていく感覚がぬぐえなかった。
「君のお気に入りの場所は素敵だね。とても自由で、楽しさと明るさに満ちている」
柔らかい声に思わず視線を上げる。小学生にしては上背のある天元は、大人の産屋敷とくらべても背丈はたいして変わらない。それでもなぜだか産屋敷の姿は大きく見えた。
「ねぇ、天元。君が一番望むものはなにかな? 聞いているのは私だけだ。ほかの誰も聞いてなどいないよ。君が本当に望むことはなんだい?」
お釈迦様の蜘蛛の糸がまた降ろされた。自分はそれなら罪人だろうか。父の意に逆らい母を苦しめる咎人か。ならば、この糸にしがみつき登っても、行きつく先はやっぱり水底なのではないだろうか。
だって、どうしたって自分は逃げられない。少なくともこれから数年は。父に反発し出奔するには、天元はまだ幼い。同年代の子供にくらべれば世慣れている自覚はあるが、しょせんは小学生だ。少なくとも働ける年までは家にいるよりほかない。
それでも。
「俺は……俺でいたい。誰かのコピーじゃなくて、猿回しの猿じゃなくて、俺は俺でいたいっ!!」
絞り出すように小さく叫ぶ。
絵を描いているときだけは、天元は自由になれた。スケッチブックの白い空間で、天元の心は自由に遊び、踊り、跳ね、飛ぶ。鳥のように、魚のように、風のように。それは天元の心の広さそのものだ。目に見える事象そのものよりも、心が捉えた色を、きらめきを、天元は白いページに描きだす。だから絵を描くのがたまらなく好きだった。
世間体もくだらない他人の噂や陰口も、弟の冷めた視線や父の支配も、そこにはおよばない。派手に、楽しく、おもしろく、自由に! 爆発するような衝動を、絵という形で天元は描き表す。
天元が自分でいられる唯一の手段が絵だ。自分を消したくないから絵を描いた。描き続けた。
母を守るために言葉や行動は閉じ込めたけれど、絵を描くことだけはやめられなかった。きっと母も本心ではそれを望んでくれていると思っていたのに。
天元が天元らしくあることを、母だけは望んでくれると思っていたのに。
「そう。君は凄いね。まだ幼いのに、自分を抑えてまでも人を守ることを知っている。そのうえで、自分を殺さず保っている」
やさしく言う目の前の人を、どこか呆然として天元は見つめた。
この人は責めないのだろうか。誰も彼もが天元が自分らしくあることを責めたのに。天元の今の言葉を罪だとは思わないのか。
「お母さんのことを守ってきたんだろう? でもね、もういいと思うよ。君のお母さんは自分自身で選んだんだ。ああして君のお父さんの庇護下で生きる代価として、自身の心だけでなく君の心までもあの人に渡すことをね」
ザクリと音を立てて、心が切り裂かれたような気がした。
青ざめる天元を見ても、産屋敷は笑みを崩さない。
「君の心は君のものだ。たとえ親だからといって、勝手にしていい道理はない。けれど君のご両親はそんなことすらわからなくなってしまっているようだね。残念だけれど君のお母さんは、君に守られていることすらもうわかっていないらしい。わかろうとしない道を選んでしまった」
ふ、と。心に空気が送り込まれた気がした。切り裂かれたその傷から。いや、傷ではないのか。
「天元、つらいだろうけれど認めなければいけないよ。君の家族はもう、君の誠意だけでは変われない。変わることを彼らは望まない。君とはわかりあえない存在だということを、本当は君も理解しているんだろう?」
なぜだろう、むごいことを言われているはずなのに、息が少し楽になった気がする。心に通気口が作られたみたいだ。
本当はもうわかっていた。自分の家族はもう駄目なのだと。天元とは違う生き物になってしまったのだと。すべてを支配しようとする父も。父のコピーである弟も。父の所有物でいることを選んだ母も。自由を求めてやまない天元とは、あまりにも違う。天元だけが異質だ。
そんなこと、本当はもうわかっていたはずだ。ただ、認めたくなかっただけ。母だけはと思っていたかっただけ。
「でも、俺はまだあの家から出られない……自由になれない。認めたら余計みじめになるだけだっ」
そうだ、認めてしまったらもう戻れない。弟のように父のコピーになることもできず、母を守るという理由も失い、けれど自由になることは許されない。光を失ったより昏い水底で溺れ、朽ちていくしかないじゃないか。
また苦しくなって吐き出すように言えば、産屋敷は今のままならそうかもねと、にこやかに笑った。そして言ったのだ。
「高等部を卒業するまでの期限付きではあるけれど、自由に生きる場所が君には必要だと思うよ。そして私はその場所を君に提供できる立場にある。どうだい、天元、私の学園に来るかい?」
キメツ学園には中等部から寮がある。学校独自の奨学金もあるから、もしお父さんが金銭面で入学を阻もうとしても、君の力だけで入学は可能だ。まぁそんなことは私がさせないけれどね。
産屋敷は楽しげに言う。これでもそれぐらいの力はあるんだよ、と、悪戯っ子のように笑う。
「ねぇ、天元。私は君が自由に描いた絵が見てみたい。この素敵な光景そのままに、きっと私の心を弾ませてくれるだろうね。じつに楽しみだよ」
これは罪人に降ろされた蜘蛛の糸なんかじゃない。溺れる天元に投げられたレスキューロープ。きっと切れることはない。
微笑むこの人は、きっと天元を引き上げるそのロープを手放さない。
「でも、俺の絵って前衛アートなんですけど」
もう心は決まっているけれど、まずは自分らしく言ってみる。
生意気でいい。それが本当の俺だ。それでもきっと、産屋敷は笑ってくれるだろう。
そして。天元が想像したより楽しげに、産屋敷は笑った。
だからもう、天元は溺れたりしない。また誰かが水底に落とそうとしたって、派手に泳ぎ切ってみせようじゃないか。
そう、派手に、楽しく、おもしろく、自由に!
だってそれこそが俺、本当の宇髄天元さまってもんだろ?