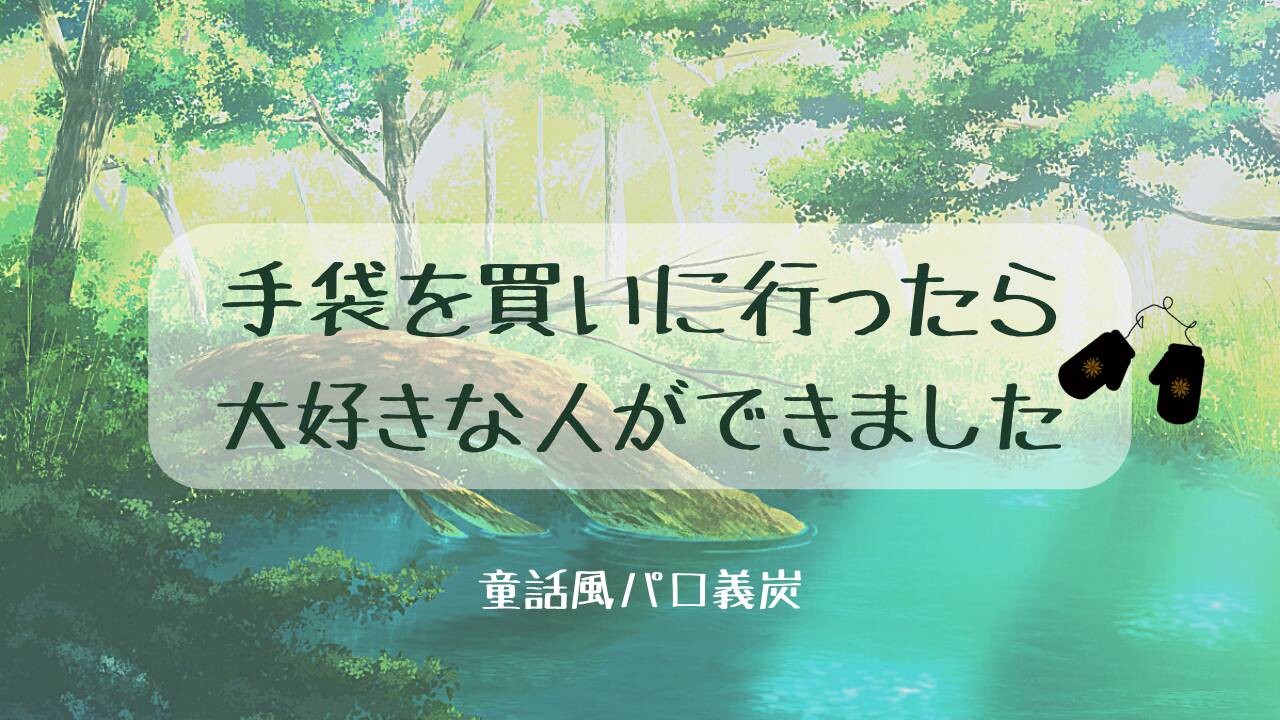キメツの森に初雪が降りました。白い真綿のような雪は静かに降り続け、森を白く染めていきます。
最後のお遣いを終えてから、もう両手の指を超える日が過ぎました。
炭治郎はあれ以来、森の外れのお店には行っていません。自分の家に帰ってきたその日の夜、洋服屋さんが言っていたとおり、お館様からのお達しが森の動物たちに下されたからです。
『災い』の首魁がキメツの森を襲う準備をしていること。襲撃はおそらく年が替わる夜であること。
恐ろしさに、森の動物たちは震えあがりました。家族や友人を『災い』に殺された者は少なくありません。その『災い』が、一斉に襲いかかってくるかもしれないのです。怯えないわけがありませんでした。
お館様のお言葉を伝える鴉は、お館様から新しいお達しが来るまで、動物たちは冬ごもりの支度や柱様へのお参り以外は出歩かず、家でおとなしくしているようにと言っていました。
お館様のお言葉は、森の動物たちにとっては絶対です。炭治郎と禰豆子も、次の朝には急いで冬ごもりの支度に取りかかりました。
洋服屋さんが別れ際にくれた食料のおかげで、支度は早く済みました。そこで炭治郎と禰豆子は、雪が降りだすまで毎日、一緒に水柱様の泉へお参りに行くことにしたのです。
水柱様へのお土産にと集めた木の実を泉に捧げて、炭治郎と禰豆子は心を込めてお祈りしました。
いつものように、助けていただいたお礼を言って、それから一心に祈ったのは、お互いの無事や善逸や伊之助の無事。それから、森の動物たちがみな無事であるように。そして、洋服屋さんのことでした。
きっと水柱様は、ほかの柱様と一緒に『災い』との戦いに赴くのでしょう。水柱様やほかの柱様のご武運を祈り、洋服屋さんにまた逢えますようにと、炭治郎と禰豆子は心の底からお祈りしました。
神様に願いを叶えてもらうには、対価を差し上げるか、いろいろな試練を乗り越えなければいけないことを、炭治郎と禰豆子はもう知っています。一所懸命集めたけれども、こんな大事なお願いの対価が木の実で大丈夫なのかはわかりません。それでも、炭治郎たちにできることはそれぐらいしかなかったのです。
だから毎日毎日、炭治郎と禰豆子は水柱様の泉へ行きました。
自分達ができることならなんだってします。だからどうか水柱様、ご無事で。そしていつか必ず、また洋服屋さんに逢えますように。
炭治郎と禰豆子はそう一心に、一所懸命に、お祈りしたのです。
ときどきは伊之助や善逸も一緒でした。みんな願いは同じです。乱暴者で礼儀知らずな伊之助も、臆病でいつだって大騒ぎして泣く善逸も、水柱様の泉に一心に祈りを捧げていました。
年が替わる夜はどんどん近づいてきています。もうあと三回、眠って起きたら新年。明後日の夜には『災い』の大群がキメツの森に襲いかかってくるでしょう。
今年の冬は友達や家族で集まって、大勢で過ごす者が多いようでした。それはそうでしょう。誰だって『災い』に一人怯えて過ごすのは嫌でしょうから。
炭治郎の家にも、今朝から善逸と伊之助が来ていました。もともと大家族だった炭治郎のお家は、善逸や伊之助が泊っても大丈夫なくらいには広かったので、炭治郎と禰豆子は喜んで二人を迎えました。
禰豆子と二人きりではちょっぴり広かったお家が、善逸たちが来てとても賑やかになりました。
洋服屋さんはずっと一人でいるのかな。悲しくないかな。寂しくなっていないかな。
窓の外に積もっていく雪を眺めながら、炭治郎は、洋服屋さんのやさしくて悲しくて寂しい匂いを思い出していました。
「雪、止まないね」
いつの間にか隣に来た禰豆子がぽつりと言うのに、炭治郎も小さく「うん」と答えました。
もっと雪が積もったら、森の外れの小さなお店に行くことはむずかしくなります。水柱様の泉へお参りに行くこともできません。
「なぁ、洋服屋さんが教えてくれた言葉、お前らちゃんと覚えてる?」
善逸もやってきて炭治郎たちに聞きます。炭治郎と禰豆子はもちろん! とうなずきましたが、伊之助はムッと唇を尖らせて、あんなもん覚えなくても大丈夫だとそっぽを向いています。
「お前には期待してなかったけど、ちゃんと覚えとけよなぁ。きっとなんか大事なことなんだからさぁ」
いつもならこういうとき、善逸はちょっと偉そうに言うのですが、今日は本気で伊之助を心配しているようでした。
「あんなごちゃくそしてんの覚えられっかっ!」
「どこがだよっ、そこまでむずかしくなかっただろぉ! 絶対に年が替わる夜までに覚えろっ!!」
真剣な善逸に、さしもの伊之助もちょっと気おされたのか、バツが悪そうにうなずいています。
それを見た炭治郎と禰豆子もクスリと笑いあって、善逸と一緒に、洋服屋さんが伝えてくれた呪文を伊之助に教えてあげることにしました。
その呪文を洋服屋さんが教えてくれたのは、最後のお遣いから戻った翌朝のことでした。家に帰る炭治郎たちに、冬ごもり用の食料を詰めた袋を持たせてくれた洋服屋さんは、炭治郎たちの前にしゃがみ込み、真剣な顔で言ったのです。
──お前たちが危険な目に遭うのを俺は望まないが、それでもお前たちはきっと、俺の願いとは反した道を進むんだろう。そのときに柱の加護が力を存分に揮えるよう、今から言う文言を重々頭に刻み込んでおけ──
「えっと、一二三四五六七八九十の十種の御寶……だったよね、お兄ちゃん?」
「うん。ほら、伊之助も繰り返してみろ」
「あぁん? ひふみ、よ……い? な……あーっ、知るかっ!」
「お前なぁ、そこでもう詰まるのかよ……」
禰豆子と炭治郎が促しても、伊之助はどうしてもなかなか覚えられないようでした。善逸も呆れ顔です。
「んなこと言ったってしょうがねぇだろっ!」
「もっと頑張って覚えろよっ、洋服屋さんがあんなに真剣に言うんだぜ? きっと覚えておかないとマズいんだって! だって、だってさぁ、年が替わる夜になったら……」
言葉を止めて、善逸はぶるりと体を震わせました。禰豆子も不安そうに炭治郎の腕にしがみつきます。伊之助も黙り込んでしまいました。
炭治郎はそんなみんなを見てもなにも答えられず、また窓の外に視線を向けました。
窓の外では雪がどんどんと積もっていきます。もしかしたら新年まで降り続けるかもしれません。
善逸の怯えはもっともで、禰豆子や伊之助も、その日のことを考えるとどうしても不安になるのでしょう。炭治郎だって同じことです。
雪が積もってしまえば、『災い』から逃げるのはむずかしくなります。深い雪は歩みを阻むし、足跡は『災い』に居場所を知らせてしまうのですから。家に隠れていたって、不安は消えないでしょう。『災い』は家のなかにも襲ってきます。炭治郎のお母さんたちだって、お家にいるときに襲われたのです。どこにも安全な場所なんてありません。
ほかの森の動物たちと違って、炭治郎たちには洋服屋さんがくれた柱の加護があります。けれど、それで助かるとは、炭治郎にも言い切れませんでした。たとえ柱の力を得た物を身に着けていても、『災い』を防ぎきれるかは誰にもわからないのです。
柱様でさえ『災い』に襲われ命を落とした方もいるのですから、ただの狐やねずみでしかない炭治郎たちなど、柱の加護を得ていても安心できるものではありません。
もちろん、柱様方はとっても強くて、炭治郎が生まれてから今まで、亡くなられた柱様はいらっしゃいませんでした。けれど、生まれる前にならば、炭治郎はお一人、『災い』によって命を落とされた方がいらっしゃったことを知っています。水柱様の姉上様である、先代の水柱様です。
もしも。もしも、今度の戦いで水柱様が姉上様のように、命を落とされたら……。
考えただけで炭治郎は、悲しくて苦しくて、泣き出したくなります。じっとしていられず、どうにかしてなにかお手伝いがしたいと、胸の奥には焦りがいっぱい生まれました。でも今の炭治郎に、いったいなにができるというのでしょう。炭治郎はただの子狐でしかないのです。どんなに柱様のお力になりたくとも、『災い』と戦うことなどできやしません。
せめて禰豆子たちの不安を払ってやらなくてはと、笑顔を作り禰豆子の頭を撫でてやったそのとき、コツコツと誰かが窓を叩く音がしました。
こんな雪の日に誰だろうと見れば、一羽の鴉が窓辺にとまっていました。お館様のお言葉を伝えに来る鴉です。
慌てて窓を開けると、冷たい風や雪とともに部屋に入ってきた鴉は言いました。
「オ館様ノオ達シデアルゥ! 森ノ動物タチハ須ラク明日ノ朝オ館様ノオ社二集ウベシィ!」
鴉が声高く言った言葉に、炭治郎たちは思わず顔を見合わせました。
「……もしかして、お館様のお社でみんなを守ってくれるのかなぁ!」
「社に動物全員なんて入れねぇだろ?」
期待を隠し切れずしっぽをピンと立てて言う善逸に対して、めずらしいことに伊之助はやけに慎重です。
でもたしかに伊之助の言うとおりでした。お館様のお社は人間もお参りに来るぐらい立派ですが、森の動物すべてを匿えるほどの大きさはありません。
それなのに動物たちを集めるのです。なにか直接仰りたいことがあるのかもしれません。
鴉はお館様のお言葉を伝えると、すぐにまた外へと飛んでいってしまいました。ほかの動物たちにも伝えなければならないので忙しいのでしょう。
「とにかく、お館様のお達しなんだから、行ってみるしかないよ」
「雪がやむといいよなぁ。あんまり積もってたらお社に行くのも大変だぞ」
「でも、洋服屋さんのおかげで今年の冬はあまり寒くないから助かったね、お兄ちゃん」
「どうなってやがんのかわかんねぇけど、マフラーだけでもすげぇあったけぇからな」
まだ雪がやむ気配はありません。もし朝まで降り続いたら、お社に行くのには時間がかかりそうです。炭治郎たちは明日に備えて早目に眠ることにしました。
不安は消えてくれそうにありませんでしたが、それでも、四人でくっついて眠ると、互いの温もりに安心してきて、炭治郎たちはいつの間にかぐっすりと眠っていたのでした。
雪は朝になっても降り続いていました。まだ幼い炭治郎たちは、積もった雪の上を歩くだけでも大変です。けれど、洋服屋さんの手袋やマフラーは、身に着けているだけでなぜだか体がポカポカとして、冷たい雪が降るなかを歩いても炭治郎たちは寒くありませんでした。
お館様のお社は、大きな大きなキメツの森の、ちょうど真ん中あたりにあります。お参りに来る人間たちは大変でしょうが、それでもお館様のご利益は苦労する甲斐があるとかで、訪れる人は絶えません。
年が替わる夜から新年にかけては、毎年多くの人間がやってくるのですが、今年は雪のせいで人はやってこれなさそうです。『災い』は人を襲うこともあるという話ですから、雪が降ったのはよかったのかもしれません。
炭治郎たちがお社に着いたころには、もう多くの動物たちが集まっていました。思ったとおり、人間の姿はどこにも見えません。
熊やリス、猿に山犬、ウサギなど、様々な動物がお社の前の広場にはいました。本当だったら今ごろはぐっすりと冬眠中の動物も、『災い』が襲ってくるのに眠っている場合ではないと、お社に集まってきています。
ざわざわと不安そうなざわめきが聞こえるなか、炭治郎たちも身を寄せ合って、お館様のお社をじっと見つめました。雪はまだ降っています。禰豆子の頭や肩に積もった雪を払ってやりながら、善逸がこそこそと言いました。
「これだけいたらお社には入れないよなぁ。だとしたらなんのお話だと思う?」
「うーん、わからないけど、お館様が俺たちのためにならないことを言うわけないから、『災い』から身を守る知恵を授けてくれるとかじゃないかな」
炭治郎が言うと、すぐ近くにいた鹿がフンと鼻を鳴らして話しかけてきました。
「そんな知恵があるなら、とっくの昔に仰ってるさ。でなきゃ俺の弟はなんで死んだんだ。身を守る方法があるのにむざむざ『災い』に殺されたなんて、俺の弟が浮かばれねぇよ」
吐き捨てるようなシカの言葉に、伊之助の後ろにいたモモンガも同意の声を上げました。
「まったくだよ。柱様が救けに来てくれるっていったって、間に合わないことだって多いんだから。もしそんな知恵を授けてくれるためだって言うなら、お館様は死んだ奴らを見殺しにしてきたってことじゃないか。今さら過ぎるよ」
大人たちの言葉に、炭治郎はしゅんと俯きました。
炭治郎と禰豆子のお母さんたちが『災い』に殺されてしまったように、ここにいる動物たちのなかには、家族を『災い』に奪われた者もたくさんいるのでしょう。
なんて考えが浅いんだろう。俺が余計なことを言ったばかりに、お館様への疑いの言葉を言わせてしまうなんて。お館様や柱様たちに申し訳なくて、炭治郎は少し落ち込んでしまいました。
「炭治郎ぉ、気にすんなよ。お館様ならなんかすごい知恵を出してくれるんじゃないかって、俺も思うもん」
「そうだよ、お兄ちゃん。あまり気に病まないで」
「あっ! 社の戸が開くぞ!」
伊之助の声に炭治郎たちが顔を上げると、お館様のお子様たちがゆっくりとお社の戸を開いていくのが見えました。
「よく集まってくれたね、私のかわいい子供たち」
大きく声を張り上げたわけでもないのに、お館様のお声はよく通り、途端に辺りは静まり返りました。
動物たちは一斉に、祈るように手を組んだり頭を下げたりして、お館様への敬意を示しています。不満げだったシカやムササビも、畏まってお館様を見つめていました。
口では文句を言っても、みなお館さまへの信頼は厚いのでしょう。炭治郎たちも気づけば頭を下げていました。
炭治郎はお館様にお逢いするのは初めてでしたが、そのお声を聞いた瞬間に、ふわふわと頭のなかが揺れるような心地がして、なんだかとても心が浮きたってきます。
けれどその頭も、続いたお言葉に思わず上がって、炭治郎は繋いだ禰豆子の手をギュッと握りしめました。
「もうじき『災い』の首魁、鬼舞辻無惨がこのキメツの森を襲うことは、もうみんな知っているね?」
息を呑んだ炭治郎の胸は、不安にドキドキと音を立てました。禰豆子の手も小さく震えています。善逸や伊之助も、大人の動物たちも、炭治郎たちと同じように、不安を隠し切れずにいるようでした。
「『災い』の恐ろしさはみんなもよくわかっているだろう。その首魁である鬼舞辻無惨はとても強くて狡猾だ。おそらくは、年の替わる夜に襲ってくるのは手下の『災い』だけで、無惨は安全な居城にこもって高みの見物をするつもりだろうね」
お館様の声はやさしくて穏やかなのですが、お言葉の内容は恐ろしく、動物たちはみんな震えあがりました。
「もちろん、柱たちは君たちを守るために戦う。今の柱たちは歴代最強だと私は信じているよ。だからきっと、無惨以外の『災い』なぞに後れを取ることは決してないだろう。それに、無惨を討ち取る手立てもすでにわかっている。無惨は闇の生き物だ。多くの『災い』と同じく日の光を嫌う。強い天の力を持つ新年のご来光を浴びせさえすれば、無惨であっても塵となり、跡形もなく消え失せる」
お館様のお言葉にワッと湧いた安堵のざわめきも、続いたお言葉を聞いた途端に、落胆の溜息に変わりました。
「けれど、無惨を倒すには、柱たちの力だけでは果たせないんだよ」
とても強くて不思議な力を揮える柱様たちでさえ敵わないというのなら、力もなく弱い自分たちに、いったいなにができるというのでしょう。なす術なく殺されてしまうよりほかないのでしょうか。
「そこで君たちに私からお願いがあるんだ。無惨の居城である無限城は、私でさえ破れない強い結界に守られている。神である私や柱たち、またその眷属では、無限城には入れないんだ。無惨にとっては餌でしかない動物でなければ、無限城は決して侵入を許さない」
お館様のそのお言葉に、炭治郎の胸がドキンと大きく鳴りました。禰豆子の手を握る手にも力がこもります。しっぽが興奮にふくらんで、我知らずユラユラと揺れました。炭治郎をじっと見つめる禰豆子の視線にも気づきません。
炭治郎はドキドキとしながら、お館様のお言葉の続きを待ちました。聞き漏らすまいと大きな耳はぴくぴく震えて、耳飾りが小さく揺れています。ほかの動物たちが不安と怯えで騒めくなかで、炭治郎だけは、大きな赫い瞳をきらきらと輝かせて、一心にお館様を見ていました。
「私のかわいい子供たち……このなかに誰か、無限城に入る勇気のある者はいるかい?」