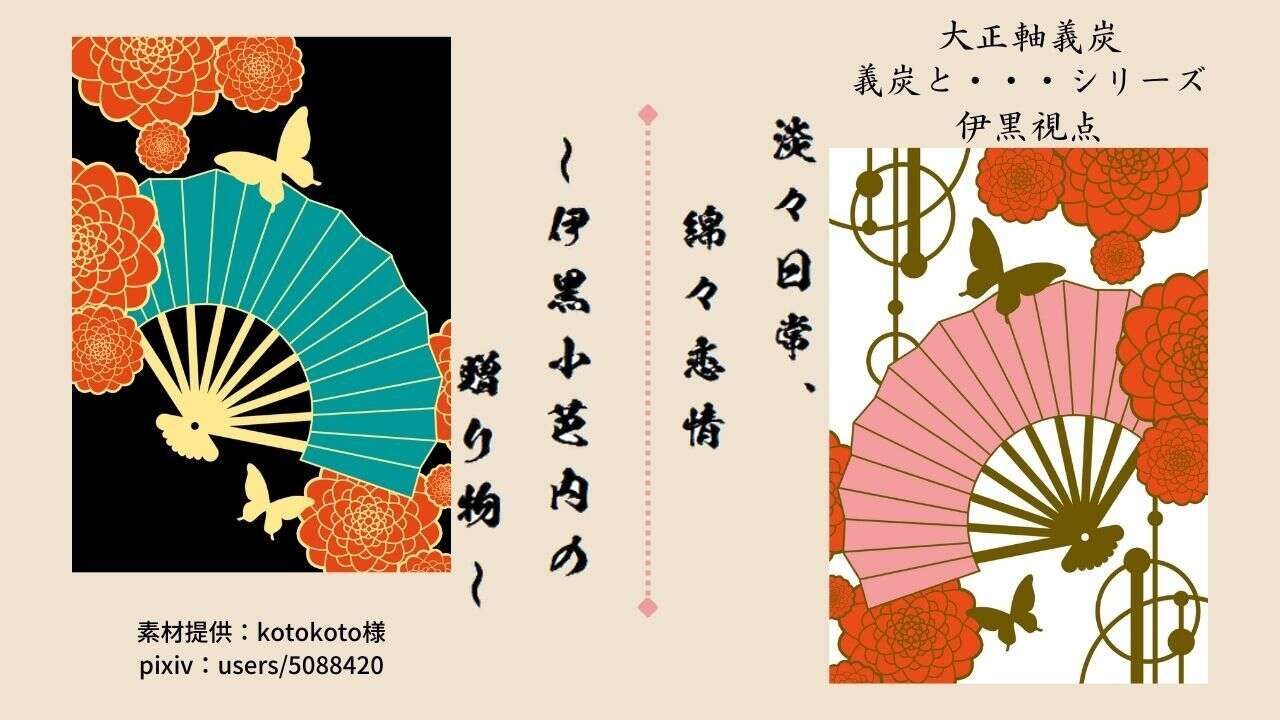青天の霹靂という言葉がある。文字通りに解するなら、よく晴れた青空にとどろく雷だ。もちろん、そんなことはめったに起きるものではない。誰もが予想していないからこそ、転じて思いがけない突発的な事変という意味を持つ言葉だ。
だから伊黒がとっさにその文言を思い浮かべたのはおかしくない。それはまさに、誰もが予想もしない事態だったに違いないのだから。
事の起こりは、臨時の柱合会議という名目でのお館様の集合命令だった。
鬼の出現は、現状、途絶えている。とはいえ、平穏な日々などと楽観する輩は、鬼殺隊にはひとりもいないだろう。嵐の前の静けさでしかないのは言うまでもない。積年の悲願を果たす日が近いことは、伊黒ならずとも、大なり小なり鬼殺隊の者ならば誰しも感じ取っているはずだ。
怠惰に過ごす時間など一秒たりとない。むしろ焦りさえ感じながら、下級隊士たちはこぞって技量や体力の底上げと痣の発現を目指して、柱稽古に臨んでいる。落後者が皆無とは言いがたいが、それでも誰もが懸命に鍛錬に励んでいることは、いかに皮肉屋な伊黒であっても認めざるをえない。
柱であっても同じことだ。万が一に備えて担当地区の警邏は怠れないし、柱も痣の発現を目指しそれぞれ鍛錬も行っているが、現在のところ主な任務は隊士たちの強化である。
そんななかでの臨時の会議だ。鬼舞辻の情報が入ったか、いざ決戦のときかと、奮い立った者は多かろう。伊黒も例外ではなかった。
いつものように鏑丸を伴い伊黒が産屋敷家に駆けつけたときには、すでに柱たちはほぼ揃っていた。庭に集う面々に視線を走らせた伊黒は、すぐに眉をひそめた。
屋敷に集まった顔ぶれには、今や「元」柱となった宇髄も含まれていたが、反して、現役の柱はひとり足りない。到着が遅れたこともあり、おそらくは自分が最後だろうと思っていただけに、正直なところ安堵したのは確かだ。だが、遅れている相手が相手である。たちまち伊黒の機嫌は地を這った。
招集された理由は告げられてはいない。ただの報告会である可能性もある。それでも、鬼狩りの任についている最中でもないというのに、柱が遅刻するなどもってのほかだ。
思わず舌打ちしそうになった伊黒の頬を、少しばかり気遣わしげに鏑丸がなめた。促す気配に視線をやれば、甘露寺がヒラヒラと手を振っている。伊黒は知らず目元をやわらげた。
胡蝶と話していたらしい甘露寺は、いかにもうれしげに笑っている。その姿を瞳に映しているだけで、伊黒の胸はほわりと温かくなる。今日も甘露寺は誰よりも愛らしい。見つめるだけでささくれ立つ心が癒やされていくのを感じる。
だがやはり、無責任な同僚への不快感は拭い難い。遅れてきた自分でさえ腹立たしく感じるのだから、短気な不死川の憤りは爆発寸前であるようだ。
「冨岡の野郎、まだ来やがらねぇのか。たるみ過ぎだァ」
いきり立つ不死川は、不機嫌さを隠しもしない。舌打ち混じりの言には伊黒もまったく同感だ。柱の自覚が足りないと常々から苦々しく思っている相手だけに、伊黒も冨岡に対する怒りの沸点は低い。
「柱合会議に遅刻するなんて……冨岡さん、お腹でも壊したのかしら」
あんな協調性皆無の輩のことすら心配する甘露寺は、本当にやさしい。思わず白布の下で唇が弧を描いたが、正直なところ同意は致しかねる。ついでに甘露寺に心配させる冨岡への苛立ちも増した。
いくらなんでも、腹痛ぐらいで柱合会議に遅れるような阿呆は柱にはいない。とは、言わないでおく。甘露寺の思いやりに水を差すなど、伊黒にしてみれば言語道断である。
とは言うものの、そろそろ指示された時刻になる。いかに冨岡だろうと、さすがに柱合会議をすっぽかすような真似はするまいと思っていたが、冨岡が現れる気配はいまだない。穏やかな悲鳴嶼や他人への関心が薄い時透の表情にも、怪訝そうな色が浮かびだしていた。
「冨岡さんの鎹鴉は高齢ですし、連絡が遅れたんでしょうか」
「そりゃねぇだろ。たしかにあの爺さん鴉は多少ボケちゃいるがな。だが伝達がうまくいかないほどじゃねぇだろうよ」
胡蝶と宇髄の会話に、甘露寺がますます心配げに顔を曇らせている。やさしい甘露寺のことだから、冨岡だけでなく鎹鴉のことも案じているのだろう。まったくもって腹立たしいやつらだ。甘露寺に心配をかけるなど極刑に値する。
君が気にすることはないと、甘露寺を慰めるために伊黒が足を踏み出しかけたそのとき、座敷のふすまが開いた。姿を現したのは予想通り、お館様の奥方であるあまねだ。
「皆様お集まりのようですね」
「恐れながらあまね様、冨岡義勇がまだ到着しておりません」
「かまいません。今回の柱合会議は、最初から冨岡様は招集していないのです」
恐縮した悲鳴嶼の訴えに返されたあまねの言葉に、柱たちにわずかな動揺が走った。瞬時に脳裏に浮かんだのは、以前にもあった冨岡不在の折での一件である。
冨岡を笑わせる。いかにお館様のお望みであろうとも、あれは返すがえすも無理難題だった。散々苦労したわりに実りはなく、徒労極まりなかったのを誰しも忘れていまい。
いや、甘露寺と時透はその限りではないかもしれないけれども。
だが、まさか再び冨岡絡みで無理難題を持ちかけられるわけもなかろう。伊黒はそう思ったし、きっとほかの柱たちだって同じことを考えたはずだ。たとえそれが「あるわけがない」という確信ではなく「あってほしくない」という願望でしかなかったとしても。
そんな一同の期待は、あまねから告げられた一言で打ち砕かれた。その瞬間に脳裏に浮かんだのは「は?」という一音であったし、一様に浮かべた表情は鳩が豆鉄砲を食ったようとしか言えない。
それはまさしく青天の霹靂ともいうべき指示だった。伊黒にしてみれば、晴天に雷が鳴るよりも遥かにタチが悪い不測の事態である。いっそ真夏に猛吹雪が吹き荒れるぐらいの思いがけなさであり、かつ、なんでそんなことをと、不遜を承知でお館様にもの申したくなるほどには。
「冨岡に祝いの品……か」
「冨岡さんと炭治郎くんがおつきあいしてるだなんて素敵だわぁ!」
一同を混乱に落ち入れたあまねが立ち去ったあと、座敷に残された者たちの顔には、疲労感や困惑が漂っていた。伊黒も例外ではない。そんななかで甘露寺だけがひとり楽しげだ。
みな一様に疲れ顔で、悲鳴嶼もさすがに困惑を隠しきれない様子だし、いつも笑みを絶やさぬ胡蝶でさえも、時透ばりに死んだ目をして虚空を見つめている。宇髄は諦めに似た苦笑しきりだ。不死川に至っては、憤死しそうな勢いでギリギリと歯ぎしりしつつ肩を震わせていた。
伊黒も不死川と大差はない。なんでそんな馬鹿馬鹿しいことをしなくてはならないのか。いっそ俺はごめんこうむると立ち去ってしまいたいのが本音である。
「やっぱりお館様は素晴らしいわっ。みんなのことをちゃんと見守ってくださってるうえに、お祝いまでしてくださるなんて! 私も冨岡さんと炭治郎くんには絶対に幸せになってもらいたいわぁ。お祝いを任されたからには、絶対に喜んでもらえるものを選ばなくっちゃ」
こんな空気のなかでもひとり同僚を寿ぐ甘露寺は、やっぱりやさしい。素晴らしいのはそんな君のほうだと誇らしくもなる。けれど、どうしても同意はできかねる。というか、いかに甘露寺が楽しそうであっても、一緒に喜んでやるにはあまりにもくだらない。くだらなすぎる。ぶっちゃけ、冨岡の色恋なんぞどうでもいい。
「冨岡さんとおつきあいして楽しいのかな。あの人置物みたいだし。炭治郎つまらなくないのかな」
「俺なら派手にごめんだが、おしゃべりで陽気なのと無口で陰気なので、似合いっちゃあ似合いかもしれねぇぞ? 割れ鍋に綴じ蓋って言うしよ」
「くっだらねェ! お館様もなにを考えてらっしゃるんだァ? そんな腑抜けたことしてる場合じゃねぇだろうがァ!」
「同感だ。惚れた腫れたなぞにうつつを抜かす暇があるなら、痣の発現に尽力すべきだというのに、柱が聞いて呆れる。だいたい、浮世のことなど預かり知らんと言わんばかりの態度でいるくせに、なんなんだ、冨岡のやつは。ああいうのをむっつりすけべと言うんだ。くだらない、じつにくだらない」
一同の言に苦笑しつつ、悲鳴嶼がなだめるように口を開いた。
「ともあれ命には従わねばならんだろう。だが……なにを贈れば冨岡が喜ぶのか。さて、さっぱりわからんな」
「色惚けさんはなんだって喜びますよ。どうせお互いしか目に入っちゃいないんです。なに贈ろうとイチャつく口実になるだけなんですから」
抑揚のない声で言う胡蝶に、おや? と視線を向けた伊黒は、思わずビクリと肩をはねさせた。
……なんだか、胡蝶がやけに怖い。胡蝶が座る一角だけ、空気が暗く凍りついている気さえする。伊黒が固まっていると、鏑丸がしゅるりと懐に逃げ込んだ。どうやら鏑丸も誇張の発する不穏な空気を察したらしい。野生の本能だろうか。
「俺は降りるぞ。誰か適当に買ってこいやァ」
「僕も。贈り物なんてしたことないもの」
端から投げやりな胡蝶は論外として、さっさと戦線離脱を宣言した不死川や時透に、伊黒が続きそこねたのは、怯えきった様子の鏑丸をなだめるのに気を取られていたからだ。冨岡と馬があわぬ自分に話を振ってくる者がいるとも思っていなかった。こういうことはお祭り騒ぎ好きな宇髄あたりが引き受けるだろう。そう楽観もしていた。
宇髄ならば嫁もいることだし、柱稽古はまだしも警邏の任からは外れている。ほかの柱に比べれば少なからず暇も見つけやすかろう。きっと伊黒だけでなく、ほとんどのものがそう考えていたに違いない。だから、まさか当の宇髄が
「派手にいっちょ俺さまが選んでやってもいいが……恋愛ごとなら甘露寺に任せるのが適任じゃね?」
などと言い出すとは思いもしなかったし、ましてや任命された甘露寺が張り切った顔で
「はい! 私と伊黒さんに任せてっ!」
なんて応えるだなんてこと、伊黒は誓って予想もしていなかった。
めったにない晴天に轟く雷が、立て続けに鳴り響くなど誰が思うものか。
よもやよもやだ……。
今は亡き友の声が頭に響くぐらいには放心したし、柱としては不甲斐ないことに、とっさには応える言葉も見つからず。
かくして、悲鳴嶼の「では甘露寺と伊黒に頼むとしよう」との言葉で、はた迷惑極まりない柱合会議はなし崩しに終わった。
「ね、伊黒さんはなにがいいと思う? ふたりお揃いのものなんてどうかしらっ。身につけられるもののほうがいいかしらね」
ほんのりと頬を紅潮させてウキウキとした声で問いかけてくる甘露寺に、笑い返してやることもできず、伊黒は居心地悪く視線をそらせた。君に任せるとつぶやいた声が、憮然としているように思われてなければいいのだが。まぁ、無理だろう。
冨岡や竈門への贈り物選びという目的に、興味や熱意などかけらも持ちようがない。なんでこんな馬鹿馬鹿しいことを、冗談じゃないぞと、腹立たしくもある。けれどもそっけない一語に含まれた響きには、そんな苛立ちよりも狼狽のほうが色濃かった。
甘露寺とふたりきりで買い物という事態には、戸惑いとともにソワソワとした喜びも感じるのは確かだ。とはいえ、ふたりで食事をすることはままあれど、こんなふうにまるで逢い引きする恋人同士のように街なかを歩くことなどなかったものだから、どうにも緊張が拭えない。
甘露寺のさっそく今から行きましょうとの誘いを、伊黒が断れるわけもなく。さりとてふたりきりはたぶん間が持たない気がして、退散しようとする不死川を捕まえて一緒に来てくれと頼んだのだが
「あぁ? なんで俺を巻き込もうとしてやがんだっ。俺はごめんだって言っただろうがァ!」
「俺だって冨岡なんぞにやる品を選ぶなんて冗談じゃない! だが、甘露寺が張り切っているんだぞっ、断れるわけがないだろう!」
「選ぶのは甘露寺に任せときゃいいじゃねぇかっ。テメェは荷物持ちしときゃいいだろ!」
「貴様は馬鹿か? 馬鹿なのか? 思いやり深くて頑張り屋な甘露寺が、同僚への贈り物を自分勝手に選ぶはずがないことぐらい、わかりきっているだろう! 俺にも意見を求めるに決まっている!」
「なら相談に乗ってやりゃいいだけだろうがァ! そんだけ甘露寺が気になんなら待たせてんじゃねぇよ!」
「待たせたくないから、さっさとついてきてくれと頼んでるんだろう! 贈り物なんか甘露寺に靴下をやったことしかないんだぞ! 俺に相談されても答えられるわけがないだろう!」
最後にはほとんど悲鳴じみた懇願になったけれど、それでも不死川は、まぁ頑張れやと肩を叩くだけでつきあってはくれなかった。薄情者め。
一番気心が知れていると思っていた不死川でさえそんな具合だ。ただでさえつきあいの悪い時透には頼れるわけもなく、年下に頭を下げるのもなんとなく癪に障る。悲鳴嶼はお館様からまだ話があるとかで呼ばれていってしまったし、宇髄はどこか面白がってるような人の悪い顔で、ニヤニヤとしているばかりだ。
胡蝶には……なんとなく、声がかけられなかった。誘ったが最後、猛吹雪のなかに素っ裸で放り出されるがごとき目に遭う気がする。誘ってきたら殺す。そんな圧を笑顔から感じるのは、たぶん気のせいじゃないだろう。野生の本能は自分にもあるのかもしれない。
ともあれ、ぐだぐだとして甘露寺をこれ以上待たせるなど論外だ。しかたなく連れ立ってお館様の屋敷を出たが、どこに向かえばいいのかすら伊黒にはわからない。
食事をともにするのはいい。幸せそうに食べる甘露寺を見ているだけで、心弾むし癒やされる。会話だってあれも食べるか、これも頼もうかと、勧めてやるだけで済む。たまに相談にのることもあるが、隊士として柱としての相談ばかりだったから、真摯に答えてやることもできた。
けれど今回はどうにも勝手が違う。普通の暮らしなどしたことがない自分に、恋仲となった者たちへの祝福の品など、選べるわけもない。そんなもの、伊黒のはばかられるばかりの人生において、一度として目にしたことなどないのだ。ましてや相手はあの冨岡と竈門だ。意見を求められたところで甘露寺を落胆させるのは目に見えている。
いったいどうしてこんなことになってしまったのか。考えれば考えるほど、同行してくれなかった不死川たちはもとより、こんなことをお命じになったお館様にまで、ついつい文句をつけたくもなる。とくに、元凶である冨岡たちへの憤りは深い。
そもそもあいつらが、大義を前にして色恋なぞにうつつを抜かすのが悪いのだ。自分の恋心はとりあえずおいておく。今生では叶えるつもりもない片恋だ。想うだけでいいのだ。報われたいなど、こんな汚れた血の流れる身では願えるわけもない。
傍らに甘露寺がいるというのに、うっかり鬱々とした思考に流れかけた伊黒は、不意につんと引かれた袖に気づき、慌てて甘露寺へと視線を向けた。
「……誘っちゃって迷惑だったかしら。ごめんなさい、伊黒さん。伊黒さんの都合も聞かずに私ったら、ついはしゃいじゃって……あのっ、やっぱり贈り物はひとりで探してくるわっ。冨岡さんたちに喜んでもらえるよう、頑張って探してくるね!」
空元気が目に見えるような笑みに、伊黒の胸がギュッと痛んだ。いつだって甘露寺は、明るくて気遣いを忘れない。ちょっとずれたところはあるけれど、いつでも人のことを思いやっている。こうして上の空でいた伊黒にも、ちゃんと聞けなどと怒ることなく、逆に気遣ってくれる。
あぁ、本当に、君はかわいくて、やさしい。
鬼を狩る鬼殺隊士の頂点に立つ柱でありながらも、恨みつらみなど甘露寺のやさしい心には存在しない。鬼殺隊に入隊した動機は、まぁ、少々理解しがたくはあるけれど。だがそんなのは些細なことだ。甘露寺が傷つきながらも刀を振るうその原動力はやさしさだと、疑うことなく信じられる。
恨みや憎しみではなく、罪なき人を食らう鬼への怒りや悲しみで、彼女は戦うのだ。鬼への、母や親族への、恨みを抱えて生きる自分とは、こんなにも違う。同じ柱である冨岡の得た幸福を、祝福してやることなど考えてもいなかった自分には、眩しいほどに。
今は亡き、炎柱――煉獄もそうだった。
前炎柱である煉獄槇寿郎に救われ、一時身を寄せた炎屋敷で、初めて接した自分以外の男の子。ともに過ごした時間は少なかった。基本的な体力がつくまで世話になったそのころには、まだ、槇寿郎の奥方も床に就いていることが多かったとはいえ存命で、伊黒をよく労ってくれたものだ。槇寿郎もまた、円熟期を迎えた堂々たる炎柱で、ときおり暗い面持ちで考え込んでいる様子を目にしたことはあるが、尊敬すべき剣士であり、初めて知る父という存在を感じさせてくれた。
やさしく聡明な母、強く頼りがいのある父。愛らしい弟。伊黒には到底望めない『普通』の家族のもとで、朗らかに思いやり深く育った、自分とさして変わらぬ歳の少年。それが煉獄杏寿郎だ。
嫉妬はなかった。嫉妬するにはあまりにも彼と自分は違っていた。
眩しくて、眩しくて、あんまり眩しくて。伊黒には、こんなふうになりたいと願うことさえできなかった。柱となるべく生まれついたような煉獄は、卑屈な思いすら伊黒に抱かせることはない。
ともに頑張ろうと笑う煉獄には、裏表などまるでなかった。心から伊黒に笑いかけてくるし、心の底から伊黒の境遇を悲しんでくれる。同情し憐れまれるだけなら反発したかもしれない。けれど煉獄は、伊黒の生い立ちをただ悲しみ、鬼に怒り、二度と悲劇が繰り返されぬようにと己を鍛えるばかりだった。
炎の呼吸は伊黒の体質にはあわず、水の呼吸の育手の元へ居を移すまで、煉獄家の人々は伊黒を家族同然に扱ってくれた。感謝は尽きない。その後も伊黒を気にかけてくれていた煉獄家の面々は、やがて伊黒の知る穏やかで慈しみに満ちた姿からは離れていってしまったけれど、煉獄は変わらなかった。
そうか。甘露寺は、ほんの少し煉獄に似ているのだ。
性格や容姿ではなく、刀を振るう原動力たるやさしさが、ほんの少し……似ている。
伊黒は初めて気がついたそれに、わずかに目を見開いた。
恨みや憎しみではなく、煉獄も甘露寺も、人を守るためだけに戦う者だ。そこには虚栄心など微塵もなく、ただひたすらに、真摯に、他者の安らぎを、平穏を願って、刀を振るう。汚れきった血を持つ、恨みに満たされた自分には、それがただ眩しかった。
容貌の優れた女性なら、いくらでも出逢った。親族のなかにも整った容姿の者はいた。けれども伊黒は美しいと思ったことなど、一度もない。
美しい人だと伊黒が初めて思ったのは、煉獄の母の瑠火だ。けれどもそこには、甘露寺に対するようなときめきや恋慕はなかった。初めて触れる『母』という存在。それが瑠火だ。実の母は伊黒の飼い主であり監視者でしかなかった。厳しくもやさしい慈しみを、無条件に与えてくれた女性は、瑠火が初めてだったのだ。
隊士を目指して育手のもとで修行する日々のなかで、出逢った隊士志願の少女はいくらかいた。可愛らしい容姿の子だってもちろんいる。けれども、どんな子も抱く恨みや憎しみは、隠しようがない。伊黒と同じく、暗く燃えた瞳をしていた。
微笑みを絶やさぬ胡蝶であっても同じことだ。笑っていてもときおり暗い陰りが瞳をよぎるのを見た。鬼殺隊に入り、年若くとも柱にまで上りつめるからには、苦労もしたことだろう。才能や素質の違いはあれど、多くの隊士と胡蝶もまた抱えるものは変わりない。それはすぐに感じ取れた。
甘露寺だけだったのだ。暗い負の感情に苛まれ、消えることのない憎しみを抱くことなく、それでも笑顔を絶やさぬ『普通』の、けれど誰よりもやさしく強い心根の少女など、伊黒は甘露寺しか知らない。
「迷惑でなどあるわけがない。すまない、甘露寺。……俺は、人に贈り物などろくにしたことがない。役に立てるかわからなくて戸惑っていただけだ。君が悪いわけじゃない」
どうか、甘露寺の耳にやさしく響くといい。胸に秘めた想いは伝わらずとも、煉獄家の人々が教えてくれた……そして、甘露寺が与えてくれた誰かを想うというやわらかな心で、彼女には接していたかった。甘露寺には、誰よりもやさしくしたいのだと願う本心は、届かずともいいから。報われるつもりはないけれど、甘露寺の記憶のなかでだけは、自分というこの汚れた存在も、やさしくあってくれたなら。それだけを、伊黒は願う。
まだ少し心配げな甘露寺の頬を、シュルリと顔を寄せた鏑丸が小さくなめた。
「ほら、鏑丸もそのとおりだと言っている」
「……そっか。よかった! 伊黒さんに迷惑をかけて嫌われちゃうなんて悲しいもの」
君を嫌うなんて、天地がひっくり返ろうとあるわけがないのに。
「鏑丸くん、くすぐったいよ」
うふふと笑いながら首をすくめる甘露寺に、鏑丸が親しげに身を擦り寄せている。伊黒の気持ちに寄り添ってくれる鏑丸は、甘露寺への好意を隠さない。楽しげなひとりと一匹の戯れは、在りし日の煉獄家を思い起こさせた。
一家の団らんをひっそりと見つめる伊黒に気がつくのは、いつも瑠火だった。こちらへと差し伸べられる手に戸惑う伊黒の手を引くのは、いつだって煉獄だ。槇寿郎がやさしくうなずき、幼い千寿郎が笑いながら小さな手を伸ばしてくる。温かな家族の光景のなかに受け入れられる泣きたいような喜びを、一度も伊黒は言葉にはしなかったけれど、彼らは知っていてくれただろうか。
「鏑丸、そこらでおしまいだ。戻れ。そろそろ買い物に向かわなければならないだろう」
「あ、そうね。早くしないとお夕飯の時間になっちゃう」
少し慌てた様子で言って、甘露寺は笑った。ほんのりと頬を染め、照れくさそうに笑いながら、甘露寺は名残惜しげに鏑丸をなでた。
「あのね、伊黒さん、よかったら……えっと、お買い物のあとで一緒にご飯をたべない?」
伊黒さんと一緒のほうが楽しいし、ご飯もおいしく感じるから。そう言って、甘露寺は朗らかに笑う。
「……それなら、食事処が多い場所で買い物もしたほうがいいな。買い物にどれぐらい時間がかかるかわからない」
断るという選択などあるわけもなく、伊黒も少しばかりの照れくささを押し隠して言った。人よりも多く食事を摂る必要がある甘露寺を、空腹のまま過ごさせるわけにはいかない。
「だったら日本橋はどうかしら! あのね、婚礼のお祝いだったらお箸も素敵かなぁと思ったんだけど、夫婦箸じゃ炭治郎くんのが女の人用になっちゃうし、身につけられるもののほうがいいかなとも思うの。それでねっ、日本橋だったら永代通りにうちでよくお買い物してる榛原ってお店があって、扇子とかも扱っててね、とっても素敵なの! 榛原ビルヂングの近くにある焼き鳥屋さんとかおまんじゅう屋さんも美味しいのよ。どうかしら」
冨岡と竈門ではいくら恋仲だといえど婚礼祝いはどうなのか、とか。扇子はたしかに縁起物ではあるけれども、婚礼にはよろしくないんじゃなかったか、とか。そんなことは些細なことだ。
「日本橋の榛原というと、正岡翁の句にもある紙屋だったな。たしか……『はい原の団扇を送るたより哉』だったか? 食事は、それじゃあ君がおすすめの焼き鳥屋にしよう」
ふと思い浮かんだだけで特に意味もない言葉だったが、甘露寺はパァッと顔を輝かせた。
「さすがだわ、伊黒さん素敵! 榛原にはお母様と一緒によくお買い物にも行ったけど、俳句にもなってたなんて全然知らなかったわ。伊黒さんは博識なのね」
ニコニコと頬染めて褒め称えてくれる甘露寺にはなんの衒いもない。あんまり素朴に喜んでくれるから、伊黒の頬も知らず淡く色づいた。
「たまたまだ。そんなに褒められるようなことじゃない。それより急がないと日が暮れてしまう」
気恥ずかしさを隠すように幾分早口で告げて、伊黒は列車に乗るために駅に向けて歩きだした。数歩も行かぬうちに立ち止まり振り返る。
「甘露寺、行こう。案内してくれ」
「はいっ!」
輝くような眩しい笑顔で応えて、駆け寄ってくる甘露寺が、ただ愛おしかった。
「扇子?」
「文句でもあるのか? 末広なら祝いにちょうどいいだろう」
怪訝な顔で小首をかしげる冨岡に、伊黒はふんっと鼻を鳴らして尊大に言い捨てた。文句など言わせてなるものか。
ふたり肩並べて選んだ扇子は、なかなか甘露寺の眼鏡にかなうものがなく。お得意様である甘露寺家が相手ということで、甘露寺が選んだ千代紙を使っての特注品となった。臨時の柱合会議から一週間。できあがった扇子を受け取りに再びふたりで向かった日本橋。一度目よりは緊張は減ったが、それでもなんだかちょっと面映い外出となった。
ふたりで他愛ないことを語らいながら通りを歩き、ときどき居並ぶ店先をひやかす。それはまるで恋仲同士の逢い引きのようで、心弾みつつもほのかに切ない時間だった。
そんな道行きのなかで、ふと、冨岡も同じだろうかと思ったのは、我ながらガラにもない感傷でしかない。
世の不幸を一身に背負ったような辛気臭い顔をして、誰とも関わらずに背を向けていた冨岡にも、自分と同じ喜びや切なさが胸にある。恋を、誰かを狂おしいほどにやさしく愛おしむ心を、あの男も抱えているのだ。
それはなんだか不思議な感慨であり、馬鹿馬鹿しいほどに感傷的な共感だ。
そして、甘露寺とともに揃いの扇子を携えて赴いた水屋敷で、伊黒を迎えた無愛想な男の顔は、以前とは少しばかり違って見えた。
排他的な陰りはわずかにやわらぎ、暗く沈んだ瞳にはほんの少しではあるが感情の光が見て取れる。
恋をしているのだ。改めて見やった冨岡の顔は相変わらず表情がないくせに、それでも隠しきれない喜びが漂っていて、幸せであることは疑いようがなかった。
冨岡は、きっと死ぬまで己の不幸に閉じこもっているつもりなのだろう。
伊黒は、ずっとそう思っていた。
悲しみと憎しみにとらわれているのは同じでも、縛りつけられまいとみなあがいているというのに、こいつは自ら不幸に閉じこもっている。そう感じていた。
だから伊黒は冨岡が嫌いだ。
宇髄だって生まれ育ちは過酷だが、暗い顔をしない。怒りや悲しみを抱えていたとしても、胡蝶は笑みを絶やさず穏やかだ。不死川だって己の感情に正直に、怒りを露わにする。時透も以前に比べると表情はやわらかくなった。
けれども冨岡だけは、己のなかに閉じこもり、自分だけが不幸であるかのような顔をする。それが腹立たしくてたまらなかった。煉獄家に救われずにいたら、もしかしたら自分も冨岡のように、不幸の檻に閉じこもっていたのかもしれない。そんなことを思わせるから、冨岡に苛立ちを隠せなかった。
たぶん、お館様は正しかったのだ。同じように無表情でいても心配ないと判じたとおり、時透は自ら感情を思い出したのだろう。だがきっと、冨岡は、誰かが無理矢理にでも扉を開かなければならなかったのだ。頑なに自ら閉じこもった男に手を差し伸べ、明かりの下に引きずり出したのが、竈門というわけだ。笑いながら伊黒の手を取り、温かな場所へといざなってくれた煉獄のように。
おしゃべりで陽気なのと無口で陰気なの。割れ鍋に綴じ蓋。なるほど、宇髄の言は言い得て妙だ。ピタリと噛みあって、補いあう、それがこいつらの恋なのだろう。寿いでやるには苛立たしさが先に立つが、少しは嫌味を控えてやってもいい。
お館様が案じるほどに、罪人然として不幸に自らとらわれていた同僚の、ようやくの解放を、ほんの少しぐらいなら喜んでやっても罰は当たるまい。
「……なんで、菊?」
「縁起がいいだろうが。貴様、甘露寺がきれいだと選んだものに文句をつける気か?」
そう、嫌味ではない。他意もない、と、言い張るつもりは満々だ。重陽はちゃんと縁起物だ。男色にかけたわけじゃない。甘露寺が選んだのだから、そんな下衆な思惑などあるわけがないのだ。
赤と黄の揃いの扇子に散る菊花に、なんとはなし在りし日の炎柱を思い出したのは、たぶん自分だけじゃなかっただろう。手にした二枚の千代紙に、甘露寺の目がほんのわずかに潤んだその意味は、きっと自分と同じだったはずだ。
互いに思い浮かべたのは、明るく雄々しく、誰よりも心が強かった男。柱を体現したような彼の人も、おそらくはこのふたりを寿ぎたいと望むだろう。だからこれでいい。
二本の扇子に顔を輝かせる竈門は、模様や色味に頓着した様子はない。自分たちの仲が祝福されていることだけを喜び顔をほころばせ、いかにも幸せそうに笑っている。複雑そうな空気をまとわせた己の伴侶の様子にも、気づいてはいないようだ。情けなく眉尻をわずかに下げた冨岡に気づいて、溜飲を下げているのは伊黒ひとりである。
素直に喜びを露わにする竈門に、甘露寺もうれしそうだ。キャッキャと竈門とふたりで笑い声を立てている。ちょっとばかり癪ではあるが、どうやら甘露寺と竈門はそれなりに気があうらしい。日本橋での会話でも、一緒に料理をしたとかなんとか甘露寺が言っていた。
ついでに、伊黒さんも今度よければ食べてくれる? 頑張っておいしく作るから。なんていう舞い上がりそうな申し出をしてくれたりもした。
だからまぁ、今日のところは文句は言うまい。
「お幸せにね!」
「はい! ありがとうございます!」
甘露寺の言葉に、陰日向のない満面の笑みで答えた竈門へ向けた、冨岡の視線がやさしい。この鉄面皮然とした男の本性は、おそらくはこの眼差しと同じくやわらかく温かいのだろう。そんな気がする。だからといって、ほだされてやるほどお人好しにはなれないが。
うれしげに扇子を広げた竈門がパタパタと扇ぐのに、冨岡の唇の端がほんのわずかに持ち上がった。笑顔というにはささやかすぎるその表情と、広げられた赤と黄の扇子に、かすかに胸が詰まる。
伊黒を救ってくれた人は己の道を見失い、初めて優しいぬくもりを与えてくれた人も、初めて友と呼んだ男も、もういない。お館様は病床に伏し、目通りすらもはや叶わぬほどに弱っておられる。
時は止まらない。得たと思っては失われ、この手からポロポロとすり抜けこぼれ落ちていく。
それでも。
冨岡と竈門の行く先が末広がりとは、伊黒だって思っちゃいない。けれど、今だけは少しぐらい祝ってやってもいい。甘露寺と恋人同士のようなひとときを過ごせた感謝など、してやるつもりはないけれど。
「ありがとう」
「ふん、せいぜい仲良くやるんだな」
もちろんのこと、実らせることもできぬ自分の恋の身代わりにとも、思っちゃいないし、冨岡たちに託すなどまっぴらだとも思うけれども。
菊は良きことの先触れともされるらしい。穏やかな冨岡と、幸せそうな竈門――そして、喜んでもらえてよかったねと愛らしく頬を染める甘露寺は、暖かな日差しの下で笑っている。
スリッと頬に身を寄せてきた鏑丸をなでてやりながら、伊黒は小さくうなずいた。
ゆく先がどうあろうとも、このちょっと腹立たしい恋人たちに実りがおとずれることを、ガラにもなく少しだけ願いながら。