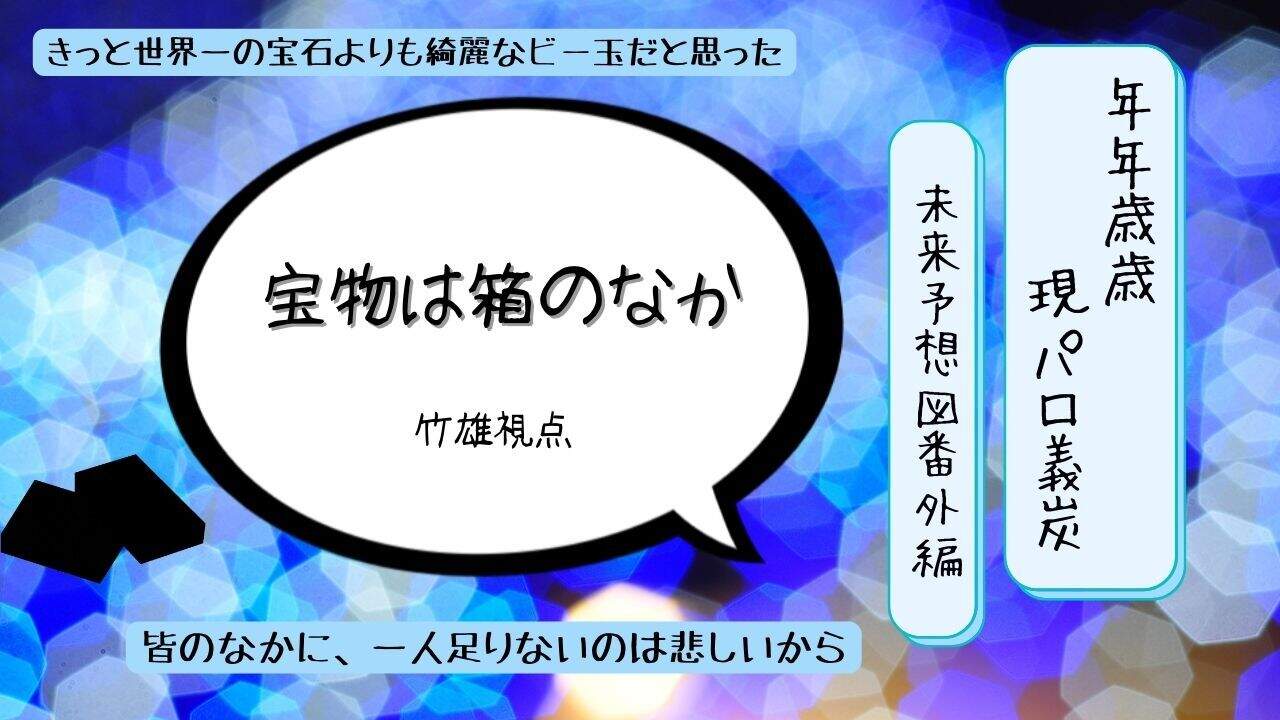※年年歳歳未来予想図。竹雄視点。
初めてその色を竹雄が知ったのは、保育園のころだった。
三郎爺ちゃんが皆で分けなとくれたビー玉のなかで、とびきり目を引いた、綺麗な綺麗な青いガラス玉。母さんが瑠璃色というのだと教えてくれた。
兄ちゃんの目に似た赤いビー玉も、姉ちゃんの目に似たピンクのビー玉も、黄色や緑も全部綺麗だと思ったけれど、その瑠璃色のビー玉は、まるで宝石みたいに見えた。宝石なんて見たことなかったけれど、きっと世界一の宝石よりも綺麗なビー玉だと思った。
それはとびきり綺麗な、竹雄にとってとっておきの特別なビー玉だったのだ。
写真で見た地球の色。遠い遠い国の海の色。キラキラして、優しくて、冷たいような温かいような、不思議に心惹かれる青くてまぁるいガラス玉は、手にしたその日から、竹雄の大切な宝物になった。
「ただいまぁ」
玄関から聞こえた明るい声に、茂と六太がパッと顔を上げた。
「兄ちゃんだっ!」
「たんじろ兄ちゃんっ!」
バタバタと走って迎えに行く二人に肩をすくめ、六太に読んでやっていた本を閉じると、竹雄も立ち上がった。
炭治郎が家を出てから、まだ半年と経っていない。だというのに、炭治郎が帰宅するたび茂や六太は大はしゃぎだ。毎日炭治郎の片割れに会える姉ちゃんや花子――ついでに竹雄も――は、それほどでもないけれど、まだ小学生のふたりは、兄ちゃんから連絡してこないかぎり様子をうかがうこともできないからだろうか。花子や竹雄に毎日『今日の義勇さん、ひいては義勇さんから窺い知る炭治郎兄ちゃん』報告をせがむくらいには、兄ちゃんの気配に飢えているらしい。
最初はずいぶんと寂しがってぐずることも多かった六太も、最近ではすっかり炭治郎がいないことに慣れてきたと思ったのに、やっぱり兄ちゃんは特別なんだな。思って竹雄は、ほんのちょっぴり落胆した。頑張っているのに、俺じゃ役不足かよと拗ねたくなる。ほんの少しだけ。
いや、毎日顔をあわせることができないから、余計に甘えるのか。まぁ、しかたないよなと竹雄は小さく苦笑した。
なにせ、六太にとっては炭治郎は兄であるのと同時に、父とも言える。竹雄たちと違って、末っ子の六太は父の顔をまったく覚えていない。六太が一歳を迎える前に、父は亡くなったから。
それからは、まだ小学六年生だった長男の炭治郎が、竈門家の父親代わりだ。炭治郎にとっても、父を知らぬ不憫さは拭いがたいようで、六太に対しては竹雄たちに対するよりもかなり甘い気がする。
居間へと現れた炭治郎の腕には、しっかりと六太が抱っこされていた。もう小学二年生だというのに、炭治郎に対しては赤ちゃん返りしてしまうらしい六太に、茂はちょっぴり不満顔だ。
「竹雄、久しぶり」
「久しぶりっていうほどじゃないだろ。前に帰ったときから一カ月も経ってないじゃん」
笑う炭治郎にあきれたように言えば、六太と茂がむぅっと唇をとがらせた。
「一カ月もだよっ。毎週来てくれたらいいのに」
「ごめんなぁ、バイトがないときはなるべく来るようにするからな」
よしよしと茂をなでながら言う炭治郎に、竹雄は、ただいまって言うくせに『帰る』じゃなくて『来る』なんだ、と、内心呟いた。
「冨岡先生とは仲良くやってんの?」
知ってるけどと思いつつ聞けば、照れたような笑顔が返ってきた。
「ん? まぁ、な」
ほんのりと頬を染める兄に、複雑な気分になっていたのは、いつごろまでだったろう。もう覚えていない。なにせ、炭治郎にとって義勇は誰より特別な存在だと、竈門家の人間なら誰だって昔っから知っている。もしも炭治郎が義勇以外の誰かと一緒に暮らすなんてことになったら、そのほうが違和感を感じるだろうし、それでいいのかと問い詰めたくなっただろう。
正直なところ、男同士で恋愛なんて、竹雄には理解できないけれども、炭治郎と義勇に関しては別だ。
小さいころから炭治郎が「義勇さんは俺のヒーロー」と頬染めて言うのを見てきているのだ。仲睦まじく一緒にいる姿以外、思い出せないぐらいには、炭治郎と義勇はセットだという刷り込みがされている。それこそ、炭治郎兄ちゃんは大きくなったら義勇兄ちゃんのお嫁さんになるんでしょう? と、確定事項として誰一人として疑うことさえなかったぐらいには。
とはいえ、まさかあの義勇兄ちゃんが自分の先生になるとは、初めて会ったころには思いもしなかったけれども。
「部活頑張ってるんだって? 義勇さんが褒めてたぞ。今度の団体戦では大将を任せてもいいってさ。ただし、次のテストで赤点がなければだけどな。おまえ、前期のテストで日本史は赤点すれすれだったんだって?」
「大将ってマジか。ていうか、兄ちゃん、そういうのは本人には内緒にしとくもんじゃないのかよっ。あと、俺のテストの点数まで聞くなよっ!」
アハハと笑って悪い悪いと頭をかく炭治郎に、ガックリと竹雄の肩が落ちる。
学校では無口不愛想で知られる鬼の生活指導も、愛の巣ではずいぶんと口が軽いようだ。この分では、竹雄の学校生活は炭治郎には筒抜けだろう。
「なぁなぁ、炭治郎兄ちゃん。義勇兄ちゃんは次いつくんの? 錆兎兄ちゃんや真菰姉ちゃんには道場で会えるけど、義勇兄ちゃんには全然会えないんだもん。顔忘れちゃうよ。なー、六太?」
少しふてくされた声で茂が言えば、六太もこっくりとうなずく。高一の花子までは年子がつづく竈門家だ。高校生組は毎日学校で義勇の顔を見ているけれども、年の離れた小学生の茂や六太は、なかなか義勇とは会う機会がない。
親戚でもなんでもない他人ではあるけれど、炭治郎同様に義勇もまた、竈門家の子どもたちにとっては父親代わりだ。まだ幼かった炭治郎ではできないことは、気がつけば義勇が全部してくれていたように思う。ときどき煉獄さんやら宇髄さんやらの力も借りてではあるけれど。
花子もかなり義勇には懐いていたし、竹雄も義勇のことが好きではあるけれども、生まれたときから知っている茂や六太は、義勇にとっても可愛くてしかたないのだろう。炭治郎と同じく、特に六太には甘い。
「文化祭が終わったから、ちょっとだけ時間が取れそうだとは言ってたけど……どうかなぁ。昨日も帰ってきたの十時ごろだったんだ。部活の顧問だから休みの日もほとんどないし」
困ったように言う炭治郎は、それでも寂しそうな様子はない。義勇の多忙さを心配はしているだろうけれども、ゆっくりと一緒の時間を過ごせないぐらいでは、ふたりの仲は揺らがないと信じているのだろう。
「義勇さんに、たまにはうちで飯食ってけって言っといてよ。母さんも会いたがってるし」
寂しいのは、むしろ俺だ。ふと浮かんだそんな言葉を消すように、竹雄は素っ気なく言った。
炭治郎が家を出たことは、もちろん寂しい。けれども、祝福もしている。
自分が頑張らないとと一人で全部背負いこもうとする炭治郎を、支えてやれたのは自分じゃない。しっかり者の姉ちゃんや母さんでさえ、それはできなかった。支えようとしても、炭治郎は心配させないよう頑張らないとと、余計に自分を追い込んでしまったから。
義勇だけが、炭治郎を泣かせてやれた。父を亡くした子どもの悲しさを、炭治郎は、義勇の前でだけさらけ出して泣けたのだ。
もし、義勇がいなかったら……なんて、考えたくもない。
「そうだなぁ。義勇さんも皆に会いたがってたし、予定を聞いておくよ」
「義勇兄ちゃん、くる? やったぁ!」
うれしげに笑う六太と茂に、炭治郎が破顔する。
もしも義勇と出逢うことがなかったら、こんな風に幸せそうに笑う炭治郎は、いなかったかもしれない。
笑ってはくれるだろう。幸せだとも言うだろう。けれど、それは自分自身の幸せを二の次に、すべての責任を背負いこんだ上でだ。子どもらしいわがままも、甘えも、なにひとつ口にせず、自分が辛いことにも気づかぬままに大人になる炭治郎なんて、見ることがなくて幸いだ。本心からそう思う。
綺麗な瑠璃色の瞳のあの人がいなければ、今の炭治郎も、今の竹雄もいない。それは疑いようのない事実だ。
知らず黙りこみ感慨にふけっていた竹雄の耳に、クスクスと忍び笑いが聞えてきた。見れば六太を膝にソファに座り込んだ炭治郎が、柔らかな眼差しで竹雄を見て笑っていた。
「なに?」
「いやぁ、初めて会ったときには竹雄も花子も義勇さんのこと、ずいぶん怖がってたみたいだったのに、懐いてくれて良かったなぁと思ってさ」
「懐くって……兄ちゃん、俺もう高二なんだけど?」
六太や茂じゃあるまいし、その言いざまはないだろうと憮然とすれば、炭治郎はごめんごめんと言いながらもニコニコしている。
なんだか照れくさくて、竹雄はプイっと視線をそらせた。
「別に……最初から怖がったりしてないし」
「そうかぁ? 竹雄も花子も人見知りじゃないのに、義勇さんには近づかなかったじゃないか」
「……そんなこと、ないしっ」
つい強く言い返せば、わかったわかったと苦笑する。その笑みを、竹雄はやっぱり直視できずに小さく唇をとがらせた。
高校を卒業して、義勇の家に住むことになってからまだ半年ほどだというのに、炭治郎の笑顔は一気に大人びた気がする。たった二つ違うだけだというのに、家を出るというのはこんなにも人を成長させるものなんだろうか。
それとも、愛されている人は、というべきか。
学校で見る厳しい鬼教師の顔をしたあの人を、竹雄はなんとはなし思い浮かべた。
怖がっていたと炭治郎は言うけれど、義勇を怖いと思ったことなんて、小さいころには一度もなかった。今は、まぁ、怒鳴り声を上げて竹刀片手に追いかけられればそれなりに、怖っ! とビビったりはするけれども。
たぶん、花子だって竹雄に同意するはずだ。怖がったことなんてないと。
怖かったんじゃなくて、本当は。
思い浮かべたのは、綺麗な瑠璃色の瞳。竹雄の宝物だったビー玉と、同じ色した綺麗な目。
炭治郎に倣って、下の子が欲しがれば自分の玩具を貸すのは当たり前だったのに、あのビー玉だけは誰にもあげたくなくて、大事に宝箱にしまい込んでいた。指ではじいてもしも割れたり欠けたりしたら絶対に嫌だからと、大切にしまって、ときどき眺めた瑠璃色のガラス。花子に泣かれても、これは俺のだもん、俺の宝物だもんと、花子以上に大泣きしたのは竹雄の黒歴史だ。
そんな大切な宝物と同じ色をした瞳の、綺麗な綺麗なお兄ちゃん。見惚れて、近づくことすら恥ずかしかったなんて、今も誰にも言えない。
きっとそれは花子だって同じことだ。花子の初恋が義勇だと、竹雄は知っている。というよりも、禰豆子以外、竈門家の子どもたちは必ず一度は義勇にほのかな憧れをいだくようになっているに違いない。茂や六太だって、三歳ぐらいのときには、おっきくなったら義勇兄ちゃんと結婚すると言っていたぐらいだ。
冨岡義勇という人は、竈門家の子どもホイホイかというぐらいに、惹かれてやまない存在なのだ。炭治郎の影響であるのは間違いない。
……男の子は男の人のお嫁さんには、今のところ日本ではなれないんだぞ、なんて忠告は、炭治郎と義勇を見て育つ竈門家においては意味を持たないのだから、しかたないのだ、うん。
義勇さんはお兄ちゃんのものと、最初から理解している禰豆子以外は、一度は夢見るのだ。義勇の特別に自分がなることを。淡い初恋はいだいた瞬間に失恋が確定するのだけれども、それはまぁしかたがない。それで傷ついたこともない。小さな六太でさえ、義勇は炭治郎のもの、炭治郎は義勇のものと、知っている。
そう、竹雄だって知っているのだ。ずっと、ずっと、昔から。
あのビー玉は、どこにいっただろう。
宝物のビー玉は、いつしかどこかに行ってしまった。宝箱なんて、高校二年生になった竹雄は持っていない。だけど、一番綺麗な瑠璃色は、今も竹雄の宝物だ。
夢見る頃は過ぎても、大切にしまい込まれている。
「兄ちゃん、今日は何時に帰んの? 冨岡先生の夕飯は?」
「今日も遅いらしいから、たまには泊ってこいって言われてさ。お言葉に甘えることにしたんだ。夕飯はチンして食べられるように冷蔵庫に用意しといたよ」
お泊りやったぁ! と喜ぶ茂と六太に、炭治郎もうれしそうだ。皆がうれしいなら、竹雄だってうれしい。
でも。皆のなかに、一人足りないのは悲しいから。
「明日は部活午後からなんだし、遅くなってもいいから冨岡先生もうちに泊ればいいのに。兄ちゃん、連絡しなよ。いつかなんて言ってたら、あの人なかなか顔出せないまま年越しちゃうじゃん」
「義勇兄ちゃんもお泊りっ!? やったっ、俺一緒にゲームするっ!」
「ぎゆ兄ちゃん、お風呂一緒に入れる? あのね、俺ね、一人で頭洗えるようになったんだよ」
唐突な提案に戸惑っても、茂や六太の期待のこもった眼差しには、炭治郎も勝てなかったようだ。苦笑しつつスマホを取り出している。
もう暫くすれば、禰豆子や花子も帰ってくる。きっと花子は義勇が泊まると聞いたら、茂たちに負けず劣らず大喜びするだろう。禰豆子もいつも以上に腕を揮うに違いない。
今夜の食卓はたいそうにぎやかになるだろう。
六太や茂に甘いあの人が、こんなおねだりを無下にするわけがないから。なによりも、炭治郎がねだれば、義勇が断るわけがないのだ。
幸せだな、と、竹雄は小さく笑う。
炭治郎を幸せにしてくれた人。竈門家の子どもたちの初恋の人。竹雄だって例外じゃない。近づくことすら恥ずかしかったぐらい、綺麗な綺麗な、宝物の目をしたあの人が、誰よりも大好きだった。誰にも言ったことがないし、これからもずっと口にすることはないけれども。
小さなビー玉はどこかに行ってしまったけれど、宝物は思い出という名の箱のなか、いつまでもキラキラ光っている。
初めて竹雄と名を呼んで、優しく微笑んでくれた人の、瑠璃色の瞳。いつまでも色あせることない、竹雄だけの、宝物。
宝物は箱のなか、誰にも見せないし、誰にも言わない。