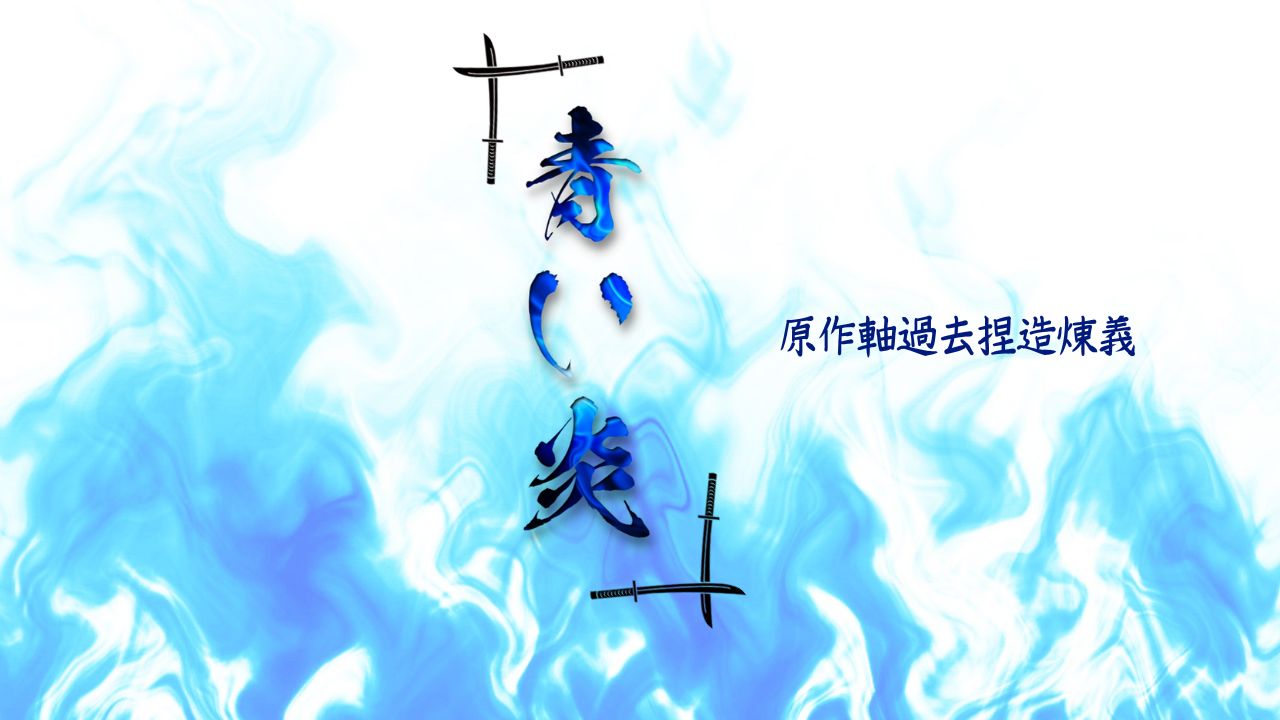ハァッと長く吐き出された息が白い。剣を鞘に収めた煉獄の腕や肩、踏みしめた足からも、霞のような湯気が立ち上っていた。
横殴りの雨風が吹き荒れる早春の森は、空気もキンと凍りつくようだ。隊服や羽織をぐっしょりと濡らす雨は、戦闘であがった体温により湯気となって、煉獄の身を包み込んでいた。
ともに任についた仲間は、どうなっただろう。絶叫や斬撃の音が聞こえるたび、嵐吹き荒れる山中を駆け巡り救援に向かったが、煉獄が目にしたのは、ほんの数時間前に笑いあった仲間の躯ばかりだ。
誰かが鴉を飛ばしたんだろう。増援が来るまでがんばれとの声を聞いたが、それもすぐに豪雨にまぎれ聞こえなくなった。
煉獄の前に生きた隊士が現れたのは、孤立無援となった煉獄が、とうとう鬼と対峙したまさにそのときだった。激しく揺れ動く梢から舞い降り、鬼に斬りかかった味方は、一人。ともに山に分け入った者ではない。鴉の報を受け救援に来た隊士に違いなかった。
ともあれ、相対した鬼は二人きりで相手をするには、少々厄介だった。頸を斬らぬかぎり分裂し続ける鬼だ。一匹斬り捨てる間に、新たな分身が二匹は湧いて出る。
四面楚歌とも言える二対無数の戦いは、嵐もあいまってなかなか決着がつかずにいたが、それもようやく終わった。援護してくれる味方がおらねば、夜明けまで続いたかもしれない。
地面に転がった鬼の頸や体は、打ちつける雨のなか塵へと変わり、地に染み込んでいくかのようだ。遺体の残らぬ鬼も、こんなふうに雨に溶け込めば、土に還ることができるのだろうか。なんとはなし思いながら、煉獄はゆっくりと頭を巡らせた。
「ようやく終わったな。的確な援護でじつに戦いやすかった、感謝する! 君が来てくれなければ、まだ手こずっていたかもしれん! 俺は煉獄杏寿郎、階級は乙だ!」
話しかけても、返答はなかった。共闘することとなってから、それなりに時間が経っているが、彼の声を煉獄はまだ一度も聞いていない。
激しい雨風のせいで聞こえなかったのなら、わからないでもないが、彼は戦闘中まったく声を上げなかった。
煉獄が入隊して、五年ほど経つ。出逢った隊士はそれなりに多い。無口な者もなかにはいたが、誰でも戦闘中は多少なりと、呻きなり気合の一声なりを口にしたものだ。ところが彼はまったくの無言だった。
豪雨のなか、少しずつ冷めていく肌身にあわせ、まとうように煉獄を包んでいた湯気が、次第に消えていく。剣を振るっているあいだはちっとも感じなかった寒気が、つま先から這い上がってきて、煉獄は知らずブルリと背を震わせた。
濡れていつのまにか額に落ちた前髪の隙間から垣間見る彼は、煉獄よりも体温が上がっているようだ。いまだ白い煙のような水蒸気に包まれている。けぶる横顔は、立ち上る湯気よりも白く見えた。
煉獄とそう年は変わらないだろう。無尽蔵に襲いかかってくる羽虫の如き鬼の分身を斬り払った彼の剣は、荒波のような水流の幻影をともなっていた。水の呼吸の使い手だ。改めて胸に湧いた歓喜に、煉獄は知らず声を弾ませた。
「水の呼吸の使い手とお見受けするが、素晴らしい剣技だった! 腕前を見るに君は甲だろうか、名前は?」
炎と水は、古より縁深い。鬼殺隊創設以来、柱は絶えず入れ替わり続けるが、炎と水だけは必ずいる。
だが、同時に水の呼吸は、全呼吸のなかでも基礎中の基礎だ。使い手はどの呼吸よりも多い。煉獄だって、水の呼吸の使い手には幾人にも会った。だというのに、彼だけになぜ喜びを感じたのだろう。煉獄自身にもよくわからない。
煉獄の問いかけにも、やはり答えは返らなかった。それどころか、彼は無言のまま立ち去ろうとさえする。
「待ってくれ! どこに行く気なんだ?」
呼び止めても、彼は立ち止まることなく歩いていく。風雨に紛れそうな彼の背からは、まだ白い湯気が立ち上っていた。白蝋の人形の如き面をした彼も、ちゃんと温もりを持つ人なのだと、白い水蒸気が知らしめてくれているようだ。
どこに行くもないものだ。煉獄は少年を追って足を早めつつ、内心で苦笑する。
この嵐のなかだ、まだ夜明けも遠い。隊士ならば、こんなときに向かう先は決まっている。
近くにある藤の家紋を持つ家は、どこだったろう。たしか、山の麓からさほど遠くないはずだ。記憶を探りながら煉獄は少年の背を追った。
真夜中ではあるが、藤の家ならばどんな時刻だろうと隊士を快く受け入れてくれるはずである。彼もきっと世話になるつもりだろう。
月明かりさえ望めぬ嵐のなか、しかも、道らしい道もない山奥だ。歩くだけでも困難極まりない悪路だが、彼の歩みはまったく危なげなかった。
だが、煉獄とて体力も身体能力も、ほかの隊士に劣るものではない。すぐに少年に追いつくと、また屈託なく笑いかける。
「君はずいぶん歩くのが早いな! しかし、この雨だ。歩いていては体が冷えて、体調を崩すかもしれん! 麓まではまだあるし、走ろうか!」
嵐の闇夜ではあるが、彼ならば問題ないだろう。たった一度の共闘だが、彼の強健さは疑いようがない。
彼が初めて煉獄へと視線を向けた。深い闇のなか、しかも豪雨に遮られ、彼の表情はよく見えない。彼の漆黒の髪もずぶ濡れに濡れて、夜目にも白い肌に張り付いていた。
「さぁ、行こう!」
彼の手をとった煉獄の手は、無造作に振り払われた。
「……かまうな」
初めて聞いた彼の声は小さく、平坦な響きをしていた。抑揚のない、感情などひとかけらも感じられぬ声音だ。だが、煉獄の目を見開かせたのは、彼の声ゆえではなかった。
「君……熱があるぞ! 俺が背負っていく、背に乗ってくれ!」
一瞬とはいえ、掴んだ彼の手はひどく熱かった。声とともに薄い唇から吐き出された息も、真っ白で、彼の体温が尋常でなく熱いことを示している。
なぜもっと早くに気づけなかった。自身への腹立ちが煉獄の腹のうちで渦巻いた。
背を向けしゃがみこんだ煉獄を、けれども彼は一顧だにせず、また歩き出した。
「かまうなと言った」
「そうはいかない! 俺は君が来てくれたおかげで助かった! 今度は俺が君を助ける番だ!」
「必要ない」
あわてて追いかけた煉獄へと返された声音は、存外しっかりとしている。けれどもよくよく見れば、彼の唇は紫がかり、小刻みに震えていた。立ち上る湯気はいよいよ白く、彼の全身を包んでいる。相当高熱が出ているに違いなかった。
言い合っていては埒が明かない。一刻も早く彼を暖かい場所で休ませてやらねば。
彼のベルトに手をかけた煉獄は、力任せに彼を肩へと担ぎ上げた。多少の手荒さは勘弁してほしいところだ。
持ち上げた瞬間に見えた彼の顔はギョッとしていたが、やめろだの下ろせだのと文句を言うことはなかった。わめきたてても煉獄は聞かないと、判断したのかもしれない。体力を消耗すれば、体調だってますます悪化する。米俵よろしく煉獄の肩に乗せられた彼は、煉獄が山を駆け下りる最中、もう一言も口を開かなかった。
日付が変わって間もない深夜、藤の家紋が描かれた門扉をドンドンと叩いて訪いを入れた煉獄に、やはり家人は、文句どころか問いただすことさえせず、即座に部屋を用意してくれた。
「湯殿の支度をしておりますが、少々時間がかかるかもしれません。ひとまず濡れた隊服をお着替えください」
火鉢やら着替えやらが慌ただしく持ち込まれる。煉獄は快活に礼を言い、水がしたたる隊服を躊躇なく脱ぎ捨てていったが、彼はぼんやりと佇んだままだ。せめて座ればいいものをとちらりと思った瞬間に、畳に残る己の足跡やら小さな水たまりに気づき、煉獄はふたたび彼に手を伸ばしていた。
座り込み畳を濡らしては申し訳ない。きっと彼はそう考えた。不思議と煉獄はそれを疑わなかった。
「ホラ、脱がないと体が温まらないぞ。こちらの人も困っている」
羽織を脱がせにかかる煉獄の手に拒否の姿勢を見せたものの、彼は『困っている』の一言に抵抗をとめた。彼は、自分のことはないがしろにできても、他人に対しては些細なことにも気を遣ってしまうのだろう。そんな気がした。
「……自分で脱ぐ」
「うむ! このままでは畳までびしょ濡れにしてしまうからな! 急ごう!」
言えばどこか幼い仕草でコクリとうなずく。思ったとおりだと、少しだけ煉獄は愉快な気持ちになった。
熱はいよいよ上がっているのだろう。彼の手はひどく緩慢だった。ようやく脱いだぐしょ濡れの羽織を彼の手から取り上げうなずいてみせれば、ハァッと疲労の色濃い息をつく。
彼が着替え終えるのに、五分ほどかかったろうか。濡れた隊服やら体を拭いた手ぬぐいを入れた盥を持って、家人が立ち去ると、彼はやっと腰を下ろした。
いや、それは座ったというよりも、むしろへたり込んだというべきかもしれない。いよいよ膝が萎えて立っていられなくなったのだろう。
「大丈夫か? もっと火鉢の近くへ」
パチパチと炭が小さく爆ぜる陶器の鉢を、ズイッと彼の前に押し出したが、彼はやはり答えない。手を火にかざすことすらせず、血の気の失せた顔をゆっくりと室内に巡らせた彼に、煉獄はキョトンと小首をかしげた。
「どうした? なにか気になることでも?」
「……手ぬぐい」
ポツリとつぶやく声はひどく億劫そうだ。視線の先をたどれば、着替えとともに持ち込まれた手ぬぐいの残りが見えた。
「そのままで。俺が取ろう」
立ち上がろうとするのを止め、煉獄が手ぬぐいを取り彼に手渡すと、彼はそのまま煉獄の頭に手ぬぐいをかぶせてきた。
「風邪を引く」
寸時言葉を失って、ポカンとなすがままになっていた煉獄は、髪を拭ってくれる気だるげな手つきに我に返ると、あわてて彼の手から手ぬぐいを取り上げた。
「君は熱があるんだぞ! まずは君が先だ!」
手ぬぐいはもう、ぐっしょりと濡れていた。改めて見れば、彼の髪だってまだしずくが落ちている。
「ちゃんと火に当たっていてくれ!」
あたふたと言いおき、残りの手ぬぐいを引っ掴んで戻ると、煉獄は、ぼうっと座り込んだままの彼の髪をワシャワシャと拭った。
嫌がるかと思ったが、彼は抵抗しない。指先がかすめた彼の首や耳は、やっぱりかなり熱かった。
「……おまえも、ちゃんと拭け」
「なに、俺は丈夫だからな! 心配無用だ! それに、今は君の体調のほうが問題だ」
つらいのは自分のほうなのに、彼は煉獄を案じてくる。無性にうれしくもあり、彼自身への無頓着さが気がかりでもあり、煉獄は落ち着かない心持ちになった。
彼は誰にでもこんな具合なのだろうか。自分のことよりも人を案じる者は、隊士には多いが、それでも彼は少しばかり度が過ぎている。
「もしや君は、救援に向かう前から体調が悪かったんじゃないのか? 無茶はしないほうがいいぞ。……ん?」
誰か、自身を顧みない彼の代わりに、彼を案じてやる者がいればいいのだが。
もしも、誰もいないのなら……。ぼんやりと脳裏に霞のように立ち上った言葉が形を取る前に、煉獄の手が止まる。
ひたいに落ちる髪をかきあげなければ、きっと気づかなかったそれ。まだ色が抜けたままのひたいのこめかみから、髪の生え際に沿う形でくっきりと大きな傷跡があった。
知らず煉獄の眉が傷ましげにひそめられた。古傷のようだが、おそらく相当な重症だったろう。出血も多かっただろうし、一週間ほどは意識が混濁していてもおかしくない傷だ。
「……ひどいな。鬼にやられたのか?」
そっと傷痕を指先でたどった煉獄の手が、音高く払われた。
「さわるな……っ!」
閉てられた雨戸の外、いまだ暴風雨は吹き荒れている。戸板を叩く雨音はザンザンと騒がしい。そのくせ、落ちた沈黙のなか、パチパチと小さく爆ぜる炭の音がやけにはっきりと聞こえた。強風で電線が揺れるのだろう。ジジッと音を立てて、白い電灯の明かりが明滅した。
嵐の今宵、彼が初めてあらわにした感情は、静かな怒りだった。
押し殺した声音には、隠しきれない憤怒が滲みだしている。濡れた髪に遮られることなく、煉獄を真っ向から見据える瞳にも、怒りの焔が燃えていた。
最も高温の炎は、青いのだとどこかで聞いた。息を呑んだ煉獄は、なぜだか不意にそんなことを思い出した。
怒りに燃える彼の瞳は、灼熱の青い炎のようだった。
「……すまなかった。その傷は、君にとって触れられたくないものだったんだな。浅慮な振る舞い、申し訳ない!」
居住まいを正し、深く頭を下げた煉獄に、彼はしばし沈黙していた。やがてフゥッと小さなため息が聞こえ、「もういい」とのつぶやきが煉獄の耳に落ちた。
ゆっくりと姿勢を戻した煉獄の目に映った彼の瞳は、もう怒りの熱は引き、夜空のような深い青をしている。きっと彼の瞳は、この深みのある青が通常の色合いなのだろう。
白く色の抜けきった彼の肌は、だんだんと赤く染まりつつあった。怒りになけなしの気力も使い果たし、ついに体力が底をついたのかもしれない。悪いことをしてしまった。煉獄はふたたび立ち上がった。
「熱が上がってきているようだな。風呂はやめておいたほうがいい。布団を敷いてもらおう。待っていてくれ」
うなずくことすら苦なのだろう。彼は目を閉じうなだれている。もはや座っているだけでさえつらいに違いない。
部屋を飛び出してすぐに、家人がやってきて幸いだ。真夜中に人を探してまわるのは、いかに火急のこととはいえ、少々気が引ける。
彼の様子を伝えると、隣の部屋にすでに布団が敷いてあるとのことだった。
「さらに熱が上がるやもしれません。同室では貴方さまも落ち着かれないことでしょう。湯をお使いのあいだに、もう一部屋ご用意いたしましょう」
「いや、それには及びません! 病のときは、心細くなるものだ。せっかく湯の支度してくれたのに申し訳ないが、彼についていてやりたい。彼の救援で助かったのですから、今度は俺が看病するのが筋でしょう!」
藤の家の者は、少しばかりキョトンと目をしばたかせたが、やがて静かにうなずき微笑んだ。
「それでは、あの方は貴方さまにお任せいたします。ひたいを冷やす手ぬぐいなどを用意いたしましょう。なにかございましたら、何時でもかまいませんのでお呼びください」
会釈とともに廊下を足早に立ち去る背中を見送る暇もあらばこそ、煉獄は急ぎ部屋に戻った。
頭痛がするようなら大きな音を立ててはつらいだろう。憂慮に気は急くが、静かに襖を開く。彼はまだ、同じ体勢で座り込んだままだった。
「隣の部屋に布団が敷いてあるそうだ。立てるか?」
穏やかな声で問いかければ、彼の顔がゆるゆると上げられた。山中での目を見張る剣技と体捌きが嘘のように、彼の体は頼りなく震えている。白かった頬はすでに真っ赤だ。
それでも彼は、差し伸べた煉獄の手にすがることなく、自力で立ち上がろうとした。
「危ないっ! 無理はしないほうがいい」
たちまちよろけ、崩れ落ちそうになった彼を、煉獄はとっさに抱きとめた。背丈は煉獄とさほど変わらないが、彼の体はひどく軽く感じられた。
「……すまない」
「謝る必要はない。こんなときはお互いさまだ。気は進まんだろうが、ちょっと我慢してくれ」
胸元に吐きかかる彼の息も、すがる手も、不安をかき立てられるほどに熱い。煉獄はためらわず彼を横抱きに抱え上げた。
彼は体を硬直させたが、すでに隣の部屋に続く襖に向かっている煉獄に、下ろせとは言わなかった。距離にすればたった数歩だ。揉めるだけ無駄だと判断したのだろう。山を降りるときも、戦闘中でもそうだったが、彼は決断を下すのが早い。この場合は、具合の悪さゆえの諦めかもしれないが。
行儀は悪いがと頭の片隅でちらりと思いつつ、襖を足で蹴り開ければ、並んで敷かれた二組の布団が目に入った。
そっと横たえられた彼は、一度だけ煉獄に瞳を向けた。間近に見た彼の瞳は、熱に潤んでいる。焦点のあわぬ濡れた瞳と赤く染まった頬に、煉獄の鼓動がドキリと跳ねた。
「……眠るといい。そばにいる」
騒ぐ鼓動を抑え、煉獄は静かに言った。彼のまぶたがゆっくりとふせられる。すぐに彼は眠りに落ちたようだ。
布団をかけ直してやり、煉獄は、ひたいに伸ばしかけた手を一瞬躊躇し、彼の頬へと触れた。
赤みに違わず、彼の頬は煉獄の手よりもずいぶんと熱い。一晩で下がればいいが、よしんば朝になっても熱が下がらぬようであれば、蝶屋敷へと使いを出したほうがいいだろうか。浅い呼吸と肌の熱さに、煉獄は深く吐息した。
長い夜になるかもしれない。閉じられ今は見えない彼の瞳の色を思い浮かべて、煉獄は、そろりと彼の頬をなでた。
嵐はまだやまない。
家人から受け取った新しい手ぬぐいをギュッと絞り、煉獄は、彼のひたいにそっと乗せた。
手ぬぐいを濡らすのはもう何度目だろう。彼の熱はまだ引きそうにない。
ガタガタと布団のなかで震え、幾度も寝返りを打つから、手ぬぐいはすぐに落ちる。まずは体を温めるのが肝心と、湯たんぽを布団に入れてやったが、それでも彼の悪寒は止まらないようだ。
雨音はまだまだ強く、夜明けまでは今しばらくあった。
そろそろ汗をかき、熱が下がりだしてもいい頃合いだと思うのだが。
火鉢で燃える炭とかけられたヤカンがシュンシュンとたてる湯気で、室内はだいぶ暖まっている。湯たんぽもまだ冷めてはいないはずだ。だが、彼にはまだ足りないのかもしれない。
逡巡は、数秒だった。
「すまん」
彼の耳には入っていないのは明白だ。それでも知らず詫びながら、煉獄はそっと彼の布団に自身を横たえた。
ギュッと抱きしめれば、意識のないまま彼は、温もりを求めてか煉獄の胸にすがってくる。いとけない仕草に、なぜだか胸が詰まった。
しばらくすると、ハァハァと荒い彼の呼吸を続けていた彼が、不意に小さくうなった。
「ん……ぁ……ない、で」
うなされだした彼のひたいに、漆黒の髪が張り付いている。汗をかき出した。ここまでくれば、一安心だ。汗とともに熱も引いてくるだろう。
安堵に煉獄は腕の力をわずかにゆるめたが、それでも、彼のうなされようは気がかりだ。
意識のないうちならばいいだろうかと、少しのためらいとともにひたいの汗をぬぐった煉獄の手が、止まった。
「……め、だ……さび……いかな……で」
とぎれとぎれに紡がれた声音は、いかにも苦しげだ。閉じた目尻から、ひとすじ、涙が落ちた。
ふせられた長いまつ毛の端で、小さな涙の粒がキラリと光る。熱に浮かされたうわ言の意味は、煉獄にはわからない。けれど、彼の涙に煉獄の心臓は、いまだかつてない痛みを覚えていた。
前髪をそろりとかきあげれば、傷痕が先よりもはっきりと浮かび上がっているのが見えた。
行かないで。彼はそう言った。誰を呼んでいるのだろう。彼を置いていった者は、彼にとってどのような人物だったのか。考えたってしかたのないことなのに、なぜだかやけにそればかりが気にかかる。
煉獄は、そっと傷痕に指先で触れた。この傷を負ったとき、彼は、もう鬼狩りだったのだろうか。それとも、この傷が元で鬼狩りへの道を進むに至ったのか。それすら、煉獄は知らない。
彼が涙ながらに苦しげに呼ぶ者は、彼をおいて行ってしまったのか、それとも……逝ってしまったのか。
なにも、煉獄は知らない。わからない。
わかっているのは、彼の涙を見るのは胸がかきむしられるほどに苦しく、切ない想いがするということだけだ。
灼熱の炎の青でも、星月夜の青でもいい。閉じた目から流れる涙ではなく、あの青が見たい。また、彼の青い瞳に見つめられたい。笑ったときの瞳の色を見られるのなら重畳。いつか、そんな日がくればいいと、不思議と思う。
「大丈夫だ……俺がいる。俺が、君のそばにいる。だから、もう泣かないでくれ。そばに、いるから」
ささやきは、煉獄自身の耳にもやさしくひびいた。幾度も煉獄はささやきかける。やさしく、力強く。祈るように。誓うように。
次第に穏やかになっていく彼の息遣いに、やわらかくほどけていく眉根に、胸にこみ上げる熱い塊は、いったいなんだろう。なぜ自分は、これほどまで強く、彼のそばにいたいと願っているのだろう。
わからないことばかりだ。彼のことも、自分のことも。けれどもいつか。煉獄は胸に強く誓う。
炎と水、一対の呼吸。いつか、自分が炎柱を継ぐ日が来たのなら。そのときには、ちゃんと彼の目を見て約束しよう。俺がいる。そばにいると。
そのときには、きっと彼も水柱になっているに違いない。彼の剣は、それだけの力があった。
いつか。いつか必ず、彼と肩を並べて笑う日が来る。そのときには、きっと。
雨は、いつのまにかやんでいた。
穏やかになった彼の寝息に安心したのだろう。いつのまにか眠りに落ちていた煉獄が、目覚めたとき、彼はすでにいなかった。
布団を抜け出す気配すら感じ取れぬとは、煉獄も疲労していたとはいえ、やはり彼は只者ではない。目覚めて一人きりだと気づいたときには、ここ数年感じたことのない驚愕に、唖然としたものだ。
「けっきょく、彼の名も知らずじまいか」
嵐のあとの晴れ渡った空を見上げ、煉獄は苦笑する。
残念だが、しかたない。昨夜、彼の涙へと誓った言葉は、しっかりと煉獄の胸に刻みこまれている。炎柱襲名を目指し、変わらず努力精進を続けていれば、いつかは必ず彼に再会する日もくるだろう。
「そのときには、笑ってくれるといいがな」
雨に濡れた枝葉が朝日に光る。キラキラとした輝きは、そんな未来を約束してくれているようで、煉獄の笑みも明るく深まった。
笑う彼の瞳は、さて、どんな色を見せてくれるだろう。
それはもしかしたら、こんな冴えた青空の色をしているかもしれない。
駆け出した煉獄の背にひるがえる羽織は、空に遊ぶ雲のように、真白くはためいていた。