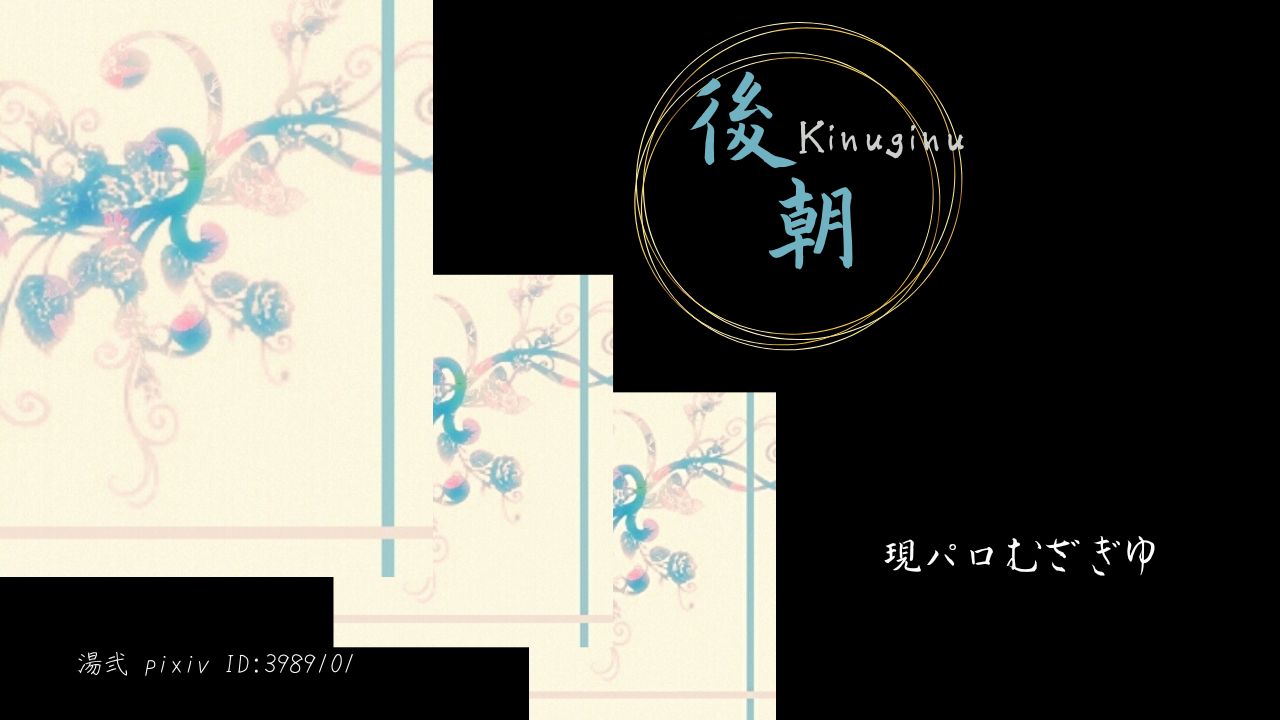その夜のことを、無惨は、人生最良の夜と言ってやってもいいと思っている。少なくとも、義勇の安アパートに転がり込んだ後から、朝目覚めるまでの出来事に関しては。
正直に言えば、人生初の自転車の二人乗りや大衆食堂だって、いつか楽しく幸せな思い出として笑いあうことになるのだろうなと、濃密な夜のなかでふと思いもした。義勇の汗に濡れた肌や、潤む瑠璃の瞳を堪能した代償と思えば、それぐらいの低俗さは不問に付してやろうと寛容にもなれたのだ。
その日のことは言うなれば、どうにか懐かせようと一年ほども手を変え品を変えかまい続けた野良猫が、ようやくすり寄ってきたようなものだ。媚を売る甘え声など出さずとも、すりっと手に頬をこすりつけ、そっぽを向きながらも寄り添ってくるだけで、舞い上がるような心地がする。ましてや相手は義勇だ。餌につられる野良猫よりもよっぽど手ごわい。
義勇と出逢う以前の無惨は、第六天の魔王を自称した武将よろしく、懐かぬ猫など殺してしまえと吐き捨てるのが常だった。懐いかれたら懐かれたで、こちらの都合などおかまいなしにまとわりついてくるなら、やっぱり不快で、打ち捨てるのに躊躇はない。
だというのに、抱き上げられた義勇が無惨の頸にまわした腕にキュッと力を込めすがりついてきた瞬間、無惨は今までの己の信条を撤回せざるを得なくなった。義勇が自分の腕に身を委ねている。好きにしてくれと言わんばかりに。ただそれだけのことで、無惨の精神と肉体を支配したのは、まさしく幸福感としか言いようのない生まれて初めての感情だ。
まったくもって柄ではないが、幸せとはこういうことを言うのかと、無惨はその夜の一部始終に内心感動すらしていた。それこそ、安アパートの壁をダンッと叩いた忌々しい隣の住人の存在さえ、甘い夜の彩りに思えたほどだった。
懸命に声を抑えようとする義勇の口をふさいでやるためという、大義名分ができたことには、少しぐらい感謝してやってもいい。口づけたまま揺さぶってやるたび、義勇の愛らしくも淫靡な蕾はキュウキュウと無惨を健気に締めつけて、それはもう法悦の極みであった。
幸せは朝になってもつづいていて、目覚めた瞬間にもギシリと鳴った安っぽくて狭いパイプベッドのきしみは気に障ったが、腕のなかにいる義勇が目に入った瞬間に、そんな不満は即座に晴れた。
息を詰め、思わず見入った義勇の寝顔は、無惨の知るどの義勇の顔とも違っていた。穏やかであどけないその顔。稚い、そんな言葉が浮かんだ。愛おしい。そんな言葉が胸を締めつけた。
常の、冷静沈着さを崩さぬ生真面目とも冷めているともいえる無表情でも、腕のなかで見せた恥じらいと恍惚に甘く乱れた顔でもない、生まれ落ちたままの無垢な義勇の寝顔。いくらでも見つめていられる。そんな気がした。
なにしろ義勇の顔は感情が読めず、苛立たされることのほうが多い。ときおり感情を浮かべて見せても、伝えてくるのは不快感や苛立ちばかりで、腹が立つやら悲しいやら。
悲しい。そんな馬鹿馬鹿しい感情が自分のなかに生まれることにすら、無惨は戸惑いを覚え、腹立ちを抱えて過ごした、一年間。その末がこの朝だ。
物心ついたときからずっと、自分の意のままにならぬ者などこの世には存在しないと、無惨は思っていた。義勇に出逢うまでは。
虚弱で極度の日光アレルギーであっても、無惨は王様だ。生まれ落ちた家の財力は、無惨が虚弱であるがゆえに、無惨が我儘な暴君であることを許してきた。
かわいそうな子。せめて我儘くらい聞いてやろう。甘やかす言葉は、無惨を苛立たせる。憐れまれるたび、鬱憤と憤怒が無惨の身の内には募る。不満と怒り。まだ三十年に満たない無惨の人生は、そればかりで占められている。
弱い体に収まりきらぬ強い意志。無惨を無惨たらしめているのは、怒りでもって現状の不満を払しょくする意思と行動力だった。
幸い、それを支える優秀な頭脳が無惨には備わっていた。無惨は己の才覚でもって、すべてをねじ伏せてきたのだ。親の財力も役に立った。少しずつ体質を改善し、体力をつけ、人並み以上の体躯を得た。だが、日光アレルギーだけはいまだ克服できない。
だから依然として、無惨は不満で、怒っていた。すべてに。
義勇に対しても、最初はやはり怒りばかりだった。自分の意のままにならぬ者。そんな存在はあってはならない。どうすれば義勇は自分の手に堕ちるのか。苛々と考え続け、何度も義勇がバイトする傘下の子会社へ足を運び、ときに恫喝し、ときに懐柔しようとし、いつのまにやら季節は一巡り。
気がつけば、このありさまだ。いつのまにやら、義勇の一挙手一投足に心を揺さぶられていた。
手に入らないから気になる。意のままにならないから手に入れたくなる。それだけだと思っていたのに、なんということだろう。
ひとたび手に入れてしまえば今までと同じように、この一年無惨を支配していた執着も、薄れて消える。そう、思っていたというのに。
腕のなかですぅすぅと寝息を立てている義勇に、無惨の胸に信じられぬほどの多幸感がこみ上げる。驚くべきことに目の奥が熱くなり、瞳が潤みさえした。
私のものだ。全部、私だけのものだ。義勇。義勇。義勇。
わきあがる独占欲は、懇願の祈りに似ている。
甘く乱れる息。淡く紅潮したなめらかな肌。振り乱される黒髪も、拒んだりすがったりする伸びやかな四肢も、恍惚の涙を流す青く青く澄んだ瞳も。安物のパイプベッドの上で見て、触れた、義勇のすべてに酔った夜。
素っ気なく無愛想で生真面目に働く姿も、初めて義勇の誘いに了承したときに見せた小さな笑みも、この無垢な寝顔も。自分の目に映る義勇のすべてが、どうしようもなく愛おしい。
誰にも渡したくない。誰の目にも触れさせたくない。もう、すべて私のものだ。
わきあがる幸せと歓喜に突き動かされて、強く抱きしめたら、義勇の顔がんんっとしかめられた。
ゆるゆるとまぶたが持ち上がり、無惨が望んでも手に入れられぬ青い空と海の瞳が、無惨を映す。まだぼんやりとして、焦点が合っていない。愛らしい。わき立つ愛おしさに、無惨は腕の力をさらに強めた。
「おはよう」
我ながらとんでもない声だと、無惨は内心で戸惑いつつも苦笑する。なんなのだ、この声は。やけに甘ったるい。胸焼けしそうなほどだ。だが、こんな朝にはきっとふさわしい。初めて隙間なく抱きあって、繋がって、ともに愉悦の極みへとたどり着いた夜の果てには、この甘さこそが似合いだろう。無惨はそう思ったし、義勇からも同等の甘さが返されると信じ込んでいた。
だからまさか。
「暑苦しい」
そんな言葉とあからさまにしかめられた顔が返されるなど、思いもしなかった。
グイッと胸を押しやってくる腕に逆らうこともできぬほど、無惨は呆然としていた。呆気にとられ思考停止した無惨を見やることなく、義勇はさっさと起き上がり、床に散らばった衣服を身につけている。
言葉もなく凝視する無惨の視線などまったく気にしていないのか、義勇は背を向けたまま、一度も無惨を顧みることなく、小さな冷蔵庫を開け牛乳やら食パンやらを取り出した。まるでなにもなかったかのように、だ。
たしかに無惨は、自分でも信じられぬほどの慎重さで義勇の体を暴いたし、痛みなどほとんど与えぬように抱いた。けれども、それにしたってこの反応はない。
痛い、体が動かないと拗ねたのなら、全部私がしてやろうと甘やかしてやってもよかった。恥らう様はぜひとも見たかった。なのに、義勇にはまるっきり動じた様子などなく、動きも職場で見る機敏さのままだ。
「さっさと服を着て飯を食え。おまえ、仕事があるんだろう?」
小さなローテーブルにトーストと牛乳だけの質素な朝食が用意され、素っ気ない声がかけられるにいたって、ようやく無惨の思考は活動を再開した。瞬時に脳裏を占めたのは、不満と怒りだ。そして、隠しようのない不安が少し。
「おい……」
「なんだ」
のそりと起き上がり義勇をにらみつける。義勇は無惨に背を向け座っている。振り返りもしない。
「私は何人目だ?」
誘いは義勇からだった。けれど、口づけに応える舌はぎこちなく、戸惑いが露わだった。息継ぎひとつうまくできず、ハァハァと息を荒げて涙目で睨みつける様に、たとえようもない興奮を覚えたのだから、間違いない。
そっと触れた小さな蕾も固く閉じて、誰かの手でやさしく花開かされたことなど一度もないことを、無惨に知らせていた。快感を得ることすらうまくできずにいるのを、丁寧に、極限までの慎重さでもって、時間をかけて教えてやったのは私だ。無惨はそう信じていた。その事実に恍惚としてさえいたのだ。
だが、目覚めてからの義勇の態度は、初めて男に抱かれた朝のものではない。慣れている。そう言わんばかりだ。
無惨は処女性になど頓着したことはない。だが、義勇だけは別だ。義勇が見せた健気な恥じらいも、陶然とした愉悦の瞳も、すべてほかの誰かの目に触れたのだと思うだけで、はらわたが煮えくり返る。憤怒はマグマのように体中を巡り、義勇の肌に触れた者すべてを焼き尽くすまで治まりそうにない。
「は?」
なにを問われているのかさっぱりわからない。義勇が口にした一音は、そう告げていた。思わずというふうに振り返った顔も、キョトンとしている。
視線が合った瞬間、パチリとひとつまばたいた義勇は、パッと顔をそらせた。無惨の顔など見たくもないとでもいうかのように。
その仕草と沈黙に、無惨の怒りは即座に頂点に達した。ベッドから降り、乱暴に義勇の肩をつかむと力まかせに振り返らせる。
「正直に言え。私の前に何人咥えこん、だ」
腹立ちのままに告げた声は、それきり続けられなくなった。
振り返り無惨を見上げた義勇の顔は、淡く紅潮していた。よく見ればローテーブルの上で握りしめられている手も、小さく震えている。無惨の顔を映しだした瞳が丸く見開かれ、パチリとまたまばたいたと同時に、頬の赤味がさぁっと増していく。
「な、なにを言いたいのかわからん! わかるように言え! い、いや、それより先に服を着ろっ! ばかっ!」
上ずる声と、そらされた視線。顔はいよいよ赤い。
これは、まさか。ゴクリと無惨の喉が鳴る。
「……貴様、照れているのか」
「うるさいっ。いいからさっさと服を着て飯を食えっ」
かたくなに目をあわせようとしない義勇は、それでも無惨の手を振り払わない。肩をすくませ縮こまるようにしていながらも、触れる手を、拒んではいない。
怒りはたちまち霧散して、込み上げたのはどうしようもなく凶暴な愛しさだ。このままベッドに引きずり戻して、メチャクチャにしてやりたい。どこまでもやさしく、どこまでも深くやわらかく、慈しんでやりたい。相反する願望は、それでいてどちらも同じものだ。愛おしい。ただそれだけが、無惨を残酷なほどに支配する。
こんな自分を無惨は知らない。一度として感じたことのない感情は、無惨のアイデンティティさえも揺るがす。自分のなかにこれほどまで他者を慈しみ愛する心が存在することすらが恐ろしい。
無惨は王様だ。冷酷無比な暴君だ。誰もがそれを疑わず、無惨自身、いっそそれが心地よくすらあった。
だというのに、こんな野良猫のごとき一介の苦学生ひとりに、これほどまでに溺れている。囚われている。愛している、なんて。そんな世迷いごとを恥ずかしげもなく口にして、膝を屈し愛を乞うてしまいそうなほどに。
「義勇……」
「おい、いい加減言うことを聞け。服を着て、飯を食え。おまえ、今日も仕事だろうが」
抑えきれぬ感情に突き動かされて口づけようと寄せた顔は、無慈悲な手のひらに躊躇なく押しやられた。
苛立ちが恥じらいを凌駕したらしい。義勇の顔はもういつもの白さを取り戻し、眉間には不快感を告げるシワがくっきりと刻まれている。
あぁ、本当に、厄介で、手ごわい。
「仕事などどうでもいいだろうが。素直にキスぐらいさせろ」
「フルチンで偉そうにするな。恥じらいってもんがないのか、おまえは」
「ふん、見られて恥じるほど粗末ではないからな。貴様も気に入っただろう?」
ニヤリと笑って言ってやれば、絶句しハクハクと唇をおののかせた義勇の顔は、また咲き誇るバラの色に染まった。
「ふざけるなっ! 誰が気に入るかっ、この遅漏!」
「誰がだっ! 貴様がつらそうだからゆっくり抱いてやったというのに! 気持ちいい、もっととねだったのは貴様のほうだろうが!」
「そ、そんなこと言ってない! 言えるわけないだろうっ、ずっとキスしてたし!」
「言わずともわかるに決まっているだろうが、馬鹿め! 場数が違う!」
「最低なことを偉そうに言うな! ……初めてで、悪かったなっ!」
「悪いわけがないだろう! 私以外に貴様を抱いた男がいたら、生きていることを後悔する目に遭わせるぞ! 貴様は抱きつぶす!」
「は? ば、馬鹿かっ! そんな奴いるわけないだろう! 抱きつぶすってなんだ! やめろっ、あれぐらいで十分だ!」
ダンッ! と、壁が叩かれなければ、多分、口論はつづいたことだろう。口論なんだか睦言なんだかもはやよくわからなかったが。いや、もしかしたら、隣の住人のやっかみがなくとも、口は言葉をつむぐ以外のことに使われたかもしれない。言い聞かせるより行動に移すほうが手っ取り早いと、思い定める寸前のことであったので。
仕事をさぼるなとかたくなに言う生真面目な義勇に、不承不承したがって、差し向かいに座りモソモソと二人で質素な朝食を食べた。もちろん、服は着て。
窓の外は上天気だ。無惨の体を痛めつける忌々しい太陽が、我が物顔で照っている。だが電話一本で運転手はリムジンをアパートに乗りつけるだろうし、不都合はない。そう無惨は思っていたが、義勇の行動はどこまでも無惨の理解の範疇を超えていた。
フード付きのダウンジャケットを着ろと押しつけてきたばかりか、マフラーだマスクだ手袋だと、いったいおまえは今何月だと思っているんだと言わんばかりの防寒具を、さも当然といった顔をして無惨によこしてくる。
「それぐらい着こめば日に当たらずに済むだろう? 駅まで送る」
言って自分は薄手のパーカーに袖を通す義勇は、この場で別れることなどきっと微塵も考えていない。当たり前のように、昨夜と同じく無惨を自転車の後ろに乗せる気満々だ。
無惨のリムジンは、紫外線を遮るスモークガラスで、居住性にも優れている。運転手は早朝だろうが真夜中だろうが、いきなり呼びつけられようと文句ひとつ言わない。今は初秋で、ダウンジャケットなど着ていればあっという間に汗だくになるだろう。不審者扱いされてもしかたないぐらいのいでたちとなること請け合いだ。
だが、無惨はそれらを着込んだ。眉間に盛大なシワを刻みつつではあったけれど。
「今日はバイトは休みだったな? 大学まで迎えに行く」
「自転車をどうしろと。置いていけないと言ってるだろうが。おまえ、意外と物覚え悪いんだな」
「電車で私と一緒に行けばいいだろう!」
不満そうに少し唇を尖らせるから、ハァッとため息をついて、無惨は舌打ちをこらえて義勇の耳に唇を寄せた。
「……電車など乗ったことがない。会社まで貴様が案内しろ」
キョトンとした義勇がクスクスと笑いだしたのに、フンと鼻を鳴らして、無惨は胸のうちでニンマリと笑う。日ごろそんなものを使う必要がないのは確かだが、いくらなんでも電車ぐらい一度や二度は乗ったことがある。恥をかき汗もかくなら、せめてそれぐらいのメリットがなければやってられない。
「しかたない。連れて行ってやる」
どこか楽しげに、子供のように義勇は笑う。思ったとおり、義勇は頼られると甘くなるようだ。家族は姉一人というから、甘えられることに弱いのだろう。年下の少女などに目が向く前に、しっかりと繋ぎとめておかねば。そのためならば、少しぐらいは甘えるそぶりをみせてやってもいい。甘やかすのはその後だ。
礼だと、ちょんと触れるだけのキスをすれば、また義勇は顔を真っ赤に顔を染めた。いずれは義勇のほうから素直に甘えてくるようにしてやる。無惨の決意は固く、その日が楽しみでならない。
後朝の別れと言うには俗に過ぎる、しめやかさなど微塵もない朝。無惨にとって人生最良の夜は、そんな具合に幕を閉じた。
振りまわされ、苛立ちや不満をせいぜい抱えながらも跪き、愛を乞う日々の幕開けとともに。