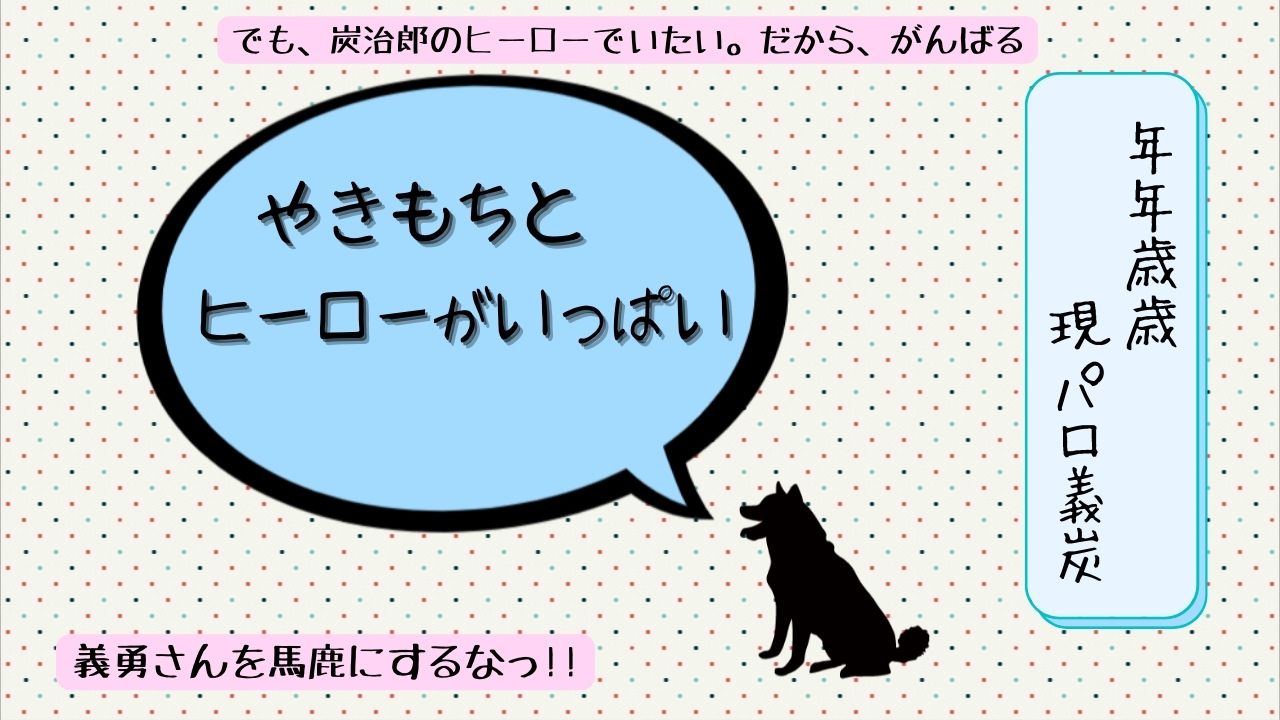7 ◇錆兎◇
銀髪忍者と大声金髪コンビの指摘は、義勇を馬鹿にしたクズの痛いところをついたらしい。
くだらない嫉妬といい、繋がれた犬や幼い子供相手でなければ強気に出れない卑怯さといい、つくづく小者だ。まだ落ち着かなげなハチをなでてやりながら、錆兎は青ざめる少年を横目でにらんだ。
おまけに妬む相手が義勇とは、身のほど知らずにもほどがある。比べることすらおこがましい。
返す言葉を見つけられないのだろう、ぶるぶると瘧のように震えていた少年は、じりっと後ずさりしたかと思ったらいきなり踵を返し駆けだした。
「てめぇら覚えてろよ!!」
捨て台詞すら小者感にあふれている。まったく、ろくでもないったらありゃしない。
「てめぇこそ証拠があんの派手に忘れんじゃねぇぞ! こっちはてめぇらの個人情報だって握ってんだからな!」
「そうなのか? 宇髄はすごいな!」
「おまえなぁ……あいつら冨岡の前の学校のやつだろ。名前や住所ぐらい、調べりゃすぐわかるだろうが」
「おお! そういえばそうだったな!」
金銀コンビの会話はいたって呑気だ。あのクズが逃げた理由の最たるものは、きっとこの二人の存在に違いない。義勇のクラスメイトということは中学三年なんだろうが、体格は平均よりもすこぶる良い。銀髪のほうときたら、小学生の錆兎では見上げる首が痛くなりそうなほどの大男だ。刃向かえない犬に石を投げることしかできないようなやつでは、向かっていく勇気なんて到底湧きようがないだろう。
義勇だってそんじょそこらのやつには負けっこないけれど、いかんせん体力が落ちきっている。すっかり線が細くなってしまって、見た目だけなら女の子のように華奢だ。あの卑怯者の義勇に対する強気な態度は腹立たしいばかりだけれど、侮られてもしかたないところではあるのだ。
侮られているのは、体格だけじゃないか。ため息を飲み込んで、錆兎は先ほど投げつけられた暴言を思い返す。
錆兎は、あいつが言ったみなしごという言葉が、常に義勇が陰で言われているものだと知っている。その言葉に含まれるものは、ときに蔑みだったり、あるときは哀れみだったり、意味合いはそれぞれだ。けれど、どんな場合でも優越感は必ず含まれていると思っているし、事実、それを感じ取ってもいる。
なぜならそれは、錆兎自身にも向けられるものだからだ。
錆兎には両親がいない。母は錆兎が赤ん坊のころに、病気で亡くなったのだと聞いている。父は最初からいなかった。
けれど錆兎は、惨めだなどと卑下したことはない。なんで自分だけと不満に思ったこともない。錆兎には厳しくもやさしい祖父の鱗滝がいたし、物心ついたころにはすでに従姉の真菰もいた。それだけで錆兎は十分満たされている。義勇が姉がいるだけで満たされていたように。
だから錆兎はひねくれることもなく、まっすぐに育った。
境遇のせいになどするな、不満があるなら自身の力で乗り越えろ。
そんな祖父の教えを、幼いながら錆兎は、きちんと理解し守っている。誰かを妬んで、自分の境遇をひがんで、薄暗い嫉妬を抱えて生きるなんて冗談じゃない。あんな下衆なやつらの同類に成り下がったら、爺ちゃんにぶっ飛ばされるし、真菰や義勇の隣に立つ資格だって失ってしまう。
自分が落ちぶれるのもごめんだが、努力をせず人の足を引っ張る輩にも、錆兎は憤りをおぼえる。くだらない嫉妬で義勇を馬鹿にするなど、錆兎にしてみれば決して許せるものではなかった。
義勇は錆兎にとって特別だ。それはもう、出逢った瞬間から。
なぜそんなふうに感じたのかはわからない。でも、はっきりと確信したのだ。少し緊張した顔で初めて道場に現れた義勇と、目が合ったその瞬間に。
こいつは俺の特別だ。俺にとって、守り抜かなきゃならない宝物みたいなやつなんだ、と。
もちろん、義勇は錆兎よりもずっと年上だし、守ってやるなんてそれこそおこがましい。義勇はすぐに剣道の腕前もあがって、まだ幼い錆兎よりずっと強くなった。それでも、やっぱり錆兎にとって義勇は、大切な弟弟子だった。義勇の心が迷子になって、以前とは比べものにならないくらい頼りなげになってしまった今は、なおさらに庇護欲がかきたてられる。
年上として、義勇が兄のようなやさしさで錆兎や真菰を守ろうとしてくれているのは、ちゃんと承知している。義勇が笑っていたころには、かまわれるのがうれしくて甘えてもいた。義勇の兄弟子だけど弟分。そんな自分の立ち位置は、こそばゆくも幸せだった。
錆兎がかなり年下であるのは変えようがないし、剣道だって中学生の義勇には、弱ってしまった今でさえかなわないだろう。それでも、自分だって大きくなれば義勇と背中を預けあって戦えるようになると錆兎は信じているし、努力もしている。義勇だって、錆兎や真菰のことを小さいからと軽く見たりせず、対等な立場だと信じさせてくれた。
学校の友達よりもずっと、義勇は俺や真菰を信用してくれている。
それを錆兎は疑ったことがない。信頼を裏切るまいとがんばってもいる。
けれど――。
そんな錆兎でも、真菰や鱗滝でさえも、迷子になった義勇の心を連れ戻すことはできなかった。
悔しくないと言えば嘘になる。どうして自分じゃ駄目だったのかと、嘆きたくもなった。それでも、義勇が少しずつ感情を取り戻してくれる幸福感にはかなわない。
炭治郎への感謝だって、絶対に嘘ではないのだ。
少しの遣る瀬なさを抱えたまま、錆兎は、茫洋とした顔で佇んでいる義勇を見やった。
さっき一瞬感じた覇気はもうない。苛立たしいばかりのクズだったけれど、義勇の雄々しい姿を久しぶりに見られたことは、ちょっとだけ感謝しないでもないな。
そんなことを考えて、思わず錆兎が苦笑しそうになったそのとき。不意に義勇が炭治郎の傍らに膝をついた。おや? と錆兎が思う間もなく義勇は、まだ怒りに震えている炭治郎の頭に、こつりと拳骨を落としている。
「あの、義勇さん……怒ってますか?」
こくりとうなずいた義勇に、炭治郎からたちまちのうちに怒りが消え失せたのが、傍目にもわかる。オロオロとする顔は早くも泣きそうになっていた。
きっと義勇に嫌われたとでも思っているんだろう。そんなことあるはずないのに。錆兎は今度こそはっきりと苦笑した。
義勇は心配してるだけなんだけどな。まだ炭治郎には通じないか。でもまぁ、あんな危ないことしたんだから、ちょっとぐらいは怒られたほうがいいだろ。
浮かんだのはちょっとの優越感。まだまだ俺のほうが、炭治郎よりも義勇のことを理解してやれる。胸をくすぐるのは、自尊心とかすかな安堵だ。
炭治郎はいよいよ瞳をうるませている。義勇も少し困っているように見えた。
しかたないな、助け舟を出してやるか。苦笑もそのままに、ハチを連れ義勇たちに歩み寄ろうとした錆兎だが、続いた会話に思わず目を見開いた。
「なんでわかった?」
「えっと、なんのことですか?」
「犬……俺が考えていたことを、なんでわかった?」
視線の先で、炭治郎が、ああ、と声を上げうなずいている。
「あの犬を逃がそうとしたことですね」
うなずき返す義勇に、錆兎の胸がシンと冷えた。
……俺は、義勇があの犬を逃がそうとしていたなんて、気づかなかった。
「わかったっていうか……義勇さん、あの犬が心配だから動けないんだなって思って。あの犬を逃がしてあげられたら、きっと義勇さんがあいつらをなんとかしてくれるって思いました!」
そんなこと、俺はまったく気づけなかった。
錆兎は呆然と、木に繋がれたままの犬を見つめた。怯えていた犬は、今ここにいるのは恩人たちだと理解しているんだろう。禰豆子になでられ、うれしそうに尻尾を振っている。
たしかに炭治郎が言うとおりだ。義勇のことだから、自分が動いたらあいつらが犬にひどいことするかもしれないのを警戒してたんだ。
錆兎は視線を落とし、自分の手をじっと見つめた。
まだ小さい手。体も心もまだまだ自分は幼い。どんなに義勇の兄弟子だ、俺が兄ちゃんだと言い張っても、やっぱり自分は義勇よりずっと子供なのだと、改めて思う。
義勇を悪く言われて、怒りで理性をなくした。状況を見定める目を曇らせた。
なんて、未熟……っ!
グッと拳を握りしめたとき、突然大きな手にぐしゃぐしゃと頭をなでられた。パッと手の主を仰ぎ見れば、銀髪の優男がどこか人の悪い笑みを浮かべて見下ろしている。
「なぁに地味に落ち込んでやがんだよ、チビ」
「チビじゃない」
ふふんと鼻で笑う男をにらみあげ、その手を払いのける。チビ呼ばわりは心外だ。不満に顔をしかめたが、それでも錆兎は、すぐにふっと息を吐くと神妙に頭を下げた。
「助太刀、感謝する。おかげで助かった。俺は錆兎。義勇の……」
一瞬の逡巡。けれど。
「義勇の、兄弟子だ」
今はまだ幼くて、まだまだ未熟者で。義勇のことならなんだってわかるなんて、思い上がりだと思い知ったばかりだけれども。
それでもやっぱり、俺は義勇の兄弟子で、義勇が大事で大切だから。
その自負をなくしたら、そんなの俺じゃない。足りないのならば努力すればいい。男なら自分の境遇は自分の力で乗り越える。それでなければ、義勇と肩を並べる男になどなれるものか!
いつか義勇の心のなかの一等席は、炭治郎のものになるのかもしれない。
だけどいつまでだって、自分が義勇の兄弟子であることは変わらない。
今は駄目でも、必ず義勇と背を合わせ戦える男になってみせるから。
だから錆兎は堂々と胸を張る。
それに今はまだ、義勇に任せたと言われるのは炭治郎じゃなく俺だしな。思いながら、錆兎は不敵に笑った。
傍らでハチが、同意するようにオン! と鳴いた。