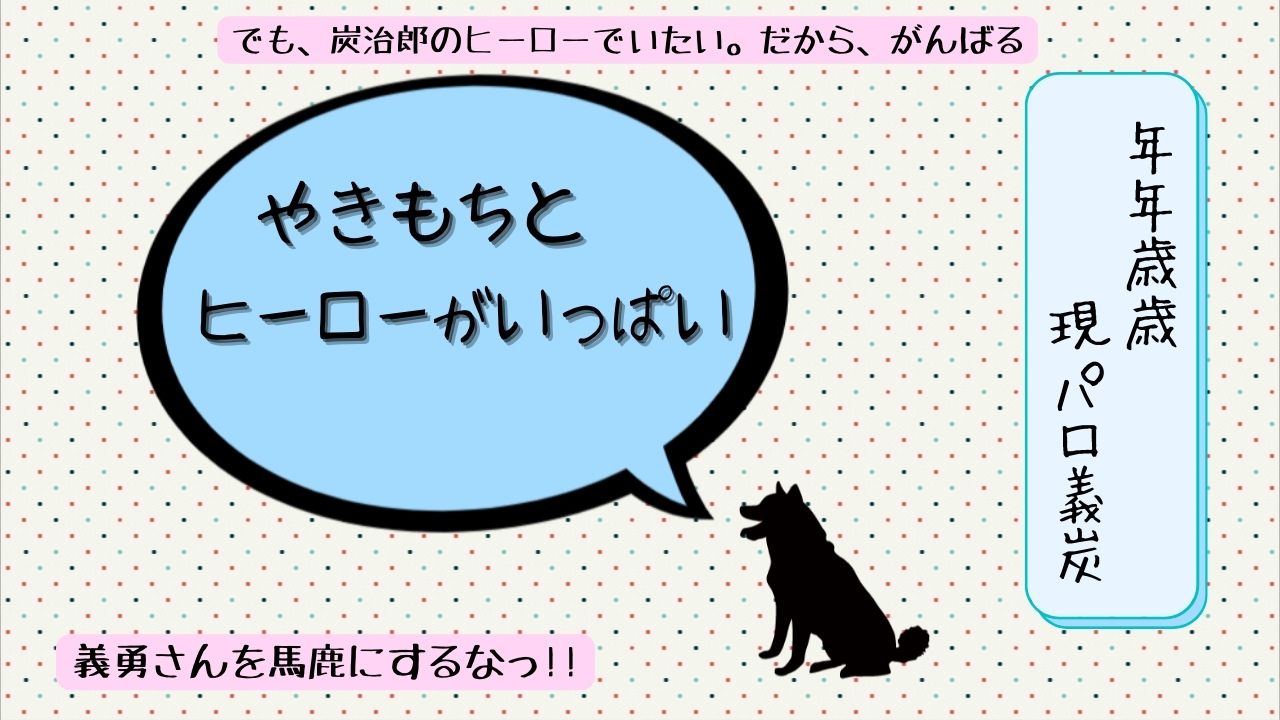3 ◇義勇◇
炭治郎の家から十五分ほど行くと、広い自然公園がある。ハチの飼い主によると絶好の犬の散歩コースなのだそうだ。
義勇の生活圏とは少し離れているから、義勇は初めて訪れる場所だが、炭治郎はいつも禰豆子や下の弟妹と一緒に来るらしい。炭治郎たちが遊ぶのは遊具が設置されたところだそうで、遊歩道に接した入口の近くだ。それより奥に進むとかなり大きな広場があり、思い思いに過ごす人たちがそこここに見えた。犬連れの人もそれなりにいる。
キャッキャと楽しげな笑い声をあげて禰豆子がハチにまたがるのを手助けながら、義勇は腰が引けそうになるのをどうにかこらえた。
だって本当に苦手なのだ、動物は。とくに犬は駄目だ。
昔は犬も好きだったと思う。けれど、幼児のころに大きな犬に追いかけられ噛まれて以来、近づくのはちょっと怖い。
犬が怖いなんて、炭治郎の前ではもちろん口には出せない。気づかれるのも恥ずかしい気がする。
なるべく離れてやり過ごそうと思っていたが、なぜだかハチは、義勇に懐いてしまったらしい。前に逢いに行ったときなど、義勇の顔を見た途端にころりと転がり、腹をみせて降参ポーズをしてみせた。
内心驚きつつ困っていた義勇とは裏腹に、炭治郎と禰豆子は、凄い凄いと大はしゃぎでハチをなでまわしていた。
義勇さんもなでてあげてくださいと言われても、近づきたくない。
錆兎と真菰はと言えば、クスクスと笑いながらも、ハチと義勇の間に入って炭治郎たちと一緒にハチをなでていた。気を遣われているなとは思ったが、炭治郎や禰豆子の前で、犬は怖いから嫌だなど言えるはずもない。
なので義勇はただ立っていただけなのだけれど、ハチは自分を取り押さえた義勇をボスと決めてしまったみたいだ。しきりと義勇にかまわれたがる。
どうしてこうなったんだろう。心のなかだけで義勇はちょっと首をひねった。
二人で行くはずの墓参りは、なぜだか両家の全員で行く流れになった。炭治郎はそれを残念がっているように見えたので、ならばと内緒で犬に逢うことを提案したのだ。犬に近づくのは気が進まないが、炭治郎が喜んでくれるならと思ったから。
炭治郎はきっと犬が好きだろうと思ったし、あの犬ぐらいしか、接点のない子供と逢う理由を義勇は見つけられなかった。
結論を言えば、二人だけでというのは、無謀な約束でしかなかったわけだが。
それでも炭治郎はうれしそうだったし、錆兎や真菰も、禰豆子だって同様だ。それぞれ犬と仲良くなり、楽しそうだったので良しとする。
炭治郎は義勇のことをヒーローだとしきりに言うが、炭治郎こそ、義勇にとっては恩人だと思う。
だって、思い出させてくれた。大切な言葉を。姉が自分に向けていてくれた愛を。
姉がいつも笑ってくれていたのは、義勇にも笑っていてほしいからだと、わかっていたはずなのに。義勇だって大好きな姉に笑っていてほしくて、いつも笑っていようと思っていたというのに。
すべてから目を逸らして、自分を慕ってくれている錆兎や真菰、思いやってくれる鱗滝をも悲しませていた。せめて心配させまいとどうにか暮らしてはいたが、それが義勇の限界だった。
自分が笑えなければ、姉も、錆兎たちも、心から笑ってくれることなどないのだ。それをずっと、炭治郎と出逢うまでずっと、忘れていた。
自分を責めて殻に閉じこもった義勇の手を取り、黒い靄に満たされた義勇の心に、光を灯してくれた子供。義勇が迷子になったなら絶対に迎えに行くと約束してくれた、炭治郎。
そして思い出したのだ。義勇を慈しんでくれる人たちが、義勇に一番に望んでいたことを。
義勇自身が笑っていること。幸せだと、笑えること。誰もが、そう望んでくれていた。
忘れていた、思い出そうともしなかったそれを、炭治郎が思い出させてくれた。
そんな炭治郎が喜ぶのなら、自分にできることはしてやろうと思った。まだ自分の心はふわふわと漂いたがってしまうことが多くて、他人から見ればまともな精神状態とは思われないのだろう。昔のように笑ったり泣いたりできるほどには、失った感情は戻っていない。
それでも、炭治郎がくれた光に見合うなにかを、少しずつでいいから炭治郎に返していきたいと思った。
錆兎や真菰はまだ心配なのか義勇をかまいたがるので、炭治郎が望むように二人だけというのは当分無理そうだ。けれども錆兎や真菰を安心させるのだって、炭治郎に恩を返すのと同じくらい義勇にとっては大事なことだからしょうがない。しばらくはこんなふうに、みんなで逢うことになるのだろう。義勇ははしゃぐ子供たちを見ながら、そんなことをぼんやりと思っていた。
「ハチはこんなにおっきいのに、義勇さんはどうやってハチを抑えられたんですか? 怖くて目をつぶっちゃったから見てないんです」
そう炭治郎に問われて、義勇は、さてどう答えたものかと、今度は現実に首をひねった。
「……竹刀で?」
「自分がやったのに疑問で返すなよ」
錆兎に笑われたけれど話をするのは元々苦手なのだ。それを知っている錆兎や真菰は、義勇がなにも言わずとも視線やちょっとした仕草で悟ってくれる。まだ小さい二人に甘えている自覚はあるが、錆兎たちも喜んでいる節があるので、まぁいいかと思ってしまう。
だが、炭治郎を喜ばせたいのなら、これではいけないのかもしれない。
とはいえ、義勇はまだまだスムーズに話ができるような状態ではない。人の言葉を理解できるぐらいには回復してきてはいるが、言葉を返すにはタイムラグが生じるのだ。
心の許容量を超えた悲しさは、今でこそ少しずつ薄れつつあるけれど、まだ義勇の心の大部分を占めている。炭治郎たちの言葉ならばともかく、他人の言葉はまだまだ駄目だ。理解するまでにも、それに自分の言葉を返すのにも、人よりずっと時間がかかる。
錆兎や真菰から言わせれば、いや口下手は元々だろうと呆れられるかもしれないが、義勇にはそこら辺の自覚はない。
実践してみせるのが一番手っ取り早いが。思いながら、しっぽを振りながら自分を見上げているハチを見やった義勇は、困ってしまって眉を下げた。
「やってみせるほうが早いなぁって思ってるでしょ」
「でもかわいそうだからしたくないなぁって思ってるよな」
笑いながら錆兎と真菰が言うのに、こくりとうなずいてみせる。
「そっか……そうですよねっ。ハチを苦しくさせちゃったの、義勇さん心配してましたもんね!」
一瞬だけ炭治郎の顔が曇った気がしたのは、気のせいだろうか。合点がいったという顔でこくこくうなずく炭治郎は、もう先の質問の答えを求める気がないように見えた。
「やっぱり義勇さんは凄くやさしいですね」
うれしそうに称賛の声をあげる炭治郎の顔には、いつもの明るい笑みしかない。
炭治郎は、義勇のことを本気でヒーローだと思っているのだろう。自分はそんな格好いいものじゃないのにと、義勇の罪悪感がちょっぴりうずいた。
本当は犬だって怖いし、中学生だというのに幼い錆兎や真菰に頼りっきりになってしまっている。どうしようもない男だと義勇も自覚している。
なのに炭治郎はキラキラとした大きな目で、義勇さんは凄い、義勇さんはやさしいと、まっすぐな好意を伝えてくるのだ。
こんなふうになって以来、人を苛つかせたり馬鹿にされたりしてきた義勇にとって、そんな炭治郎の称賛と憧憬の眼差しは、まぶしすぎていたたまれない。それに、なんだかちょっと照れくさくもある。
返す言葉を見つけられずに、視線をついと逸らせた矢先。
キャインッ!
突然聞こえた犬の悲痛な鳴き声に、思わず全員が声のしたほうへと視線を向けた。
広場を取り囲むように植えられた木立のなかから、その声は聞こえた。大型犬のハチを連れているからか、義勇たちがいる場所の近くに人の姿はない。その鳴き声に気づいたのは義勇たちだけなようだ。
「……おばさんが言ってたよね、ハチを置いてトイレとか行くときは、人から離れた木に繋いでねって」
「犬を連れた人はみんな、林のなかに繋ぐようにしてるからって言ってたな」
真菰と錆兎のつぶやきが終わる前に、義勇は、ハチのリードを持ったまま走り出していた。
考えるより早く体は動く。突然走り出した義勇に、ハチも義勇を引っ張る勢いで義勇が望む方向へと駆けだした。
キャンキャンと悲しげな声は、断続的に聞こえてくる。後を必死に追いかけてきている子供たちの気配が遠くなるのを感じ取りながら、義勇は木立の間に飛び込んだ。
そこに見えた光景に、義勇の眉根がグッと寄せられた。
パーカーのフードを被った人影は三人。木に繋がれた中型犬はうずくまって震えている。辺りに散らばった石ころは一つや二つどころじゃない。犬を取り囲む三人の手には、それなりに大きい石があった。
足元でグルルルルとハチが唸り声をあげた。姿勢を低くして威嚇の体勢だ。
ハチの唸り声に気づいたのか、三人が振り返った。顔は一様に深く被ったフードの影になってよく見えない。だが、おそらくは義勇と同じ中学生くらいの少年たちだ。
万が一に備え竹刀を取り出そうとしたが、義勇はすぐに傍らのハチの存在を思い出し逡巡した。この状況でリードを放すわけにはいかない。ハチはかなり興奮しているように見える。炭治郎たちに襲いかかろうとしたときの姿を思い出せば、楽観はできなかった。大型犬のハチが人を噛めばどうなるのかなど、考えずとも答えは明らかだ。
「……なんだ、冨岡じゃん」
嘲笑うような声があがった。
義勇が訝しむ間もなく、お手玉のように石を弄んでいた少年が、ハチを見て舌打ちをひびかせた。
「なぁ、あれ、鎖千切って俺に飛びかかろうとした馬鹿犬じゃねぇか?」
「え、マジで? 犬の区別なんてつかねぇよ。でもあれ、本当にムカついたよなぁ」
「もっと痛めつけてやれば良かったよなぁ。くそ犬が人間様に歯向かいやがって。マジムカつく」
ハチはまだ低く唸っている。だが少年たちは馬鹿にした態度を崩す様子もない。
「そんな馬鹿犬が一緒だからって強気になってんじゃねぇぞ。人噛んだらそんな犬、すぐに殺処分だからな。そんぐらい狂った頭でもわかんだろ? 頭のおかしい冨岡くぅん?」
そう言って三人はゲラゲラと笑った。
俺の名前も現状も知っているということは、こいつらは知り合いなんだろうか。訝しみつつ義勇がパーカーの影になった顔を見定めようとしたと同時に、真ん中の少年がハチに向かって石を投げつけてきた。
キャウン! と声をあげてハチが後ずさる。
ギッと少年を睨みつけ、義勇がハチを庇うために進み出ると、少年はまた舌打ちした。
「なに偉そうににらんでやがんだよ。頭のおかしいやつが、まともな人間にそんな態度とっていいと思ってんのかぁ?」
「だよなぁ? 教科書に落書きしたり上履き捨てたぐらいでコソコソ転校した弱虫のくせに、にらんでんじゃねぇよ」
「大体、こんな犬っころ苛めたぐらいで怒るほうが馬鹿だよな。あぁ、そっか。姉ちゃんが死んだぐらいで頭おかしくなった馬鹿だったな、おまえ」
嘲笑いながら一人の少年が、まだうずくまって震えている中型犬に近づき、蹴飛ばそうと足を振り上げる。
「やめろっ!!」
怒鳴り駆け寄ろうとした義勇の足が、少年たちの言葉を思い出し止まった。
殺処分。ハチが殺されるかもしれない。
義勇が動けば、ハチもきっと少年たちに襲いかかってしまうだろう。あの日、炭治郎と禰豆子に対してさえ飛びかかろうとしたように。
それは駄目だ。しかし、義勇が動くなと命じたところで、飼い主でもない義勇の命令を聞いてくれるだろうか。
こんなやつらにかまう気など毛頭ないのだから、このまま立ち去ってしまうのが最善なのかもしれない。交番なり公園の管理人なりに伝えればいいのだ。だが、それでは遅い。大人がくるまでに、木に繋がれたままのあの犬がどんな目に遭うかわからない。
ハチの動きを抑えつつ、あの犬を逃がす。そんな手立てがあるだろうか。
義勇の沈黙を怯えと取ったのか、少年たちはますます嘲笑をひびかせた。それを止めたのは、幼い子供の呼び声だ。
「義勇さんっ!!」
「義勇っ!!」
到着するなり子供たちは事態を理解したらしい。タッと走り寄った炭治郎たちは義勇の前に回り込んでくる。義勇とハチを守るように大きく両手を広げ立ちはだかった様は、まるで壁になろうとしているかのようだ。
「おまえらがハチに石投げた犯人だな! 義勇に近づくな!」
「義勇になにする気だったの! ひどいことしたら許さないんだから!」
錆兎と真菰が口々に怒鳴るのに、少年たちは一瞬呆気にとられたように見えた。だが、すぐに前にもまして大きな声で笑いだした。
「やっべ、おかしすぎんだろ。笑えるぅ」
「こんなガキどもにお守されてんのかよ、冨岡のやつ」
「俺らに苛めはやめろとか偉そうに言ってたくせに、そこまで頭おかしくなってんのか。いい気味!」
少年の言葉に義勇はようやく、目の前にいるのが以前のクラスメイトだと思い出した。
教師の前ではおとなしく、素行も悪いわけではない。傍目には普通の生徒たちだ。だが影では気弱な同級生を脅して、金を巻き上げたりしている奴らだ。義勇がそれを知ったのは偶然だが、見過ごすことはできず、絡まれていた子を庇いやめろと注意したことがある。
成績も優秀で真面目だった以前の義勇は、ほかの生徒たちや教師からの信頼が厚かった。そんな義勇に、少年たちは分が悪いと思ったのだろう。悪態をついたものの、それ以降は嫌な目つきでときどき義勇を睨みつけるだけで、手を出してくることはなかった。
このままとくに問題もなく終わるだろうと義勇は楽観していたし、実際そうなると思われた。
義勇の姉が亡くなったのは、その矢先のことだった。
「おい、ガキ。そんな頭おかしくなってるやつといたら危ねぇぞ。近くにいたらなにされっかわかんねぇよなぁ?」
「そうそう、油断してると殺されるかもよぉ?」
「いきなり暴れだしたりしそうだよな。なんせ狂っちゃってっから」
ゲラゲラと馬鹿にして笑う言葉ぐらいでは、義勇の感情は動かない。姉のことを言われれば怒りは湧くが、自身についての侮蔑には、義勇はなにも感じない。深すぎる悲しみは、義勇から感情を奪ってしまっていたから、苛められることに苦しむような余地すらなかった。
それよりも、子供たちに危害を加えられるほうが、よっぽど怖い。それだけは阻止しなければ。義勇の頭のなかで、目まぐるしく状況打破の手立てが浮かんでは消える。
木に繋がれて動けないあの犬。あの犬さえ逃がせば、ハチを子供たちに任せることができるか? 犬に一番近いやつがおそらくは主犯格。あいつを抑えられれば、残る二人はどうとでもなりそうではある。
だが、どうやって近づく? 自分を犬の代わりに痛めつければいいとでも言えば……却下。そんな提案を子供たちが許すわけがない。下手したら事態が悪化する。
なにか。なにか一つでいい、この状況を変える出来事があれば。あいつらがあの犬へと意識を向けないようにできたら。
思いながらちらりと顔を犬に向けたとき。義勇を気遣うように振り返った炭治郎と目が合った。
視線が交わったのはほんの一瞬。
その一瞬で、炭治郎はなにかを決意したように息を吸い込んだ。
「義勇さんを馬鹿にするなっ!!」
叫ぶなり少年たちに向かっていった炭治郎に、瞬時に義勇の頭にわきあがったのは怒りだ。
馬鹿なことをと怒鳴りつけそうになった義勇は、けれどそのまま息を飲んだ。まっすぐに走っていた炭治郎の小さい体が、わずかに右にかしいだ。気づいた刹那、その意を悟る。
なるほど。しかし無謀であることには違いないぞと眉を寄せ、義勇は、迷うことなくリードを錆兎に向けて放り投げた。竹刀を取り出しながら、任せたとだけ言い残し、義勇は駆ける。
その言葉にハッとして、リードを握った錆兎と真菰がハチに飛びついて抑えた。ハフハフと息を切らせて追いついた禰豆子も、わけがわからないなりに一緒になってハチに抱き着いている。
「ハチ、動くなよ!」
「義勇の邪魔しちゃ駄目!」
「ハチ、おすわり!」
口々に言う声を背に炭治郎を追った義勇は、炭治郎のシャツを掴み引き寄せ、すぐにその手を放した。ワッと声を上げて背後で尻もちをついた炭治郎をそのままに、跳ぶように踏み込みながら、鋭く竹刀を突き出す。
炭治郎に気を取られていた少年は、突然の義勇の行動に反応さえできなかったのだろう。首を掠めてフードに突き入れられた竹刀に、ヒッと小さく悲鳴が上がった。
それに頓着することなく、義勇はそのままフードをねじるように竹刀を返した。フードにくるまれた剣先を、迷うことなく下に向ける。さらに一歩大きく踏み込みながら体をひねり、義勇は少年の背後を取った。そのままの勢いで剣先をフードごと地面に突き立てる。
それは義勇が駆けだしてから三十秒にも満たない間の出来事。
うつぶせに倒れた少年は悲鳴を上げたが、おそらくは、自分の身になにが起こったのかすらわかっていないだろう。その背に片膝をつき動きを抑えると、義勇は、ゆっくりと炭治郎に視線を向けた。
「……こうした」
「え? えっと、なにがですか?」
炭治郎が立ち上がりながらキョトンとした顔で聞くのに、無言で義勇は、錆兎たちに抱え込まれているハチにちらりと目をやった。そうしてまた、炭治郎をじっと見る。
「あ! ハチを抑えつけたときですね!」
こくりとうなずけば、炭治郎の顔がパァッと輝いた。
「凄い! 凄いです、義勇さん! やっぱり義勇さんはすっごく強いやっ!」
大興奮ではしゃぐ炭治郎と同じく、錆兎たちもハチと一緒に駆け寄りながら、凄い凄いと大喜びだ。
「ふ……ふざけんな! どけよ!」
「冨岡てめぇ、頭おかしいくせに生意気なんだよ!」
怒鳴りながら仲間を抑えつける義勇を蹴りつけようとする少年たちに、ハチが思い切り吠え立てる。びくりと震えて足を下ろしたものの、少年たちは憤懣やるかたない様子で、口々に義勇を罵倒しだした。
「こんなことしてどうなるかわかってんだろうなぁ、冨岡ぁ!」
「てめぇがいきなり乱暴してきたって言いふらしてやるからな! てめぇみたいな頭おかしいやつは、鉄格子ついた病院にでも入ってりゃいいんだよ!」
「さっさとどけよ、痛ぇだろ! 絶対怪我したぞ、慰謝料よこせよな!」
そんな言葉に激高したのも、義勇ではなく子供たちのほうだった。
「義勇さんになんてこと言うんだ! おまえらこそハチやその犬を苛めてたくせに!」
「ふざけてんのはどっちだ! 天網恢恢疎にして漏らさずっ、おまえらの悪行が許されると思うなよ!」
「義勇を馬鹿にするなんて、なにがあろうと絶対に許してやんないんだからね!」
「大嫌い! 馬鹿ぁ!!」
ギャンギャンと喚きたてる子供たちに、義勇はちょっと困ってしまう。主犯格っぽいこいつを放すわけにはいかないが、このまま膠着状態というのもいただけない。子供らに危害を加えられるのだけはなんとしても防がなければならないが、どうしたものか。
自分はまったく気にしてないのだから、そんなに怒ることはないのに。
それなのに炭治郎たちは、絶対に許すものかと小さな全身に怒気を孕ませ、一歩も引く気がないようだ。禰豆子にいたっては、嫌い嫌いと泣き出してしまっている。ハチもそんな子供らにつられて吠え続けているうえ、石を投げられていた中型犬も少年たちの劣勢を感じ取ったのか吠えだす始末だ。
途方に暮れていた義勇の思考を、少年らの言葉が引き戻した。
「うるせぇガキどもだなぁ。そうだ、こいつらも冨岡と一緒に犬に石投げてたことにしてやろうぜ」
「お、それいいな。注意した俺らに冨岡がいきなり襲いかかってきた、と」
「ガキや頭の狂ったやつの言うことなんか、誰も信じるわけねぇもんな。俺らのほうが被害者でーす、頭おかしいやつらに襲われて怖かったですーってな!」
ニヤニヤ笑って子供たちに言う少年らに、義勇の体がカッと熱をおびた。
自分のことなどどうでもいい。だが、この子たちに対しての悪意は絶対に許さない。
義勇は、試合や鱗滝との打ち合い稽古以外、人に向かって竹刀を振るうことはない。ハチとの一件だって、首輪の隙間を狙って極力痛めつけぬようにしたぐらいだ。
けれど、もしもこいつらが子供たちに手を上げようとしたら、きっと自分はこいつらを叩きのめしてしまうだろう。それで危険視されて本当に病院送りになったとしても。
竹刀を持つ手に、ぐっと力がこもったそのとき。
「ふむ。だが、第三者の証人の言葉なら信じると思うぞ!」
「証拠もあるしな。派手にばら撒いてやってもいいぜぇ?」