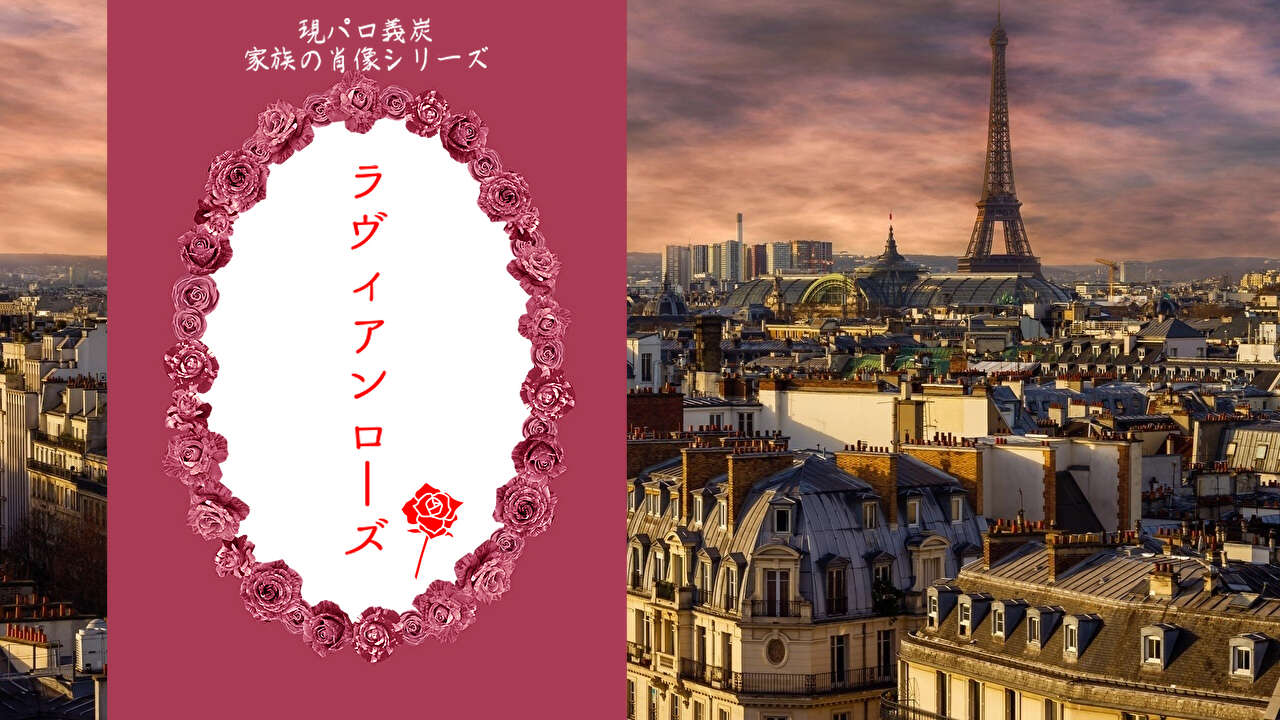毎日退屈だった僕の人生に、バラ色の輝きがもたらされたのは二年前、九月のとある日のことだった。
だからといって、くだらないことばかりの僕の人生の、さえない日常は、ちっとも変わりゃしないけど。
「おい、スリミの在庫出てないぞ。サボってないでちゃんと働けよ」
そりゃないだろ。僕が今なにしてるのか見えてないのか? 棚に並べてる最中だった瓶詰を片手に、思わず主任を睨みつけそうになった。気持ちだけは。
「ノロノロしやがって、おまえが遅いぶん、俺がカバーしなきゃいけなくなるんだぞ」
今まさに僕は、アンタが補充し忘れていた瓶詰を品出ししてるんですけどねぇ? 言えないけどさ。
「これを並べたらやります」
「さっさとしろよ」
フンと鼻を鳴らして去ってく主任にゴマペーストの瓶を投げつけて、嫌味ったらしいあの銀縁眼鏡をたたき割ってやりたい。しないけど。真面目に働きますよ、ええ、アンタと違ってね。
あぁ、くだらない毎日だ。主任みたいなラシストには蔑まれ、ユニヴェルシテを卒業したって、職場はスーパーマーケット。毎日品出しにレジ打ち、憧れの日本に行くなんて夢のまた夢の安月給だ。
毎日毎日商品を並べて売ってくたくたになって、家に帰ったら動画サイトで日本のアニメを見るぐらいしか楽しみはない。日本の出版社に就職して、マンガ雑誌の編集者になりたいなんていう大それた夢も、今は遠い昔だ。まだ二十五。もう二十五。諦めるには早いと年寄りどもは言うけれど、二十五年間も生きてりゃ、自分の限界ぐらい悟りますって。
爺ちゃんもさ、移民するなら日本にしてくれりゃよかったんだよ。まぁ、大戦後の日本に渡ろうなんてのは、土台無理な話だってことぐらいはわかってるけども。
大戦が終わって、フランスの植民地だったアフリカから、爺ちゃんたちがフランスに渡ってきたのは、正解だったとは思えない。アフリカにいたって先がないって考えたのは、わからないでもないけど。
フランスは平等と友愛の国なんていったって、主任みたいなラシストはどこにだっているもんさ。表立って黒ん坊なんて言われなくとも、僕だって馬鹿じゃない。嘲りぐらい感じとれる。
爺ちゃんや婆ちゃん、父さんみたいな真っ黒な肌じゃなくても、僕のなかのアフリカの血は濃い。パリ生まれパリ育ちの、生粋のパリジャンであってもね。
ヘルシーだと日本食がもてはやされるようになってから、スーパーで扱う食材にも日本っぽいものが増えた。今並べてるゴマペーストもそうだし、スリミもそう。まぁ、スリミが日本の食材だったなんて、SNSで知り合った日本の友達に教えられるまで知らなかったんだけど。日本ではカニカマっていうらしい。
日本はアニメやマンガだけじゃなく、食べ物も素晴らしいよね。マヨネーズをつけて食べるのがお気に入りだ。通りを歩けばピザ屋よりもテイクアウトのスシ屋のほうが多いのもうなずけるよ。だってヘルシーだしおいしいもの。
毎日くだらないことばかりだけれど、楽しいことがまるでないってわけじゃない。今年もジャパンエキスポに行けたし、久しぶりに会えた友達とも、日本で人気のマンガやアニメの情報交換だってできた。
それに、今日ももうそろそろ僕の天使たちがやってくる時間だ。彼らの姿を見てるだけで、僕の砂漠みたいな人生にもバラが咲くってものさ。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
築八十年になるアパルトマンの、一階にあるスーパーマーケットが僕の職場だ。
近代的なアパルトマンもかなり増えたけど、いかにもフランスらしい昔ながらの石造りのアパルトマンへの憧れからか、外国籍の住民は割合多いらしい。アジアンもそれなりにいる。
僕らからするとアジアンはみんな同じように見えるから、日本人なのか中国人なのかも見た目じゃわからないけど、会話を聞けば日本人の区別はつく。
アニメで覚えた日本語は、披露する機会なんてあまりない。日常で聞く機会も。職場は普通のスーパーマーケットだからね。観光客なんてそんなに来ないんだ。やってくるアジアンは、このアパルトマンの住民ばかり。彼らは家族とは母国語で話すけど、僕らには英語かフランス語だ。
不思議なんだけど、なんでフランス人に英語が通じるなんて思うのかな? 僕もそうだけど、フランス人はあんまり英語は得意じゃないんだ。英語で話しかけられても困っちまうよ。英語はHの発音がネックだよね。どうにも馴染めない。
そりゃまぁ、パリは色んな人種がいるから英語を話せる人も多いし、僕だって簡単な会話ぐらいならなんとかできるけど。英語なら通じるだろうって思うのか、アジアンがバーッと英語で話しかけてくると、思わず腰が引ける。
でも、彼が初めて僕に話しかけてきた言葉は、すっごくぎこちないフランス語だった。
今から二年ほど前の話だ。
「ボンジュール。このお店にダイコンは売ってますか?」
ラディブランを言いにくそうに言った彼は、リセの学生に見えた。赤みがかった髪と目のアジアン。カードっぽいデザインの大きなピアスは、アニメで見たことのある日本の花札に似てる。
「あぁ、ありますよ。あちらの野菜コーナーにあるので、探してみてください」
「メルシー! それから『えーと、鮭ってなんて言うんだっけ? 味噌や鰹節も買わないと……でもフランスで売ってるのかなぁ』魚! 魚の場所どこですか? ミソはありますか?」
彼が独り言みたいに言った言葉は、アニメで馴染んだ日本語っぽかった。
「ニッポンジン?」
「え? あ、日本語話せるんですか!? うわぁ、うれしいなぁ!」
僕の手を握ってブンブンと振る彼は、輝くみたいな笑顔をしていた。まるでお日様さ。日本人はスキンシップやはっきりとした意思表示が苦手だって聞くけど、彼はとてもフレンドリーであけっぴろげだった。
「ゴ、ゴメナサイ。もっとゆっくり」
「あ、ごめんなさい! フランスの人に日本語が通じたの初めてで、つい興奮しちゃって!」
彼は僕の黒い肌を気にしていないみたいだった。僕がフランス人だっていうことにも。
英語もだけど、なぜだかアジアンっていうのは、フランス人は白人ばかりだと思ってる人が多いんだ。観光客なんかは特にそう。エッフェル塔の辺りなんか歩いていると、僕も観光客に間違われてるんだなって思うことがたびたびある。
ともあれ、それが僕とタンジローとの出逢い。
彼はこのアパルトマンに引っ越してきたばかりだった。マルシェやアジアンスーパーまで買い物に行かないと日本食は食べられないかと思ってたけど、このスーパーである程度買えて助かったと笑ってた。
フランス語はうまくないけど、表情豊かで、物おじせず話しかけてくるから、意思疎通はそんなに問題はない。フランス語、英語、日本語が入り混じる片言の会話もけっこう楽しいもんだ。
僕はすぐにタンジローが大好きになったし、彼も店にくると必ず僕に声をかけてくれるようになった。
ビックリしちゃったのは、タンジローが僕よりも年上だってことだ。どう見たって、せいぜいリセの学生。下手したらコレージュに通ってたっておかしくないベイビーフェイスなんだ。なのにタンジローは僕よりひとつ年上の二十四歳だっていうんだから、驚いたのなんのって。
日本人は若く見えるって本当なんだな。言えばタンジローは、
「俺は日本でも年よりも若く見られてたけどね」
と、頭をかきながら照れ笑いしてた。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
あれから二年経ったけど、タンジローはすっかりお得意様だ。毎日のように買い物にきてくれる。フランス語もだいぶうまくなった。
僕だけじゃなく、タンジローがくると店員はみんな、明るく声をかける。タンジローもうれしそうにみんなと献立のことなんかの話をするんだ。
タンジローは、愛らしいマリーゴールドの花みたいな子……失敬、人なんだよ。見ている人をみんな微笑ませちゃうんだ。
そりゃもちろん、全員が全員、タンジローに好意的とは言えないよ? 主任みたいなラシストからすれば、アジアンだって小馬鹿にする対象だ。タンジローの姿が目に入ると、主任は「ああいうののせいで店がソース・ドゥ・ソジャ臭くなる」って小馬鹿にしてた。調香師をしているタンジローから、そんな匂いがするわけないってのにさ! それに、ショーユの匂いは別に悪い匂いじゃない。僕は大好き。だっておいしい日本食にはショーユがつきものだもんね。
主任がタンジローを嫌がるのは、タンジローが日本人だからってばかりじゃなかった。
「やぁ! この前話してた雑誌、弟が送ってくれたから持ってきたよ!」
聞こえてきた明るい声に、スリミの段ボールを抱えたまま慌てて振り返ったら、タンジローが手を振ってた。
「ワォ! 本当かい!? アリガトゴザイマス!」
フランスでも大人気なアニメの原作マンガが載ってる雑誌を見てみたいって、僕が口にしたのは二週間ぐらい前だ。ほんのちょっとした会話だったのに、タンジローはちゃんと覚えていてくれたらしい。きっと日本にいる弟くんに頼んでくれたんだろう。こういうところが本当にいい奴なんだよ、タンジローって。
「……幼稚だな」
「コラッ、月彦」
ぼそりと呟かれた流暢なフランス語に、思わずこめかみが引きつった。タンジローに叱られてもまったくめげた様子なんてなく、フンと鼻を鳴らした男の子は、顔だけ見れば天使だ。
ゆるくウェーブした艶やかなブルネット。真っ白い肌に深紅の瞳。生きて動くビスクドールみたいなツキヒコという名の男の子が、タンジローと一緒に店にくるようになったのは、一年ぐらい前のこと。
彼は、タンジローの息子だ。
年はたしか八歳だって聞いたけど、スキップしてコレージュに通ってる。驚くほど頭のいい子なんだ。すごく体が弱くて学校にはあまり通えないせいか、今年は留年しちゃったみたいだけどね。
「ごめんな、留年が決定してからずっと機嫌悪いんだよ」
「い、いや、気にしてないよ」
「パパ、口が軽い男なんてろくなもんじゃないよ。少しは黙ってるってことを覚えたら? ……だからオトウサンと一緒に家にいるって言ったのに」
お父さんっ子の月彦くんは、タンジローには手厳しい。
そう。彼はタンジローとそのパートナーである『お父さん』の息子だ。血の繋がりはない。養子なのだ。
同性婚もめずらしくなくなったけど、保守的な人や差別的な目で見る人は今もいる。主任がタンジローを毛嫌いする理由は、それで察してくれよ。僕は口にするのも嫌だね。
「今日はギユーは家にいるのかい?」
「うん! ほら、月彦がこの調子だからさ。体調も崩しちゃったから、義勇さんも心配しちゃってね。最近は休日の仕事を減らしてるんだ」
コソコソと耳打ちしたタンジローの言葉は、しっかりとツキヒコくんの耳にも入っちゃったみたいだ。「余計なことを言うなっ」って、キリキリと眉をつり上げてる。
「えぇー! 家にいるならギユーも一緒にきてくれればよかったのにぃ!」
「ルシィ……仕事しなよ」
「おしゃべりしてる人に言われたくなーい」
聞き耳立ててたな? 嘆きながら近づいてきた同僚のルシィは、タンジローのパートナーであるギユーの大ファンだ。気持ちはわかる。だってさ、ギユーってすっごく格好いいんだ! 細身だけど、スポーツジムのインストラクターをしてるだけあって、すごく鍛えられてるのがよくわかる体をしててさ。ムッキムキのマッチョマンと違って、まるで日本刀みたいなんだよ! おまけにとんでもなくハンサムだ。そりゃもう、初めて彼を見た日にバックヤードでルシィが、「なにあのアジアンビューティー! 人類の至宝かっ!」って叫んだぐらいにね。
まぁ、ルシィはもともと僕と同じく日本贔屓で、日本のアイドルに目がないからってのもあるかもしれないけど。
でも、ギユーが美貌の人であることに間違いはない。
タンジローが愛らしいマリーゴールドなら、ギユーはフルール・ド・リスだね。そう、我がフランスのブルボン王朝で紋章にもなっていた美しいあの花さ。
そんなタンジローとギユーがカップルであることを、ルシィはどう思ってるのか、こっそり聞いたことがある。だってさ、心配だろ? ふたりの仲を裂いて後釜に……なんて。そんなことをたくらむような子じゃないとは思うけど、幸せなふたりに水を差すようなことがあっちゃいけないもの。
ルシィの答えは。
「アイドルはね、触れずに愛でるものなのよ。わかる? それにギユーの美貌が一番輝くのはタンジローといるときだし、タンジローの愛らしさが花開くのはギユーの微笑みがあればこそよ! ふたりセットで推してるに決まってるでしょ!」
うん、まぁ、わかってたよね。いいファンだと思うよ、うん。
美しいもの愛らしいものは、誰だって好きだ。僕は同性愛者じゃないけれど、僕だって彼らを見ているのがとても好きだもの。
彼らのことを好きなのは、見た目だけじゃないよ? ふたりともとても誠実で、思い遣りにあふれてるんだ。さっきの雑誌の件でもわかるだろう?
僕の黒い肌のことも、彼らはちっとも気にしない。日本が好きなんだと言ったら、とてもうれしそうに笑ってくれた。日本から届けられたお菓子なんかをおすそ分けしてくれたりもする。残念ながらふたりは、僕の愛するマンガやアニメには興味はないみたいだけどね。でも僕を馬鹿にしたりは絶対にしないんだ。
さて、そんなふたりのもとに、一年前やってきたツキヒコくんはといえば、見た目は天使、中身は暴君。可憐なのに猛毒な鈴蘭みたいな子さ。最初のうちはおとなしく控えめで、心をえぐる毒舌なんてちっとも口にしてなかったんだけどね……本当に天使のようだったよ。
初めて彼がタンジローに手を引かれてやってきたときの、ルシィの興奮っぷりったらなかったね。
「なんって美しい家族なの! あんなの国で保護しなきゃ駄目よ! 彼らの身になにかあったら国家の、いいえ、人類にとってとんでもない損失だわ!」
っていう握りこぶしを振り上げての演説は、ちょっとアレだったけど、まぁ、いいや。気のいい同僚である彼女が楽しそうでなにより。
でも、彼女の好意もツキヒコくんにとってはうんざりするものらしい。なにせ、大のお父さんっ子だ。ギユーをべた褒めされるのはうれしくとも、近づかれるのは真っ平なんだろう。天使のフリをしていたころはともかく、素を出すようになってからは、ルシィへの風当たりはべらぼうに強い。
「義勇さんも一緒にこようとしてたんだけど、月彦が……」
苦笑して月彦くんを見下ろしたタンジローに、
「職場をコンサート会場かなにかだと勘違いしているような店員がいる店に、オトウサンを連れてこられるわけないだろう? オトウサンは目立つのが嫌いなんだ。キャーキャー小うるさくされたら、オトウサンの耳が穢れる」
なんてこと言って、ちろりとルシィをねめつけちゃうぐらいには。
「コラッ。ごめん、ルシィ」
「いいのよぉ。氷の王子はこうでなきゃ! はぁぁ、虫けらを見るみたいな目にゾクゾクするぅ」
……ルシィはいい子だと思うんだよ。明るいしさ。ストロベリーブロンドがよく似合ってて、気にしてるらしいそばかすだって可愛いし……いや、これはいいんだけども。うん。えっと、そうそう。一緒に日本の話で盛り上がれる人なんて、職場にはルシィしかいないし、仲良くしてもらえて本当にうれしいよ。でも、こればかりは共感できない。ていうか、したくない。
うぅ、ツキヒコくんの冷たすぎる視線が僕にも突き刺さってるんだけど! 違う意味でゾクゾクするんだけど! 怖すぎるよ、この子!
でも。
「ホラ、もう行くよ、パパ。早く買い物済ませないと。オトウサンが待ってるんだからノロノロするな」
「もうっ、急かすなってば。じゃあ、またね!」
グイグイと手を引くツキヒコくんに、苦笑しながら炭治郎が手を振る。
初めて逢ったときよりも、逞しくなったよなぁ、ツキヒコくんも。あのころは、歩く姿も頼りなくて、今にも倒れそうな顔をしていることも多かったのに。まぁ、まだまだ毎日学校に通うのは難しいみたいだけど。それでも、少しずつ健康的になってきた気がする。
あ、そうだ。
「ツキヒコ!」
野菜コーナーに向かう背に声をかける。ちらりと振り向いたツキヒコくんに向かってサムズアップ。すぐに意味を悟ったんだろう。形のいい唇が小さく笑みを作ったのが見えた。
「メルシー」
ワォ、あのツキヒコくんから、お礼のお言葉を貰っちゃったよ。
「なに、今の! 氷の王子の微笑みなんてすっごいレア!」
「大したことじゃないよ。ホラ、仕事しなって。主任に見つかるぞ?」
主任にネチネチ厭味を言われるのは、ルシィだってまっぴらなんだろう。あとで絶対に教えてもらうからねと僕に釘を刺して、ルシィもデリのコーナーに向かった。
天使の顔した暴君は、誰がどう見たってお父さんっ子だ。僕らの前じゃ、タンジローなんてギユーのオマケって態度をくずさない。でもさ、本当は、タンジローのことだって大好きなんだよな、あの子。
『タラの芽って食材、仕入れられるか?』
タンジローの目を盗んでこっそりと聞いてきたのは、たしか、マンガ雑誌の話をしたのと同じ日だ。聞き馴染みのない名前にキョトンとした僕に苛々と、日本の山菜だ仕入れとけと命じてきたツキヒコくんは、まるで我儘な王様のようだったけど。
『タンジローの好物だ。いつでも買えるようにしろ』
少しだけぶっきらぼうな口調は、どこか照れているようにも聞こえて、いつも大人びてるツキヒコくんも、そのときばかりは年相応に見えた。
あの子はちゃんと好きなんだよな、タンジローのことも。素直じゃないけどさ。
あのときのツキヒコくんは、やっぱり傲慢な王様みたいな態度ではあったけど、それでも天使の羽が見えた気がしたもんさ。
あれを見られただけでも、サボりまくりの主任の目を盗んで仕入れのラインナップにタラの芽を入れるぐらい、お安い御用さってほどにね。
スリミのパックを並べながら、なんとなく鼻歌なんか歌ってみる。今日も変わりばえのない一日だ。くだらないことばかりの僕の人生の、さえない日常。毎日大差なく繰り返されて過ぎてゆく日々。
でもさ、バラ色の輝きだってあるんだぜ? 他人から見たらなんてことないことかもしれないけど。
たとえば、そう、思いがけず手に入った遠い国の雑誌だとか。大好きな友達の笑顔だとか。
それから、暴君が見せてくれた天使の顔とかね。
だからまぁ、捨てたもんじゃないよね、僕の人生も。
うわぁ! タラの芽売ってる!
そんな嬉々とした声が聞こえてくる、この職場も、なんだかんだ言って悪くないと思うんだよ。