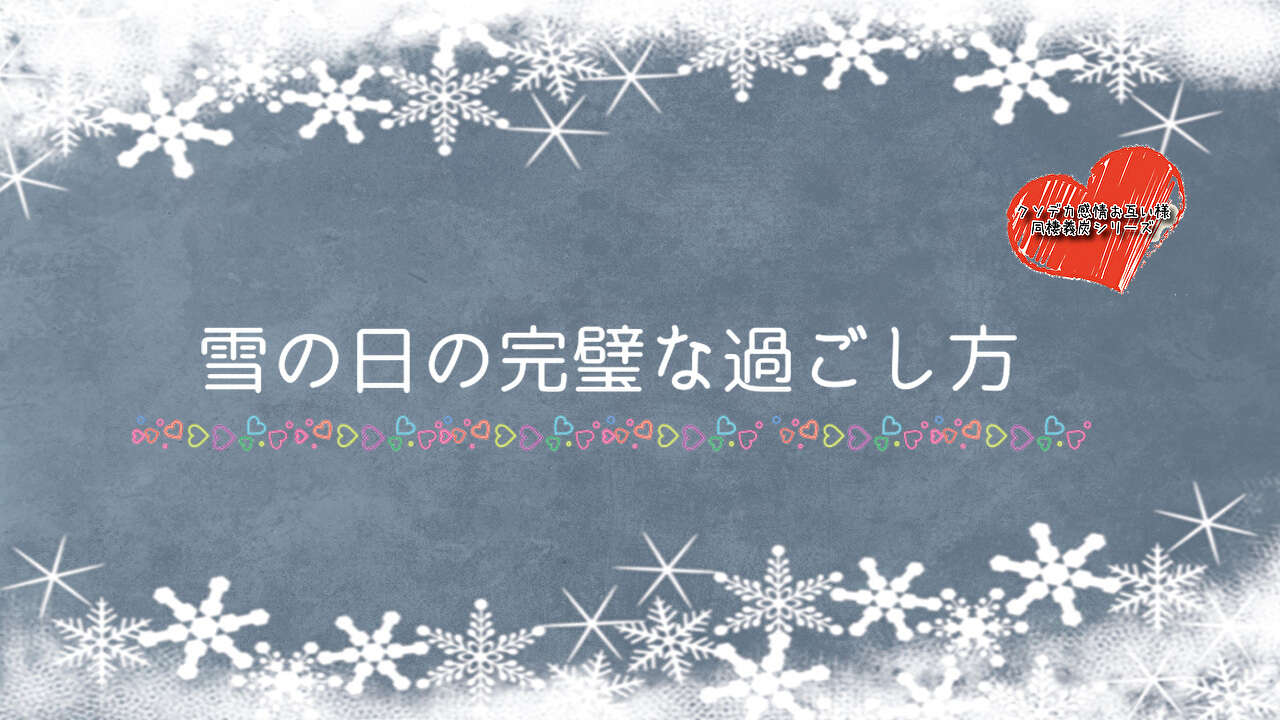香ばしい香りにひくりと鼻をうごめかせ、炭治郎はコンロの火を止めた。
流しに面した窓に結露が光る。今日はずいぶん冷え込みが厳しい。冬用のスリッパをはいていても、足元に溜まった冷気はつらく、早くエアコンが効いてこないかなぁとちらりと思う。
先に火を止めておいた味噌汁に、ちょっとしょうがを入れておこうかな。内側からも体を温めたほうがいいだろう。時節がら、義勇に風邪でも引かせてはたいへんだ。
考えながらフライパンの蓋をとると、湯気とともに、食欲を刺激する香ばしい油と魚の匂いが立ちこめた。
「よし、出来上がりっと」
昨夜寝る前にサラダ油を塗って冷蔵庫に入れておいた鮭の切り身は、フライパンの上でプツプツと小さく脂をはぜさせている。グリルで焼くのと違って、皮に焼き目がついていないのが少々物足りない気もするけれど、なかなかいい出来だ。いかにもふっくらとジューシーに焼き上がっていて、いつもの鮮魚店で買う鮭と遜色ない。
スーパーで買った見切り品の切り身でも、ちょっとの手間でおいしくなるのだから、ネット検索様様である。
これならグリルに残った魚臭さと格闘することもないし、これからはこの手でいこうかなと、鮭を皿に移しながら、炭治郎は満足げにうなずいた。
商店街の鮮魚店で買った切り身なら、手間をかけて下ごしらえしなくても十二分においしいのだけれど、休業中ではどうしようもない。正月明けそうそうぎっくり腰とは、鮮魚店のおじさんも災難なことだ。
腰は大事だもんな、俺も気をつけなきゃ。
しみじみうなずきながら、炭治郎は、ひとりきりのキッチンで頬なんか染めてしまう。
昨日買い物に出たのが炭治郎ではなく義勇だったのも、ようは炭治郎の腰を義勇が気遣ってのことだ。思い出してしまえば、ワーッと叫んで転がりまわりたいようないたたまれなさと、ピョンピョン跳びはねて浮かれまくりたい気持ちがないまじり、なんとも言えない顔になる。
春になれば義勇と暮らしだして満三周年を迎えるというのに、いまだにそういったことへの羞恥は消えない。
今も時折これは夢じゃないかなと、思ってしまうことだってある。
それでも、同棲当初から比べれば、愛されていることを疑う気持ちはかなり減った。炭治郎が義勇を心の底から思うのと同じように、義勇も炭治郎を愛してくれている。わずかずつとはいえ、愛される自信がついてきたとも言えよう。
だから炭治郎は、赤く染まった頬はそのままに、転がりまわったり飛び跳ねたりはせず、くふんと面映ゆく笑うにとどめた。
すりガラスの外に見える空はまだ暗い。夕べの天気予報では、今日までは快晴。煌々と明かりの灯ったキッチンには、味噌汁と焼き鮭の匂いが満ちている。昨日は一日中甘やかされて休んでいたから、腰の具合をはじめ体調も万全。今朝も寝起きの目が映しだした義勇の寝顔はスッキリと整い、それでいて少しのあどけなさを見せて、いっそ拝みたいほどに眼福そのものだった。うん、いい朝だ。
皿に移した鮭をテーブルに置いて、これなら義勇さんの舌にも合うだろとにんまり笑い、炭治郎は壁にかけられた時計を見た。
時刻は六時。そろそろ義勇を起こさなければと思ったのと同時に、隣にかけられたカレンダーが目に入って、炭治郎は思わず動きを止めた。
空気が抜けていく風船みたいに、一瞬前までの上機嫌はシューっとしぼんで、なんならため息だって出そうになる。
今日は一月七日金曜日。新学期の始まりだ。
炭治郎の大切な恋人である義勇が務めるキメツ学園はもちろんのこと、炭治郎が通う大学も、冬休みは六日までだ。とはいえ、今年は七日が金曜日なこともあって、新学期が始まったとたんに三連休という、うれしいようなシャキッとしないようなスケジュールではある。
それでも、本当なら休みが増えるのはやっぱりうれしい。ちゃんと休めるのなら、だけれども。義勇と過ごせる時間が増える機会は、一緒に暮らしていてさえ貴重なのだ。できることなら三日間まるっと堪能したい。まぁ、今更どうしようもないのだけれど。
壁にかけられたカレンダーを見る視線が、恨みがましいものになってしまったのは、しかたがないだろう。
何度睨みつけたって、一月八日の欄に書き込まれた『炭・ゼミ合宿二泊三日』の文字は消えやしない。とうとう落ちたため息は、たいそう深かった。
義勇と同棲を始めてから知ったのだが、学校が完全に無人になるのは精々二十九日から三が日までだけで、冬休み中といっても、教員は必ず誰かしらが交代で出勤するものらしい。もちろん、夏休みや春休みだって同じことだ。
おまけに義勇は部活の顧問もしているし、剣道部には部員が地獄の一丁目と称する――高校時代の炭治郎にとっては、義勇を朝も夜も見られる天国のごときものだったけれど――恒例の、二十七日から三十日にかけての冬合宿だってあった。だから、義勇が完全に休みだった日数は、一般的なサラリーマンにくらべればかなり少ない。
大学生の炭治郎はといえば、今年は集中講義には出なかったので、丸々冬休みを満喫したうえに、二週間ほど通えばすぐ春休みだ。毎度のことながら、多忙な義勇にくらべて気楽すぎる境遇に、なんだか申し訳なくなる。
長期休暇のたび、自分ばかり楽をしてるとなんとなく落ち込んでしまう炭治郎に、義勇が
「気楽に過ごせるのは今だけだぞ。四年になれば嫌でも忙しくなる。教師になったら俺と同じような生活だ。今のうちに精々ぐーたら生活を満喫しておけばいいだろう」
と、苦笑するのも、いつもの光景となって久しい。
「そうは言っても、なんだか義勇さんばっかり損させてる気分になっちゃうんですよね」
ダラダラするのも性に合わないしと、いつも通り返して頭をかいた炭治郎に、ニヤリと笑った義勇の顔が近づいて、耳元でささやかれたのは、一月五日の夜のこと。
「それなら大事な仕事をまかせていいか?」
「大事な仕事?」
耳をくすぐる吐息に首をすくめつつ聞いた炭治郎にも、なんとなく次の言葉と、それからの流れは予想がついた。それぐらいには、一緒にいる時間を積み重ねている。
「恋人の疲れを癒すっていう、重大な仕事を頼みたいんだが?」
「それは責任重大ですね。俺で務まります?」
クスクスと笑いながら義勇の首に腕をまわして言えば、おまえじゃなきゃ駄目だろと、少しあきれた声とともにひょいと抱き上げられた。
時刻は九時。食事も風呂も済ませた。眠るには早すぎるけれど、ベッドの上で運動するにはそこそこいい時間だ。そして明日は冬休みの最終日。寝坊しても、ベッドから抜け出せなくなっても、誰にも叱られない。
「二日間一人寝になるからな。たっぷり癒してもらわないと」
「いいですよ。俺も義勇さんを補充しとかなきゃなんで」
クリスマスにも同じようなやり取りをしたばかりだが、それはそれ、これはこれだ。
笑いあってふたりでダイブしたセミダブルのベッド。同棲初日に買ったベッドのスプリングは、まだまだ衰え知らずで、その夜もたいそういい仕事をしてくれた。
冬休み最後の日を、義勇のお達しの通りダラダラとベッドの上で過ごす羽目になったのは、まぁいいのだ。義勇の機嫌はすこぶる良かったし、炭治郎だって、甲斐甲斐しく世話を焼かれながらイチャイチャできるのは、少し申し訳なくも喜ばしいことではある。
いつもなら土曜か日曜の恒例行事ではあるが、明日の朝から炭治郎は二泊三日で留守だ。だからこそ、五日の夜に前倒しということだったのだろう。本当なら、学校が始まれば忙しくなるからと五日に、連休に入れば休みだから中日辺りにと、都合二晩は熱い夜を過ごせたはずなのに。
いや、まぁ、夜のムニャムニャはともかく、年末にも一人寝をせざるを得なかったというのに、またすぐに二泊三日とはいえ離ればなれというのは、正直こたえる。
「なんでこんな時期にゼミ合宿なんてするんだろうなぁ」
「全国の郷土のおせち料理研究だったか?」
はぁっとため息をつきつつ言った独り言に、返ってきたのはそんな言葉。振り返れば、少しぼんやりした寝起き顔の義勇が立っていた。
「おはようございます。はい、もう松の内も過ぎてるっていうのに、おせちを作るってのもアレですけど」
「松の内は十五日までという説もあるぞ。おはよう」
苦笑する炭治郎の唇に、チュッとかわいらしい音をたててキスして、義勇が席に着く。お返しのキスは義勇の頬に。こんなやり取りを照れずにできるようになったのは、つい最近だ。いや、今もドキドキしてしまうのは変わらないのだけれども。
「今日も寒いな」
「エアコンの調子悪いみたいで、なかなか暖まらないんですよね。年末にフィルター掃除したんだけどなぁ」
昨夜の週間天気予報では、日曜あたりから雪が降るらしいので、エアコンには頑張ってもらわないと困る。なにせ、義勇は結構な寒がりだ。学校ではジャージで過ごしているけれども、実は貼るカイロのお世話になっていることを、炭治郎だけは知っている。
以前、外食の約束をしたときに、大学まで迎えに来てくれた義勇を見て、キャーキャーと騒いでいた同級生たちをなんとなく思い出す。
あの子たちが知ったら多分幻滅するんだろうなと、炭治郎はくすりと笑った。
アンダーウェアにぺたりと貼られたカイロは、なんだかかわいくて、なのにそれを脱ぎ捨てれば現れるのは見事なシックスパック。その落差に炭治郎は、これがちまたで言うギャップ萌えってやつかと感動したぐらいなのだけれど、禰豆子や花子はあきれ返っていたから、女の子の感想は違うのかもしれない。
以前なら、女の子に騒がれる義勇を見れば嫉妬に身を焼かれもしたけれど、このごろはだいぶ余裕が出てきた気がする。そうだろそうだろ、俺の義勇さんは格好いいだろ、もっと褒め称えてもいいぞ。なんて。内心でうんうんとうなずきながら、ニンマリとしてしまったりするのは、愛されている自信がついてきた証拠だろう。
義勇が女性とふたりきりでいれば、今でもギュッと胸が痛くなって不安に駆られるけれど、姦しく騒がれているぐらいなら、さほど嫉妬はしなくなった。炭治郎をさいなんだみっともなくて浅ましい嫉妬も、自分はあんなふうに好きだの格好いいだのと、軽々しく口にできない立場だったことによるものが大きい。
だから、毎日好きと告げられる今は、それほど苦しくないのかも。でも、なんでだろう。いまだに体の芯がきしむような心地がときどきする。いつだって俺の義勇さんは完璧と思うたび、誇らしくなるのに、体の奥がかすかにきしむ気がする。愛されていることを疑ったりしていないのに、不思議だな。
そんなことを考えつつ、もぐもぐと昨夜の残りの白菜のおひたしを咀嚼していた炭治郎は、また頭に浮かんだゼミ合宿の四文字に、再びため息をつきたくなった。
「そんな顔をして食うな。飯がマズくなる」
いただきますと味噌汁に口をつけた義勇は、責めるつもりで言ったわけではないだろう。
『おまえがせっかくおいしく作ってくれたのに、浮かない顔をしながらでは心配になる』
言いたいことはそんなところだと、わかっているから不安にもならない。ほかの人にもこんな具合だから誤解されるんだよなぁとの心配はあるが。
ついでに、しかたのないことだろうとの慰めと苦笑も、つっけんどんに思える言葉には含まれている。それがちゃんとわかるから、炭治郎も苦笑した。
「そうなんですけど……やっぱり寂しくって。冬休み中はお互い外泊が多かったですから」
義勇が研修や修学旅行の引率で何泊か留守にすることはあるし、炭治郎だって実家に帰って留守にすることもあった。正月にも、たまには家族水入らずで過ごせと言われて、一泊だけとはいえ実家に泊ったばかりだ。
だから、離れて過ごすのは初めてではない。なのに、なんだかとっても寂しい気がしてしまう。
それは多分、炭治郎にとっては本意ではない外泊だからだろう。
部活の恒例だから合宿はしかたがない。実家へのお泊りだって義勇の厚意からだし、久しぶりに茂や六太にしがみつかれて眠る夜は、炭治郎にとってもほっこりと心温まるものだった。
でも、ゼミ合宿はそうじゃない。
ゼミ合宿に参加しなくても、単位にはとくに影響しない。不参加の生徒だってそれなりにいる。炭治郎としては、義勇と過ごせる時間は一秒たりと減らしたくない。
だから炭治郎も、最初は断ったのだ。だというのに、なぜ義勇と一緒にいられる時間を減らしてまで、しなくていい外泊をしなければならないのか。解せぬ。
ゼミの仲間や教員と交流し親交を深め、結束力を強くする。良いことだと思う。思うけれども合宿という形でなくても、十分果たせることだとも思うのだ。それに自分がいないほうが、ゼミの人たちも気兼ねなく過ごせるだろうにというのが、炭治郎の掛け値なしの見解だ。
なにせ炭治郎が専攻する家政科は、ほとんどが女子で構成されている。同じゼミには炭治郎しか男子はいない。炭治郎はあまり性差を気にしたことはないが、やはり女の園に男が一人というのは、気にする人もいるだろう。ましてや泊りともなれば、炭治郎だけが個室をあてがわれるわけで、その分みんなが負担する金額も、多少なりとも増えることになる。
なのに、断った炭治郎にゼミの全員ががっかりした様子をみせたものだから。おまけに男手があるほうが安心だからだの、一緒に行けるのを楽しみにしていたのにだのと言い募られれば、炭治郎の性格上断ることなどできなくなった。
決まってしまえば、もうしかたがない。断頭台に登るような心地でゼミ合宿の件を告げた炭治郎に、義勇は苦笑して、楽しんでこいと言ってくれたけれども、残念だと思っている匂いが少しした。炭治郎がいたたまれなくなるのがわかっているからか、そんな素振りは露と表には出さないけれど、炭治郎のよく利く鼻は義勇のちょっぴりの落胆を、しっかり嗅ぎとってしまった。
不自然な男同士の行為で炭治郎にかかる負担を、たいそう慮る義勇は、炭治郎が休めるという前提がなければ、激しい行為におよぶことは決してない。挿入をともなわないイチャつき程度なら、かなりの頻度で手を出されはしているものの、最後までするのは休みの前日と決めている節がある。
基本的に義勇は、真綿でくるむような愛しかたをする人なのだ。快楽の頂点へと追いつめるような抱き方よりも、溶けあうような優しい交わりを好む。
どこまでも甘く優しい交合は、とろとろと煮詰まっていくジャムに似ている。義勇の愛という火にかけられて、ゆっくりと煮崩れ溶けていく苺になったような心地がするのだ。
炭治郎という赤くみずみずしい苺を、甘くとろけるジャムへと作り上げるのも、余さずそっくり食べるのも、義勇一人。それがうれしい。火傷しそうに熱いけれど、ひたすらに甘く抱かれる夜が炭治郎は好きだ。
とはいえ、炭治郎はまだ若い。義勇だってまだまだ衰え知らずだ。たまには理性や自制心をかなぐり捨てて、激しく求めあう夜を過ごしたくなることだってある。ふたりの欲求がピタリと合致して、かつ、炭治郎が確実に休める日の前夜。それが絶対条件ではあるけれども。
五日の夜がその日になったのは、至極当然の成り行きだっただろう。
秋口には早くも決まっていた義勇の冬休み期間中の出勤スケジュールで、義勇が留守がちになるのはわかっていた。幼い弟妹達が炭治郎のお泊りを楽しみにしていたのも、しかたがない。今年も一緒に二年参りへ行こうと約束もしていたし、義勇の実家に新年のご挨拶に顔を出すのは恒例行事だ。となれば、炭治郎がベッドの住人になっても支障がない日は、自然と限られる。
だからなんとなくそういう夜になるなら五日だろうなと、かなり前から思ってはいたのだけれども、問題が一つ。激しい夜を過ごしたあとが問題なのだ。
満たされて、しばらくご無沙汰になってもいいかなとはなぜだかならず、いつもの優しい夜も堪能したいという気持ちに駆られる。この連休は、そんな炭治郎の望みを完璧にかなえてくれるはずだったというのに、ゼミ合宿のために絵に描いた餅になってしまった。しかもとびきりおいしいことが約束された、極上の餅である。
惜しい。あまりにも惜しい。
ため息がまたこぼれそうになるのをこらえて、箸を進めていると、一足先に食べ終えた義勇がようやく口を開いた。
「俺も連休中に出勤することになった」
「え? そうなんですか?」
冬休み中に出勤した代わりに、連休は三日とも家にいると言っていたはずなのに、どうしたことだろう。
「不死川が弟たちと旅行するらしい」
「あぁ、代わってあげたんですか」
なるほど。強面でたいへん厳しい数学教師が、実は弟妹想いの長男だというのは、つとに知られるところである。不死川も義勇同様に忙しいから、家族サービスもなかなかできないに違いない。この連休に休めるのは幸いだろう。
義勇と不死川は表向きそれほど仲がいいわけでもないけれど、いがみ合っているわけでもない。マイペースが過ぎる口下手の義勇に、不死川は始終怒っているようだが、なんだかんだと文句を言いつつも世話焼きの血が騒ぐのだろう。義勇が時間を空けようとスケジュールを詰めていると手伝ってくれたり、出勤日を代わってくれたりもするらしい。
今回の交代は、そんな不死川へのいつものお礼というところだろう。付け加えるならば、ゼミ合宿の参加が決定した炭治郎の罪悪感と落胆を、幾ばくかでも減らすためというのもあるに違いない。もしかしたらそちらのほうが比重は重いかも。
「楽しんできてくれるといいですね!」
「あぁ」
ちょっと眉を下げた困り顔で笑った炭治郎に、義勇はおまえも楽しんでこいと、小さく笑ってくれた。
◇ ◇ ◇
学校から帰ったと同時に留守のあいだの食事をひたすら作って、保存して、慌ただしく旅行の準備もしているうちに過ぎた一月七日。
一月八日の本日、冨岡家の冷蔵庫はいくつものタッパーが占拠していた。冷蔵庫にも冷凍庫にも、チンするだけで食べられるようにしたおかずの数々が入っている。ご飯も一膳分ずつラップして冷凍したし、インスタントの味噌汁も用意した。準備は万端だ。
「今日の昼と夜の分は冷蔵庫に入ってます。明日から明後日の昼までの分は冷凍庫にありますから。日付をかいた付箋を貼ってあるんで、それを食べてください。ご飯は全部冷凍してあります。多めに用意したんで、おかわりしても大丈夫です。味噌汁はテーブルの籠のなかです。何種類か買っておいたんで、好きなのを飲んでください。冷えるようなら冷蔵庫にしょうがのチューブが入ってるんで、少し入れてみてくださいね。温まりますから。明日の昼の弁当も冷凍庫に入ってます。凍ったまま持っていって学校でチンしてください。洗濯は帰ったらまとめてしますから、仕分けだけしといてもらっていいですか? えっと、あとは……あ、そうだ! エアコン! もし調子がよくならないようだったら、電気屋さんに電話してきてもらってください。日曜は休みだから、今日か明後日ですよ? 電話番号はホワイトボードに貼ってありますから。あとは……」
「わかったから。おまえが作ってくれたんだ、ちゃんと飯は食う。味噌汁も飲む。弁当まで悪かったな。ありがとう。洗濯ぐらい俺もできる。おまえがしてるように、部屋干しして扇風機を当てればいいんだろう?」
マシンガンのような炭治郎の言葉を止めて玄関先で苦笑いした義勇に、炭治郎は思わず照れ笑いを浮かべた。
義勇だっていい大人なのだ。炭治郎と暮らす前までは一人暮らしだってしていた。竹雄たちじゃないのだから、細々と注意しなくても大丈夫だとわかっているのに、ここまで心配するのも失礼だろう。
わかっているのに、ついつい長々と話してしまったのは、離れがたさゆえだというのは否めない。
「遅刻するぞ」
「はい。風邪ひかないように気をつけてくださいね」
「おまえもな。向こうはこっちより寒いらしいぞ」
言いながら伸びてきた腕が、ゆるく巻かれたマフラーをしっかりと巻き直してくれる。ゼミ合宿は隣県だ。たいした遠出ではないのに、心配性はお互い様だろう。昨夜の準備中から、やれカイロは持ったか、常備薬は入れたかと、日ごろの口数の少なさがうそのように、義勇は炭治郎の準備に口を出してきた。
夫婦は似てくる。なんて言葉が頭の隅に浮かんで、くふふと思わず笑った炭治郎に、不思議そうな目をして小首をかしげた義勇は、それでもふわりと口元をゆるめ微笑んでくれた。
「気をつけて行ってこい」
「はい、いってきます」
落ちてきたキスは、いってらっしゃいのキスにしては少しばかり濃く、深かった。
◇ ◇ ◇
「ついてないね~」
「いきなり停電だもんね。怖かったぁ。水も出ないとか、ありえないよね」
「ホント。でも電車が止まらなくて良かったんじゃない? これで帰れなかったら最悪だもん」
ワイワイと話しあう声に、炭治郎はうんうんと強くうなずいた。
「竈門くんも、無理に来てもらったのにごめんね」
「いや、設備の故障じゃしかたないよ。気にしないで」
三連休の中日だというのに、電車は空いていた。さもありなん。合宿所に着いたころから降り出した雪は、夜通し降り続け、起きたら山の麓近い合宿所の外は一面の雪景色となっていた。
昼前になってようやくやんだものの、どうやら関東は雪国並みの積雪量らしい。出かけようにもこの雪では、スリップ事故やら電車の運休やらが心配だ。大人しく家にいようというのが、大方の人の判断なのだろう。
炭治郎たちだって、凍結による水道管の破裂と送電線の破損で、合宿所のあらかたの設備が使い物にならなくなったりしなければ、大人しく合宿所にこもっていたはずだった。今ごろは、目的である全国各地の郷土おせち料理づくりに、精を出していたことだろう。
だが、電気も水道も使えないのでは、屋内にこもっているほうがマズい。エアコンの使えない施設で凍死なんてしゃれにならないのだから、帰宅を決定した教授の判断は、正しいしありがたかった。
腐らせるだけになるのも惜しいと、食材を持ち帰れることになったのも、ちょっと得した気分だ。
おまけに、一日早く帰れる。炭治郎に文句などあるはずもない。
最寄り駅で車内に残る同級生に別れを告げ、深い雪に足をとられながら帰路を急ぐ炭治郎の頭には、早く早くという言葉ばかりが浮かんでいた。
こんな雪のなか出勤している義勇の邪魔をしてはたいへん申し訳ないし、万が一電車が途中で止まったら、ビジネスホテルかネカフェにでも泊るしかないので、連絡はしていない。義勇さんを驚かせたいななんていう、ちょっぴりの悪戯心もあったりした。
時刻はそろそろ四時になる。義勇はもう帰宅しているだろうか。できれば義勇よりも早くに家に着きたいのだけれど、微妙なところだ。
もし義勇より先に着いたのなら、エアコンをつけて部屋を暖めておいてあげなければ。それから熱いコーヒーを淹れてあげて、お風呂も準備しておくのだ。お土産に新巻鮭がありますよと、じゃーんと掲げてみせたら、義勇はどんな顔をするだろう。重い丸ごとの鮭は、雪道を歩く今でこそ正直厄介な手荷物ではあるけれども、義勇のビックリ顔を見られるのなら苦でもない。
明日は連休最終日だ。一日中ゴロゴロしてたってかまわない日だ。いつものように甘く甘く溶かされる夜を過ごしたって、誰にも文句を言われない。
寒さのためばかりでもなく顔を熱くしながら、炭治郎は、マフラーをぐいっと口元まで引き上げた。
どうしたってにやけてしまう顔を、誰かに見られるのは恥ずかしかったので。
そんなふうにえっちらおっちらと帰った部屋には、明かりがついていた。ちょっぴり残念だけれどしかたがない。
ならば予定変更だ。いつもだったらチャイムを鳴らして義勇に鍵を開けてもらうけれど、よりビックリしてもらうためにも、新巻鮭片手に自分で開けることにする。いそいそと紙袋から新巻鮭を取り出したら、スタンバイオーケー。
義勇はきっと予定より早くに帰った炭治郎に驚き、ついで炭治郎がかかげた鮭に呆気にとられるかもしれない。いつもよりもちょっと幼くなるビックリ顔を思い浮かべ、くふふと笑いながら勢いよく炭治郎はドアを開けた。
「ただいま、義勇さん! お土産は新巻鮭ですよー!」
「炭治郎!? ……いっ!!」
「義勇さん!? だ、大丈夫ですか!!」
とりあえず、ドッキリは成功、なんだろう。炭治郎も義勇に負けず劣らずビックリしたけれども。
ドアを開けてすぐに見えた義勇の顔が、ちょっと幼く見える仰天顔だったのはいい。それが見たかった。ソファから即座に立ちあがったのもべつにいい。一瞬、巨大なミノムシかと思ったけれども。
予定外に早く再会できた大切な恋人に対して、いだく感想じゃないかもしれないけれど、しょうがないじゃないか。頭からすっぽりかぶったうえ、体にぐるぐる巻きつけた毛布が茶色かったもんだから、見た目はどうしてもミノムシだったんだもの。
いや、まぁ、色はしかたがない。派手な色合いは炭治郎も義勇も好まないし、発熱効果のある敷きパッドとともに義勇を温めてくれる寒い冬の心強い味方だし、肌触りも良くていい毛布なのだ。うん、毛布は悪くない。
けれども、着るものではないので、足まで巻きつけていたら、動きが制限されるのは当然だろう。そんな状態でいきなり歩き出そうとしたら、転ぶのも道理だ。
えっと、なんだっけ、こういうの。そうだ、大惨事。まさしく、それ。
見事に転んでローテーブルに膝をしたたか打ち付けた義勇は、うずくまって痛みをこらえているし、揺れて倒れたマグカップからはコーヒーがこぼれて、床に滴り落ちているし。思わず駆け寄った炭治郎がお土産もバッグも放り出したのだって、いたしかたないことだ。玄関先に転がる新巻鮭が、家のなかの当たり前の光景になんとも言えない違和感を醸し出しているが、鮭よりも義勇のほうが大事なんだから、しょうがないのだ。
「立てますか? ケガは?」
「……おまえ、どうして」
そうとう強くぶつけたのだろう、義勇の声は呆然としつつもまだ苦しげだ。どうにか立ちあがりはしたものの、義勇はすぐにソファに深く腰掛けて、いかにも落ち込んだため息をついている。
「合宿所の水道と電気が、この雪で止まっちゃいまして。驚かせたくて連絡しなかったんですけど……ごめんなさい」
ドッキリなんてしかけなければ、義勇が痛い思いをすることもなかったのに。炭治郎がしょんぼりと言えば、義勇は困ったように視線をさまよわせて、わざとらしい咳払いなんかした。まったくもって珍しい反応だ。
「いや……おまえが悪いわけじゃない。俺がこんな格好でいたのが悪い」
「そういえば、どうして毛布なんか巻いてるんです?」
そもそもの原因はそこだ。きょとりと首をかしげた炭治郎は、今さらのように部屋に充満した冷気に気づき、ぶるっと体を震わせた。
外が寒かったから気づかなかったけれども、こんなに寒いんじゃ毛布を着たくもなるだろう。でも、なんで? 寒がりの義勇がこんな日にエアコンなしで過ごすなんて、そちらのほうがビックリだ。
「……壊れた」
「へ? えっと……あ、エアコンですか?」
こくりとうなずく義勇はなんともバツが悪そうで、せっかく早く帰れたというのに、炭治郎と目をあわせてくれない。
「昨日は大丈夫だったんだ。むしろ調子がよくて、直ったなら電話なんかしなくてもいいだろうと思ったんだが……今朝になって動かなくなった」
「電気屋さんは、電話した当日でも修理にきてくれますよ?」
「学校に着いてから、電話番号をメモしてくるのを忘れたのに気づいた。電気屋としか呼んでなかったから、店名がわからなくて調べようがなかった。帰ってすぐに電話したが、休みだから出なかった」
ぼそぼそと口ごもりながら、そっぽを向いて義勇は言う。
「あ、そっか。日曜日でしたね。でも、ほかにも修理業者はいるんだし、調べれば見つかったんじゃ……」
今まさにそれに気がついた。義勇はそんな顔をしていた。
炭治郎があきれて呆気にとられたのは、そこまで。
「おい……笑うな」
「ご、ごめんなさい。でも、かわいくて」
アハハと声をあげて笑う炭治郎に、義勇が憮然と眉を寄せるのさえもが、なんだかかわいくてしかたがない。
はぁっと、あきらめたようにため息をついた義勇が、ギュッと抱き締めてくれた腕は、なんとなくすがるようだった。やっと目をあわせてくれたのがうれしくて、炭治郎も、冷えた義勇の背中をギュッと抱き締め返す。
眉尻を下げた情けない顔なんて、めったに見られないレアものだ。いつだって炭治郎にとって義勇は完璧で、こんなふうにドジな場面なんて見ることはない。なにしろ、口の周りに食べかすをつけているのですら、長男としてつちかった庇護欲をかきたてられる要素にしかならないのだ。だというのに、日ごろは見られないドジっ子な一面なんて見せられたら、キュンとしちゃうのは当然のなりゆきだろう。
完璧な義勇の、ドジな姿。完璧さを求める人なら、百年の恋も冷めそうなミノムシ状態の義勇なんて、炭治郎にとってはご褒美でしかない。不釣り合いだなんて自己嫌悪も、吹き飛ぶぐらいの。
あぁ、そっか。不安だったのは、完璧な人に釣り合わない自分か。
不意に納得して、炭治郎は笑みを深くした。義勇は決して完璧な人なんかじゃない。だけどやっぱり、炭治郎にとっては完璧な恋人だ。自分がついていなくちゃ、エアコンの修理ひとつしそこなうような人。引け目を感じさせずにいてくれる人。キュンと胸が高鳴ってしまう、不完全だからこそ完璧な、恋人。
「珍しい義勇さんを見られて得しちゃいました」
「頼むから忘れてくれ……」
声までも情けなさをにじませて言う義勇を、炭治郎はくふくふと笑って見上げた。
「無理です」
だって、ますます愛おしさが増していく。今までだって気が狂いそうに好きだったけれど、それをまた凌駕して、大好きが募っていくから。
「幻滅されたくないんだが……」
覇気のない声で紡がれた言葉に、なおも笑いたくなるのをどうにかこらえて、炭治郎は真剣な顔を作ってみせた。厳かな声なんかも装ってもみる。
「義勇さん、俺、大発見しちゃったんですけど……実は俺、ギャップ萌えってかなりツボみたいです」
「は?」
義勇さん限定ですけどねと悪戯っ子な笑みで言えば、義勇の顔にもやっと苦笑が戻って、ますます炭治郎の胸はときめいてしまう。
「萌えたのか」
「ええ、バッチリと! キュンキュンします」
「それはよかった」
クスクスと笑いあえば、ときめきが胸のなか加速していく。
冷蔵庫のなかにいるみたいに部屋はキンと冷え切っているし、ラグにできたコーヒーの染みは落ちないかもしれない。玄関先にゴロンと新巻鮭が転がり、バッグも放り出したままだ。それでもそんな大惨事の痕跡すら愛しいから。
明日はふたりとも完全なお休みで、ここまで雪が積もってしまえば、業者を呼びつけるのもためらわれる。だからきっと、エアコンは明日になって電気屋に電話しなくちゃ直らない。
やっとやんだとはいえ、雪はまだまだ溶けそうになく、くっつきあって温めあわなきゃ、寒さを耐えることはできないだろう。お膳立ては完璧だ。
「ね、義勇さん。夕飯の分は冷凍してあるから、明日でもいいと思うんです」
「奇遇だな。俺もそう思ってた」
「染みはもう手遅れだと思うし、鮭も、これだけ寒かったらキッチンに置いておいても腐らないんじゃないかなって」
「……明日手伝う」
「はい。じゃあ、今日はもう……」
「うん、今日はもう、温めあって過ごそうか」
ベッドで、という一言は耳に直接囁きで。
ふたり一緒に布団と毛布をすっぽりかぶって過ごしたら、炭治郎はまた、ジャムみたいにとろとろと溶けて崩れて、義勇にぺろりと食べられる。義勇の愛という火にかけられて、くつくつ煮詰められていく。
隠し味にはかわいいギャップ。寒がりさんを心のなかから温めるのには、しょうがよりも甘い甘いジャムが効く。
きっと、世界で一番素敵な寒い雪の日の過ごし方だ。